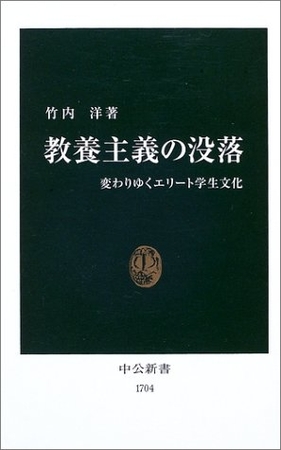ブルデューの社会学を通して日本の学歴社会を批判してきた研究者の新著。これまで読んだ『立身出世主義ー近代日本のロマンと欲望』(NHKライブラリー、1997)や「日本の近代12 学歴貴族の栄光と挫折」(中央公論社、1999)をもとにして、新書らしく簡潔にまとめられている。さらにこれからの教養のあり方について示唆する点がこれまでの著作と違う。
竹内の基本理解によれば、明治以降、とりわけ本書の主題である大正以降の教養主義は行動や自覚的な反省に対し知識の詰め込みを優先した態度だった。こうした外形的な教養は学歴主義や量だけを問う読書主義を助長し、創造的な行為や思考からは遠ざかる。
著者は和辻哲郎が創作に意欲的な若者に向けた言葉を引きながら次のようにまとめる。
教養主義とは、万巻の書物を前にして教養を詰め込む預金的な志向・態度である。したがって、教養主義を内面化し、継承戦略をとればとるほど、より学識をつんだ者から行使される教養は、劣位感や未達成感、つまり跪拝をもたらす象徴的暴力として作用する。『そういう物の前にひざまづくことを覚えたまえ』なのだから。(1章 エリート学生文化のうねり)
日本社会における教養主義がエリート意識の内面化へ向かわなかった要因として、竹内が指摘するのは、明治以降の知的エリートが、ヨーロッパにおける貴族とは違い、言語や生活習慣において大衆と乖離していなかった点。
明治から大正にかけて日本の重要政策であった富国強兵は、下級武士や地方出身者が中央で成功する「立身出世」によって推進された。つまり教養主義は日本において最初から大衆主義と混濁していた。
この経緯は社会全体が大衆化を極めている現代に教養のあり方を考えるためにはとくに重要に思われる。
ところで、『学歴貴族の栄光と挫折』に引き続いて、竹内は丸山眞男を戦後教養主義の典型として俎上にあげている。しかも、その取り扱い方はきわめて否定的であることも前作を踏襲している。
大正末期からすでに教養主義は大衆化を強めていた。しかし大衆社会の中へ霧消するはずだった教養主義は敗戦とともに復興を推進する精神的基盤として復活した。その中心的存在が「学者的学者」である丸山と竹内はみる。
丸山がそうした象徴性を帯びていたことは否めない。それでも丸山の発言や業績をつぶさにみると、竹内が言うほど教養主義の権化であったわけではないことがわかる。むしろ、象牙の塔に閉じこもるのではなく、積極的に政治的な発言を行い、研究書以外に新書などの啓蒙書も書いた丸山は単に学者的学者と言い切ることはできない。しかも、彼の発言や行動は、自身の専門である政治思想史に軸足をおいており、今日のように何にでも好き勝手に語る学者コメンテーターとは表現方法も基底意識も著しく違う。
結論を急ぐと、著者は、大正時代の教養主義に現代の「教養」を考えなおす手がかりを見出そうとしているけれど、それだけではなく、いわゆる戦後教養主義にも、そうした手がかりがまだまだあるように私には思われる。丸山眞男だけでなく、しばらく小林秀雄、森有正など、戦前から戦後にかけて書かれた文章を読んできた。彼らは彼らなりに、教養のあり方について苦闘し、表現を試みている。まだ読んではいない作家や評論家についても、同じことが言える人は少なくないのではないだろうか。
ただし、問題はここでも大衆社会。敗戦により、政治、経済、文化、生活、社会のあらゆる面はどん底に落ちた。人々には失望感とともに復興への意志も共有されていたに違いない。言い換えれば、戦後の日本は成熟しはじめていた大正社会からリセットがかかり、再び右肩上がりを目指した。
膨張する大衆社会が教養主義者をみる態度は、特権階級に対する糾弾ばかりではない。主体的な関わりの欠けた偶像化や、ブームとして消費する記号化も考えられる。つまり、丸山をはじめとして戦後に教養主義者と呼ばれる人々がどう振舞ったかということだけではなく、どのように受容されてきたかという問題が戦後教養主義を考えるためには無視できない。
そして、大衆社会による受容というベールを剥ぎ取った時、戦後教養主義のなかにまだ多くの学ぶべき点が見えてくるような気がする。
偶像化と記号化はマス・メディアの進展によって急激に加速する。個人的な体験を踏まえると、その分水嶺は80年代前半にあったように思う。この見方はビートたけしの登場によって、戦後教養主義は大衆社会の中へ完全に霧消したという竹内の分析とも符合する。
ビートたけしの登場を一言で言えば「バラエティの教養化」。70年代、バラエティの王者だったドリフターズと萩本欽一たちは、政治はもちろんのこと、社会や文化についての発言は一切しなかった。ひたすらお笑い芸人だった。
これに対して80年代のビートたけしは、風刺ギャグを出発点に社会批評的な発言もはじめた。著者も引用している通り、漫才師が吉本隆明の動向について一言するということ自体、ビートたけし以前には考えられないことだった。
教養化したのはバラエティだけではない。アニメやテレビゲームの隆盛は、独自の知識体系を生み出し、サブ・カルチャーを教養主義化した。それは後にオタク文化と呼ばれるようになる。また80年代の半ばに『朝日ジャーナル』で連載されていた対談記事「若者たちの神々」にも、教養主義拡散の一例とみることができる。聞き手は筑紫哲也。
対談の相手として登場したのは、ビートたけしをはじめ、映画監督、ミュージシャン、劇団主宰、漫画家など、従来の教養主義の枠には収まらない人々。ビートたけし同様、彼らは自分たちの仕事だけでなく、社会や文化についても積極的に語った。
もちろん一方的に大衆文化が教養主義を飲み込んだのではない。教養主義も積極的に大衆文化へ降下し拡散した。若い学者がロック・コンサートやサブ・カル系の雑誌に登場した80年代初頭のいわゆるニューアカの流行は、そうした相互流入を象徴する。また、現在のようなニュース・ショーが始まったのも80年代初頭。
久米宏がアンカーを務める「ニュース・ステーション」が大人気を博す前に久米とビートたけしが司会をする「TVスクランブル」という情報バラエティ番組があったことは、報道とバラエティ、双方が歩み寄ったことを物語る。
21世紀の今では、ルポルタージュを得意とするジャーナリストやサブ・カル系雑誌のライターも最高学府で教鞭をとる。教養の担い手も内実も今では特定することはできない。
もっとも大学のブランドだけは残っているようにも見える。あるいは、そのような大学の見事な序列は、著書の奥付に彼らが「特別講師」をしている学校名を付けずにいられない出版業界のなかにだけ残っているのかもしれない。
80年代以前にも教養主義の大衆化の傾向はあったし、大衆文化からの挑戦もあった。たとえば坂口安吾のような無頼派の作家、「書物を捨て町へ出よ」と言った寺山修司、竹内も再三とりあげる庶民出身の思想家、吉本隆明。彼らはいずれも既存の教養主義に抵抗しながらも、結果的にはそれを無化するのではなく、異端としてそれを活性化させる存在になった。これもまた、彼らの個人的な資質というより、社会の受容の仕方に要因がある。
80年代前半を教養主義が没落した時期とみるとき、これまでみてきたような教養主義と大衆文化の相互流入に加えて海外体験の拡大も大きな影響を与えた要因として見逃せない。この点は、本書では触れられていない。
元々、教養主義は読書主義と表裏一体の関係だった。西欧の文物を買える、読める、ということ意味していたと言っても過言ではない。竹内は岩波文庫に圧倒的に西欧作品の翻訳が多かったことを指摘している。戦争中はもちろん、戦後も外国渡航の道は長く閉ざされた。独立を取り戻し日本国のパスポートが発行されるようになっても、海外渡航ができる人はほんの一握りだった。その多くは官吏、学者、留学生などで、従来の教養主義の担い手と多分に重なっていた。その一方で教養主義者の大半は、外国語を読めても、行ったことも話すこともできない人たちだった。
この点、大正時代は事情が少し違う。大日本帝国が戦勝国だった第一次大戦後は、文化的には先進国ではあるがインフレに苦しむ敗戦国ドイツへ、多くの人が安い費用で渡り、インフレに苦しむドイツ人研究者に個人教授を受けたと聞く。
経済成長が加速すると、海外渡航者も増える。それまでとは異なり、商社や銀行の社員、メーカーの技術者なども続々海外へ出るようになり、80年代には円高にともない、海外旅行も手に届くものになった。個人的に言えば、家族の一員が初めて海外旅行へでかけたのは1987年、私自身は、1988年。そのときすでに大学の生協では個人旅行が販売されていた。
こうなると西欧の本が読めるだけの人は、これまでのような訳知り顔はできない。人文学の本や横文字の本を読んだことがなくても、外国の文化について実感をこめて語る人がでてくるから。80年代は、海外での実体験が読書による擬似的な海外体験を凌駕しはじめた時期ということもできるのではないか。
確かに実体験にもとづく発言には重みがある。としても、それは読むだけの教養主義と同じように、体験だけを求める体験主義に陥る可能性ももつ。
では「教養」とは一体何か。竹内の結論をみる前に、もう一つ、竹内の取り上げていない教養主義の一面をあげておく。それは自然科学、理工系の知識。竹内が分析するのはもっぱら文学や思想に支えられた教養主義。これらが理工系学生にまで強い影響をあたえていたところに、大正から学園紛争時代までの教養主義の強さがあった。
戦後復興の牽引者は、産業界、とくに製造業。その担い手は、理工系学部の出身者だった。ノーベル賞だけが学問、文化の指標ではないとしても、日本国出身の受賞者を一覧すれば、物理学や化学などの分野が教養主義の本丸である文学や思想に比べ早くから国際的な評価を得ていたことは容易に見てとれる。
教養主義の過剰な影響を受けていた理工系学生が独立独歩を始めたとき、教養主義はもぬけのからとなり、同時に技術の自己目的化も始まったとみるのは性急だろうか。また、経済成長の担い手は高学歴者だけではなかった。学歴はなくても熟練した職工が日本経済の成長を支えたことも、教養と社会の発展の関係を考えるときには見過ごすことはできない。
さて、竹内の論考を読めば、彼が教養主義を社会生活の上昇志向と不可分にとらえていることがわかる。教養主義が上昇志向であるのに対し、竹内はあるべき教養の姿を上昇志向に対して「じゃまをする教養」と定義する。
「じゃまをする教養」を構成する要素として、竹内が重視するのは、従来のような知識の詰め込みではなく、コミュニケーション能力。前尾繁三郎(通産大臣、1905‐81)や木川田一隆(木川田一隆、東京電力会長、1899‐1977)など、政界や実業界で多くの人々と関わりながらも、教養を体現した人を例にとりながら、竹内は本書を結ぶ。
教養「主義」(原著傍点)が敗北・終焉し、同時に教養の輪郭が失われているが、そうであればこそ、いまこそ、教養とはなにかをことのはじめから考えるチャンスがやってきたのだともいえる。これからの教養を考えるためのひとつのヒントになるとおもわれるものは、大正教養主義はたしかに書籍や総合雑誌などの印刷媒体とともに花開いたが、それとともに忘れてはならないのは、前尾や木川田にみることができるように、教師や友人などの人的媒体(ヒューマン・メディエム)を介しながら培われたものであったことである。戦後の大衆教養主義は、こうした教養の人的媒体をいちじるしく希薄化させたのではなかろうか。教養の培われる場としての対面的人格関係は、これからの教養を考えるうえで大事にしたい視点である。教養教育を含めて新しい時代の教養を考えることは、人間における矜持と高貴さ、文化における自省と超越機能の回復の道の模索であることを強調して、結びとしたい。(終章 アンティ・クライマックス)
「対面的人格関係」という言葉は終章で初めて登場するので、すこし唐突な感じもする。著者が意図するところを汲み取ることは難しいことではないが、これまでの知識偏重に対して対面的人格関係を安易に対立させても、教養に対する新しい見方は生まれてこないように懸念する。
たまたま本書を読んだ夜に、NHK教育テレビ『視点・論点』で、教育学者の苅谷剛彦が、戦後に中心的だった知識詰め込みの教育も間違いならば、それを緩めただけのゆとり教育も間違いであり、そうかといって、総合学習に見られるような体験主義、自発的な調べ学習も学習者の家庭環境や性格を無視してはこれまで同様、お題目に終わると警告していた。
教養に関する議論が難しいのは、倫理や信仰と同じく、結局のところ、その内実が個人の内面のあり方に関わるために、方法論はどうしても個人にゆだねられるほかない点にある。
対面的人格関係は確かに重要としても、それが単なる烏合の衆に終わらず、人格の関係となるためには、個々の人格が独立していなければならない。
ストレス過剰な現代社会は、個人の内面を危機に陥れている。人々は孤立し連帯を求めている。人との関わりが心の傷を癒す性質をもつことも私は否定はしない。それでも、個人が個人としてあるためには孤独を感じることを避けて通ることはできないと思う。
連帯のなかに孤独があり、孤独の末に連帯がある。教養とは、前者に耐え、後者を模索していくことではないだろうか。それは一直線の道のりではない。孤独と連帯、どちらが先にくるかは、人それぞれではあるとしても、それらの往復こそ「教養」ではないか。
とりあえずの結論として、近頃私はそんな風に考えている。
この考えを深めるために教養主義の歴史的解体はさらに進める必要がある。とりわけ私自身の中に巣食う上昇志向的な教養主義への憧憬はまだまだ反省し自己批判しなければならない。その孤独な思索は同時に過去の教養主義から「主義」に埋もれた真の教養への手がかりを探索する道にもなるに違いない。
その道のりを楽しげに走る自転車。教養主義の暴力的装置でもあった読書に今後も意味があるとすれば、そんな素朴な小道具としてだろう。
uto_midoriXyahoo.co.jp