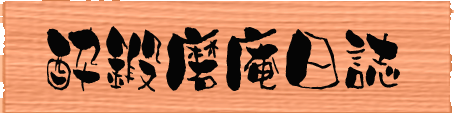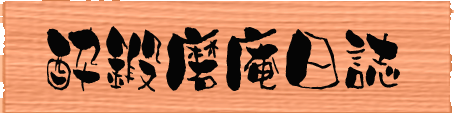|
|
�@�H�[���F�ߑO�P�O���S�T���@�@��ƊJ�n�F�ߑO�P�P���Q�O���|��ƏI���F�ߌ�S���S�T��
�@�H�[�̋C���F�R�R�x
�@�����́w�ʌ`�����x�̐���\��ł����A�w�ۃe�������E���x���肪��̒��j���H�[�ō�Ƃ������Ƃ������ō������邱�ƂɂȂ�܂����B
�@���j�͍�����獡���Ɋ|���ē����ł����B�E��́w�T�L�x�Ȃ̂łi�q���g���Ďw��w�ō������邱�ƂɂȂ��Ă��܂��B�\��ł͂P�O���P�T���ɍ����ł����B�F���͂P�O���O�T���ɑ҂����킹�ꏊ�ɍs���܂����B�����œd�b������ƁA�܂��w�k�^��x�Ƃ������ƂŁA����ł͂ƍH�[�֍s���N�[���[�𒅂��Ă����Ɏw��w�ɖ߂�܂����B����ƒ��j�͓�������ő҂��Ă��܂����B
�@�b���ƁA�ދΒ��O�Ɏ�p���̊Ō�t���ɖ�܂̂��ƂŘA���𗊂܂�Ă��܂��A�\�����{�x���Ȃ����Ƃ������ł����B
�@�r���̃R���r�j�Œ��j�̒��H�E���H�A�����Ĉ��ݕ����w�����čH�[�ցB���j�ɗ��܂ꂽ�̂͗o��Ɍ����J���邱�Ƃł����B�K���X�p�h�����r�b�g�ŊJ������ƍl���č�Ƃ����Ƃ���A�ȒP�ɊJ���邱�Ƃ��o���܂����B�������A���̃h�����̐n�̓ӂU�����ŁA������X�������ɍL����K�v������܂����B���H�p�̃h�����Ō����L���悤�Ƃ���Ɨo��͊���Ă��܂��܂����B�����Ń��[�^�[���g���čL���邱�Ƃɂ��܂������A����Ɏ��Ԃ��|����܂����B����ƌ����d�オ�����Ƃ���ŌF���͒b���ƂɈڂ�܂����B�b���ƃX�^�[�g�͂P�Q���߂��ɂȂ��Ă��܂����B
 �@ �@
�K���X�p�h�����̐n�ƃ��[�^�[�Ō����J����@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�y�������ɗo��������č�Ƃ����钷�j
�@�܂��͋��̂�͂ރ��b�g�R�̌���������������Ƃ���X�^�[�g���܂����B����̌��̌a���Q�O��������P�T�����ɂ��܂����B�������A����ł��܂��傫�������ł����B����ł���킴�킴������ۂ߂č��̂ł͂Ȃ��A�ł��L���č���������ȒP�ł����E�E�E�B
 �@ �@
Before�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@After
�@���b�g�R�̏C�������������Ƃ���Łw�ʌ`�����x�̐���Ɏ��|����܂����B
 �@ �@
�@�@�@�@�f�� S45C�ۖ_ ��30mm�@����30mm�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���`�ɑł��o���Ă��� ���b�g�R�͂�����Ƒ傫��
�@�\�z�͂��Ă��܂������Z�`�ɋʂ̐ԓ������E�ނ悤�ɂȂ��Ă��܂��܂����B�����t���������������̂ł�����`�ɑł��o���̂͂܂��y�Ȃ̂ł����A�����t���̕������悯�Ēb�����邱�ƂɂȂ�A�ǂ����Ă��ԓ����̌E�݂������Ƃ͏o���Ȃ���Ԃł����B
 �@ �@
�@�@�@�@�@�@�@�@�b�����I�����w�ʌ`�����x�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�O���C���_�[�ō���Ăقڊ�����Ԃ́w�ʌ`�����x
�@���̂�͂ރ��b�g�R�͖��ɗ����܂������A�܂����悪�傫�������ł��B�O���b�v�͂͊��Ғʂ�ł������A��ɂ��������悤�ɁA���������������Ȃ�Αł��L����`�̕����ǂ������ł��ˁE�E�E�B
�@��������������A�Ώ��ɉ����Ă̍�ƁA��Ǝ��̋C���͂S�Q�x�ɂȂ�܂����B�V���������l�b�N�N�[���[�����ɗ����܂����B
�@�����̏d���͂P�T�O�����ɂȂ�܂����B�\�z���Ă������̂��R�O���ʏd���Ȃ�܂����B�d�����ɂ͍������킯�ł�����A�ꉞ����ō����낤�Ǝv���ċ��܂��B�����̍r�����I�����̂͂S���ł����B
�@��������A���ɐ���������āA���j�ɂ͎����A��p�Ƀs�[�}����V�V�g�E�����n�����܂����B�F���̓L���E���Ɠ��h�q�����n���܂����B
�@���ւ������ċA�H�ɒ������̂͂S���S�T���ł����B���j�ƍH�[�ō�Ƃ��ĉ߂����̂͂Ƃ��Ă����������Ƃł����B���@��ł͗������Ƃ���܂����A���q����Ƃ��ċ���̂��`���`���ƒ��߂Ȃ��炱�������Ƃ���̂͗ǂ��ł����I�I �F�X�ȍH����g���ėo��Ɍ����J������A���܂ꂽ�v���X�`�b�N�̓��ꕨ�Ɍ����J����̂����āA�u�悭����ȂɍH��W�߂��ˁE�E�E�v �ƁA���S���Č��Ă��܂����B���q�B�͐{���̔����̒�ō�Ƃ���F���̂��ƌ��ċ��܂��B���̍��͓���Ȃ�ċɁX�킸���ł�������A�����Ƃ���Ɣ�ׂĂ̌��t�������Ǝv���܂��B�F�����g�A�悭������W�߂Ă����Ǝv���Ă��܂��E�E�E�B���C�t���u���Ȃ������������������A�ǂ���������Ηǂ��́E�E�E�H�v �ƁA�S�z���Ă���Ă��܂��B�m���ɂ����ł��ˁE�E�E�B�X�v�����O�n���}�[�Ȃǂ͂ǂ���������Ηǂ��ł��傤�ˁE�E�E�B�b���Ƃ��Ɖ��N���炢�o����ł��傤���E�E�E�H
�@�����̍�Ƃ͍����b�������������d�グ�邱�ƁA�����āA�����̕��̌����삷���Ƃɐ���܂��B�������d�オ�����Ƃ���Ŋ��̒��q�̕������܂�܂��B
�@���T���F�X�Ƃ����āA�R�O���͂R�P���ɋ���ōs���w���ʋ~���u�K�x�̏����Łw�����u���h���x�ɋ@�ނ����ɍs���Ȃ���Ȃ炸���x�݁A�R�P���͍u�K�����A�ߌ�͋@�ނ̕ԋp�ł��x�݂ł��B�P���͌ߌ�S������ł�������̖h�Ύ{�݂̓_���ɗ�����̂ŁA��Ƃ͂Q���ɂ͏I�����Ȃ���ΐ���܂���B |
|
|
|
|
|
�@�H�[���F�ߑO�P�O���P�T���@�@��ƊJ�n�F�ߑO�P�O���R�T���|��ƏI���F�ߌ�R���T�O��
�@�H�[�̋C���F�R�T�x
�@�����͏[�����߂ɉƂ��o�܂������w�O�� �T�x�ł̍�Ƃ̂��ߓ������x���Ȃ��Ă��܂��܂����B���ꂩ��͂��傭���傭�����������Ƃ����邩�Ǝv���ƂȂ����ȋC�����ɂȂ�܂��B���[�g��ς��������ǂ������m��Ȃ��ł��B
�@�H�[�ɒ����Ă܂��͎U����Ƃ���X�^�[�g���܂����B�S�̂ɎU�����āA���̌�A�L���E���̐��̊Ԃɐ����o���������ɂ��āA��������p�Ɂw�V�\�x�Ɓw�V�V�g�E�x�����n���܂����B���n��͗����̐��̊Ԃɐ��𗬂����ςȂ��ɂ��܂����B�����āA�O�X��ċp���c�����A���肵�Ă��鑤�̎G�����ċp���邱�Ƃɂ��܂����B�����͂悭�R���Ă���܂����B
 �@ �@
�@�@�@�����̐��ւ̎U���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�G���̏ċp ���ƂQ�R�c���Ă��܂�
�@�G���͂��ƂQ�R�c���Ă��܂��B���ƈ�T�Ԃ��炢�����Ă����ċp���悤�Ǝv���Ă��܂��B�����ւ̎U���͂R�����܂ōs���܂����B�ȑO�A�����s�������Ƃ��̗����̓|�N�|�N���ŗ���Ɠ��̂˂��Ƃ芴�������Ȃ��Ă��܂��܂����B���ׁ̈A����I�Ƀ^�b�v������^����悤�ɂ��Ă��܂��B
�@�ċp�����̍ۂ͖T�Ō��ċ��Ȃ��Ɗ�Ȃ��ł�����m���ɑ��v�Ƃ�����ԂɂȂ�܂ł͌��Ă��܂����B���̈גb���Ƃ͂P�Q������ɂȂ��Ă��܂��܂����B�ܘ_�A�Ō�͊m�萅���T���ď����Ă��܂����B
�@����b�������������d�グ���Ƃ���X�^�[�g�ł��B�`�𐮂��邽�߂ɍ�����̂ō�������U���ʌy���Ȃ�܂����B���͋v���U��Ɂw�T�b�b�x���̂��K�ɍ��܂����B���b�g�i���o�[�͍����t���a�̋߂��ɑł��܂����B���`�̕��ɍ���̂͏��X��ςł����B
�@���ʕ��������ō�i�Ƃ��邱�Ƃ͂��Ă��܂���ł������A���̕����͍��ׂɃ��b�g�R��V�����܂������A����Ȃ�ɑ�ςł��������i�Ƃ��ăJ�E���g���邱�Ƃɂ��܂����B
 �@ �@
�@��i��2249�@�w�ʌ`�����x�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���̒��q�̓��镔���ƌ���
�@�������d�グ�����Ƃ́w�����x�̒��q�̓��镔�����o���āA�����삵�܂����B�����͕��Q�T�����@�����R�����̃t���b�g�o�[���g���܂����B���킹�ڂ͗n�ڂ��܂������A�Ȃ��Ȃ��Y��ɗn�ڏo���܂����B
�@���������ɔ[�܂�悤�ɂ��Ă���A���q�̓��镔�����o���܂����B�R���^�[���g���Đ�o���A�؍H���X�����g���ĂR�����ʂ̌��Ԃ����܂����B���q�͂ł��邾�������Ƃ����w���Ȃ̂łQ�T�O�����ɂ���\��ł��B���̕����̌����͂R�`�S�����ɂȂ�Ǝv���Ă��܂��B���q�̕��͌��������łQ�W�����ƂȂ�܂��B
�@�����͒����珋���āA����̍ō��C���͂R�V�x�����悤�ł��B���ꂩ�������ȏ�ԂȂ�ł��傤���A�b���Ƃɂ͉ߍ��ȋC���ł��B
�@�A�H�͍r��E�݃R�[�X�ŋA���ė��܂����B�ǂ����q�ŋA���ė��܂������A�����s�ɓ��钼�O�œ��H�H���ʼnI�����A���Ǐa���铹�ɏo�Ȃ���Ȃ炸�A�����M�����S����҂��ƂɂȂ�܂����B�T�O���|���炸�ɋA���Ǝv���Ă��܂������A�P���Ԃ������Ă��܂��܂����B�ł��A�V��{�o�C�p�X���g�����`���b�g�͑��������̂ł͖������Ǝv���Ă��܂��B
�@�����A������͋���ł́w���ʋ~���u�K�x�̏����Ȃǂł��x�݂��܂��B���j���͂Q���܂ł̍�ƁA���{�̂̒b�����o����Ηǂ��Ǝv���Ă��܂��B�n�n�肪�Q�Q�����Ƃ����w���A���q�͂Q�T�����ɂ��܂�����A�F���̉Ώ��A��ԍL������Ԃō�Ƃ��邱�ƂɂȂ�܂��B�b�ڏ�肭�o����Ɨǂ��ł����E�E�E�B |
|
|
|
|
|
�@�H�[���F�ߑO�P�O���P�O���@�@��ƊJ�n�F�ߑO�P�O���R�O���|��ƏI���F�ߌ�R���R�T��
�@�H�[�̋C���F�Q�V�x
�@����͌ߑO���̂R���ԁw���ʋ~���u�K�x����u���܂����B�ސE��X�V���Ă��܂���ł�������V�K�����ł��B�v���U��Ɂw�~���Z�\�F����i�����̊O�����ד���Ɩ��]���ҁj�x�����܂����B�ȑO�͐�����Ɏ��܂������A���͑������s�ł����B
�@���āA�����͏_���q�e���˗��̍����̖{�̂�b�������Ƃł��B�V�C�ł����A�䕗�X�������ݖk�㒆�ŃX�s�[�h�������オ��A�R�[�X�͓����ɂ���Ă��銴���ł��B�����͂��̉e�����ܓV�ʼnJ�����X�~�銴���ł����B�����́w���̉ԉΑ��x�ŁA�䕗�̉e�����S�z�ł������A���Ӓʉ߂��Ė����̌ߌ�͐���Ă���悤�ł��B�ԉΑ��͏o�������Ȋ����ł��B�P�͎����čs���܂������A��肢��ɉJ�ɓ����炸�ɍς݂܂����B
�@�H�[�ɒ����Ă܂��̓L���E���̎��l�A�����͂X�{���n�o���܂����B�܂��A�V�V�g�E�����n���܂����B�}���͋A��ۂɎ��n���邱�Ƃɂ��č�ƂɎ��|����܂����B
�@�܂��͂Q�T�����~�P�X�����~�P�T�O�����̋ɓ�S���o���A�V�O�������Z���^�[�ɐ荞�݂����܂����B�����Ĕ����Q���������S�����@���Q�O�����@�����V�O�����ɑł��o���܂����B�����ɋɓ�S�̐荞�݂���ꂽ�Ƃ�����L���č|�����ݍ��ނ悤�ɏ������܂����B�X�ɍ��̃��b�L���Ă����Ƃ����āA�Ώ�����������g�߂܂����B
�@�b�ڍ�Ƃ͂P�Q���S�O��������ɂȂ�܂����B�v���U��̒b�ڃ��N���N���܂����B�ł������Ă����Ƃ��̊����ł͏�肭�b�ڂł��Ă���悤�Ɏv���܂������ǂ�Ȃł��傤���E�E�E�B
�@�������A�����͒b�ڍ܂̓������ʂ��Ђ�����Ԃ��Ă��܂��A�Q�^�R�ʑʖڂɂ��Ă��܂��܂����E�E�E�B(�L�w�M;) �V�������Ȃ���Ȃ�܂���E�E�E
 �@ �@
�@�@�@�@�f�ނ̏����@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���q������ł�����
 �@ �@
�@�@�@�n�̕�����ł������@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Ă��݂����|���钼�O�̊��{��
�@�b�ڂ��Ă��炭�͒����I�ɑł������Ă����A���݂��P�O�����ʂɐ������Ƃ���łk���ɉ��H���܂��B���̊��͐n�̒������Q�Q�O�����{���q���A���q�̒������Q�T�O�����Ƃ����傫�ȕ��ł��B���̂��߂��̂܂܂ł̓X�v�����O�n���}�[�ł͒b���ł��Ȃ��̂Ŏʐ^�̂悤�Ɉ�U�Е����Ȃ��ăX�v�����O�n���}�[�őłĂ�悤�ɂ��܂����B�܂��͐n�����Ȃ��Ē��q��ł��o���܂����B
�@���q���ł��o�����Ƃ���Őn�̋Ȃ�������ɖ߂��A���q���ʐ^�̂悤�ɋȂ��Đn��ł��o���Ă����܂��B�e���̎w���ł͐n�̕��͂Q�Q�����Ƃ������Ƃł��B���݂Q�W�����ȏ�̕�������܂��B������Q�Q�����ɂ�����Ȃ��o�����X���������������܂����E�E�E�B
�@�n�̑ł��L�����I�������Ƃ���Œ��q�����ɖ߂��A���q�E�n�̘c�݂���菜���A�n���������ł��Đn�t���̏��������āA���̍ۂɏ��X�ɉ��x�������Ȃ����Ƃ��Ă����܂����B�Ō�͏Ă��݂��ł��B�������A�傫�����̂Ȃ̂Œ��q�͊D����̃y�[���ʂ����яo�Ă��܂��܂����B
�@�Ă��݂����|���I������̂͂Q���S�T�����ł����B��������}�������n���܂����B�����͒��j�v�w�E�`���v�w���ԉΑ��ʼn䂪�Ƃɗ��܂����炢�������������n���܂����B
�@���ւ������āA�L�^��t���A�H�ɒ������̂͗\����R�O���ȏ�x���Ȃ�܂����B�����͂S�����狳��̖h�Ύ{�݂̓_�����L��܂��B�F���͒x��邱�Ƃ͓`���Ă���܂����A�h�ΊǗ��҂ł�����Ȃ�Ƃ��Ԃɍ����悤�Ɋ撣��܂����B�܂��́w�O�� �T�x�t�߂̍�Əa������邽�ߔ��������g���܂����B�����āA�w�^��x���獂�����g���܂����B������͂S���P�T���ł����B�������A���x�_�����I������Ƃ���ł����E�E�E�B�_������Ɠ_���ɎQ����������ψ�����l�q���m�F���ċA���Ă��邱�ƂɂȂ�܂����E�E�E�B(;^_^A
�@���j���ł����܂��܂��a�@�s���ł��x�݂ł��B����Ԃ̎�f�Ȃ̂ōs���邩�ȁE�E�E�H�@�ł��A�����͂��Ȃ������ǂ��ł��ˁE�E�E�B����̍�Ƃ͊��̐��`��Ƃł��B�n���������ł����琬�`�ɂ͎��Ԃ��|������̂Ǝv���܂��B�Q�Ă��ɍ�Ƃ��Ă������Ǝv���Ă��܂��B |
|
|
|
|
|
�@�H�[���F�ߑO�P�O���Q�T���@�@��ƊJ�n�F�ߑO�P�O���S�T���|��ƏI���F�ߌ�Q���P�O��
�@�H�[�̋C���F�R�U�x
�@�����͊֓��n���͍ЊQ���̏����ɂȂ�Ƃ������ł����B���͂���ς�_���_�����Ă��܂��Ƃ��o��̂��x���Ȃ�܂����B�I�}�P�ɓc�������_�߂��ŏ�����ƁA�����āw�O�� �U�x�t�߂ł̍�ƂŁw�O�� �Q�x�߂����Ƃ��납��a�ɂȂ�A�d���Ȃ��w�O�� �T�x���甲�����ɓ���܂����B����ł��H�[�܂łP���ԂQ�O���߂��|����܂����B
�@�Ƃɂ��������Ă܂��͔��̍앨�Ƀ^�b�v�����������܂����B�����āA�t����^���܂����B�����āA�L���E���ƃV�V�g�E�E���h�q�����l���܂����B���ꂾ���Ń^�b�v�����������܂����B
�@�����̍�Ƃł������̐��`��Ƃ��l���ċ��܂������A�ǂ����n�̕����ׂ�����ƍl���˗����ꂽ�}�ʂ��悭���܂����B����ƂQ�Q�����ł͂Ȃ��R�Q�����̂悤�ł����B�Q���R�Ɍ�����悤�ȏ������ł����B�����Ńu���[�h���S�����ʍL����悤�ɍ�Ƃ��܂����B���݂ɂ͏[���ɗ]�T���L��̂ʼn��Ƃ��Ȃ�܂����B
 �@ �@
Before�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�s���{�̂̏C���t�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@After
�@�Ώ��ɉ����Ă̍�Ƃł����獡���͏��X���������ł��B��̂R�S�����ʂ̕��ɂ��鎖���o���܂����B���`����ƂR�O�����ʂɐ������Ⴄ��������Ȃ��ł��B�����͌��������T�����ʁA���������łS�D�U�����ʂɐ���܂����B
�@���{�̂ɏĂ��݂����|���Ă��獽�������߂��āA�w�ʌ`�����x�����t���Ă݂܂����B���t���a�̍��킹�ڂ̗n�ڂ͑g�ݏグ��Ƃ��ɂ��邱�Ƃɂ��܂����B
 �@ �@
�@�@�w�ʌ`�����x�����t�������@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�^�b�v�����������������̐���
�@�����ƍ���t������͕��̒��q�̓��镔���̕��������L����悤�Ƀ��X�����|���܂����B��͖{�̂𐬌`������ɔ��������܂��B
�@���̒i�K�łP�������ł����B�����wMAX�x�ł������Ƃ͂����܂łɂ��邱�Ƃɂ��܂����B�����������̐��Ԃɐ����o���������ɂ��Ă����܂������炻���Еt���A��p�̐������݂ɍs���܂����B
�@�A�H�́w���͎��x����w�O�� �Q�x�ɔ����铹���g���ċA���ė��܂����B�Ԃ̊O�C���v�͂S�O�x�ł����B�����͊֓��e�n�łS�O�x�����A�Q�n�� �ɐ���s�ł͂S�P�D�W�x�̊ϑ��j��ō��C�����L�^���܂����B����������ɂȂ�܂����珋���킯�ł��E�E�E�B
�@�����̍�Ƃ͊��̐��`��Ƃł����A�Ƃɂ����ЊQ���̏����ł����炻��ȂɊ撣��Ȃ��ŋA���Ă��悤�Ǝv���Ă��܂��B |
|
|