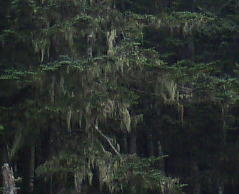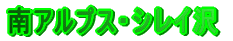 (親睦沢登り)
(親睦沢登り)
9月4−5日(前夜発)
南アルプスの沢は初めてです。標高が高いので、行く前からだいぶ寒いと聞いていましたが、用心したため、問題なく行けました。2日目、もう少し天気が良ければ、沢登りにはあまりない大展望が楽しめたと思います。
L:S林さん、メンバー:Ta田さん、F浦さん、M井さん、自分
 |
今回の山行の大まかな図
沢登り:赤、登山道:黄(共に手書き) |
9月4日
天気:晴れ
4:00 甲府駅出発(バス)
5:30 夜叉神峠(バス停)M井さん、Ta田さんと合流
6:05 シレイ橋着(下の大まかな図で1)
リーダーより、登攀リーダーをするよう言われる。自分がトップ。わからない所はF浦さんに聞いて、どうしようもなくなったらM井さんに助けてもらうようにと。もちろん、うれしい。でも、怖い。特に、このシレイ沢は出だしから滝です。普通なら、入渓地点から少し歩いた所あたりに、滝があるのですが、橋から沢に下りた所からもう滝です。さらに、「全部巻かずに登るつもりで(もちろんつもりだけ)」とのこと。気を落ち着かせる間もなく、滝。準備をする間に、ルートを見る時間もあったのですが、ド緊張でした。
 |
橋の向こうに見えるのが、出だしの滝です。 |
| 橋から滝を撮る |
 |
7:00 出発
実は、7月の18、19日とうちの会の人たちがこのシレイ沢に来ているのですが、その時はきちんと巻いているのです(橋の左側に上部の吊橋に至る道あり)(注:その時はもっと水量が多かったとのこと)。橋から見て、登れないことはなさそうですし、いくらなんでも「最初から登れません」は避けたかったし、橋の左側にロープがありそれを伝って下降しました。
 |
右から登って、矢印で示した辺りから左に移り |
橋から見た時から、「右から登って途中から左に移れば」というのが考えられました。左に移る所までは行けたものの、左に移るにはちょっと水量があり、進めませんでした。M井さんに行っていただき、ロープを出して無事通過。さらに上部の方で、ちょっと濡れるも、とりあえず第一の難関突破。
7:25 ガレ場を通過した後の2番目の滝
この滝は登れそうにありません。 |
 |
ガレ場を通過して、次の滝ですが、どうも登れそうもありません。そのため「右を巻きます」と宣言したものの。M井さんより、「滝の落ち口に下りるように巻くこと、出ないと大高巻きになってしまう」とのようなことを言われる。自分が考えていたよりもさらに下流に、左から巻けるルートがありました。相変わらず、巻き道を探すのが下手です。
 |
7:50 この滝ちょっと記憶ありません |
| 8:10 ここで今シーズン初ビレイ |
 |
いきなり滝の上部を登っている写真です。その上の7:50の滝とは別だと思います。今回、登攀リーダーのルートファインディングに気をとられ、写真を撮る回数が減りました。仕方のないことです。いずれにしろ、8:10の滝で登るM井さんを今シーズン初ビレイしました。と言っても下からロープを送り出すだけのボディビレイでして、当然ですが「最初の支点をとるまでは変にビレイをしてロープを送り出すのが遅れるよりも、ある意味、支点をとってからビレイすればいい」です。登っているのがM井さんであり、補助みたいなビレイでしたが、しないよりした方がまし。でも、今回のビレイは特別だと思います。やっぱり、トップで登って、自分で支点を作成して、それで登る人をビレイです。その他、今回、自分はハーケンとハンマーを持って行きまして、そのハンマーで写真の所にある(M井さんが打込んだ)ハーケンを無事回収。
 |
8:35 滝(それとも二俣?) |
致し方ないですが、上の写真は滝を撮りたかったのか、二俣を撮りたかったのか、今となってはわかりません。おそらくは滝だと思うのですが…。慣れていない登攀リーダーのため、見苦しい点、ご了承ください。
| 8:40 流れている水が黄金色 |
 |
上の写真は、流れている水が黄金色に見える個所があったので撮りました。ですが、フラッシュがたかれ、黄金色は消え失せてしまいました。当然ですが、写真は「真実ではない」です。
 |
8:42 木々の間から北岳が |
| 8:43 この滝はどう通過? |
 |
この滝もどう通過したか忘れてしまいました。8時50分の休憩までに巻きを2回して、登るときはたいてい右だったとメモにあります。でも、その時のメモなのに、巻き2回という数字はあまり信頼性の高いものではありません。1回は確実に7時25分の滝ですが…
8:50 高度計で1770mの地点で休憩
 |
9:10 右だと思います |
9時10分の滝もそうですが、シレイ沢の滝の淵は流された花崗岩の砂利が淵にたまっていました。
| 9:15 連続する滝 |
 |
縦の写真で撮ってみました。今まで、写真は横!と思っていたのですが、確かに基本は横ですが、縦にした方が良い写真は縦の方が良いかもしれません。
 |

左が9:30の写真
上が左の写真の滝を右から巻いている途中に、撮ったもの9:35 |
| 9:50 再び木々の間から北岳 |
 |
 |
10:05 渓相も明るくなってきました |
10時5分の滝は右を行きました。下からは登れそうに見えたものの、登ってみるとどうも難しかった。下からリーダーが「登れるかー」聞いてくる。これに、どうも反射的に答えられない。「登れるか―」の主語は「全員」、自分だけじゃない。少しでも難しそうと思ったら、即「難しいです」と今後、答えよう。最後の上がる所だけが難しく、ロープを出してM井さんに登っていただきました。さらに上のマンントルする所で、右にも左にも「これ!」というホールドがなく、迷ってしまいました。実際には左から行った方が楽。迷っていたのは自分のみ。
| M井さんの作っていた、支点から離れた所でビレイするシステム |
 |
 |
10:30 早くこういう所でビレイができますように |
| 10:35 20mの滝 |
 |
20mの滝は巻いたはずです。今回、シレイ沢では巻き道がどこも踏み跡がしっかりしていました。でも、つかめるような笹、低木があまりないです。
10:45 標高2025m手前の二俣
 |
10:50 基本的に急ですが、こんななだらかな所もありました。 |
上の写真から、3分後の滝
右を行ったと |
 |
 |
10:55 20mの滝が見えてきました |
| 手前の滝を登るリーダー |
 |
 |

11:00 20mの滝(この滝は巻きました) |
20mの滝を過ぎて、今回のハイライトでもある、「白い花崗岩のスラブ+25mの滝」が見えてきました。時間的に余裕もあるので滝手前の平らな所で休憩です。
| 11:15 白い花崗岩のスラブ |
 |
 |
25m滝 |
11:20 白い花崗岩のスラブ手前で休憩
休憩と言っても元気なので、横になっているわけにもいかず、今のうちに写真をとっておこうということで、スラブと滝の写真を撮りに滝の近く(といってもスラブの下まで)まで行きました。「こんなもんだろう」という感じで、休憩している所に戻ると、リーダーより、「ルート偵察に行ってきたか?」とのこと。そこまで考えていなかったので、再度滝の近く(スラブの下)へ行き、ルートを偵察。スラブの下よりもさらに滝に近づくことも考えられましたが、一人での偵察なので、さらに近付くのは戻れないと困るのでそこまでにしました。ガイドブックには右から登ると書いてあったし、踏み跡のようなものが見えるから「スラブを登って左にトラバースすればいいだろう」との予測を立てました。下見は無事終わり、休憩も終わってさあ、出発!
| 北岳がどんどん姿を現してきました |
 |
 |
25mの滝 |
| 休憩地点と北岳 |
 |
 |
踏み跡?も見えるし、このラインで行けば |
12:05 出発
出発して、自分の思ったスラブの所を行くラインに進んでみたものの、皆さん来てくれません。自分の予想はハズレでした。踏み跡に見えたのは、気のせいだったのか。M井さんが選んだのは、滝の落ち口まで行ってそこから左を巻くルート。落ち口から右のルートは、踏み跡があるものの、「滑った時に、滑りを停めるような木がないからよくない」等言われて、左を登りました。踏み跡はあるにせよ、つかまる低木、笹等が少ないので、緊張。
 |
おおよそこのラインで |
| 12:35 滝の右を登った? |
 |
12:45 二俣(右を行きました)
 |
12:50 18mの滝 この滝は巻いたはずです |
18mの滝を上がった所で、ずいぶん沢幅が狭くなる。「水が汲めるうちにテン場を決定かな」等考えているうちに、見事なテン場登場
13:00 18m滝を上がった先をテント場とする(高度計の標高2230m)(下の大まかな図で2)
時間的に早いので別のよいテン場を探しに行きましたが、上のテン場は先行パーティーが使っていたので、結局この場所で一晩をすごすことが決定しました。相変わらず、他の方はテン場に着いてからの行動が速い、自分はと言えばスラブ手前で元気だったのでそれほどバテていないはずなのですが、テン場に着いた安心感からか、登攀リーダーの重圧か? どっと疲れが出てくる。他の方は薪を集めるのもうまく、どんどん集めてくる。せめて、明日の朝の焚き火用に、小さい小枝を集めておこう。夕食を食べ、7時頃に寝てしまいました。明日はS林さんだし、ゆっくり朝食、寝るのが早いし、4時頃にはいやでも起きるだろう。
| 今回のテン場 |
 |
 |
焚き火用の枯れ枝を採取 |
| 焚き火 |
 |
9月5日
天気:曇り時々晴れ、一時雨
それほど急ぎの山行ではないという安心からか、自分にはこれまでにないくらいぐっすり寝て(それでも3回ぐらい起きましたがすぐ寝てしまう)しまい、いつもなら3時くらいに目が覚めてそれからはじっと朝が来るのを待つのですが、目が覚めて辺りを見回すとS林さんと、F浦さんいません。4時30分だったでしょうか。二人はもう焚き火の前にいました。
 |
さあ、出発 |
6:55 テン場出発(高度計の標高は2205mになってました)
| 7:00 テン場に使えるかな |
 |
テン場を出発してから、水が枯れるまで、2、3個所テン場に使えそうな場所がありました。
 |
7:13 白根三山 |
ここいら辺はそれほど難しい滝もなく、昨日のリベンジもありトップを行くことに夢中になっていたら、下から「水枯れていない?」との声。しまった。
7:15 水枯れる(高度計の標高2305m)
| 水を汲まずに、小滝を上がってしまいました。水筒を下に落として、水を汲んでいただき受け取りました。 |
 |
 |
北岳 なんか重量感があります |
| 7:50 立ちはだかる枯れ棚 |
 |
水を汲んでから数か所、枯れ棚が立ちはだかりました。8時頃からか、明瞭な踏み跡が断続的にあるものの岩のない、急な登りとなりました。なお、けもの道もあり、踏み跡のみを信じると痛い目に遭います。つかまる低木は点々とあります。
8:20 高度計の標高2530mで休憩
「少し右側を行けば、砂礫地に出て、砂礫地と藪の際を進む」ということで前進。
9:00 砂礫地着(北岳・仙丈の見える地で立ち休み)
 |
砂礫地から見える仙丈岳(右奥) |
| 北岳 |
 |
 |
北岳を前に、立ち休み |
M井さん、Ta田さんらは、北岳を前に、話が尽きないようでした。
9:20 出発
落石をしないように、しないように、なんとかかんとか進みました。
| 砂礫地 |
 |
平坦な所に出て、少し右へ行った所で、無事登山道です。
9:25 登山道(下の大まかな図で3)(高度計の標高2685m)
 |
薬師岳 |
| この頃からガスが出てきて、北岳さようなら |
 |
この頃から、ガスが出てきて、展望は見れなくなりました。やっぱりアルプスの眺めが期待できるのは9時までか。沢装備を外して、出発です。
 |
今回の沢登りの大まかな地点
1.入渓地点
2.テン場
3.登山道に合流 |
10:00 出発
10:15 薬師岳山頂着(2780m)
| 薬師岳山頂 |
 |
登山道に出て、登攀リーダーの重圧から解放されたからか、自分はどんどん前に進めました。
 |
10:20 薬師岳小屋 |
| 巨岩が散在 |
 |
11:00 南御室小屋着・昼食(高度計の標高2365m)
 |
高校の頃と変わってないかもしれない |
高校の頃来た時は、クワガタがいた。
下写真・木から垂れ下がる苔のようなの
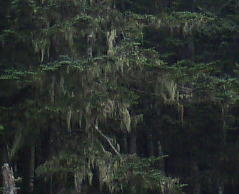 |
 |
鳳凰三山に来るのは、これが三度目、といっても今回は正確には鳳凰三山でないのですが…。高校1年の夏、初めての2泊3日のテント山行がここ鳳凰三山、あのころは今より体力がなくついていくだけで精いっぱいだった。ここ南御室小屋で泊った記憶がある。クワガタがいて、木から垂れ下がる苔のようなのが印象的だった。2度目は大学生の秋、ほとんど記憶にない。今回来て現在の所、10代、20代、30代と来ている唯一の山となりました。
11:30 出発
11:50 苺平
 |
苺平 |
12:35 杖立峠着
ここで少し雨が降ってきてどうなる事かと思いましたが、その後やみました。
13:05 出発
13:40 夜叉神峠
夜叉神峠小屋
鳳凰三山は、小屋に、昭和の感じがある小屋が多い |
 |
 |
夜叉神峠 |
14:25 夜叉神峠登山口(バス停)
14:50 出発(M井さん車)
自分が、甲府駅のコインロッカーに荷物を置いてきてしまったため、甲府駅解散となりました。
昨年もそうでしたが、メンバーとしては問題なく行けるようになってきたので、リーダーに手を出したところ、その次の山行は一つ一つが怖かった。今回といえば、その前に沢単独行をしていて、そのせいもあってか一つ一つが怖かったというのは少しはありました。
戻る
![]() (親睦沢登り)
(親睦沢登り)