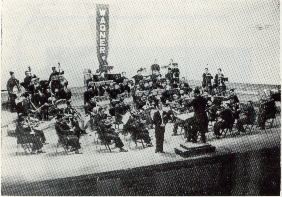声楽家 増永丈夫
《新人演奏会》
 昭和八年、四月、二十七日、春の楽壇を飾る読売新聞社主催の新人演奏会が日比谷公会堂で開催された。藤山は母校の東京音楽学校を代表してこの演奏会に出演している。東京音楽学校からは、、声楽において、異例の二人を出場させた。バリトンの増永丈夫とソプラノの長門美保である。藤山は、この演奏会では、レーベ作曲の《詩人トム》をバリトン独唱している。 この曲は、ドイツの文豪フォンタネ−がスコットランド古謡をもとに作った詩を作曲したものである。詩人トムが古城のほとりで寝ているところへ、白馬の乗った貴婦人があらわれる。トムは七年間下僕になることを約束して、くちずけをして二人は森の奥深く歩んでいく。その白馬の蹄の音、たて髪にむすばれた鈴の音が優雅な色彩を感じさせ、聞き手を夢幻的おとぎの世界に誘い込む、という内容の歌である。会場は溢れんばかりの聴衆で埋まっている。<Der Rei mer Tho-mas lag Bach am Kie sel-bach bei Hunt-ley>と増永丈夫の華麗なテノールを思わせるような美しいハイバリトンがホールいっぱいに響く。澄んだ美しい響きだ。よく洗練された高音から低音までコントロールされ、発声に無理がないので音質が柔らかい。芯のある強靭さのなかに優美なデリケートさを失わない音色。幻想的優雅な旋律をレガートに歌う歌唱は、パストラルの世界へと導くのである。当時の日本の楽壇は、柔らかく美しくハリのあるバリトン歌手がいよいよ登場したことに大きな期待を寄せたのだった。恩師プリングスハイムに「美しい、しかも訓練されたバリトン」と絶賛された増永丈夫は、彼が指揮する演奏会では欠かせな存在だった。プリングスハイム指揮で東京音楽学校主催の演奏会が日比谷公会堂で行われた。注目のベートーベンの《第九》である。いよいよ、本格的に日本楽壇注目の舞台に増永丈夫のバリトンが登場した。
昭和八年、四月、二十七日、春の楽壇を飾る読売新聞社主催の新人演奏会が日比谷公会堂で開催された。藤山は母校の東京音楽学校を代表してこの演奏会に出演している。東京音楽学校からは、、声楽において、異例の二人を出場させた。バリトンの増永丈夫とソプラノの長門美保である。藤山は、この演奏会では、レーベ作曲の《詩人トム》をバリトン独唱している。 この曲は、ドイツの文豪フォンタネ−がスコットランド古謡をもとに作った詩を作曲したものである。詩人トムが古城のほとりで寝ているところへ、白馬の乗った貴婦人があらわれる。トムは七年間下僕になることを約束して、くちずけをして二人は森の奥深く歩んでいく。その白馬の蹄の音、たて髪にむすばれた鈴の音が優雅な色彩を感じさせ、聞き手を夢幻的おとぎの世界に誘い込む、という内容の歌である。会場は溢れんばかりの聴衆で埋まっている。<Der Rei mer Tho-mas lag Bach am Kie sel-bach bei Hunt-ley>と増永丈夫の華麗なテノールを思わせるような美しいハイバリトンがホールいっぱいに響く。澄んだ美しい響きだ。よく洗練された高音から低音までコントロールされ、発声に無理がないので音質が柔らかい。芯のある強靭さのなかに優美なデリケートさを失わない音色。幻想的優雅な旋律をレガートに歌う歌唱は、パストラルの世界へと導くのである。当時の日本の楽壇は、柔らかく美しくハリのあるバリトン歌手がいよいよ登場したことに大きな期待を寄せたのだった。恩師プリングスハイムに「美しい、しかも訓練されたバリトン」と絶賛された増永丈夫は、彼が指揮する演奏会では欠かせな存在だった。プリングスハイム指揮で東京音楽学校主催の演奏会が日比谷公会堂で行われた。注目のベートーベンの《第九》である。いよいよ、本格的に日本楽壇注目の舞台に増永丈夫のバリトンが登場した。
《ベートーヴェンの第九》
昭和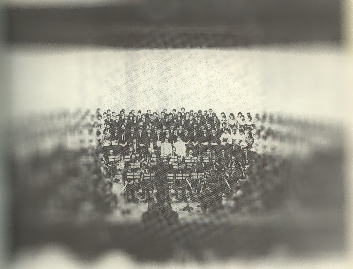 八年、六月十八日、日比谷公会堂で東京音楽学校第六十七回定期演奏会が催された。この演奏会では、ベートーベンの曲が中心で、前半は、東京音楽学校管弦楽部とロベルト・ポラックのバイオリン独奏で、オーケストラ『レオノーラ』序曲第三番とバイオリン独奏《ロマンス》ヘ長調作品第五十、後半が《第九交響曲》である。中でもこの《第九交響曲》が話題を呼んだ。というのは、六月、十七日に近衛秀麿指揮で新交響楽団がベートーベンの《第九》を演奏したので、官立と民間の第九の共演として注目されたからである。指揮は、クラウス・プリングスハイム。独唱、添川はな(ソプラノ)丹治はる(アルト)薗田誠一(テノール)増永丈夫(バリトン)管弦楽、東京音楽学校管弦学部員 合唱、東京音楽学校生徒であった。第一楽章、第二楽章、第三楽章と進行していよいよ「歓喜の主題」である第四楽章に入る。そして、増永丈夫のバリトンがたくましく
八年、六月十八日、日比谷公会堂で東京音楽学校第六十七回定期演奏会が催された。この演奏会では、ベートーベンの曲が中心で、前半は、東京音楽学校管弦楽部とロベルト・ポラックのバイオリン独奏で、オーケストラ『レオノーラ』序曲第三番とバイオリン独奏《ロマンス》ヘ長調作品第五十、後半が《第九交響曲》である。中でもこの《第九交響曲》が話題を呼んだ。というのは、六月、十七日に近衛秀麿指揮で新交響楽団がベートーベンの《第九》を演奏したので、官立と民間の第九の共演として注目されたからである。指揮は、クラウス・プリングスハイム。独唱、添川はな(ソプラノ)丹治はる(アルト)薗田誠一(テノール)増永丈夫(バリトン)管弦楽、東京音楽学校管弦学部員 合唱、東京音楽学校生徒であった。第一楽章、第二楽章、第三楽章と進行していよいよ「歓喜の主題」である第四楽章に入る。そして、増永丈夫のバリトンがたくましく
<O Freunde
nicht diese Tone !Sondern Last uns angenebmere anstimmen und fredenvollere! おお、友よ、この調べではない、さらに快く、より喜びにあふれた歌をうたおうではないか、>
とレチタティーヴォ風に歌い、その声は日比谷公開堂に響きわたった。明治近代以降、洋楽が受容されてから、ようやく美しい響きで歌う声楽家が登場したのである。まさに近代日本洋楽受容の所産であった。この増永丈夫のバリトンを聴いた人は、まさかマイクロホォンにメッツァヴォーチァで歌うクルーン唱法で《酒は涙か溜息か》をレコードに吹き込んだ藤山一郎とは誰も信じなかったであろう。 第四楽章の最初のバリトンのソロは、レチタティーヴォ風に独唱するが、レチタティ−ヴォとは語源は朗読という意味で、叙唱・歌劇・オラトリオなどの中で、物語りの進行や状況の説明などをする「語り」唱法で、言葉と歌の中間的なものである。藤山がレチタティーヴォ風にしっかりとオ−ソドックスに歌った。この叙唱がもつ特質を自然な言葉のリズム。アクセント、抑揚を見事に表現したのだ。詩人であり作詩家でもある藤浦洸は、藤山の《第九》のバリトン独唱を聴いて感銘を受けた聴衆の一人であった。藤浦は、こうのべている。
「私は彼から切符をもらって客席にいた。藤山は、増永丈夫の名で、そのコワイヤのバリトン・パ−トを受け持ってさっそうと立った。第四楽章にはいって。チェロのソロがあり、つづいて『おおフロ−ト』という、たくましい藤山のソロが始まった。なんという堂々たる声楽家ぶりであっただろう。」( 『なつめろの人々』)
藤浦は、この増永丈夫の独唱を聴いて内心こう思った。こういうクラシックをりっぱに歌える人が何人も出てきて流行歌を唄ったら、もっと素晴らしい音楽ができるだろうと。ベートーベンの《第九》のバリトン独唱を見事にこなしたことは、完全に「アートソング」の増永丈夫と「大衆音楽」の藤山一郎を完全に分業させ、どちらの分野でも卓越した実力があることを十分に示したといえる。そして、バリトン増永丈夫はいよいよラジオ放送にも登場し、声の悦楽を堪能させるハイバリトンは全国に流れるのである。
《増永丈夫の声価》
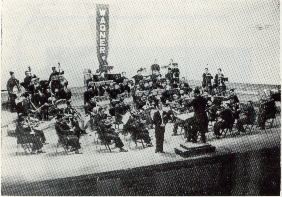 昭和八年、九月、二十日、「世界民謡しらべ」というNHKラジオ番組で、ベートーベンの作品にしては非常の珍しいベートーベン編曲のアイルランド、ウエールズ、スコットランドの民謡が特集された。出演者は、東京音楽学校出身者の若手の演奏家が中心。ピアノ川上良武、バイオリン大岡運英、チェロ小沢弘、独唱者は、四家文子(アルト)、岩谷廣子(ソプラノ)、薗田誠一(テノール)、増永丈夫(バリトン)、1 ソプラノ・テナー・バリトン三重唱《羊飼いの歌》2 アルト独唱《いとしのジョニー》《元気な若者》《山の若者》3 テナー、バリトン二重唱《狼狩り》4 ソプラノ独唱 《あ〜私のパトリックを愛することができるなら》5 ソプラノ、アルト、バリトン三重唱 《チャーリー》6 テナー独唱 《魔女よさようなら》7 ソプラノ、アルト二重唱 《見よ青ずむ森を》 8 バリトン独唱 《さまよへる歌人》 《アイルランド気質》9 ソプラノ、アルト、テナー、バリトン四重唱 《小舟は滑かにすべりゆく》。藤山は、音楽性豊かに聴衆に語りかけるような甘美な唱法できれいに歌ったそうである。ファルセットのように柔らかく、それでいて芯のある声と端正な歌唱は絶賛された。これには、幼いころ帝劇で聴いたイギリスのテナー・ジョンマッコ−マックの歌が大分影響している。少年時代の藤山の耳に残っていた当時の外人声楽家といえば、ショーマンハインク、ガリクルチである。そして、昭和十年代に入ってシャリアピンなどが日本へ来て歌った。これらの声楽家のプログラムは、ほとんどがオペラのアリアなど、いわゆる大曲で構成されていた。しかし、ジョンマッコーマックはアイルランド民謡などの小品ばかりを歌った。声帯を鳴らし、大向うを唸らせるようなものではなく、音楽性豊かな佳曲を、聴衆に語りかけるような甘美な唱法で、きれいな響きで歌った。マッコマークの声量は小さいが極めて情緒的な歌唱に藤山は陶酔した。少年時代の感動を藤山は忘れていなかった。 その年の十月に日比谷公会堂で《藤山一郎と増永丈夫の会》という音楽会が開催され多くの聴衆を集めた。藤山の初リサイタルである。ここにジャズ・流行歌とクラシックの融合が見られた。 『藤山一郎・増永丈夫の会』、日時、十月九日、(月)午後七時、場所 日比谷公会堂 第一部 詠唱と歌謡曲の二重唱 一 詠唱 1グノ−作曲《ファストのヴレンテン》、2ロルツイング作曲《密猟者の歌》二 歌謡曲 1ブラームス作曲《思い》2シューベルト作曲《小夜曲》3プリングスハイム作曲《願い》4シューマン作曲《放浪の歌》三 二重唱 ヴェルディ作曲《椿姫》ヴィオレッタ(中村淑子)ヂェルモン(増永丈夫)第二部 ジャズと流行歌、第三部 音楽スッケッチ《僕の青春》、賛助 クラウス・プリングスハイム、中村淑子(ソプラノ)、小林千代子(ソプラノ)、徳山鑅(バリトン)
昭和八年、九月、二十日、「世界民謡しらべ」というNHKラジオ番組で、ベートーベンの作品にしては非常の珍しいベートーベン編曲のアイルランド、ウエールズ、スコットランドの民謡が特集された。出演者は、東京音楽学校出身者の若手の演奏家が中心。ピアノ川上良武、バイオリン大岡運英、チェロ小沢弘、独唱者は、四家文子(アルト)、岩谷廣子(ソプラノ)、薗田誠一(テノール)、増永丈夫(バリトン)、1 ソプラノ・テナー・バリトン三重唱《羊飼いの歌》2 アルト独唱《いとしのジョニー》《元気な若者》《山の若者》3 テナー、バリトン二重唱《狼狩り》4 ソプラノ独唱 《あ〜私のパトリックを愛することができるなら》5 ソプラノ、アルト、バリトン三重唱 《チャーリー》6 テナー独唱 《魔女よさようなら》7 ソプラノ、アルト二重唱 《見よ青ずむ森を》 8 バリトン独唱 《さまよへる歌人》 《アイルランド気質》9 ソプラノ、アルト、テナー、バリトン四重唱 《小舟は滑かにすべりゆく》。藤山は、音楽性豊かに聴衆に語りかけるような甘美な唱法できれいに歌ったそうである。ファルセットのように柔らかく、それでいて芯のある声と端正な歌唱は絶賛された。これには、幼いころ帝劇で聴いたイギリスのテナー・ジョンマッコ−マックの歌が大分影響している。少年時代の藤山の耳に残っていた当時の外人声楽家といえば、ショーマンハインク、ガリクルチである。そして、昭和十年代に入ってシャリアピンなどが日本へ来て歌った。これらの声楽家のプログラムは、ほとんどがオペラのアリアなど、いわゆる大曲で構成されていた。しかし、ジョンマッコーマックはアイルランド民謡などの小品ばかりを歌った。声帯を鳴らし、大向うを唸らせるようなものではなく、音楽性豊かな佳曲を、聴衆に語りかけるような甘美な唱法で、きれいな響きで歌った。マッコマークの声量は小さいが極めて情緒的な歌唱に藤山は陶酔した。少年時代の感動を藤山は忘れていなかった。 その年の十月に日比谷公会堂で《藤山一郎と増永丈夫の会》という音楽会が開催され多くの聴衆を集めた。藤山の初リサイタルである。ここにジャズ・流行歌とクラシックの融合が見られた。 『藤山一郎・増永丈夫の会』、日時、十月九日、(月)午後七時、場所 日比谷公会堂 第一部 詠唱と歌謡曲の二重唱 一 詠唱 1グノ−作曲《ファストのヴレンテン》、2ロルツイング作曲《密猟者の歌》二 歌謡曲 1ブラームス作曲《思い》2シューベルト作曲《小夜曲》3プリングスハイム作曲《願い》4シューマン作曲《放浪の歌》三 二重唱 ヴェルディ作曲《椿姫》ヴィオレッタ(中村淑子)ヂェルモン(増永丈夫)第二部 ジャズと流行歌、第三部 音楽スッケッチ《僕の青春》、賛助 クラウス・プリングスハイム、中村淑子(ソプラノ)、小林千代子(ソプラノ)、徳山鑅(バリトン)
藤山は、当時の『音楽新聞』(昭和八年十月一日)においてつぎのようなこのリサイタルに臨む決意をつぎのようにのべた。
「今度プリングスハイム氏の応援を得て、大衆の耳にクラシックなものを入れたいと思っています。大衆音楽にクラシックなものを取り入れられ、そして、成功したら僕として幸甚の至です」
この言葉には、クラシックを世俗化し、芸術音楽と大衆音楽の垣根を越えることによっクラシックの素晴らしさを普及させようとする藤山の情熱が見られる。これが、藤山一郎の歌唱の精神の原点でもある。その藤山の狙いを充分に汲んだプリングスハイムは、「増永丈夫讃」と題してして芸術家としての輝かしい門出を祝してつぎのような一文を『音楽新聞』に寄せている。
「増永君は声と個性に於て類希な才能に恵まれている。今同君はその才能を世界有数の大演奏会場で示そうとしている。彼の美しい、しかも充分訓練されたバリトンは、その無理のない、磨きのかかったテクニックは、そして又彼の真に芸術家としての素質は、日比谷公会堂に集まる数千の聴衆に心からの悦びを與へ、同時にその中に新しい友人を獲得するであろう事を信じて疑はない。これは大変六ケ敷い事なので誰にでも出来るといふわけには行かない。私は永年に渉り職業上澤山の声楽家と近しくして来たが、この若い日本人の如く心から音楽的でありどこまでも音楽家である人には殆出会ったことがない。増永君は僅か数カ月前に音楽学校を卒業しただけで已に今日充分出来上がった芸術家として聴衆にまみえる事が出来るまでになっている。」
第一部はバリトン歌手増永丈夫が恩師クラウス・プリングスハイムのピアノ伴奏でドイツ歌曲を独唱。特にプリングスハイムをして「増永君の如く欧州の四ケ国語に渉って歌い得る歌手はそうたくさん知らない。彼が独逸歌謡を歌う場合には、すっかり言葉をマスターしていて、その発音と意味とは実にぴったり一致している。」と言わしめた語学力と歌唱テクニックを存分に披露している。第二部では、増永丈夫が藤山一郎に早変わりし当時日本最高のバンドマンで編成したビクター管弦楽団の演奏でジャズと流行歌の共演、第三部では、ガソリンスタンドを舞台に『僕の青春』というテーマで和製ミュージカルで最後を締めくくっている。)この演奏会は、充実した内容だった。作品の統一された精神性を鑑賞しようとするクラシック志向と快く響く感性体験のポピュラ−志向の聴衆は、演奏空間において一体化した。この演奏会について月刊楽譜22巻12月号の「晩秋独誌」の欄では、「流行歌の寵兒藤山一郎君は、藤山一郎と増永丈夫の会を催し、一人二役を演じ、増永丈夫としては歌劇曲とリートを歌ひ、藤山一郎は流行歌を歌ひ、オペレッタを演じた。然かもマイクロフォンを通して流行歌を効果的に歌ったことは独唱会に一つの革命をもたらしたものといへる」とその斬新な試みが絶賛されている。藤山は、マイクの有無にかかわりなく、歌は、「響き」で歌うことをよく知っているので、発声のフォームは一緒でも、共鳴のさせかたを変えれば可能なのである。共鳴をフルに使って声量をたっぷり歌うかか、軽く響きを電気にのせるかの違いにすぎないのだ。藤山一郎はすでに時代の先を読んでいた。サウンド文化が進歩した今日では、エレクトロニクスによる電子音楽とナチュラルな音、アコステックなサウンドとの違いはあたりまえであるが、昭和の初期にすでに二つの音楽作品の成立を予想し、それを実演してみせるのだから驚きである。文明の利器の登場によるオーケストレーションの変化、アレンジ、舞台構成の多様化の到来、新しい音楽文化の成立と未来に目を向けていたのだ。
《バリトン歌手の真価》
昭和九年は、当時日本の楽壇をさわがせたプラーゲ問題が解決して外国の新しい現代楽曲がふんだんに聴けるようになった。プラーゲとは、昭和六年に来日したドイツの法律家で、万国著作権協会の東洋代理人を努めていた。彼は、麻布に事務所をかまえて日本における外国人作曲家の作品演奏にたいする著作権料取り立てという業務を行い、当時、著作権という概念などなかった日本の楽壇におおきな波紋を投げかけた。その問題解決後、放送のトップを切って、コロナ・オーケストラの管絃楽(篠原正雄・指揮)の演奏と藤山一郎の独唱がNHKラジオから放送された。やはり、ここにもジャズとクラシックの融合が見られるのである。
1、管絃楽 《ボレロ》ラヴェル作曲。2、独唱 《想い出の歌》アルトマン作曲。《ペールムーン》ローガン作曲。3、管絃楽 《船唄》ネーヴィン作曲。4、独唱、合唱、《フォスター名曲集》
この放送では、芸術歌曲を独唱するバリトン歌手増永丈夫ではなく大衆歌謡のテナ−藤山一郎として出演している。芸術を大衆化した藤山一郎でクラシックの素晴らしさち感性に快く響くポピュラーの楽しさを作品として提供したのである。最初の曲の《ボレロ》は、古くはスペインにあったぶ舞曲の名前であったが、その名前は現代フランスの代表的作曲家モーリス・ラヴェルの作曲のそれによって人々の記憶に蘇った。この曲は、当時ジョーライト主演のジトーキー映画の主題曲として使用されていたので、ジャズ風に編曲され心浮き立つような陽気な調べを表現している。最後の『フォスター名曲集』は、コロナ・オーケストラが以前発表した『フォスター名曲集』の第一集からもれた名曲を蒐めて独唱と管弦楽に編曲し、「魂の音楽」ともいうべきフォスターの美しい旋律を綴った幻想曲である。昭和九年十二月十六日、第七十三回東京音楽学校の定期演奏会で、プリングス・ハイムの指揮でわが国初演のヴェルディの《レクイエム》が演奏された。《レクィエム》は、『鎮魂曲』と訳すが、原曲名は『Misaa da Requiem』とって死者のための追悼のミサ曲。これは、ヴェルディの友人である詩人マンツオーニの一周忌のために作曲された。この初演はヴェルディの指揮で、1847年、ミラノのサン・マルコ寺院において管弦楽付き大合唱で行われている。数多くの華麗な歌劇を作曲したヴェルディは晩年宗教音楽を作曲した。このヴェルディの大曲が昭和のヒトけたの時代に演奏されたことは、日本楽壇史上特筆すべきことである。独唱者に藤山一郎はバスを受け持っている。この時の独唱者の評価については『朝日新聞』に山根銀二の批評がつぎのように掲載されている。
「若い独唱が稍々のぼせ気味で総練習のときの自信に充ちた歌いぶりが再現されなかったのは残念だが、老大家に比して遜色ない力量を示した事は力強い。就中、中村、丹治両嬢の出来栄えを賞する。丹治嬢の或る発声に現れた歪みが耳についた。増永氏は確実だが、声質が此曲のバスに求められる荘重な味にそぐわなかったのは惜しい」(『批評から見た音楽二十年』)
この批評でのべられている「確実」とは低音の安定度、「惜しい」とは音色の不適格をしめしている。プリングスハイムは、当時の音楽レベルの低い日本人のバス歌手よりも、音色こそ荘厳ではないが、この大曲を成功させるために、藤山の音楽センスとバスの音域まで安定して発声できる低音の確実性に期待したのである。この安定度があるからこそ古賀メロディーなどの流行歌をヒットさせる一因でもあった。
昭和十三年十月十一日、、NHKラジオに声楽家増永丈夫で独唱した。《蒼い月》《永遠の誓い》《セレナード》などのポピュラー歌曲を中心に放送された。昭和十四年四月二十七日、日比谷公会堂でオール日本新人演奏会を記念するコンサートが開かれた。新人演奏会によって世に送り出され楽壇の今日を背負う第一線の代表的音楽家が総出演し最高水準の演奏を披露した。増永丈夫はヴェルディーのアリアを独唱した。ヴェルディーの高いバリトンの音域をものともせず、低音の安定度も十分にみせ芸術歌手の貫禄をみせた。テイチクで再び古賀政男とのコンビでヒットを量産後、本来の藤山一郎とクラシックの増永丈夫の二刀流に戻った。昭和十五年四月十四日、NHKラジオでマンフレット・グルリット指揮のベートーベンの《第九》が放送された。増永丈夫のバリトン独唱が放送され感銘をあたえた。増永の確実な歌唱はグルリットから賞賛を受ける。テノール・木下保、ソプラノ・関種子、アルト・竹本光江、合唱・日本放送合唱団、管弦楽・日本放送交響楽団。クラシックの増永丈夫の力量をいかんなく発揮した。昭和十五年コロムビア十月新譜の国民歌謡の名曲《旅愁》では増永丈夫で吹込んだ。テノールの美しい響きをいかしたハイバリトンによる名唱盤である。
この内容に関する著作権は、菊池清麿(近代日本流行歌史研究)にあり無断転載を禁じます。
Copyrights(C)2003 Kikuchi Kiyomaro.
all rights reserved.
藤山一郎歌唱の精神へ
 昭和八年、四月、二十七日、春の楽壇を飾る読売新聞社主催の新人演奏会が日比谷公会堂で開催された。藤山は母校の東京音楽学校を代表してこの演奏会に出演している。東京音楽学校からは、、声楽において、異例の二人を出場させた。バリトンの増永丈夫とソプラノの長門美保である。藤山は、この演奏会では、レーベ作曲の《詩人トム》をバリトン独唱している。 この曲は、ドイツの文豪フォンタネ−がスコットランド古謡をもとに作った詩を作曲したものである。詩人トムが古城のほとりで寝ているところへ、白馬の乗った貴婦人があらわれる。トムは七年間下僕になることを約束して、くちずけをして二人は森の奥深く歩んでいく。その白馬の蹄の音、たて髪にむすばれた鈴の音が優雅な色彩を感じさせ、聞き手を夢幻的おとぎの世界に誘い込む、という内容の歌である。会場は溢れんばかりの聴衆で埋まっている。<Der Rei mer Tho-mas lag Bach am Kie sel-bach bei Hunt-ley>と増永丈夫の華麗なテノールを思わせるような美しいハイバリトンがホールいっぱいに響く。澄んだ美しい響きだ。よく洗練された高音から低音までコントロールされ、発声に無理がないので音質が柔らかい。芯のある強靭さのなかに優美なデリケートさを失わない音色。幻想的優雅な旋律をレガートに歌う歌唱は、パストラルの世界へと導くのである。当時の日本の楽壇は、柔らかく美しくハリのあるバリトン歌手がいよいよ登場したことに大きな期待を寄せたのだった。恩師プリングスハイムに「美しい、しかも訓練されたバリトン」と絶賛された増永丈夫は、彼が指揮する演奏会では欠かせな存在だった。プリングスハイム指揮で東京音楽学校主催の演奏会が日比谷公会堂で行われた。注目のベートーベンの《第九》である。いよいよ、本格的に日本楽壇注目の舞台に増永丈夫のバリトンが登場した。
昭和八年、四月、二十七日、春の楽壇を飾る読売新聞社主催の新人演奏会が日比谷公会堂で開催された。藤山は母校の東京音楽学校を代表してこの演奏会に出演している。東京音楽学校からは、、声楽において、異例の二人を出場させた。バリトンの増永丈夫とソプラノの長門美保である。藤山は、この演奏会では、レーベ作曲の《詩人トム》をバリトン独唱している。 この曲は、ドイツの文豪フォンタネ−がスコットランド古謡をもとに作った詩を作曲したものである。詩人トムが古城のほとりで寝ているところへ、白馬の乗った貴婦人があらわれる。トムは七年間下僕になることを約束して、くちずけをして二人は森の奥深く歩んでいく。その白馬の蹄の音、たて髪にむすばれた鈴の音が優雅な色彩を感じさせ、聞き手を夢幻的おとぎの世界に誘い込む、という内容の歌である。会場は溢れんばかりの聴衆で埋まっている。<Der Rei mer Tho-mas lag Bach am Kie sel-bach bei Hunt-ley>と増永丈夫の華麗なテノールを思わせるような美しいハイバリトンがホールいっぱいに響く。澄んだ美しい響きだ。よく洗練された高音から低音までコントロールされ、発声に無理がないので音質が柔らかい。芯のある強靭さのなかに優美なデリケートさを失わない音色。幻想的優雅な旋律をレガートに歌う歌唱は、パストラルの世界へと導くのである。当時の日本の楽壇は、柔らかく美しくハリのあるバリトン歌手がいよいよ登場したことに大きな期待を寄せたのだった。恩師プリングスハイムに「美しい、しかも訓練されたバリトン」と絶賛された増永丈夫は、彼が指揮する演奏会では欠かせな存在だった。プリングスハイム指揮で東京音楽学校主催の演奏会が日比谷公会堂で行われた。注目のベートーベンの《第九》である。いよいよ、本格的に日本楽壇注目の舞台に増永丈夫のバリトンが登場した。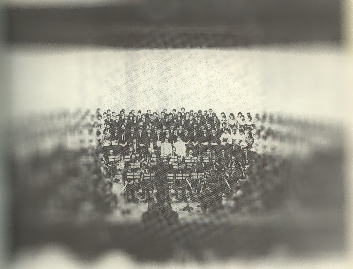 八年、六月十八日、日比谷公会堂で東京音楽学校第六十七回定期演奏会が催された。この演奏会では、ベートーベンの曲が中心で、前半は、東京音楽学校管弦楽部とロベルト・ポラックのバイオリン独奏で、オーケストラ『レオノーラ』序曲第三番とバイオリン独奏《ロマンス》ヘ長調作品第五十、後半が《第九交響曲》である。中でもこの《第九交響曲》が話題を呼んだ。というのは、六月、十七日に近衛秀麿指揮で新交響楽団がベートーベンの《第九》を演奏したので、官立と民間の第九の共演として注目されたからである。指揮は、クラウス・プリングスハイム。独唱、添川はな(ソプラノ)丹治はる(アルト)薗田誠一(テノール)増永丈夫(バリトン)管弦楽、東京音楽学校管弦学部員 合唱、東京音楽学校生徒であった。第一楽章、第二楽章、第三楽章と進行していよいよ「歓喜の主題」である第四楽章に入る。そして、増永丈夫のバリトンがたくましく
八年、六月十八日、日比谷公会堂で東京音楽学校第六十七回定期演奏会が催された。この演奏会では、ベートーベンの曲が中心で、前半は、東京音楽学校管弦楽部とロベルト・ポラックのバイオリン独奏で、オーケストラ『レオノーラ』序曲第三番とバイオリン独奏《ロマンス》ヘ長調作品第五十、後半が《第九交響曲》である。中でもこの《第九交響曲》が話題を呼んだ。というのは、六月、十七日に近衛秀麿指揮で新交響楽団がベートーベンの《第九》を演奏したので、官立と民間の第九の共演として注目されたからである。指揮は、クラウス・プリングスハイム。独唱、添川はな(ソプラノ)丹治はる(アルト)薗田誠一(テノール)増永丈夫(バリトン)管弦楽、東京音楽学校管弦学部員 合唱、東京音楽学校生徒であった。第一楽章、第二楽章、第三楽章と進行していよいよ「歓喜の主題」である第四楽章に入る。そして、増永丈夫のバリトンがたくましく