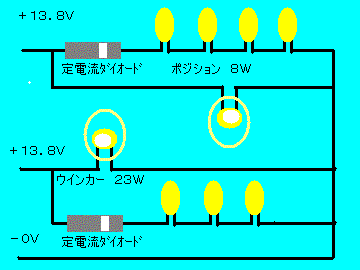フロント・ウインカーの強化
第一章 はじめに
はじめに、「フロント・ウインカーの強化」に入る前に、ここに至るまでの過程についてお話しします。
皆様もご存知のように、FDのエンジンルームは、熱しやすいですよね?
設計的にもロータリーは熱放出量が高いエンジンだから、特にこの傾向が強いみたいです。
その理由は様々考えられますが、ボンネットを低く設定した関係で、熱気は上昇したいのに、エンジンとのクリアランスが
狭いため、逃げ場無く滞留するのではないか?と考えました。
もちろんエアロボンネットからも抜けますが、そのほとんどがラジエターの熱気でしょう!!
当然このままでは、エンジンルームのエアクリは、熱せられた「酸素」を吸うことになります。
ここに注目です!!
現状では、始動中であれば永久に発生する熱気を、エンジンルーム
に充満させて、その一部を放出しているのにすぎないのではないでしょうか?
つまり一番言いたい事は、フレッシュ・エアを入れなければ、いくら熱気を抜いたと
しても、エンジンルーム全体の温度は下げられないだろうということです。
また、フレッシュ・エアの導入目的は、吸入温度を下げる目的だけではありません。
ナビ側からのフレッシュ・エアは、出来るだけ「プラグ部」に当てたいと考えています。
マツダいわく、この辺りを冷やすと、パワーが安定するとのことです。

非常に前置きが長くなりましたが、フレッシュ・エアを取り入れる場所として、熱の影響を受けないウインカー部を小型化することで、
そこから導入させようとしたのがきっかけでした。
ここはGTマシンの初期の頃や、ポルシェ964のオプションにもここに開口部がありましたし、小型化となれば、軽量化にもつながる
でしょう!!
さらに、ウインカーはオーバーハング突端のパーツなので、走行性能にも少なからず影響を与えるのではないでしょうか?
以上の一石二鳥を狙ってかなり前に装着したパーツですが、実際には照度がイマイチに感じられてしかたありません。
このままガマンするのは、カラダに毒です。
そこでLEDを利用して、照度を「補おう!!」と考えたのが、このページです。
★ フレッシュ・エア導入について追記 ★
空気導入については、現時点ではまだまだ私の求める理想ではありません。
結論から言うと、ウインカー小型化による、この部分からの走行風導入は、サーキット走行等でかなりスピードを出さないと
空気が入らないようです。そのため、公道での装着はあまりお勧め出来ません。
※なにしろ、このパーツは自己満足で作成したものですから!!
オリジナルのデザインが好きなので、あまり触りたくないのですが、今後の改良点として、開口部の淵を盛り上げて、横や上に逃げる
空気を捕まえられるようにしたいと考えています。
その時は、「新たなる構想」として、ここで紹介出来ると思いますので、それまでお待ち
頂ければ幸いです。

第二章 オリジナルとの比較
右の画像が小型ウインカーのアップです。
バイクの汎用品を流用したもので、自分好みのクリアレンズで、点灯させればオレンジに発光するタイプです。
予備を購入しようと、このバルブの金額を調べたんですが、ビックリ!!特注なのか、一個2千円以上するんです!
絶対に破損は許されません!!
車体側との接続ですが、後々抜き差しが簡単なように純正のカプラーを流用しました。
さらにテストがしやすいように、カプラーの手前を「ギボシ」で接続するようにしました。
後述しますが、後々発覚したトラブルは、このカプラーが問題だったのですが ・ ・ ・

RE雨宮製のADフェイシャーN1(オリジナル)との比較です。
さすが、バイク用の中でも小型の部類に入るだけあります。
前面投影面積なら、5分の1位しかありません。
基本データの比較
| 項 目 | ウインカー | ポジション | 重 量 |
|---|
| 純 正 | 21W | 5W | ? g |
| フェイシャーN1 | 21W | 5W | 150g |
| 小型ウインカー | 23W | 8W | 90g |

「純正」の重量は計量していないので正確な数値は判りませんが、おそらく「フェイシャーN1」と同等か、若干重い位だと思います。
軽量化に関しては、2個でわずか120gしかありませんが、突端部分ということで少しは改善されると信じています。
あと意外だったのが、暗いと感じた「小型ウインカー」のワット数が、オリジナルよりも明るいということです。
これは、レンズ面積の違いなのではないか?と予想しました。
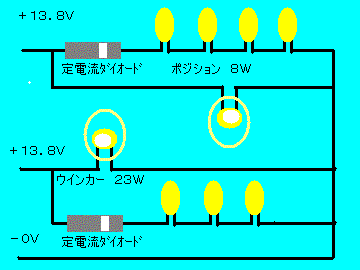
第三章 LED回路図の考察
それでは、暗さを補うために、どのようにLEDで強化するか考えます。
回路を考える前提として、既存のバルブを抜いてしまうと、ハイフラッシャー状態になることが予想出来たので、バルブを併用すること
にします。
今回使用する「超高輝度LED」の特性は以下の通りです。
無色透明タイプで発光すると黄色に点灯するタイプです。
黄色(超高輝度)
TLYH180P 8000mcd 波長590nm
直径5mm 2.1V 20mA 指向特性8度
LEDの数は、バルブの周りに配置することを考えると、7個入れられそうです。
その配分は、ウインカーもポジションも暗いので、ポジション4個、ウインカー3個に分けます。
尚、このバルブはダブル球を使用しているので、回路図ではわかりやすく2個表示しておきます。
その結果が、このような回路図となりました。
この回路の特徴として、並列にバルブとLEDをつないでいるので、4線のいずれかで断線があっても、他方側で点灯できるところです。

第四章 回路の作成と装着
まず一番デリケートな「定電流ダイオード」の固定方法をいろいろ考えた結果、左の画像のようにしました。
これは、ダイオードに直付けだと引っ張り強度に負けて破損してしまう可能性があるため、土台が必要だと感じられたからです。
これを2つ、ウインカーボディに内臓させるのはかなり厳しく、コードも通常よりも細い「0.5sq」コードを使用することにしました。
しかも余分なコードがあると収まらないので、ハンダでつなぎながらの配線となりました。
これが量産するとなれば、外に出すところですが、ワン・オフのこだわりで頑張りました。

これがLED回路の正面です。
ユニバーサル基盤をウインカーに合わせて削りました。
レンズカバー取り付けビスの逃げ部分が1mm位とかなり薄いので、振動で割れないかちょっと心配です!!
あと、LED間に隙間があるところは、裏側に配線がきているので、仕方なく抜けてしまっています。
理想を言えば、ひまわりのように埋め尽くせれば美しいのですが ・ ・ ・

これがLED回路の裏側です。
かなり配線が密集していて、自分的には限界かな?
この裏側が、ウインカーボディのアースとショートしないように絶縁が必要です!!

これが仮にセットして、点灯した状態です。
ここでの注意点は、ウインカーボディ全体がアースとなっているので、LEDの配線裏側でショートしないように注意することです。
画像では判りにくいですが、バルブとLEDとの隙間がほとんどありません。
紙が1枚入るかどうかのクリアランスしかありません。
ここで実際に点灯させて気がついたのですが、23Wのバルブを点灯させたら、とても高温になります。
3〜5秒位で一瞬も触れないぐらい、熱せられます。
何度位まで上昇するのでしょう?
どのバルブもこんなもんなのでしょうか?
LEDの規格では、耐熱温度が70℃とのことなので、少し心配です。
それと、バルブって発熱すると、やっぱり膨張するのでしょうか?
前述のクリアランスでは、もしも膨張するようなら接触するかもしれません。
そうなると、溶ける可能性があるかも ・ ・ ・

車体に装着したところです。
画像では見にくいのですが、ポジション点灯でウインカー下側のLEDが4個点灯しているのが判りますか?
実際に見ると、さすが指向性が強いLED(照射角が8°)だけあって、その範囲であれば十分明るいです。
そこから外れると、点灯しているかな?くらいの自己主張ですが ・ ・ ・
まぁ、もう少し広げるつもりなら、LEDの頭を少し削るか、瞬間接着剤を塗って反射角を変える手もありますが、自分的には満足
しています。
◎ 必見!!意外なトラブル!!
実は、片側を作成した時点で車体に装着してどんな具合か見てみました。
すると、ある条件で点灯しません!!
それは、ポジションとウインカーを同時に点けると「ウンともスンとも」しないのです。
単体では問題なく点灯するのに、不思議です。
失敗したと思い、もうひとつ作成しましたが、同様な結果になります。
勿論、自分で作成した回路をまっ先に疑ったので、予備バッテリーに「ギボシ」をつないでの単体テストも十分に行い、問題なく点灯
します。
テスターで計測しても、ちゃんと導通しています。
それなのに、車体につなぐとうまくいきません。
車体側のリレーを疑ったり、左右で試したり、最後はヒューズ切れまで疑いました。
皆さん、原因は何だと思いますか?
最終的に、純正のカプラーを交換したら正常になりました。
これは盲点でした。一番信頼していた「メーカー純正」でのトラブルです。
しかもテスターでは正常です。
ある方が言うには、「電気は引っ張られることがあるから難しいんだよ!」と聞いた
ことがあります。
ウム〜ン!このことなのか!!と思いました。
結局、「原因」は突き止めましたが、「理由」は判らないまま完成となりましたが、とても良い経験になりました。
一覧へ戻る
TOPページ
Since 2003.1.18
Copyright (C) 2003 Kyasui,ALL rights reserved.