 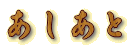 |
| 研 究 業 績 |
本山が、これまで発表した研究です。
1.著書(共著)
本山方子 2004 現場から問題を生成する:<出来事>との遭遇から始まる自己・現場・学問との対話 無藤隆・やまだようこ・南博文・麻生武・サトウタツヤ「質的心理学:創造的に活用するコツ」新曜社,84-89頁
本山方子 2004 クラスの仲間とともに学ぶ 無藤隆・麻生武編「教育心理学」北大路書房,60-72頁
本山方子 2003 自主学習の授業における小学生の居場所:詩のレパートリー形成を事例にして 住田正樹・南博文編「子どもたちの「居場所」と対人的世界の現在」九州大学出版会,290-301頁
本山方子 2001 学級の中の人間関係 無藤隆・澤本和子・寺崎千秋編「崩壊を防ぐ学級づくり(21世紀を生き抜く学級担任1)」ぎょうせい,75-100頁
本山方子 2000 単元Ⅵ人間は食べ方の習慣・きまりで心をあらわす? 東京学芸大学教授科学研究会(代表:多田俊文)「総合学習「にんげん科」のカリキュラム開発:食で学ぶ命・環境・異文化・生き方」明治図書出版,136-157頁
本山方子 1999 「活動」主体の形成 川口幸宏編「モラル・エデュケーション:市民的資質形成のために」八千代出版,69-87頁
本山方子 1998 学習を支える状況 無藤隆・市川伸一編「学校教育の心理学」学文社,136-155頁
2.学術論文
本山方子 2004 小学3年生の発表活動における発表者の自立過程:「声が小さい」ことの問題化と「その子らしさ」の発見を中心に 「質的心理学研究」第3号,49-75頁
藤江康彦・本山方子 2003 学校の原風景としての語りの構成 「東京大学大学院教育学研究科紀要」第42巻,319-335頁
本山方子 2001 質的研究実践を読むこと・読まれること 「Inter-Field」Vol.2,フィールド解釈研究会,2-8頁
本山方子 2001 自主学習の授業における教師の行為の解釈可能性と養育的意味の生成 「研究年報」第45号,奈良女子大学文学部,91-107頁
本山方子 2000 課題としての「学級文化の生成過程」における二重性:詩の普及とある子どもの関係性との連動的変容を事例にして 「Inter-Field」Vol.1,フィールド解釈研究会,69-88頁
本山方子 2000 フィールドワークにおいて<出来事>に遭遇すること:民族誌『森の狩猟民』の記述を手がかりにして
「人間文化論叢」第2巻,お茶の水女子大学大学院人間文化研究科,157-168頁
本山方子・無藤隆 1999 小学生の詩の暗唱活動におけるレパートリーの形成:自主学習の授業における個性の生成と学級文化の生成との連動
「子ども社会研究」5号, 日本子ども社会学会,29-42頁
本山方子 1999 社会的環境との相互作用による「学習」の生成:総合学習における子どもの参加過程の解釈的分析 「カリキュラム研究」第8号,日本カリキュラム学会,101-116頁
本山方子 1998 民俗芸能の学習における徒弟的学習形態の生成過程:子どもによる新座市「野火止の神楽」の囃子を事例として 「歴史民俗資料館紀要」新座市立歴史民俗資料館,1-29頁
森茂岳雄・本山方子 1997 単元Ⅴ「世界の人々は何を食べ,何を食べないか?」(44-56頁)
東京学芸大学教授科学研究会(代表:多田俊文)「「食をとおして人間を学ぶ」総合学習カリキュラムの開発(第四報)」所収,『東京学芸大学紀要第1部門教育科学』第48集,東京学芸大学,43-104頁
無藤隆・本山方子 1997 子どもはいかに授業に参加するか 「人間文化研究年報」第20号,お茶の水女子大学人間文化研究科,1-9頁
本山方子 1996 単元Ⅵ「人間は食べ方の習慣・きまりで心をあらわす?」の実践と評価(272-294頁)
東京学芸大学教授科学研究会(代表:多田俊文)「「食をとおして人間を学ぶ」総合学習カリキュラムの開発(第三報)」所収,『東京学芸大学紀要第1部門教育科学』第47集,東京学芸大学,251-314頁
本山方子 1992 「人間理解」に導く指導内容の構想:民族音楽<さくら>を教材として 「季刊音楽教育研究」第35巻第2号,音楽之友社,79-88頁
本山方子 1988 多文化教育としての音楽科教育の意義:カリフォルニア州音楽科フレームワークの検討を通して 「音楽教育学」第18-1号,日本音楽教育学会,13-22頁
3.報告書など
本山方子 1997 自主学習の授業における「個性」の発見過程:社会文化的分析 「幼稚園と小学校における身近な環境への関わりと総合的な学習の研究」平成7年度~平成8年度科学研究費補助金(基盤研究(B)(1))研究成果報告書(研究代表者:無藤隆),
291-313頁.
本山方子 1995 学習を支える対人関係・状況 お茶の水女子大学授業研究会(研究代表者:無藤隆)「認知のメカニズム及び子供の認知能力の発達に関する学問研究の動向」平成6年度文部省「教育研究開発に関する調査研究」委託研究報告書,139-149頁
本山方子 1991 用語の定義と調査対象の属性 関口礼子編「週休二日とともに青少年はどこへ行くか:中学・高校生の授業外活動に関する調査報告書」図書館情報大学教育社会学研究室,8-30頁
4.研究論評
書評
本山方子 2003 書評 杉万俊夫(編著)『フィールドワーク人間科学 よみがえるコ
ミュニティ』 「質的心理学研究」第2号,197-200頁
エッセイ
本山方子 2003 ゲンミツとゲンジツのあいだで 「Inter-Field」 Vol.3,100-103頁
5.教育論評など
本山方子 2002 「教養」としての学びの構成:公教育における総合的学習の意味 「学習研究」第398号,奈良女子大学文学部附属小学校学習研究会,62-67頁
本山方子 1997 「計画表」の授業を生きる:3年間にわたるある学級の観察から 「フレネ教育研究会会報」No.45,フレネ教育研究会,60-76頁
無藤隆・本山方子 1996 授業と学級の文化 「児童教育」第6号,お茶の水女子大学附属小学校児童教育研究会,56-64頁
本山方子 1993 単元Ⅵ人間は食べ方の習慣・きまりで心をあらわす? 東京学芸大学教授科学研究会「連載「人間を学ぶ」カリキュラムの開発10」『現代教育科学』No.434,明治図書出版,108-115頁
6.学会発表(個人発表)
本山方子・羽山純子・阪本一英 2004 小学1年生における集団的コミュニケーションの生成:談話を〈つなげる〉ことをめぐって.日本教育心理学会第46回総会,発表論文集
薗田章恵・本山方子・椙田萬理子 2004 小学校低学年の話し合い場面における〈配慮〉の形成過程.日本教育心理学会第46回総会,発表論文集
池田曜子・本山方子 2004 中学生の仲間集団における維持のダイナミクス.第11回日本子ども社会学会大会抄録集,62-63頁.
平野裕子・本山方子・堀本美和子 2003 就学移行期の小学1年生における質問行為の形成過程.日本教育心理学会第45回総会,発表論文集672頁
李陽子・本山方子・田村美帆 2003 老年期女性による学生時代のライフ・ストーリー(3):共同語りにおける「モノ」の媒介作用と社会文化的意味.日本教育心理学会第45回総会,発表論文集664頁
本山方子・田村美帆・辻田典子・李陽子 2003 老年期女性による学生時代のライ
フ・ストーリー(1):共同語りの談話における「割り込み」の機能.日本発達心理学会 第14回大会,発表論文集421頁
田村美帆・本山方子・辻田典子・李陽子 2003 老年期女性による学生時代のライ
フ・ストーリー(2):共同語りにおける「物語りの厚み」の生成.日本発達心理学会第
14回大会,発表論文集422頁
藤江康彦・本山方子 2003 学校の原風景の語りにみる想起者の自己定位:大学生の
記述の分析から.日本発達心理学会第14回大会,発表論文集419頁
本山方子・倉田直美・谷岡義高・辻 博美・城井協子・日和佐尚 2002 小学3年生の理科の授業における「調べる」行為の境界:学級文化の協同的構成(1).日本教育心理学会第44回総会,発表論文集385頁.
辻 博美・本山方子・城井協子・日和佐尚・倉田直美・谷岡義高 2002 小学3年生の朝の会における発話の継承:学級文化の協同的構成(2).日本教育心理学会第44回総会,発表論文集386頁.
藤江康彦・本山方子 2002 学校の原風景に対する意味づけの変容:大学生の記述の分析から.日本教育心理学会第44回総会,発表論文集591頁.
藤江康彦・本山方子 2002 学校の原風景としての語りの構成.日本教育方法学会第38回大会.
本山方子 2002 小学3年生の発表活動におけるルーティンの変容と可視化:発表者による「出題」と聴き手による解答をめぐって.日本発達心理学会第13回大会,発表論文集314頁
本山方子 2000 自主学習の授業における教師の養育的行為:教師の行為の解釈可能性と意味生成.日本教育方法学会第36回大会,大会発表要旨61頁
本山方子 2000 小学3年生における聴き手の社会文化的反応形成:発表活動における技法の問題の扱いをめぐって.日本発達心理学会第11回大会,発表論文集120頁
本山方子・無藤隆 1999 小学3年生の発表活動における発表者の自立過程:発表者,聴き手,教師の関係性の変容に着目して.日本教育心理学会第41回総会,発表論文集600頁
本山方子 1998 徒弟的学習形態における差異化への子どもの葛藤と受容:お囃子の学習における地位形成に着目して.日本教育心理学会第40回総会,発表論文集126頁
本山方子・無藤隆 1998 小学生の詩の暗唱活動におけるレパートリーの形成:自主学習の授業における個性の生成と学級文化の生成との連動.第5回日本子ども社会学会大会,抄録集65-66頁
本山方子・無藤隆 1997 学級文化の変容における小集団の関係形成的意味:自主学習におけるアクロスティックの製作及び発表活動の分析.日本教育心理学会第39回総会,発表論文集251頁
本山方子・無藤隆 1996 レパートリーの形成にみる学級文化生成のダイナミクス:定性的研究の実際(20).日本心理学会第60回大会,発表論文集20頁
無藤隆・本山方子 1995 個性的関係からの学級文化の生成:定性的研究の実際(13)
.日本心理学会第59回大会,発表論文集5頁
本山方子 1995 総合学習の授業研究の方法としてのフィールドワーク論:授業実践に参加した一男児の学び方の解明に向けて.日本カリキュラム学会第6回大会,発表要旨集録15-16頁
本山方子 1990 多文化教育としての音楽科教育(3):MENC発行『音楽教育における多文化の視点』(1989)に取り上げられた指導計画の批判的検討を通して.日本音楽教育学会第21回大会,発表要旨集26頁
本山方子 1989 多文化教育としての音楽科教育(2):指導計画の検討を通して.日本音楽教育学会第20回大会,発表要旨集29頁
本山方子 1987 多文化教育としての音楽科教育.日本音楽教育学会第18回大会,発表要旨集30頁
7.学会におけるシンポジウム/ラウンドテーブルなど
本山方子(上淵寿との共同企画) 2004 教育実践と心理学のあいだの「ことば」の了解可能性:「問題児」または「問題」ということばをめぐって.日本教育心理学会第46回総会自主シンポジウム,発表論文集
本山方子(掘越紀香との共同企画) 2004 教育/保育場面における子どもの活動の解釈可能性と選択的解釈.第11回日本子ども社会学会大会抄録集,104-105頁.
本山方子(上淵寿との共同企画) 2004 フィールドにおける意味づけの功罪:人はつまずいて意味づけを行う.日本発達心理学会第15回大会ラウンドテーブル,発表論文集.
本山方子(上淵寿・磯村陸子との共同企画・司会) 2003 現場(フィールド)の狭間で
「もだえる自己」.日本発達心理学会第14回大会会員企画シンポジウム,発表論文集
S74-S78頁
本山方子(磯村陸子との共同企画・司会) 2002 質的研究実践を「読む」ことの可能性.日本発達心理学会第13回大会ラウンドテーブル,発表論文集S147頁
本山方子(齋藤正典との共同企画・司会) 2001 現場(フィールド)における調査者の変容.日本発達心理学会第12回大会ラウンドテーブル,発表論文集.
無藤隆・本山方子 1996 学級文化の生成:ある学級の縦断的観察研究 日本教育心理学会第38回総会準備委員会企画シンポジウム「教室の会話と相互作用:その課題と方法」,発表論文集S60-S61頁
多田俊文・森茂岳雄・仲久徳・藤江康彦・河原直美・本山方子・岡田裕 1993
「“食”をとおして人間を学ぶ」総合学習カリキュラム開発の問題点から 日本教育学会第52回大会ラウンドテーブル,発表要旨集録32頁
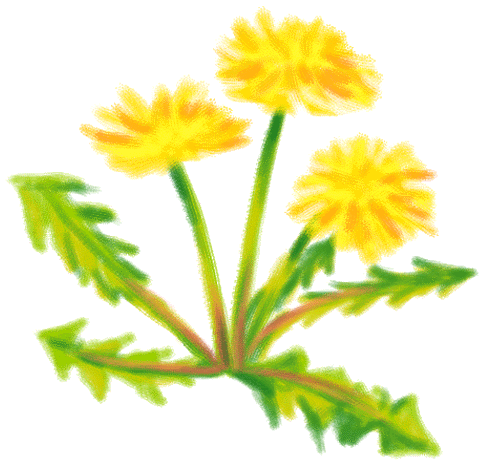 Home
Home 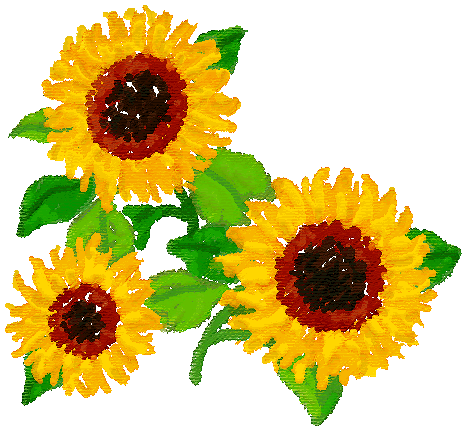 Page Top
Page Top