彼女はうっすらと瞳を開けた。 「わたしは………ココは……………痛………」 体を起こすと、全身に鈍い痛みが走った。 「いた……い……」 ほんの少し体を動かすだけで肩や背中、足の関節に鈍い痛みが襲ってくる。 痛みを堪えながら、ふと周囲を見回す。 光は、閉められたカーテンの隙間から外の明るさがほんの少し差し込む程度。 しかし、それでもうっすらと周囲の風景が見えてきた。 職員室の、教員用の鉄製の机と同じモノが、今自分がいる場所の向かいの壁に置かれている。 ココでようやく、今いる場所が室内である事に気付いた。 しかし、全く見覚えがない部屋だった。 「ココは………?」 何処なのだろうか、何故自分はココにいるのだろうか。 彼女が呟きかけたその時、かちゃりとその部屋のドアノブが廻った。 かちゃりとノブが回され、キイと独特の音を立てて扉は内側にほんの少し開いた。 部屋の外から中へと光が差し込んで、その扉の対角となるベッドへと伸びていく。 ほんのわずかな光であったのだが、暗闇に慣れた目にはそれだけですらも強すぎた。 そして、ドアは大きく開かれて、逆光を背負って人影が立っていた。 「目が覚めた?怪我は、大丈夫?」 表情は見えなかったモノの、その声はとても穏やかで、暖かい女の声だった。 「う……ん、大丈夫………あの……ココは………どこ?」 ベッドの上で、シーツをぎゅっと握りしめながら、彼女は彼女にそう訊いた。 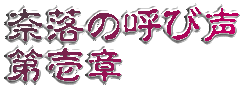 第十九話 「これくらいあれば、あの食いしん坊さんのお腹もいっぱいになりますよね」 両手で抱えるように茶色の紙袋持ちながら女性が呟いた。 ちなみにその紙袋には溢れんばかりのタイ焼きが湯気を立てて入っている。 その中の一つ、一番上で空を見上げてるタイ焼き君に、ぱくりと噛みつく。 そして、もぐもぐと紙袋を持ったまま租借して飲み込む。 美人である。 さらに知的で凛々しい雰囲気である。 確かに美人で凛々しいのだが、その抱えている物がタイ焼きでなければどれほど良かっただろう。 さらにそのタイ焼きをほおばりながら租借する姿は、彼女に対するあらゆる幻想を打ち砕くには十分すぎるだろう。 しかも飲み込んだ後、かすかに微笑んで幸せそうにする姿は、そこらにいる女子高生と変わらなく見えた。 「さて、これ以上減らしてしまうとあの子がすねてしまいますからね………冷める前に持っていきましょうか」 そう呟くと、彼女はほんの少し歩みを速めた。 白い上下一対のスーツが、風に揺れる。 「あっ、シンシアー」 そう言うと金髪の女の子はベンチの上に立ち上がって公園の入り口に向かってぶんぶんと両手を振った。 その女の子の動きと同時に、隣に座っていた萌もひょこりと顔を出して入り口の方を見る。 するとそこには、ぺこりと一度会釈して、優雅な足取りで近づいてくる女性の姿があった。 「タイ焼きって結構売ってないモノなんですね、探してしまいましたよ」 ベンチのすぐそばまでやってくると、彼女はそうぼやきながら女の子に紙袋を渡す。 当の女の子は満面の笑みを浮かべながら、お腹の虫がその存在を自己主張しながら、女性から紙袋を受け取った。 「で…………もうお友達ですか?」 紙袋をがさがさやって、中からタイ焼きを取りだしてほおばる女の子を尻目に、【シンシア】と女の子が呼んだ女性が、萌をじっと見下ろして言った。 「はふん。んふんふぁーふぁふ、んふふ………んぐ」 一個目のタイ焼きをほおばりながら女の子は言った。 その行動に、【シンシア】はため息を零した。 「口に物が入っている人に聞いた私も悪いんですけど………もう少し我慢は出来ないのですか?」 女の子は首を振った、素晴らしいほど横に。 その女の子の素晴らしいほどの首の振りように、シンシアは腰に手を当ててため息をつく。 「食べるのは良いですけど。【一人】で【全部】食べるつもりですか?」 彼女が女の子をじと目で睨むと、女の子の租借がぴたりと止まった。 そしてつつ〜と視線を横に向けると、桜模様のハーフパンツに、葉っぱの模様付きのパーカを身に纏っている少女がいた。 どうすればいいのかと目を丸くして、女の子とシンシアにきょろきょろと視線を動かしている少女の姿。 そこでようやく金髪の女の子はベンチからシュタッと降りて、ベンチに座ろうとしたところでトラ猫をむぎゅっと座布団にした。 「わっ」 ふぎゃっ、と言うトラ猫の一瞬の抗議に女の子は驚いて腰を浮かす。 「ごめんねー」 今度はネコがいないことを確認してお尻をベンチ深くにうずめる。 そして、タイ焼きをほおばって租借しながら、隣に座っている萌へと、紙袋を差し出した。 「えへへ……ゴメンね、ねねこだけ食べちゃって………食べて、ね?」 女の子がそう言ってにぱっと笑った。 そして、シンシアが微笑み、女の子の頭、麦わら帽子の上から手を置いて撫でるように動かす。 すると、女の子は嬉しそうに微笑んで、シンシアにも紙袋を差し出す。 「いっぱいあるから、みんなで食べる」 「あー、よかった、ピッタリみたいね。でもさすがに下着を貸す訳にはいかないからね………開けてない下着あってよかった〜」 と、真由は、ほんの少し頬を上気させながら浴室から出てきた少女を見て、頷きながらそう言った。 「あの………あたしは、どうしてココに………?その………池宮さん………?」 しっとりと湿った髪の毛を垂らしながらおずおずと尋ねる少女に、真由は複雑な表情を浮かべながら近づいて、手を取る。 「あ……」 「詳しい話は後、とりあえず何があったのかだけ、聞かせて。ね?キササゲさん」 真由がそう言うと、少女―キササゲ―は目を丸くした。 「あたしの名前………」 彼女が呟くと真由はにこりと笑った。 「変わった苗字だと思ってたから、印象に残っているのよ。さ、みんなもいるから、話は後で」 そう言いながら真由は彼女の手を引いた。 「え………あの、話って………?それに、みんなって………」 彼女の言葉に真由は応えず、ただ引く力を強くするだけで、リビングへと向かう。 そして、彼女はそのリビングにいた面々を見て、目を丸くする。 同級生と、下級生、先輩は居なかったモノの、数えること十名以上。 それらの全ての瞳が、自分自身に向いているのだ、驚かない方がどうかしている。 そしてさらに、ほのかに憧れていた、『あの人』の姿にも。 「怪我の具合はどう?」 『あの人』の隣にいる女性がそう呟いた。 ほんの少し心が痛かったけれど、彼女は決して表情に出さずに首を振った。 「あたしは………大丈夫。みんなが…………助けてくれたの………?」 彼女がそう言うと、あの人が首を振った。 そして、別の所に座っている男の人がこう言った。 「そうであるならばよかったのだがね………」 彼はそう言うと手に持っていた新聞を畳んで、リモコンを手に取るとテレビを点けた。 『…………頃、都立日暮高等学校の屋上で痛ましい事故が起こりました………』 女性アナウンサーが原稿を読んでいる姿がモニターに映された。 「………学校の屋上………?」 「柊 摩弓が死んだのよ」 『犠牲となったのは、都立日暮高等学校二年生の【柊 摩弓】さんで。強風に煽られ吹き飛ばされてきたグラウンド隅の倉庫のトタンに、首を切断された模様………』 真由の声と、テレビの女性アナウンサーの声が同じ事を言った。 「摩弓が…………?」 「…………それだけじゃない………」 『え………?』 雨水 健太の声に、彼女だけではなく、真由も、真希も、その場にいる全ての人物が、彼の顔を見た。 『え…………?コレ本当の事ですか………?そんな………信じられ………すみません。大変失礼しました、たった今新しいニュースが入ってきました』 アナウンサーの声がそこまで言ったところで、健太はじっとテレビの画面を見る。 健太の眼差しに、全員、モニターを見て、そして……… 『同日、午後2時36分頃、同高校内で、【椿 琴音】さんが同じく強風に煽られ折れたポールが体に刺さり即死。午後2時40分頃、【榎 鳴鈴】さんが…………』 アナウンスをみて、その場にいる全てのモノは、愕然と、絶句した。 そして、テレビを見るように無言で示した健太すらも、同じように。 「………鳴鈴まで………なんてことだ………」 時計の時刻は【14:35】 「ごめん………健太君………」 榎 鳴鈴は一言だけ、その場にいない人物に謝ると、右手の親指に力を入れる。 ピッと音を立ててメールが送信される。 鳴鈴は健太とメールのやり取りをしていた。 しかしそれだけの関係であり、恋人とか、付き合うとか言った話は全く無く。 ただ、健太が鳴鈴の相談にのる事が多々あったため鳴鈴は健太を頼りにしていた。 けれども、甘える訳にも行かず、摩弓との関係も、言えずじまい。 彼女は中学の頃苛められていた。 高校に上がってからは、あの辛い思いはしたくない一心で、明るく振る舞おうとした。 結果、摩弓に懐かれてしまった。 それからは、苛められる側から、苛める側へと。 摩弓の父親が警察の偉い位置にいることを知って、鳴鈴は摩弓に逆らうことが出来なくなった。 逆らえば、次は自分になってしまうから。 苛められるのはもういやだった。 あの辛い中学生活を、高校で繰り返すことなど、彼女には耐えきれなかった。 だから、彼女は苛められるより苛める方を選んでしまった。 それが正しかったか、正しくなかったかなどと、今となってはもう意味のないこと。 そう、意味がない。 目の前で、二度起こった、死に。 他の何かに意味などはありはしない。 【幸せを呼ぶメール】と【お迎えです】と言う件名の二つのメール。 摩弓の死の直前、琴音の死の直前。 同じように、二人の元へ来ていた【送らなければ連れていく】と言う内容のメール。 何処へなのか、何故なのか、そんなことはどうでも良い。 ただ明らかなのは、確かに二人は死んだということ。 メールを受けて、二人とも条件を満たしていた【連れていく条件】を満たしていたこと。 そして、鳴鈴にもタイムリミットが迫っているということ。 メールを受けて、満三日以内、異なる3つのアドレスに送らなければ……… 【連れていく】ということ。 目の当たりにした事実、連れていくと言うことは、まさしく死後の世界。 なんのために、そして一体何が、このメールにあるのか、それすらもわからない。 けれど、送らなければ死んでしまう。 鳴鈴は、三つ目のメールを送ろうと手の中の携帯に視線を落としながら歩いていた。 道路の向こう側の信号機は青く光っていた。 そのすぐ真下の地面には白い縞々が横断歩道と呼ばれるモノとなって、鎮座していた。 鳴鈴は、携帯電話に視線を落としたまま、顔を上げず、横断歩道を渡ろうとしたその時。 時計の時刻は【14:38】 ―ピロリロ・ピロリロ― 彼女の携帯にメールが届き、直後、彼女の左の方から聞こえる車のブレーキの悲鳴。 キイィー、と長い悲鳴のあと、彼女の目の前に広がるのは、車のフロントバンパー。 そして、その直後、彼女の視界は暗転した。 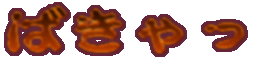 公園でタイ焼きをほおばる女の子。 そして、その隣で女の子から貰ったタイ焼きをほおばる萌の姿。 そしてさらに萌の隣に腰掛けて、シンシアが胸ポケットから本を取り出して開いて読み始めた。 「シンシアも、食べるー?」 女の子がタイ焼きの詰まった紙袋をがさがさと揺すりながらシンシアにそう言った。 「わたしは一ついただきましたから、後はねねこさんと………そう言えばお名前伺っていませんでしたね?」 シンシアは本にしおりを挟んでぱたんと閉じると、隣の萌の顔をのぞき込むように見下ろす。 「………?………………んっ、雨水 萌、小学二年生っ」 口の中のタイ焼きをお腹の中に収めて、萌は元気にそう言った。 「お母さんの名前は雨水 萌枝、お父さんの名前は雨水 竪、お兄ちゃんの名前は…………」 「はいはい、それくらいで十分ですよ、萌さん」 苦笑しつつ萌の肩をぽむぽむと叩いて優しく制する。 フワリと香った良い匂いに、萌はすこし無言になりながらも、隣の女の子の持つ紙袋からタイ焼きを取ってほおばった。 「で、ねねこさん、貴女自身自己紹介は既に終えたのですか?」 シンシアがじっと女の子を見ると、ついっと視線をそらした。 そんな女の子の仕草にまたため息をついた。 「こっちは『ねねこ』と言います、ごらんの通り、気紛れでワガママですけれど………」 苦笑しながら「仲良くして上げてくださいね」と言った。 |