「すみません、ちょっとよろしいでしょうか?」 「はい?なんで………」 と言って顔を上げた青年は目の前にいた女性を直視して言葉を失った。 真っ白な上下一組のパンツスーツを纏い、度の薄い縁なしのメガネを耳に掛けて。 栗色のほんの少しカールした髪の毛が、妙に綺麗に見えた。 染めている訳でも、脱色している訳でもないような。 それが地毛であるような、汚れも混じりけも全く存在しない栗色の髪の毛。 白い肌は曇り空であるにも変わらず眩しく見えて、首筋に思わず見とれてしまっていた。 「………どうかしましたか?」 と言う彼女の言葉にようやく彼は意識を取り戻した。 「えっ、あ、いえ。な、なんでもないです、なんでしょうか」 少し動揺しながら、平静さを取り戻そうとして彼は深く息を吸って、履いた。 唇をすぼめて、怪訝そうにするも、彼女はコホンと咳払いをして、訊いた。 「あの…………」 「は、ハイッ」 彼女は何を話そうというのだろうか………はっ、まさか愛の告白!? と、恐ろしいまで見当違いの事を考えている青年に、彼女は尋ねた。 「タイ焼きって………何処で買えるのでしょうか……?」 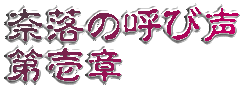 第十八話 「あああぁあぁあぁあぁあああぁっ!」 池宮邸に響き渡る絶叫。 そして唐突に玄関のドアが開かれる。 ちなみに、内側に。 「ど、どうした、なんだ今の悲鳴は!」 ガチャッ、バンッ、ガンッ、バタッ ドアノブを回した音、ドアを開いた音、ドアに何かがぶつかった音、何かが倒れた音、の順番である。 玄関先で起こった惨事に、ドアを開けた本人を目を丸くして視線が飛んでくる。 「………大丈夫?」 「………ちょっとダメっぽいです」 ドアを開けて、百日 紅の後頭部をそのドアで思いっきり強打した張本人、雨水 健太。 そして、玄関とリビングをつなぐ廊下にばたりとうつぶせで倒れる百日 紅。 かなり異様な光景だった。 「ゴメン、悲鳴が聞こえたから慌ててしまって………起きられる?」 ピッタリ三秒の沈黙の後、紅がむくりと起きあがる。 ただし、立ち上がらずに廊下にぺたりと膝をついた状態で、左手に携帯を持って右手で後頭部をさすりながら、である。 「痛〜………………あ、雨水先輩、お帰りなさい」 「ゴメンな、頭大丈夫か?」 【頭大丈夫?】などと、普通の状況だったらバカにしてるとしか捉えられない言葉だが、 コメディとしか思えないほどの見事なコンボにそれ以外言える事はないだろう。 ちなみに、真由の悲鳴(?)が聞こえたのが健太が呼び鈴を押した瞬間だった。 さらにそれは実は紅がドアノブを回そうとした時でもある。 そんなとき悲鳴らしきモノが在れば、誰もがその大元に視線を向けるだろう。 ちなみに紅も例外じゃなく、ドアノブを回そうとした手を引っ込めてくるりと真由の自室の方へと向いた、その瞬間ドアが開いたのだ。 で、今の状態である。 「いつつ………たんこぶ出来ちゃってる………って、そんなことより、今の声っ」 おそるおそる後頭部に手を当てて痛みの箇所を確認して、紅はそう言った。 自分の事なのに、そんな事、で片付けるのか。 と、健太は思ったが、口に出す事はしなかった。 確かに、今の大声がなんなのか気になる。 薫と目が合うと、こくりと頷いた。 そして、真由の部屋に行くのを薫達に任せて、健太は紅のそばに膝をついた。 「見せてみろ」 「えっ?先輩何を………」 片膝を付いて後頭部に手を伸ばして触れようとする健太の行動に驚いてずいっとお尻を動かして遠のく。 「逃げるなって、見せてみろ」 しかしあっさり肩を捕まれて、健太の右手が髪の毛に触れる。 床に手をついて起きあがろうとするが、肩をしっかりと捕まれて身動きが取れなかった。 髪の毛に軽く触れるように、払ってドアが直撃した辺りを健太は撫でる。 「つっ………」 「ここか」 紅の反応でドアが直撃したところを確認した健太は、右手の平を紅の後頭部に当てる。 そして、まるで猫を愛撫するような、そんな優しい手つきで紅の頭を撫で始めた。 「せ、せ、せ、先輩っ!?」 (た、たしか髪を触ったり、撫でたりする行為って。い、意外とエッチの次の段階じゃなかったっけ!?) と、どこぞからか仕入れた情報が紅の頭の中に浮かび、ものすごく動転する。 「こぶになってるね、大丈夫だとは思うけど………」 なでなでしながら健太がそう言うと、はっと思い出したように紅が健太から離れた。 「そ、そうです、大丈夫ですってばっ、心配はいりませんっ」 「いや、でも僕は医者じゃないから詳しい事は判らないし…………それに頭だから、一応医者に診せて貰った方が………」 「お、お医者さんなんて………そんな大げさな………」 「いや、頭をぶつけた場合は油断できない、ふとしたところで実生活に弊害が出る可能性がある」 不安げにしていた健太の瞳が、すっと細くなって険しくなった。 その健太の眼差しに、紅は思わずどきりとした。 それに、健太の言葉の中にある、何となく感じられる重みにも。 健太はほんの少し表情を曇らせたが、すぐにその曇りも消える。 すぐ近くの紅にも気付かれない程度の曇りだった。 すっと音もなく立ち上がると、右手を紅の腕に伸ばしてつかんで、引っ張り起こす。 「起きれるか?」 「え………っと」 健太に促されて紅は後頭部をさする。 心なしか少し痛みが薄くなった気がした。 「大丈夫です………それよりも先輩、その格好は……?」 右手を下ろして、紅は健太の格好を上から下までじっくりと堪能してそう言った。 「走ってきただけだよ。僕は走る時はこの格好するのが習慣だから」 そう言いながら健太はクツを脱いで、踵を揃えて玄関の隅に置く。 「………快走族………」 紅がポツリというと健太が驚いて目を見開いた。 「知っているのか………あまり騒ぎを起こしているつもりはなかったんだけど………」 苦笑する健太に、慌てて紅はフォローを入れる。 「え、あ、違うんです、悪い方の噂ではなくて………全国のバイク乗りの鑑だ、と言う話を聞いたんです………やっぱり先輩だったんですね」 紅が小声で言うと、健太は人差し指を立てて、唇に当て、彼女の耳元で囁いた。 「他言無用で、よろしく」 池宮 真由はイスに座ると、屈んでパソコンの電源をぽちっと入れた。 隣に立つ向日 葵は、イスの背もたれに手を掛けてモニタを凝視する。 一分そこそこで起動完了すると、真由がイスから立ち上がって葵に座るように促す。 こくりと頷いて葵はイスに座り、ブラウザを立ち上げてアドレスバーに己のHPのアドレスを打ち込む。 すると、すぐに真っ暗な背景が現れ、画面中央に青白い十字架と、その両端から白い翼の画像が現れた。 HPのタイトルロゴをそのままバナーにしてトップページに置いているようだった。 そしてその下に【いらっしゃいませ、アナタは2542562人目の生贄候補者です。さぁ、甘美なるミステリーの世界は目の前です】と書かれていた。 もちろん数字はアクセスカウンタである。 三年前開設したってことは………………大体1日2000人弱が訪れているという計算になる。 オカルトサイト………何気にコアなのに、結構ヒト来るんだ……… と言っても、怖い話とかホラー、ミステリー好きな人って結構居るからそれほど不思議ではないのだが。 イスの後ろでモニターを見ながら考えてる真由に気付かず、葵はアクセスカウンタの下の扉の絵をクリックしてHP内に入る。 そして手慣れた動作でマウスをクリックして、掲示板を開く。 するとツリー式の掲示板がぱっと表示された。 一番新しい日付は今日の二時五分頃だった。 タイトルは………… 「ああぁああああぁあぁああぁあぁっ!?」 掲示板の書き込みを見て、真由が唐突に叫んだ。 「マユー?どないしたん?唐突に奇声あげて、近所迷惑やでー?」 と、ドアを開けて里花を初めとする面々がぞろぞろと入ってきた。 しかし、里花の言葉に返事をする余裕が真由にはなかった。 「こっ、こっ、こっ、こっ、こっ、こっ………」 「池宮、君の前世はニワトリだったのか………」 目を見開いてモニターを指さしている真由に呆れた口調で伊沢が呟いた。 「…………っ、これっ!」 一拍置いて、真由がモニターを指したまま再び叫んだ。 仕方がないのでみんなも集まって、真由の指の先に視線を伸ばす。 そこには、掲示板の書き込みが一つ。 件名は ―――幸せを呼ぶメールについて――― 投稿者 ―神獣― 予想だにしなかった書き込みに、一同は唖然と言葉を失う。 神獣?幸せを呼ぶメールについて?どういう事なのだろうか。 この書き込みをした人は、何を知っているのだろうか。 「………池宮、内容は何だ?」 時緒の言葉に、真由ではなく葵がかちっとタイトルをクリックして書き込みを表示させる。 そこにはこう書いてあった。 ―幸せを呼ぶメールという件名のチェーンメールが存在する― ―そのメールには、この世界に数少ない本物の呪いがかかっている― ―呪いは、条件を満たしたモノを確実に殺す最悪の呪いだ― ―此処を見ている人にも実際その現場に立ち会った人がいるだろうと思う― ―もう一度言う。【幸せを呼ぶメール】と言うチェーンメールの呪いは本物だ― ―逃れる手段はただ一つ。ルイがばらまいた【警告メール】を広げる以外に手段はない― ―我々が出張れば呪いから君たちを守る事も可能なのだが、それは不可能に近い― ―君たちは数が多すぎる。【本】の呪いは強力すぎる。我々では全てを守りきる事は不可能だ― ―己の命を守る事が出来るのは、己だけだ― 決定的だった。 【神獣】なるものは、呪いの存在を知っている、しかも、自分たちよりも遥かに多く。 「………葵………返信してみて」 恵子の言葉に、葵は【判った】と言って、更新ボタンを押す。 そして返信しようとしたところで、新しい書き込みが現れる。 【投稿者:神獣】 再び、神獣と言う人からの書き込み。 そして、葵は無言でその記事を表示させる ―あまり多く言っても理解しきれないと思うから言わないけど― ―自分は大丈夫、なんて思っているのは危険だよ― ―呪いは、文字通り無差別の呪い― ―逃れる手段は【警告メール】か、呪いを吹き飛ばすほどの強さを持つモノに守られているか― ―けれど、後者はほとんど望めないと思って― ―人間の数が多すぎる― ―ボクらでは防ぎきれない― ―こっちはこっちで呪いの大元を探っているから、そっちはそっちで呪いを食い止める事に集中して― ―おねがい― まただ………… 【理解できないから】【知る必要がないから】 ただ危険であると言う事だけを言って、警告を発するだけ。 ルイも、そしてこの神獣という人からの書き込みも………そして。 「同じや………」 文面を読んでいた里花がポツリと呟いた。 「ウチのバイト先の上司の携帯取った男の人と、同じ事をゆうてる………」 「え」と言って里花に視線を向けるみんなに、里花は静かに言った。 「実はウチ、今日バイト入ってたんやけど………橋本さん………上司の名前なんやけどな、そん人に連絡せなと電話したんけど、別の人がでたんよ。そしたら………」 一呼吸置いて、里花はさらに言った。 「【本の呪いに気付く人間がいるとは】とか【本の呪いは強力だがそれ以上成長などはしない】とか………そないな感じの事ゆうてた………」 【神獣】 何者なのだろうか、彼らは、彼女らは、何を知っているのだろうか。 「ルイのことを知っている風な事もゆーとった。【こっちも動いているけど、本は巧妙だ】って。ウチ等の方が油断するかもしれないから、そっちはそっちで対策を考えてくれ、って………」 里花からの告白に一同は顔を見合わせる。 「あの、すみません、ちょっとレスしてみます」 葵はそう言うとキーボードをカタカタと叩いて文字を打ち込む。 「他に何か情報があれば呼びますから、みなさんリビングに行っててください、さすがにこの部屋に10人近くいるのは圧迫感ありますから………気が散ります」 葵がそう言うと、わかった、と言いながら各々出ていった。 真由の部屋でたった一人、モニターを見つめながら葵はキーボードを叩く。 「神獣………か………」 他に聞いてるモノがいない、正真正銘の独り言。 「やっぱり、本ってアレの事なのかな………【Evil Bible】………」 既に亡き祖父の書斎にあった、一冊の黒い表紙の本。 それを読んで、葵の世界観がガクッと変わったのだ。 この世界は、己の小さな頭で全てを理解する事など出来はしないのだと言う事を、知ったのだ……… 向日 葵、高校一年生。 日暮高等学校に姉の百日 紅とともに入学、直後にオカルト部を設立。 この世界にある、数々の不思議な出来事。 伝説や神話として伝えられている数々の現象。 そして、祖父の書斎の黒い本。 作り話で片付ける事が到底不可能な、歴史の闇に隠された、決して語られぬ、神獣達の物語。 人と同じ世界に生き、その強大な力を持ちながらそれを誇示することなく、ひっそりと人の世界に紛れて生き続けている存在。 そして今日。 神獣達は、今もこの世界のどこかに存在しているという事を知った。 |