「確か………この角を右に………」 ヘルメットの中で健太はそう呟くと、カチカチとウィンカーを点滅させるとスムーズに右折する。 しばらく走って、次は左にウィンカーを出して曲がる。 そして、一時間ほど前に見た、記憶通りの建物が目の前に現れる。 携帯を取りだしてデジタル表記の時計を見ると【15:18】と表示されていた。 「ちょうど一時間ちょっとか………まだ作戦会議中かな?」 健太はバイクから降りると、何も入っていない車庫に己のバイクを手押しで入れて、ヘルメットを取る。 シートの下の収納スペースにヘルメットを入れると、階段を上がって玄関へと向かう。 少し耳を澄ますと、中から男女の声が聞こえてきた。 まだ会議中みたいだな、と思いながら、健太は呼び鈴を押した。 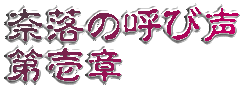 第十七話 「………みゃぁ?」 思わず雨水 萌は復唱した。 すると、目の前の金髪の少女はベンチに座ったままごしごしと目をこする。 とろんとしてた目はぱっちりと開かれて、まん丸い目がじっと萌の目を見つめる。 「…………おはよぉ」 にぱっと笑うと、金髪の少女はそう言った。 そして、少女のお腹がぐぐぅと鳴る。 お腹をおさえて少し頬を赤らめて、恥ずかしそうに舌を出した。 んしょんしょ、と言いながら、少女はベンチの上でずりずりと体を動かして足をベンチから下ろす。 少女の邪魔にならないようにどいていた猫たちが再びベンチの上にシュタッと登って、すぐそばで丸くなる。 そして、自分の右側にいる猫を両手で押す。 不満げににゃーと鳴きながら近づいてくるその猫に、ちょっと苦笑しながらも膝の上に乗せる。 そして、左手で猫を撫でながら、右手でベンチをポンポンと叩いた。 「すわる?」 金髪の少女が可愛く首をかしげると、その頭に乗っていた麦わら帽子も一緒に傾いた。 時計の針は【14:20】を指している。 「さて、麻野で遊ぶのはここいらにして本題に入ろう、呪いに関してだ」 薫がソファから立ち上がってそう言うと、笑っていたみんなの顔が凍り付いた。 「池宮、その【ルイ】という電子妖精とかいったモノは、どうだ?」 薫が真由に聞くと、真由は首を振った。 「ゴメンだけど、火曜日話したっきり。音信不通、メール送っても反応無し。ゴメンね」 シュンとなって謝る真由を、竜平がフォローする。 「池宮が謝るコトじゃないと思う、そのルイとやらも事情があるんだろう………それに、他を当てにしてるだけではダメだ」 竜平の言葉に、みんなが無言で頷いた。 「あのぅ………ボクらが呼ばれた理由は………?」 と、そこで百日 紅が口を開いた。 そういえば、真由が紅と葵を推していた、その理由がはっきりとしていなかった。 すると、真由がバツが悪そうに顎に手を当てる。 「うーん………まいったわね。百日さんと向日さんには校内に流す噂の火付け役になって貰おうと思ったんだけど………」 真由が薫を見ると、薫はお手上げ、と言ったジェスチャーで両手を上げて見せた。 「………柊の件でまた休校だ。短期間に二人も………一週間は休校解けないだろうな」 薫の言葉に真由は深いため息を零した。 「そう言うこと………休校になるなら校内に噂を流せない、今の状態で計画は破綻よ」 「え?どうしてですか?」 「………本当、何で破綻するんです?」 『へ………?』 紅と葵の言葉に、二人を覗いた全員が素っ頓狂な声を上げる。 「校内がダメなら校外で噂流せばいいじゃないですか」 「ネットで流すという手段もありますよ?」 自信満々に言う二人に、再び彼女たち以外の全員は顔を見合わせて、薫が言った。 「………できるのか?」 「出来ます。と言うより私、HP持ってますから、そこで呪いに関するコンテンツと、その警告メールに関する事を載せればすぐ噂が広がると思いますよ」 すぐ広がるって………どんなHPなのだろうか、と思ったモノの、何となく怖くてみんなはそれ以上詮索するのをやめた。 しかし葵は妙に嬉しそうに言った。 「三年前の6月に開設したんです、ミステリーやホラーなどのうわさ話や、学校の七不思議などを話し合ったりするんです、日曜日の夜11時からチャット大会ですよ、参加しますか?」 するとみんなは首を振った。 「あたしはちょっと気になるけどなぁ………」 誰にも聞こえないくらいの声で真希が呟く。 しかし、すぐ隣にいた真由には聞こえていたようで、真由が顔をしかめた。 「ボクの方も、実は校内より校外の情報の方が詳しいんです」 と言う紅にみんなの視線が移動する。 そしてさらに紅は続けた。 「情報源は教えられませんけど………そうですね、例えば………伊沢先輩の母親は、大女優の伊沢 結衣華である、とか」 「…………何故それを………」 「心配しないでください、不必要に情報を漏らすという事はしませんから。それにココにいる人なら、呪いを信じる事が出来た人ですから、信用は出来るでしょう?」 紅の言葉に、薫はみんなの顔を見渡す。 口をぱくぱくと金魚のように開閉する男女を見て、一つため息を零した。 「はぁ………まぁ、確かに信用は出来るが………吹聴しないでくれると助かる。母のスキャンダルの種には成りたくないのでね」 薫の言葉に、再起動スイッチオン。 「…………っ!伊沢先輩っ、伊沢 結衣華の息子って、本当なんですかっ!?」 と、小岩井 恵子は大声で叫ぶ。 「あー、申し訳ないんだが、少々声のトーンを下げてもらえると助かる」 「えっ、あっ、すみません………」 恵子に先を越され、弥生と碧が薫の言葉を待った。この二人も沢居 結衣華のファンだからである。 「苗字一緒なのに、もしや、とは思わないのか………不思議なモノだ。確かに伊沢 結衣華は私の母だ」 「ちょっと待ってよ、伊沢君が高二で、17として………ちょっと待って、伊沢 結衣華って、今30じゃなかったっけ………?」 「逆算すると…………13歳の時に先輩を産んだって事ですか!?」 きゃあきゃぁと騒ぐ女生徒を右手で制する。 「論点がずれてる、それに母は今年で38だ。8つほどサバを読んでいるのでね。この事も他言無用で頼む」 薫がぺこりと頭を下げる。 全ては、己の母のため。 薫に頭を下げられて、弥生も碧もぴしっと固まった。 そんなやり取りをしているそばで、真由はコソリと真希に聞いた。 「ねぇ、伊沢 結衣華って、そんなに有名なの?」 「マユ、芸能人興味ないもんね。実力派女優で、25の時………5年前か、突然現れて、突然脚光を浴びた人じゃなかったかな、確か」 「へぇ、そうなんだ…………」 興味が薄いのか、淡々と返事を返す真由に、真希はポツリとこう付け加えた。 「真由がはまってるこの間劇場公開された映画。『人形達ハ人間ニ成リタガル』の主演の女優よ、真由その原作の小説好きだったじゃない」 「アレなの!?あの春日 桜の役が、伊沢君のお母さんッ!?」 驚きに真由はものすごい大音量の声を出す。 そして薫は複雑そうに顔をしかめて、消極的に言う。 「あーーーー私の家でないので何とも言えないのだが………池宮、お願いだからもう少しボリューム絞ってくれると嬉しい」 「あ、ごめんなさい………へぇ〜、あの人が伊沢君のお母さんだったんだ、へぇ〜、ふぅ〜ん」 「………まぁ、伊沢の母親の事はおいといて、だ。話がずれまくって居るぞ、その話をするために来た訳じゃないだろう」 「………すみません、ボクが余計な事を………」 時緒の言葉に紅が申し訳なさそうにうつむいた。 「まぁ、このメンバーなら私は特に気にしない、吹聴さえしなければの話だがね。しかし………百日君、どこからそんな情報を仕入れたのかが気になるのだが………」 薫が言うと、紅はペロンと舌を出しててへへと笑った。 「企業秘密です。でも、これで信じてくれますよね?ボクは校内より校外の方が強いんです」 胸を張って言う紅に、薫は苦笑する。 「と言う訳で、早速噂流しましょうか?ボクの情報網使えば、呪いはあっという間に都内に広がりますけど……」 そう言いながら紅は苦笑した。 「都外にはちょっと時間かかるんです。日本が島国とはいっても、さすがに広いですから」 「どれぐらい時間かかる?」 「そうですね………都内には………明日の夜までには中・高生の話の持ちきりに………」 「十分ね、そうすると少なくとも都内の犠牲者を最小限に止める事が出来る………警告は、どうしたらいいかしら」 「あの、池宮先輩………」 葵がすっと静かに挙手をする。 「ちょっと私のHP開いてみてもらえますか?ひょっとしたら掲示板に呪いに関しての書き込みがあるかもしれませんから………」 そうね、と言うと真由は葵を連れて自室へと行く。 「じゃぁ、ボクも早速取りかかりますね。みなさんはお話をしておいてください」 紅はそう言うと、制服のスカートのポケットから携帯電話を取り出す。 そしてトコトコと玄関へと向かう。 時計の針は、あっという間に廻っていた。 彼女の携帯のデジタル表記は、ちょうど今【15:18】に変わった。 呼び鈴と、真由との大声が重なった。 綺麗な金髪、銀色の瞳。 真っ白なワンピースを身に纏い、その先から伸びる白い素肌。 麦わら帽子が女の子の動きと同調してゆらゆらと動く。 ベンチから投げ出した両足をぶらぶらと振り子のように降り続けるも、女の子はじっと傍らの猫をなで続けていた。 (外人さんかなぁ、メグ英語わかんないよぉ、どうしよう………) 隣に座る女の子の横顔をちらちらと見ながら萌はそう思っていた。 知っている友達は公園にいない、それは覚悟していたけど、嬉しい誤算で隣の女の子が公園にいた。 お話ししたい、と思いつつ、言葉が通じなかったらどうしよう、と思う。 女の子に促されて座ったは良いものの、彼女自身が口を開く事はなく、ただ猫を撫でながら両足をぶらぶらと揺らしているだけ。 お話ししたい、お話ししたいけど言葉が通じなかったらどうしよう、話しかけられても言葉が通じなかったらどうしよう。 ジレンマだった。 右手のおしるこに口を付けて中身をつつっとすする。 暖かくて甘いモノが萌の喉を通る。 と、その時、何となーくチクチクとしたモノを感じた。 そして、そのチクチクするのは、萌の隣から感じられる。 おそるおそる顔を左に向けると。 だーーーー 「わ、わ、わぁっ、よだれよだれっ!」 萌がポケットからハンカチを取り出して女の子の口に当てる。 女の子はハンカチを受け取ると、口の中のよだれをごくんと飲み込んで、口の周りをごしごしと拭いた。 「………えへへ」 金髪の女の子が頬を染めながら恥ずかしそうに笑った。 「あのね、おなかすいたから、シンシア、たい焼き買ってくるって言ったの。でもね、帰ってこないの、おなかすいたぁ………」 再び【くゅるるる】と女の子のお腹が再び鳴った。 そして、女の子の銀色の目が、自分の右手のおしるこを凝視している事にようやく気付いた。 きゅぅ〜るるるぃ〜 女の子は奇っ怪なお腹の虫を飼っているようだった。 まだ半分近く残っているおしるこをじっと凝視して、萌は女の子に差し出した。 「………飲みかけだけど、飲む?」 と萌が言うと女の子の目がすっと細くなった。それはまるで獲物を射程に入れた荒野のライオンのように。 「いいの?」 細めた目で、萌の右手のおしるこを凝視しながら女の子はそう言った。 猫の背中を撫でる左手がワシャワシャと高速に動いていた。 コレは、速く渡さないとにゃんこの背中にハゲが出来てしまう。 「うん、まだ暖かいから、冷めないうちに飲んでね」 そう言うとさらにずずいと差し出す、缶の口から甘い香りが湯気となって女の子の鼻孔をくすぐった。 猫を撫でるのをやめて、女の子はそーっと両手を差し出して萌からおしるこを受け取った。 くぅ〜、るるるぃ〜〜〜きゅぃっ おしるこに求愛するように女の子のお腹がものすごく奇っ怪な音を立てた。 「えへへ」 頬を赤らめながら缶を両手で持ち、いただきますを言って、口を付けて缶を傾ける。 ほこほこしたおしるこが少女の口の中に流れ込み、独特な粘着性が濃厚な味わいとなって広がり。 「ごほっ」 吹き出した。 「はひー、はひー、はぅ〜、はふー、はふー」 ピンク色のはずの女の子のベロが真っ赤になって、女の子はあかんべのような形で舌を冷やしていた。 「………ねこじた?」 萌がそう言うと、女の子は涙目でこくりと頷いた。 「…………もうちょっと冷めてから飲んだら?」 萌がそう言うと、女の子は右手を膝の上に持ってきて、じっと缶を見下ろす。 【あったか〜い】じゃなくて【あつ〜い】の間違いじゃないの?と思ったりしたかどうかは定かではない。 缶に両手を添えて口元まで持ち上げて、真っ暗な缶の口にふーふーと息を吹き込む。 中で暖まった空気が少女の吐く息に押しのけられて外に出てくる。 そして再び、缶に口を付けて傾ける、さっきよりは角度を少なく。 ほんの少しだけ口の中に移して、ほんの少し舌の上でおしるこを転がして、ごくんと飲み込む。 その繰り返しで、少女はおしるこを飲んでいった。 |