椿 琴音は、カバンを背負って中庭を歩いていた。 足取りは重く、また、隣を歩く榎 鳴鈴の足取りも同様に重かった。 摩弓が死んでからまだ一時間も経っていない。 目の前に浮かぶあの光景。 冗談であって欲しい、あの摩弓の最期の姿。 なぜ、あんな事が………イジメをしていた報いだというのか……… それとも……… 「まさか…………メールに連れて行かれた?」 琴音は、ポツリと呟いた。 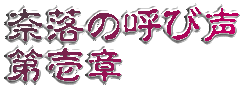 第十五話 「え?」と鳴鈴は聞き返す。 「摩弓から送られたメール、『幸せな世界に連れていく』って書いてあったでしょ?まさか、死ぬって意味………」 「冗談はやめてよ!」 琴音の言葉を遮って鳴鈴は叫んだ。 「チェンメで人が死ぬ?じゃぁ摩弓はあたし達二人だけに送って『満三日で三人』と言う条件を満たさなかったから死んだって言うのっ!?」 「だったらっ!何で摩弓はチェンメを受け取った三日後、同じ時間に死んだって言うのよっ!!!」 鳴鈴の声をかき消すほどの声で、琴音も叫ぶ。 「否定するなら、否定できる理由を説明してよっ!『チェンメの所為じゃない、単なる偶然だ』って! メールを受け取って三日後に死んだ事も!受け取った時刻が一緒の事も! 死ぬ直前摩弓の携帯に『お迎えです』って言う件名のメールが来ていた事も!! あんたっ、ソレが全部………全部偶然で片付けられると思ってるのっ!!!?」 琴音の絶叫に呑まれ、鳴鈴はぐっと押し黙る。 返す言葉がない。 琴音が言っている事は、全て事実なのだから。 『満三日で三人に満たない場合』連れて行かれる。 何で、こんなチェンメがあるのかは知らない、しかし摩弓は確かに死んだ。 いや………『連れて行かれた』のだ、その『幸せな世界』とやらに。 「断言してよっ!『偶然だ』って!言ってよっ、言ってよ!」 難しい注文だった。 「ぐっ………じゃ、じゃぁ、琴音がメール受け取った時間に、何ともなければ、偶然って事になるでしょ?」 苦し紛れにそう言うと、琴音は携帯のデジタル表記の時計を見る。 【14:33】 「………後2分後………あたしが何ともなければ………?」 琴音がそう言うと、鳴鈴は嬉しそうにこくこくと頷いた。 「そうそう、後2分ではっきりするって、単なる偶然って事が。心配ないって、大丈夫大丈夫ッ」 確かに、単なる偶然である事がはっきりするだろう。 何もなければ。 【14:34】 携帯の表記が変化する。 季節の風は、なおも強く、二人の間を通り過ぎていた。 何を感じる事もなく、風は、ただただ運ぶだけ。 「後………1分」 そう、風は唯、運ぶだけ。 運ぶモノが何であろうと、どのようなモノであろうと。 風は、ただ……… 【14:35】 ―ピロリロ・ピロリロ― 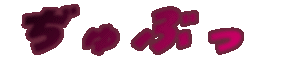 運ぶだけ。 折れた鉄柱は、その断面を歪に、かつ鋭利なまま宙を舞った。 そして、くるくると回天しながらまるで狙いを定めていたかのように、少女を襲った。 「か……ふぁ」 ゴポリと、少女の口から紅い液体が泡となって吐き出される。 「こと………ね………?」 すぐ隣で、ついさっきまで話していたはずの、友達の姿に、鳴鈴は呆然と呟いた。 真正面から飛んできたモノ、それは紛れもなく体育館のあのポールだった。 何故、こんなモノが飛んでくる、しかも、何故………何故、今!? 「琴……音………」 折れた鉄柱は、彼女の胸を貫いていた。 すでに彼女の目に生気は見られず、まだ暖かいはずの腕は力無く垂れ下がり、体ごと後ろに倒れようとした。 しかし、鉄柱がそれを許さなかった。 彼女の体を貫いている鉄柱は、彼女の体が地面に付くより先に、ガリッと地面を掻いて、そこで止まる。 そして、彼女の足から力が抜ける。 膝が折れ曲がりぺたりと正座をするような形で収まった。 貫かれた胸からはそれほど血が出る事はなく、ただじわりと、鉄柱を伝い血が地面を赤く染めて行った。 「!!!!!!」 飛んでいった鉄柱は、何故こうも一人の少女を直撃するのだろうか。 しかも、その心臓を一突きに。 即死だろう、今の状態で生きていられる訳がない……… なぜだ、何故、同じ日に、同じ場所で二人も死ぬ。 そんな偶然が、あるモノか、いや、違う、あってたまるか。 だが………偶然でしかないのも事実。 グラウンドの隅の倉庫が吹き飛んだのも、体育館のポールがへし折れたのも。 全て、今の季節に吹く風の仕業。 それ以外、有り得ない………有り得ないはずなのに……… なぜ、死ぬ直前に、また、メールが届いていたのだろうか。 摩弓が死ぬ直前にも、そして琴音が死ぬ直前にも。 そして、一人残された少女は駆けだした。 三人に送らないと、死ぬ。 摩弓は、琴音と自分にしか送ってなかった、三人に足りなかったから死んだ。 琴音は、受け取ったまま誰一人に送らず、摩弓と同じように足りなかったから死んだ。 では、次は? 「私………だ」 榎 鳴鈴は、少女の遺体を目の前に、焦点の定まらない目をしながら呟く。 彼女は立ち上がる、が膝が笑う。 笑う膝を叱咤して、とにもかくにも彼女は駆けだした。 次は自分、自分が死ぬ、時間がない……… 逃れるには、三人の人にメールを送らなければいけない。 早く、早く……早く送らなければ死んでしまう。 時間がない。 真っ白になったテレビを、険しい表情で健太は睨んでいた。 「………」 一瞬だけ、映った。 ポールが突き刺さっていたモノ。 偶然が、そうそう重なってたまるものか。 紛れもなくコレは何かある、表面には何も出てこないけれど、確実に何かが。 「呪い…………」 薫から聞いた事を思い出す。 今の、テレビの一瞬の映像。 そして、ほんの一時間足らず前の、屋上での惨劇。 『幸せを呼ぶメール』と『お迎えです』と言う件名のメール。 あの薫から聞いた話でなければ、すぐに忘れ去っていたであろう話だ。 聞いたその日に、二人も、唐突に死んでしまうとは………。 呪いとはなんなのか、一体、何がこの事件を引き起こしているのか。 薫も、そして真由も、その事を知っている様子はなかった。 ただ一つ言える事は、警告メールが在れば助かるという事……… 健太は自室に行き、机の上に置きっぱなしにしてある携帯を取り、メールをチェックする。 「………大丈夫、ちゃんと届いているな」 メールボックスの最上部にある『警告メール』と言う件名のメール。 今日は携帯を忘れてしまっていたのだが、自分のアドレスくらいは暗記している。 ソラで言って、薫にメールを送ってもらった。 なぜか驚かれていたが………ひょっとして自分のアドレスや携帯電話の番号は覚えないのだろうか?考えられない。 電話を落としたりした時、自分の番号に掛けて何処にあるか確認しないのだろうか。 理解できないな………… そう思いながら、健太は携帯を己のGパンのポケットに入れる。 そして、タンスの奥から長袖のシャツを取り出して身につけた。 タンスを閉じて、部屋の端にハンガーで掛けてあった革のジャケットを羽織り、小物入れに入れてある愛用のグローブを手にはめる。 そこへ、半開きになっていたドアの隙間から萌が顔を出して、健太に問いかける。 「おにいちゃん、でかけるの?」 牛革のグローブを引っ張って、手首までぴっと伸ばし、何度か手を開いたり閉じたりして馴染ませる。 「あぁ。ちょっと約束があってね。退屈ならパソコン使ってても良いよ、ただ、メールは見るなよ」 と、健太はベッドの隣にあるパソコンラックを指していった。 しかし、萌は足のつま先でフローリングの床をカリカリと掻きながら、胸元で両手の指を絡ませながら、指先でつんつんとつつき合わせる。 「メグも………連れてって…………?」 甘えん坊だとは思っていたが、これほどとは……… 可愛い妹にねだられて、叶えてやりたい気持ちも山々だが、真由達との約束に萌がいては色々困る。 そもそも、小学生に聞かせるような話ではない。 灰色の靴下をはいて、健太は部屋を出る。 「日曜日、約束するから、ごめんな、メグ」 ポンと萌の頭に手を置いて、革の匂いがする健太の手がくしゃりと髪の毛のセットを崩す。 すると、萌はたちまち笑顔になった。 「うんっ、約束破ったら、お父さんに言いつけちゃうんだからっ!おにいちゃんっ、気を付けてねっ」 おう、とだけ答えて健太は下駄箱からクツを取り出す。 いつも学校に履いていくクツとは違って、黒革のクツだった。 外側にはジッパーが着いていて、健太はそのジッパーを下ろして足を差し込む。 玄関先に座り込み、右手で左足首をつかみ、左手でジッパーをつかんでいっぱいまで上げる。 そして今度は逆、左手で右足首をつかみ、右手でジッパーをつかんで上げる。 「よし、じゃぁ、行ってくる、知らない人が来てもドア空けるんじゃないぞー」 すると、ドタドタと玄関先に萌がやってくる。 「おにいちゃんこそ、ヘマやって病院行き、何てことにならないようにねっ」 無い胸を張って威張る妹に頭をぺしっと叩いて、健太はドアを開いて外に出る。 さて…………急ぐか。 真由の家ほど大きくはないが、健太の家も一軒家なのだ。 車庫はしっかりとある。 そして、その車庫の片隅で。 中学の頃から興味があって、高校入ると同時に始めたバイトで貯めたお金で買った自分専用の車。 「さて、行こうか、相棒」 そう言って、健太は相棒のガソリンタンクを叩いた。 ボン、と鈍い音がした。 うるさいのは、最初だけ。 ハンドルを持って押しながら車庫から出す。 そして、ドルン、とエンジン始動の音を最後に、後は信じられないほどの静かさを保つ。 健太は、この相棒が好きだった。 バイクメーカー『HOW-WOW』 それが、彼のバイト先の名前だ。 どう言ったポリシーなのか、HOW-WOWはバイクの静音性に重点を置いているようだった。 しかし、健太はHOW-WOWが何よりも好きだった。 何よりも静かで、しかも速く。 中学一年のとある日、学校の帰り道突然背後から風が吹いた。 と思ったら、目の前にバイクが走り去っていた。 音が、無かった。 突然風が吹いて、そして颯爽と走り去るバイクの後ろ姿。 一瞬にして心を奪われた。 あの姿に比べたら、ネオンピカピカ、バックファイアをボコスカ鳴らす車はゴミほどの価値もない。 静かなる事そよ風の如く。 速き事、烈風の如く。 コレこそ、何よりも格好良い。 「さてと」 健太はバイクにまたがって、アクセルをふかす。 と言っても、ほとんど音がない。 たとえるならば、パソコンのハードディスクの回転音に似ている感じだろうか、なんにせよ、バイクの音としては異常なほど無音だった。 「相変わらず、無口な奴だ、おまえは」 それが気に入ってるんだけどな、と心の中で呟いて、ガソリンタンクを叩いた。 「さて、池宮の家に速く行かないとな、待ってるだろうし、何しろ………」 テレビを思い出して、健太は表情を険しくした。 「今日で二人か………急がなきゃ、まずいね」 アクセルをいっぱいに回すと、一気に後輪が回転して前輪が浮き上がってウィリー状態になる。 そして、ゆっくりと前輪が降りると、健太はそのまま走り去った。 |