「マユ…………まさか…………?」 柊 摩弓のそばで何らかを叫んでいる先生達を尻目に、可憐がマユに言った。 そして、マユは無言で頷いた。 「覚悟はしていたけど………校内での犠牲者が出る事は………でも………」 まだ、序の口なのだ。 名を知り得た者だけで。 【早乙女 茂之】【堺 珠美】【富士 皆人】【柊 摩弓】 四日連続で、四名もの人が死んでいる。 メール媒介にした【本の呪い】と。 ルイは、確かにそう言っていた。 【本】とは、何の事なのだろうか。 そして、ルイ達は一体何者なのだろうか。 そして、この呪いを終わらせる事が………… 出来るのだろうか? 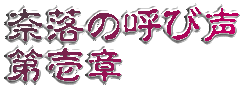 第十三話 予想通り、臨時休校となった。 その旨は、昼休みを取りやめにしてHRを行っている時に伝えられた。 ピンポンパンポン、と独特なコール音の後、慌てた様子の声が校内のスピーカーから流れてくる。 「ひ、昼休みの途中ですけど。み、みなさん、今すぐ教室に戻ってください。た、大切な話があります、早くしてください!」 それだけで、放送は終わり、事情を知らない大多数の生徒達は頭の上に疑問符を浮かべる。 ――ズダダダダダダダダダッ 廊下を走ってはいけません、と言う校則も何のその、正面切ってぶち破るのは各々のクラスの担任だった。 「み、みなさんっ。大変な事が起こってしまいました、詳しい事を話す時間はありませんが、本日は午後の授業は中止になりますっ!気を付けて下校してください!」 やったー、なんだかわからないけどラッキー、と言う生徒達の中で、一人だけ、己の携帯電話と睨めっこをして、険しい表情を作っている人物がいた。 「………あかんなぁ………また、犠牲者がでたんか?」 川崎 里花。 身長162㎝。 スリーサイズは………スレンダー、と言うのだろうか。 余分な肉、と言うのもおかしいが、ともかく、それは胸だけについて、全体に引き締まった体つきをしている。 なぜなら、彼女はテニス部だからである。 運動部故の特性か、体を動かす事が多い為、必然的に贅肉は絞られ体は引き締まる。 まぁ………里花自身は、もう少し胸は引き締まらなくても良いなぁ、と思ってたりするが、割愛する。 同じテニス部である碧と弥生と、良くゲームを行う。 勝敗は、弥生とは五分五分、碧とは九割の確立で里花が勝利する。 理由は、里花自身の性格の特性にある。 彼女は、理論づけて動く事が苦手なのだ。 『こうした方が良いんじゃないかな?』とか『あっちにしてみようかな』 と、突発的な閃きに流されて行動を起こす事がものすごく多い。 結果。 碧は里花にほとんど勝てない。 予想だにしないところに打ち込まれて、反応する暇もなくポイントを奪われてしまう。 ようするに、薫を理論型の天才とするならば、里花はまさしく閃き型の天才という事になる。 ばいばーい、とカバンを持って教室を去る生徒達の中、里花はイスに座ったまま頬杖をついてぼーっと何かを考えていた。 「どないしよか………バイト入れとるんやけどなぁ」 送られてきたメールと睨めっこをする。 送信者は【団 ミドリ】とある。 【ミドリ】ではないのは、アドレスを登録した時に変換するのがめんどくさかったからである、それにカタカナの方が見やすい。 と、里花は考えている。 そして、そのメールの内容を読み返す。 「えーと――屋上で五組の柊 摩弓先輩が亡くなられました。今後の対策を考えたいから池宮先輩の家にできたら来てください――か………」 右手で携帯を握ったまま、里花はポリポリと左手で後頭部をかく。 自宅から駅三つ行ったところにある大鳥出版と呼ばれる会社で、アンケート葉書などの仕分け作業が、里花のバイトの内容だ。 給料は、バイトにしてはかなり良い。 しかし、里花はその事を誰かに言う事はしようとしない。 理由、美味しい話は独り占めが鉄則。 らしい。 つまり、書店に並んでいる【こうすれば誰もが事業を成功させる事ができる】など、平積みされている本は、里花にとって鼻をかむティッシュに劣る紙である。 『そないに儲かるんなら自分でせぇや、うちはうちのやり方でビッグになったるで~』 が、彼女のモットーらしい。 しばらく考えた後………ちなみに里花はぼーっとする時、携帯を開いてメモ帳に【ま行】を連打する癖がある。 考え事をする時、携帯のアンテナをあまがみする癖がある。 歯を立てずに、唇だけではむっ、って感じである。 ちなみに、この時もはむってアンテナを噛んでいた。 携帯のメモリーから一つの番号を引っ張り出して電話をかける。 ――ぴるるっ、ぴるるっ、ぴるるっ―― 数回のコール音の後。 『――ガチャッ――もしもし?』 電話の向こうから若い男の声がした。 「あ、もしもし、橋本さんでっしゃ………ですか?突然で申し訳あらへ………申し訳ないんですけど。 何にも代え難い急な用事ができてもうて………できてしまったので。 今日のバイトは勝手ながら休ませてもらぉ………お休みを頂きたいのですが………」 油断したら口から飛び出てこようとする関西弁を必死で抑えつつ、里花は慣れない敬語で電話先の男の人にそう伝えた。 『橋本君は出張で携帯忘れてるんだ、すまないね。オレから橋本君に伝えておくから、君はその用事というモノに行きたまえ』 「え………?」 聞き覚えのない言葉に、里花は一瞬戸惑う。 『心配は要らない、この携帯は今日これから橋本君に届けるから、君はその【何にも代え難い急な用事】に行って構わないよ』 心なしか、電話の向こうの男の人がクスクスと笑っているような気がする。 気のせいだろうか………? 『君たちも、色々大変だろう。友達と知識を出し合って、どうすべきかを考えてみたまえ。ひょっとすると、思いがけないところから活路が見えるかもしれないからな』 「何を………?」 『我々も別な方向から動いてはいるが、如何せんアレは巧妙だ。もしかすると君たちの方が近いかもしれない、アレも君たちなら油断するだろう、期待しているよ』 「あ、あの…………一体何を言うてんでっしゃろか?」 訳がわからず、里花はつい聞き返した。 『……いいや、ただ、予想外に君たちの行動が早かったモノでね…………【本の呪い】に気付く人間がいるとは、驚いたよ』 「!!!!!!!????????」 電話口のむこうから放たれた言葉に、里花は絶句し、携帯を思わず取り落とす。 歩きながらではなく、教室の机に座った状態だった為、携帯は無事だった。 ほっとしながら、里花は気を持ち直して携帯を拾って、耳を当てる。 『人の話の途中で携帯を落とさないでいてくれると助かるのだけどね………まぁ、気にしないでくれ』 どうやら向こうの人にはバレバレらしい、携帯を落としたという事が。 「き、気にするなって、突然そないなこと言われたら誰かてびっくりしますわ!」 と、電話の向こうに大声で、しかもイスから立ち上がりながら言った。 結果、教室に残っていたクラスメイトや、廊下を歩いていた別のクラスの生徒達が何事かと里花に視線を向ける。 『電話なのだから、余り他者に会話を聞かせないようにしてもらえると助かるのだがね。それに、立ち上がる時はゆっくりと、イスが倒れてしまうよ』 と言われて、里花はくるりと背後を向く。 急に立ち上がった際、イスを後ろに吹っ飛ばしていた。 生徒達の興味が無くなり、視線が外れた事を確認すると、里花は紅潮しながらイスを元通りに立てて腰掛ける。 「本の呪い…………どういう事か、話してくれまへんか?」 すると、電話の向こうの声はただ一言『いや』と言った。 そして、こう続けた。 『話したからと言って、そう簡単に信じる事はできないだろう、また混乱させるだけだと思うし、今は話さないでおく』 「そんな!」 そこまで言っておいて、あんまりな言葉に、里花は今にでも噛みつきそうな黒豹のように携帯電話を握る手に力を込めた。 しかし、どう頑張っても噛みつく事はできない、電話なのだから。 『ルイから話は聞いている。【一人だけ気付いてくれた】と。君はその気付いた人物か、あるいはその人物から聞いて、信じたかのどちらかだろう?』 「……………………」 『本の呪いは強力だが、その分拡張が効かない。一度掛けた呪いはそれ以上掛けられないという特性を持つ。 ルイはその呪いを防ぐ手だてをメールに託した。そのメールを持っている間は大丈夫だ、心配は要らない』 そして、彼は最後にこう言った。 『本は、人の欲望その物だ。完全に滅する事は不可能だろう。だがそれでも我々は野放しにする事はできない。 我々は今君たちに協力する事はできない。そちらはそちらで事に当たってくれ、頼む』 そして、電話はぷつりと切れた。 里花がコールしても、かえってくる音声は『おかけになった電話番号は、電波の届かないところに居られるか、電源が入っていない為届きません』だけだった。 彼は、何者だったのだろうか、何を知っているのか、何をしようとしているのか。 全くわからない。 わからなかったけど、一つ、はっきりしている事が彼女にはあった。 「バイト………休もう、マユんとこいこか」 この事を話さなければならない。 話を聞かなければならない。 これ以上犠牲を増やさない為に。 大切な人を失いたくないが為に。 里花はカバンを手に取ると、教室を飛び出した。 プツッと携帯を切って、さらに電源まで切る。 そして、さっきからポケットの中で自己主張をしていた自分の携帯を取って、電話にでる。 「もしもし、どうした?」 『どうした?じゃありませんよホウカっ!こっちは忙しいんですから、遊びほうけてないでたまには手伝ってくださいっ、大変なんですからっ!』 と、電話の向こうから飛んでくる大声に、男は顔をしかめて。 「あー、もう、聞こえてるって、そんな大声出さなくても………老けちゃうよー」 『ご心配なくっ!私は老けませんから!そもそも貴方がしっかりしてくれさえすれば私だってこんな電話しなくて済むんですっ!どうでも良いですから、さっさと帰ってきなさいっ』 と、電話の向こうからの女の声に、男はクスクスと笑う。 『な、何がおかしいんですか!!』 「いや、可愛いなー、って思って」 『!!!ふ、ふざけないでくださいっ、じゃあ、早く帰ってきてくださいよねっ!』 と、感嘆符が非常に多い相手からの電話は、一方的な捲し立ての後あっさり終わって、携帯は沈黙する。 「やれやれ…………以前の彼女は何処に行ったのやら」 苦笑いの中に暖かな微笑みを浮かべながら、男は己の携帯電話をじっと見つめていた。 1人で住むには広すぎる。 かといって、20人も入れる程広くはない。 けれど、10人くらいなら、ちょっとしたホームパーティーみたいな感覚で十分だった。 そして、一同は目の前の半豪邸を前にふへー、と首を少し上に見上げるような形で声をもらす。 「じゃぁ、わたし先に入ってお茶淹れてくる。みんなは適当にくつろいでてね」 そう言って、真由は一足先に家の中に消えた。 「コレはまた………東京郊外とはいえ、都内のこのような一軒家に住んでいるとは…………」 と、薫が呆れが混ざった口調で呟いた。 「池宮の両親は何の仕事を…………?」 「………その話、真由の前ではしないでよね」 時緒の言葉に、マキが静かに、かつ有無を言わさない口調で、時緒を一瞥していった。 「マユの両親、マユが中二の時旅行中行方不明になっていて………まだ見つかってないの………たぶん……もう………」 「わかった………悪い」 時緒はバツが悪そうに謝ると、マキは苦笑混じりで言った。 「ありがと、可憐。マユの両親が、マユの為にって貯めていた銀行の口座に毎月決まった額のお金が振り込まれるんだって」 最初は可憐に、後の言葉はその場にいる全てのモノに投げかけられる。 「『お父さんが勤めていた会社の偉い人が』ってマユは言ってたけど………かれこれ三年、一度もその人と会った事はないって、一度きりの手紙だけしか知らないって」 そう聞いたのは、中学三年の夏休み、マユの家で好奇心でお酒を飲んだ時だった。 「ほんの少し悲しそうにしてたけど、すぐに笑って『感謝しなきゃ。だって、その人がいなかったら、今こうして真希と話できなかったと思うから』って………」 後は徐々に小声になっていき、真希は恥ずかしそうにして両手の人差し指をつつきあってもじもじとした。 ビバ、女同士の友情! たしかに、中学三年生一人、しかも女の子と来た。 生きていく為には、体を売る事すら考えたかもしれない。 「ま、まぁ、そう言うことだからっ、その事はマユに触れないでよねっ!」 そう言ってくるりと真希は体を振り回して家の方に向ける。 しかし、後ろ姿を見る限り、真希の顔が真っ赤になっている子はバレバレだった。 「真希先輩………」 「……………なによ」 碧の声に、少しどもりながらマキは言った。 しかし、次の碧の言葉に、真希は脱兎した。 「みみたぶまで、真っ赤ですよ?」 「っっっっっ!!!」 |