葵は、満足そうに頷くと、人形の口元を親指でこすって、ペンの跡を拭き取る。 「…………あ………」 すると、ため息と友に恵子が言葉を発した。 「なかよく……クラスメイトだから……ね?」 屈託のない笑みに、恵子はただうん、とだけ言った。 そして葵は、またにこりと微笑んで、己の弁当箱から海苔巻き卵をつまんで、恵子の弁当箱の中に入れた。 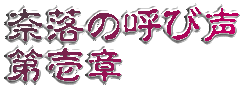 第十話 一部始終を見ていた人は、沈黙する。 訳がわからず、何があったのか、葵が何をしたのか、恵子が何をされたのか、それすらもはっきりとわからず。 そして、次第に興味が薄れたのか、友達と談笑したり、残っている弁当を片付けはじめた。 ……………えーっと。 葵は何をしたのだろうかと、碧はそう思った。 手に持った人形は、なんだったのだろうか、何故恵子は突然黙り込んでしまったのだろうか。 …………わからない。 と、そのとき、唐突に廊下がザワッと騒ぎ出した。 何かと思って碧が振り返った瞬間。 廊下側から、窓のワクにもたれかかるように、胸元で腕を組んで、その豊かな胸を強調するように。 「どうしたの碧、神妙な顔しちゃって」 と、弥生が首をかしげて、訪ねてきた。 「あ、弥生ちゃ…………」 「で、どうなの?」 「どう…………ってそれより、どうして一年の教室の所に来てる……んですか」 一応先輩なので、途中で敬語に変える。 「んー、昨日ああは言ったけど、やっぱりあんた一人にまかせるのって、ちょっと不安でね。様子見に来たわけ」 「それでだ、団くん。百日 紅と、向日 葵は何と言ってきたかな?」 再び、ザワッと喧騒が広がる。 伊沢 薫、二年生にして生徒会長に就任した男だ。 それが、何故一年の教室に、しかもたった一人の女生徒を訪ねてきたらしい。 さらに、用事というのは、あの双子に関することとの事。 いやでも、気になるだろう、当事者以外は。 現に、周りにいる同級生はしんと静まりかえって、団をじっと見つめている。 そして、自分たちの名前が出たことに、あの二人も、じっと、廊下に立つ伊沢 薫を凝視する。 「……………まだ、話していないのか?」 碧の視線に、怪訝そうに薫は碧にそう訪ねた。 「は、はい、ちょっと、あの…………ごめんなさいっ、チャンスが無くてっ」 ガタンとイスを蹴飛ばしながら碧が立ち上がり、背筋を伸ばして頭を下げる。 「あー………その、なんだ…………はぁ」 「あの………」 「かおりーん、女の子苛めるのは感心しないよ〜」 「……………私のことか?」 主語を抜いて薫が弥生に訊くと、弥生は無言で頷いた。 「あのぅ………」 「………まぁ、私はなんと呼ばれようが気にしないが………では、団くん、君から二人に話してくれないか?えっと、百日くんと、向日くんは、何処に………」 「あの、ちょっと、先輩、聞いてくださいっ!」 さっきから、声を掛けられていたことに、薫はようやく気付いた。 「…………私か?何かな、君は?」 そして、伊沢に声を掛けた勇気ある少女、百日 紅は、胸元の大きな赤いリボンを強調するように背筋を伸ばした。 「二年一組の百日 紅と言いますっ、伊沢先輩、お話がありますっ」 そこで、ようやく薫はそっくりな顔が二つ並んで自分をみていることに気付いた。 「キミか、入学式当日のその日に新聞部を作り上げた一年というのは」 「はい、先輩っ、お褒めにあずかり光栄です」 「うむ、その行動力は称賛に値する。して、私に話とは?」 薫は、じっと紅の顔を凝視する。 コレは薫の癖で、人と話をする時は相手の目、と言うか顔を凝視するというモノである。 人と対話をする上で重要かつ当たり前のことではあるが、それを無意識に出来るモノはそうはいない。 紅は、思わず視線をそらした。 見ることは得意だが、見られることは苦手だった。 それが、己の学校の生徒会長であるなら、なおさらだ。 さらにその生徒会長がさり気なく文武両道で、実は段持ちの空手家で、成績も常にトップをキープしているから、なおさらだ。 そんな人間がいるモノか、と思うかもしれないが、いるんだから仕方ない。 細かいツッコミは却下する。 突然視線をそらされて、薫はきょとんとしたが、すぐその理由を把握した。 「あ、あぁ、すまないね、癖になってしまって」 そう言ってその端正な顔を崩し、苦笑いする。 その笑みに、一部の女生徒は胸をときめかせた。 ここだけの話、薫は、美形だ。 並の上、お寿司風に言えば上と言ったところだ。 手入れの行き届いた黒髪、荒れを知らない指先、すらりと伸びた足。 つり目がちで少々目つきが悪いところもあるが、それがクールで良いと、また人気がある。 かといって、男子に嫌われているわけではない。 どうやら、異性も、同性をも引きつける魅力を、薫は持っているようだ。 そして、紅も例外なく頬を赤く染めていた。 その隣で、葵がため息を漏らしながら、ただ一言ポツリと。 「面食い………」 と、言った。 「先輩っ、次の校内新聞で、先輩のインタビューを載せたいと思うんですっ、質問にお答えくださいっ」 と言って、紅は制服の胸ポケットからメモ帳とボールペンを取り出した。 「………私の話か?ふむ………面白い話を出来るかわからないが………と、その前に、私の話を聞いてもらえないかな?」 メモ帳にペン先を当てた状態で紅の手が止まる。 「話………ですか?ボクに?」 目をキラキラさせる紅を前に、薫はバツが悪そうに苦笑いした。 「正しくは、君たちに、だな」 薫の代わりに塚本 時緒が、教室の前のドアにもたれつつ、そう言った 「塚本先輩っ、どうしてここにっ!?」 と、塚本 時緒を見て驚きの声を上げたのは、小岩井 恵子。 「ちょっと野暮用。事情は後でゆっくり話してあげるから、静かにね、恵子」 子供をなだめるような口調で諭されて、恵子は不満げにしながらも、時緒の言葉に従った。 あの恵子が、静かになるなんて………… と、彼女のクラスメイトは驚いた。 ここだけの話、塚本 時緒は背が高い。 と言うよりも、日暮高等学校の生徒は、総じて質が良い。 質が良い、と言うとモノ扱いするようであまり好きではないが、わかりやすいと思うのでそう言わせて貰う。 男子生徒は、大概運動部に所属し、ほぼ確実に大会などでは好成績を収める。 ただ、塚本 時緒は天文部だが、その辺は愛敬というモノだろう。 また、質が良い理由は、彼らを影から引っ張っているモノがいるのだが、その事に気付いている人は存在しない。 話がずれた、元に戻そう。 不満げにしながらも、小岩井 恵子は黙り込んで席に付く。 すると、塚本 時緒は『偉いね』とでも言うかのような笑みを恵子に向けた。 そして恵子は頬を赤く染めて、恥ずかしそうに下を向いた。 「塚本………なぜ君がここに?」 「夏目が部活のミーティングで来れないって言ってたからな、オレが代役だ、不満か?」 塚本の言葉に、薫は一つだけ嘆息し、いや、と首を振った。 「不満がどうの以前に、単に君が気になっただけじゃないのか?それに」 と、薫は赤面している恵子を一瞥する。 「彼女もいるからな」 「…………」 図星だったため、時緒は何も言うことなく押し黙る。 「あのぅ……………」 突如聞こえた少女の声に、時緒と薫、また、その二人の会話をじっと見てた弥生も、声の主を見る。 ちなみに、昼休みの一年の教室なので、生徒は他に沢山居るが、関係ないところは割愛する。 向日 葵だった。 「………私達に話って、なんなんですか?」 葵がそう言ったところで、伊沢は辺りを見渡す。 「失敬、塚本の所為ですっかり脱線してしまったな、場所を変えよう。塚本、何処か良い場所を知らないか?」 「俺が悪いのか………そうだな、屋上が良いんじゃないのか?俺も良く行くし」 それだ、と薫が言った。 「ここでは人目がありすぎる、あまり騒がれるのも好ましくないからな、百日くん、向日くん、付いてきてくれるかな?」 紅と葵は、お互い顔を見合わせ、こくりと頷いた。 昼休み、校内は生徒達の喧騒に包まれる。 午前の授業が終わり、親しい友人と雑談しながら食事を取る。 これほどまでに楽しい時間が、他にあるだろうか。 だが、楽しいはずのその時間を、楽しめない人というのは必ずいる。 「きゃっ」 ガシャーンと、独特の金属音を立てて、フェンスが揺れる。 日暮高校の屋上は、解放されている。 また、高校自体高台の上に位置するため、日当たりが良い。 そのため、昼休みには生徒達の食事の場となったり、甘酸っぱい恋の告白場所として選ばれたり。 また、不本意ながら、あまり真面目ではない生徒の格好のサボり場となったり………。 階下から見上げることが出来ないため、少数の心ない生徒達により、イジメという行為に使われてしまうことがあった そして、この場所に呼び出され、イジメを受ける子と言うのも、存在した。 今、この時にも。 |