ぬれタオルを受け取ると、真由は可憐の頬に付いた血をぬぐった。 また、真希はその隣で可憐の両手の返り血を拭き取っていた。 一体何故、こんな事に。 あんなに、幸せそうだったのに、何故こんなことが。 「メール…………」 「え?」 「早乙女くんに来てたメール、何だったんだろう」 真希がそう言ったから、真由も思い出す。 死ぬ直前、彼の携帯にメールが届いていた。 しかし、真由は着信音しか聞き覚えがなかった………『上』を見ていたから。 「早乙女くんが話してた、チェーンメール………わたしのと、同じ内容みたいだった……それに、あの直前のメールに、その内容……」 「まさか、じゃぁマキは、早乙女くんがメールを回さなかったから『呪い』で死んだって言うの?」 「そうじゃないけど…………でも、偶然にしては……」 「偶然よ、呪いなんかあるわけ無いでしょ」 イライラしながら、真由は真希の言葉を一喝した。 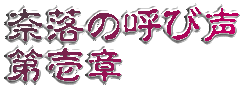 第三話 ――二日目 真希に言ったモノの、真由自身も戦々恐々だった。 茂之が受け取ったというチェーンメールと、真希が真由に送ったチェーンメールの内容の一致。 そして、死の直前に送られてきた『迎えにくる』と言う、メール。 偶然にしては、タイミングが良すぎる。 まさか、呪い………? そう思ったところで、ぷるぷると頭を振って考えをふき飛ばした。 呪いなんて、あるはずがない。 そう、単なる偶然に過ぎない。 メールを送らなかったから、死ぬなんて、そんな呪いが…………… 「あ………」 「あ………」 お互い、示し合わせたわけでもないのに、可憐の家の前で真希とばったり出くわした。 昨日と同じように今日は学校は休みになった。 真希も真由と同じように可憐のことが心配になったんだろう。 理由などはない。友達の心配をするのに理由などは必要がない。 玄関のインターホンを押すと、少しの沈黙のあと、ドアが開いた。 「マキちゃん。マユちゃんも、可憐のお見舞いに……?」 『おはようございます、小母さん』 可憐のお母さんが出てきた。 真由が可憐の様子を聞くと、俯きながら首を振った。 「よっぽどショックだったみたいで………ずっと部屋の中ですすり泣く声が聞こえるのよ………わたしも、心配で………」 真由も真希も、顔を見合わせて、言った。 「可憐………早乙女くんと、本当に好き合ってましたから………目の前であんな事があったら、誰でも………」 「………そうね………でも、待つしかないわね。ありがとう、可憐の事心配してくれて」 可憐は、良い友達を持ったわね、と言われ、二人は恥ずかしそうに、そそくさとその場を去った。 「これから、どうする?」 歩きながら真希が話しかけてきた。 「そうねぇ…………こう言うのも何だけど、せっかくの休みだし………隣町にでも行く?」 「でもあたし手持ち無い」 「…………少しくらいなら貸してあげるから、付き合ってよ」 「………ん、わかった。じゃぁ、隣町、駅にいこ、駅」 そして、真由達は隣町に行く電車に乗るため、駅に向かった。 駅に行き、乗車券を買って電車に乗り込む。 そして、電車は何事もなく、隣町に着いた。 真由がおしりを触られたこと以外は、何事もなく。 隣町。 と言っても、名前を出すほどでもない、ローカルなところ。 少なくとも真由が住んでるところよりは、店が沢山在る程度。 と言っても、二人とも入る店は大抵決まってる。 服や化粧水にはほとんど興味ないから、大抵本屋やCDショップがメイン。 真由は小説で、真希がマンガ。 かといっても、二人ともどちらも読む。 担当になってるのかもしれない。小説担当と、マンガ担当。 他には、聴く音楽は、クラシックが多い。J-POPや、洋楽も結構聞く。 最近は、Nightwishって言うのに二人は注目してるのだ。 フィンランドのグループで、ボーカルの女性ががオペラ調で凄い唄い方をしているのである。 これはもう、カラオケで歌えないね、ってくらい。 そんなこんなで、収穫はNightwishのアルバムと、BUMP OF CHICKENのユグドラシルってアルバム。 好きなモノは好きなんだから、しょうがない。 「来ないでッ!」 突然頭上からそんな怒声が聞こえて、二人は立ち止まって、顔を頭上へ向ける。 道行く人々も、何事かと立ち止まり、顔を上げていた。 すると、今は空きビルとなった、その屋上で、フェンスを乗り越えて女の人がいた。 どうやら、痴情のもつれの様だ、フェンスの内側に男の人も見える。 誰かが呼んだのだろうか、パトカーが二台、ビルの下に停車すると、中から二人ずつ四人の警官が現れた。 そのうち、二人は下で拡声器を持って屋上に呼びかけ、残りの二人は廃ビルの中に入り、屋上に駆け上がっていった。 少しすると、上からドアが開く音が聞こえた。 何となく、気になって、真由も真希も、暗黙のうちにその場で成りゆきを見守る事にした。 しかし、その選択により、二人はまた人の死に直面する事となる。 ビルの屋上で男女が二人。 一人は内側、もう一人は外側。 フェンスを挟んで、対峙する。 「もうイヤッ、もうしない、もうしないって言って、そんなに女が好きなら、何処にだって行けばいいでしょっ!」 屋上の縁に立って、怒声と悲哀が混ざった声を上げる、女性。 それに相対するのは、彼女の、夫。 夜、彼女が眠りについたあと、こっそりと家を抜け出し、そして翌日、酔っぱらって帰ってくる。 そう言う事が、たびたびあったのだ。 けれど、彼は何も言わない。 自分の何が気にくわないのか、何が不満なのかも、言ってくれない。 今回、さすがに彼女も我慢の限界だったのか、唐突に家を飛び出した。 彼の愛を信じられなくなったから。 彼の愛を信じたかったから。 だから、最後の希望と、自分がでていったら、追いかけてくれるか、どうかを。 ただ、確かめたかった。 そして、彼は、追いかけた。 彼女は、それだけで嬉しかった。 彼は、自分を愛してくれていると、思いこむ事が出来ると。 まだ、彼を信じる事が出来ると。 「珠美…………お前が、そこまで思い詰めているなんて…………」 夫が、うつむき加減で呟いた。 その言葉に、珠美は、目頭が熱くなった。 この人は反省している、まだやり直せると、愛ゆえの盲目に、浸りながら。 まだ、やり直せると、思う事にした。 けれど、もう少し、彼の心が知りたい。 もう少し。 ――メールが届くまで、あと三分―― 「あ、なんか、和解したみたい」 額に右手を当てて、逆光を遮る様に屋上を見上げていた真希があっさりそう言った。 『どんなやり取りをしていたのかはわからないけど、あの二人………恋人か夫婦か、どっちでもいいけど』 『まぁ、何とかよりを戻せたみたいね、よかった』 と、人事だけど真由はほっとした。 全く、人騒がせな………。 腕時計を見ると、午後五時三十三分。 「そろそろ日が暮れるわね、マキ、そろそろ帰らない……」 「…………まって………」 「…………どうしたの?」 「……あ、ごめん、うん………」 と言って、真希はもう一度屋上に振り返る。 「………より戻ったみたいだし、飛び降りなんて事にはならなさそうだから、大丈夫だよね」 その言葉に、私はふうと軽く息を吐きながら言った。 「二日連続で目の前が死ぬなんて………」 ――カッ――ゴロゴロ 眩い閃光と、その直後の雷鳴。 「あらら………コレは一雨来そうね、雷も心配だし、電車止まらないうちに帰ろう」 再び、稲光が轟音とともに夕暮れの町を輝かせた。 ――メールが届くまで、あと十秒―― 「ねぇ………たかし、何で、他の人の所に行っちゃうの?私、何か悪いところ、ある?」 己の夫に、まるで子供に尋ねるように穏やかな口調で珠美は訊いた。 「え………それは…………」 バツが悪そうに彼は視線をそらす。 「お願い…………私、貴方の事好きなの。愛してるの、だから、貴方の気持ちが他の人の所に行ってしまうのが怖いの………お願い、教えて」 「………………」 「たかし…………お願い」 彼の目が、少し足下のコンクリートの汚れを行ったり来たりしてそして真っ直ぐになった。 「俺………お前の事、好きだぞ?」 「………それなら、何で……」 他の人の所に…………と言う言葉は、彼女の口からは出なかった、出せなかった。 「だって……お前、酒飲ませてくれないじゃないか、自分が飲めないから、って」 「え…………?」 「そりゃぁ、飲み過ぎるつもりはないけど……たまには飲みたいし、酌ぐらいして欲しいし………」 「そ……それだけ?」 「………?それ以外に理由があると思ってるのか? 少なくとも、お前よりいい女を、俺は知らない……… ただ、酒が飲めないのが唯一の欠点って所だけど」 彼女の瞳に、涙がじんわりと浮かび上がる。 「ど、どうしたんだよ、泣く事無いだろっ」 「っっっっ!バカァッ!お酒飲みたいなら言えばイイでしょっ、お酌くらいなら好きなだってやって上げるわよっ、だからって………」 彼女がボロボロと涙をこぼすと、彼はバツが悪そうにぽりぽりと後頭部をかいた。 「………わかった。じゃぁ、はっきり言う」 そう言って、彼はすー、はー、と深呼吸をして。 「堺 敬。自分は酒が好きです、たまに愛する人とお酒を飲みながら語らうのがしたいです………コレで良いか?」 敬がそう言うと、珠美は両目から溢れる涙をぬぐって、こくりとうなずいた。 「うんっ………でも、あんまりは、ダメだからね」 「わかった………だから、珠美。こっちにおいで、そこは危ないから…………」 「うん、ごめんね、たかし………」 「いいさ、夫婦なのに、言いたい事言ってなかった俺の方がもっと悪い」 珠美が、フェンスに近寄り、よじ登ろうとしたその時。 彼女に落雷した。 ――メールが届くまで、あと十秒―― 「キャアアァァアァァァアァァァ」 突然の閃光と轟音、そして、絶叫。 声は、上から! とっさに真由は視線を上に向けた。 するとそこには、よりを戻したはずのカップルの、女性の方が屋上を飛び越えて、空中に舞っていた。 え…………っと。 突然のことだったので、きっちり三秒間、思考が停止していた。 『そうだっ!助けなきゃ』 理由はわからないけど、あの人は落ちてくる。 しかも、ビルから数メートル離れたところを、一体何が起こったのか、ずっと見てればよかった。 上に行った警官から、事態が収拾したという連絡を受けたのか、万が一落ちた場合でも大丈夫なように敷いていたマットを消防の人が片付ける。 アレ、そう言えばいつ消防の人来たんだろ、見てない。 って、そんな事考えてる時間もない、助ける時間もない。 そして、彼女は…………… ――メールが届くまで、あと一秒―― 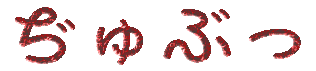 「あ……ぐぁっ はぁ……っ」 ビルから離れる事、数メートル。 そこには、等間隔に設置されている、街灯が存在した。 そのデザインは、支柱を挟むように球状のライトが二個ずつ付いて、支柱の先端は、まるで槍のように尖っていた。 そう、槍のように。 そして、彼女は、その支柱に腹部から突き刺さった。 「アアAa嗚呼アァ亜あァァぁァあァぁぁァ亞ぁあァアッッ!!!!!!!!!」 激痛に、耳をふさぎたくなるような絶叫が、彼女の口から怒号の如くあふれ出る。 鮮血が突き刺された腹部から流れ出て街灯を伝う。 そして彼女も、その口内からゴポリと泡だった血を数度吐き出し。 それっきり動かない。 街灯の明かりは、白色のライト。 時間によって作動するライトは、丁度その時間に一斉につき始める。 等間隔に点在する街灯の中にただ一つ、赤く照らす街灯が生まれた。 彼女のポケットから落ちた携帯電話が、カラカラと音を立てて、真由の足下に転がってきた。 彼女は、何故か、目の前の凄惨な光景に慌てる事もなくその携帯を、拾った。 『………ロリロ、ピロリロ』 どくんと、心臓が飛び跳ねた。 このパターンは彼女は知っていた。そして、この電話に来た【メール】の内容も。 真由は、おそるおそるメールボックスを開いて、メールの内容を………読もうとしたところで、題名に気付いた。 【お迎えです】 |