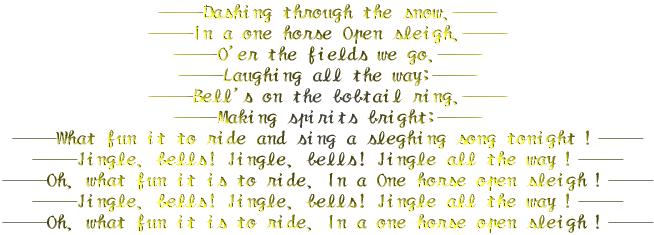日は既に落ち、夜の闇が町全体を覆い尽くしている。 金色に輝く月が、ささやかな光を町全体に施していた。 そんな中、鮮やかな『青色』のコートを纏い、頭までフードをかぶった小柄な人影がトコトコと歩いていた。 表情は見えないが、ほんの少しの街灯が、ほんの少しだけその影の顔を照らしている。 血色の良い桜色の唇が規則正しく動き、その口内から息が断続的に吹き出す。 すると、不意にその人物はコートのポケットに手を突っ込み、そこから折りたたまれた紙を取り出した。 ビニールコーティングをされている何かの情報誌。 『ご自由にお取りください』 と銘打たれている、何処にでも置いてあるようなパンフレットだった。 「んーと………………この辺だと思ったんだけど………」 妙に高い声だった、男とも女とも取れない声をその影は発した。 ぱたぱたとパンフレットを閉じて、再びポケットに突っ込むと、影は首をきょろきょろと動かしながら歩き始めた。 しばらく歩き、街の角をいくつか曲がると、すぐ目の前に洋菓子店が現れる。 既に営業時間も過ぎ、店内の明かりは一つだけにされ。 その中で1人、店員とおぼしき人影がほうきを片手に床を掃いているのが見えた。 それを見て、町を徘徊していた影は嬉しそうに足を速める。 閉店している店に駆け寄って、ガラス張りの壁を、コンコンとノックした。 その店の中で掃除をしていた人影はすっと顔を上げて、音のしたガラスの方へと顔を向ける。 ガラス越しの向こう側、ノックをしたその人物は、頭に被せていたフードをぱさりと背中側に下ろした。 すると、見事なまでの『銀髪』が現れ、外の月の光と、店内から外へ漏れる電灯の光が当たり、キラキラと輝いた。 そして、二人の視線が絡み合う。  洋菓子店『Sweet Kiss』 その業界では知らないモノなど居ない、とも言われる個人経営の洋菓子店。 店主は女性で、しかも若い。 彼女はチョコレートのような黒髪、生クリームのような白い肌、苺のような赤い唇。 洋菓子に必要不可欠なモノのオンパレードの外見をしている。 そして名前は『美景 春美』 甘さそのままカロリー控えめなケーキ。甘くないケーキ等も彼女は作る。 故に、ダイエットを気にする女性に絶大な支持を受けている。 そんな有名な洋菓子店の、応接室にて。 『赤い』コートを身に纏った、『金髪』の子供が、ふかふかのソファーに座っていた。 「全く、来るなら来るって言ってくれればいいのに………売れ残りしかないですけど、ごめんなさいね」 トレイにケーキを二つ、湯気を立てて香りを立てるマグカップを持って、美景 春美はその応接室に入ってきた。 「あはは、ごめんねー。まさかテレビに映るとは思っていなくて。それにぼく、早く会いたかったから、連絡忘れちゃって………」 一人称から判断すると少年だろう。ただ、『ぼく』を一人称とする女の子もいるから、断言は出来ないが。 春美は微笑みつつ、ケーキとマグカップを少女の目の前にコトリと置く。 「どうぞ、ミスティ、温かいミルクココアですよ」 春美はそう言うと、少年に向かい合うようにソファーに腰を下ろす。 ミスティ、と呼ばれた少年。呼ばれたからにはそれが彼の名前なのだろう。 ミスティはマグカップを両手で包み込むように持ち上げると、中に入っている飲み物にフーと一つ息を吹きかける。 暖かく甘い香りがミスティの鼻孔をくすぐる。 小さな唇をカップの縁に付けて、ミスティはミルクココアをすすった。 はふぅ、と少年の割に色気のある溜息を漏らしてカップをテーブルに置いた。 「で………?元気そうですけど、どうしました?」 春美が嬉しそうに微笑んで、そう尋ねた。 「あ、うん、ぼく元気だよ」 フォークで目の前に出されたショートケーキの苺をぶすっと突き刺す。 「あっちこっち行ったの、えっとね、フランス、オランダ。アメリカも行ったし、ブラジル、チリ、アルゼンチン………」 ミスティは右手にフォークを持ちながら、左手で指折り数える。 「そう………楽しかったですか………?」 苺をほおばりながら質問に答える。 「んとねー………ねぇ、苺貰って良い?」 話し出そうとしたところで、ミスティはめざとく春美のショートケーキに狙いを定めてそう言った。 苦笑しながら『どうぞ』と言って春美はショートケーキを差し出す。 満面の笑みを浮かべ、ミスティは遠慮無く苺を串刺しにして口の中に運んだ。 もぐもぐと租借し、ごくりと飲み込んで後、ミスティは言った。 「んとね、色々大変だったけど、楽しかったよ」 「ふ〜ん………」 美景 春美は、目の前で口の周りを生クリームでべとべとにしながらケーキを食べるミスティを見ながら嬉しそうに微笑んだ。 最後の一口を口の中に放り込んで、もぐもぐと租借して飲み込む。 そして、きょろきょろとテーブルの周囲に何かを探すように見渡した後。 「ま、いっか」 といって、赤いコートの裾を掴んで口の周りをごしごしと拭こうと……… 「あぁっ、もうっ、ほら、貸してください」 慌てて春美が腰を浮かし、テーブルに左手を付いて、 胸ポケットから苺マークの付いたハンカチを取り出して、テーブルの向こう側にいるミスティに手を伸ばす。 「まったくもう、フォーク使ってるのにどうして口の周りにクリームが付くんですか……」 そう言いながら春美はミスティの口の周りのクリームをハンカチで拭き取る。 「えへへ、ありがと♪」 「いいえ、どういたしまして」 吹き終わり、ハンカチをたたみ直して胸ポケットに放り込む。 「で………どうするんです?ミスティ」 「へ?」 はぁ、と溜息をついて春美は時計に目をやる。 午後11時、子供は既に寝る時間。 「『へ?』じゃありませんよ、こんな時間に来るなんて………泊まる場所は確保してるんでしょうね?」 「………ケーキもう一個食べていい?」 「え?構いませんけど………野宿するつもりですか?」 春美はお皿ごとケーキをミスティの目の前に滑らせ、溜息混じりでそう言った。 「えへへ………」 そして、ミスティは嬉しそうにケーキにフォークを突き立てて。 「美春って、何処で生活してるの?」 一口目をぱくりとクチに放り込んで、そう言った。 「わ〜、おっきー、きれ〜〜〜」 Sweet Kissの裏から車は出発し、隣の県へと入って海岸線を走っていた。 両側とも目も眩むような崖な場所を数十分走っていただろうか。 不意に右側の崖が途切れると、入り江を挟んで向こうの岬に、馬鹿でかい建造物が現れた。 照らす物は月明かりのみ、その月明かりに照らされて、その建物はどこか物憂げに、そして、異世界の建物のような雰囲気を纏わせていた。 「わ〜、おっき〜、ひろ〜い、きれ〜〜〜」 建物を見て後十数分、ようやく春美の運転する車は建物を目の前に捕らえた。 そして、ぐいっと首を真上に向けてすら、建物の全景を視界に収められないほどに近づいていた。 「ねぇねぇっ、ここに住んでるの?他の人はっ?」 後部座席で喜々として、かたかたと車内を揺らしながらミスティが言った。 「お願いですから揺らさないでください………今使ってるのは私だけです。と言うよりも、私は使わない訳にはいかないですから」 ミスティをたしなめつつ、視線はじっと前を見据えて春美がそう言った。 ――ぐぅ〜………きゅるるるる 「………何の音ですか?」 「えへ………えへへ………やっぱりケーキはおやつだね、ご飯食べなきゃ………」 春美がルームミラーに映ったミスティの顔を見ると、ほんのり頬を赤くしていた。 「判りました、すぐご飯作ってあげますから………だから動くなっ!」 ピタッ、と車の振動が規則的な物に変わる。 「はぁ〜い………」 キコキコと動かしていた上半身を停止させ、後部座席に背中全部ぺったりともたれ掛かる。 そして、ドアに左肩を付けて、ことんと窓ガラスに側頭部をぶつけた。 「ミスティ、ミスティ、着きましたよ。ほら、起きてください、ミスティっ!」 後部座席の右のドアを開けて、春美は体を半分乗り込ませてミスティの肩を揺する。 「う、う〜ん……………」 「起きましたか?ミス………」 「カレー食べたい…………」 ガクッと、座席のシートについてた左手の力が抜けた。 「全く、仕方ないですね…………『ミカゲ』………」 呆れながら体を車の外に全て出した後、春美はそう言った。 すると、どうした事か。 月明かりに照らされて生まれたミスティの影が、その本体の体から離れ、同じ輪郭でその隣に座る形で実体化した。 輪郭が、全く同じ。 座席に座っている形であるにも加えて、【影】が実体化しているだけに過ぎない。 だから、目や耳、鼻や口と言った【顔の付属品】のような物は、形こそはあるものの、真っ黒でその機能があるとは思えない。 ただ、春美は構わずこう言った。 「その子、抱き上げて降ろしください、中の部屋で寝かせましょう」 すると、実体化した影はこくりと頷くような仕草をすると、座席と背中の間に手を突っ込み、膝の下から右手を回す。 そして、軽々と抱き上げると、ずりずりと動いて車から降りる。 ミスティ本人は、未だに寝息を立てていた。 「はぁ………全くもう、寝顔は極上の天使なんだから………」 それだけを言って、春美は建物に歩いていき、正面玄関を開く。 そして、実体化した影も、ミスティを抱き上げたまま、春美の後を追って建物の中に入った。 真っ白なベットの上に、不自然なふくらみ。 窓から差し込む太陽の光にもぞもぞと布団の中で身じろぎをしていたかと思うと…… 「ふ………ぁ〜〜〜〜………ぁ?」 とつぜんむくりと起きあがって、一つ大きなアクビをしながら上半身のみで精一杯の伸びをし、最後に疑問符が付いた。 レースのカーテン、差し込む光、豪華な調度品、可愛いアンティーク、ふかふかなベッド、ふかふかな枕、そしてやけに大きいシングルベッド。 ちゅんちゅんと、窓の外の小鳥のさえずりをバックグラウンドミュージックにして、ぼさぼさの『銀髪』を手で軽く撫でながら呟いた 「ここどこ?」 と、その時、正面右の壁に位置していたドアが開かれた。 「お早う御座います、ミスティ。ぐっすりお休みでしたね」 開かれた扉から、カラカラとカートを押して、春美が笑顔で入ってきた。 「……………あっ、ここってあの建物か」 と、ようやく気付いたようだった。 「そうですよ、あの後あなた眠ってしまってましたから、そのまま眠らせてあげたんです………おなかすいたでしょう?ご飯持ってきましたから」 と春美が言いながらベットの横でカートを止める。 すると、ミスティはひくひくと鼻を動かして、ハイハイでベットの中央部から端へと寄ってくる。 「カレーの匂い………」 ミスティのその声を聞くと、『正解』と言って春美は微笑みながら器を手渡す。 「はい、どうぞ、食べたかったんでしょう?」 壊れ物を扱うような手つきで春美から器を受け取ると、ミスティは再びずりずりとベッドの上を移動する。 ぺたりとお尻を付けて、するりと両足をベッドの端から投げ出す。 そして、変わった持ち方でスプーンを握り、カレーをぱくぱくと食べ始めた。 ほっぺたの周りのカレーの跡を拭き、空っぽの器を舐めようとするミスティから器を奪ってカートに置く。 「ふぅ〜、お腹いっぱ〜い」 ぽふっと背中からベットに倒れ込んで、ぽこんとなったお腹をなでなでする。 「……………春美、今日もお仕事?」 「えっ?」 唐突に訊かれて思わず何が何だか聞き返す。 「はぁ〜…………遊びたかったのになぁ………」 じっと天井のシミを数えるミスティの『金髪』が、哀しくベッドに広がる。 「えっと、今日は休みですけど………」 と言った瞬間、ミスティの髪の毛が一瞬にして鮮やかな銀髪へと変化した。 「ほんとっ!?おやすみなのっ?」 上体を起こして、純真無垢な金色の瞳をキラキラと輝かせて春美を見る。 「え、ええ………あ、お店は休みじゃないですけれど………まぁ、品物はすでに用意してありますし、後はアルバイトの人達だけでも…………」 「じゃっ、じゃぁさ、じゃあさ。あのね、あのねっ、ぼく遊園地行きたいの、遊園地。お願い、連れてって、春美っ」 はっしと春美の右手を取って、ブンブンと振りながらミスティはそう言った。 やれやれ、と溜息をつきながらも、春美はどこか嬉しそうにミスティの手を握りかえした。 「そうですね………それじゃぁ行きましょうか、他の方も喚びましょうか?きっと、あなたが会いたい、って言ったら来てくれると思いますよ?」 春美のその言葉に、ミスティは満面の笑みを浮かべてこくこくと頷いた。 『…………と、言うわけなんです』 「へぇ〜、ミスティか、久しぶりな名前ね、もう3年くらいかしら?」 友人の私室の、ベッドの上で、体育座りでファッション情報誌を広げながら、しかし雑誌に目を向けるも内容は全く頭に入ってこない。 そして、床の上でクッションに座って一心不乱にゲームをしている友人をちらりと見ながら、再び携帯電話の会話に集中する。 『それで…………大丈夫ですか?ミスティがみんなに会いたい、と言ってるんですけど………【ミク】は………?』 「あぁ〜、うん、あたしも大丈夫よ。マドカんちに来てるのはただ暇だっただけだし……………マドカ、泣かないでよ………」 ゲームを一時中断して、上目遣いで、ぽろぽろと涙をこぼしながらやってきた友人を見下ろしながら彼女はそう言った。 もちろん、携帯電話の音声送信側は手で押さえている。 「ひどい…………みく、あなたにとって私は単なる暇つぶしの導具だったって言うの………?」 「んー、ちゅーかね。あんたといると楽しいんだけど………やっぱり優先するのはミスティかな、って思って」 ミクがそうあっさり言うと、マドカの顔がもの凄い事になった。 「うわっ………あ、あのね、ミスティとは古い知り合いなのよ、それでその子があたしに会いたいって言ってる訳で………」 「みく、みくは今の友達と昔の友達どっちを取るの………?」 「昔」 即答されてさらに凄い事になる。 「うっわっ………」 『………あの、ミク、もしよろしければ、そちらにいるお友達も一緒にいらしてはどうですか?』 「へっ?」 予想だにしない電話の声に思わずミクは素っ頓狂な声を上げる。 「何言ってんのよ、ミスティの能力見られでもしたら…………あ、いや、大丈夫か」 『?』 「ううん、何でもない、こっちの話。んで、どうするの?いつもん所にいるんでしょ?そっち行けばいいわけ?」 ミクの言葉に、うーんと電話の声は唸った。 「どしたの?あそこなら人気もほとんど無いから…………」 『いえ、ミスティが遊園地に行きたいと言って…………』 「…………大丈夫なの?それって」 数秒の間があって、ミクが困ったように言った。 『大丈夫だと思いますよ?紫陽花は一番下にすればいいわけですし、後は上に何か羽織って、帽子をかぶれば………』 「たしかに。あの子、歳が一緒なら顔も一緒だからね……」 『そうでしょう?ですから、お願いしますね、ミク………あ、お友達も一緒に来られてくださいね』 「で、何処の遊園地?」 最も重要な事を、ようやくミクは訊いた。 Stardust Rainbow Park スターダスト・レインボウ・パーク 世界最大とギネスに登録される事12年、いまだに破られていない海上遊園地。 その入場ゲートの所に5人は立っていた。 「ほぇ〜、さすがにおっきいねー…………」 紫色のリュックサックを背負って、ミスティが驚きのあまりそう漏らした。 園内に入っていないのに、すでにジェットコースターのレールが見える。 また、もの凄く大きな観覧車がずーっと奥でゆっくりと回っているのが見えた。 「……………で、どうしましょうコレ…………」 と言って春美が置いた紙袋の中にあるものは、上記した遊園地の、全てのアトラクションのフリーパスポート。 しかも、ただのフリーパスポートではない。 名前通りのゴールドフリーパスポート、有効期限は無い。 純金で出来ていて、何らかの書体で文字が書かれ、中央には1ctの天然ダイヤモンドが永遠の輝きを象徴している。 重さは一枚約50g 金の値段を1g1000円として、それにダイヤの値段を加算すると、おおよそ一枚10万円となる。 そして、その数……………狂い無くぴたりと100枚。 総額1000万円。 「いくらミスティが遊園地に行きたいって言ったからって………此処までしなくても………ホウカは何考えてんのかしら」 あきれ果てたようにミクは額に手を当てて、やれやれと溜息をつく。 「まぁ、ミスティはオウカも、ホウカも気に入っていたからな………ホウカの名前で渡されたが、実際用意したのはオウカだろう………」 と、ミクの後ろでマドカに腕を掴まれながら長身の男がそう言った。 「で、ミク………なぜ俺はこの女に抱きつかれてなければならないのだろうか、解答を求む」 男の言葉に、ミクはしれっとして言い捨てた。 「良いでしょ別に、ミスティも会いたいって言ってたんだから、来れない他の連ちゅーの代わりよ、文句ある?」 「………別に文句はないが…………」 「なら良いじゃない、男前よ、カンナ」 ミクはパチッとウインクをして、にこりと微笑む。 「はぁ…………まぁ、別に構わないが………で、ミスティ、何故お前は俺の腰に抱きついているのだ?」 空いてる右手で、前から腰に腕を巻き付けてぶら下がっているミスティの頭をぐいぐいと押す。 「えへへー、カンナもお久しぶり〜」 にこっと上目遣いでミスティが微笑う。 「………そうだな、久しぶりだな」 すっぽりとかぶった、キャベリンと呼ばれる帽子の上から、カンナはミスティを優しく撫でた。 「やっぱり。定番はジェットコースターとかの絶叫系よね〜」 指先でくるくるゴールドフリーパスポートをもてあそびながら、マドカが言った。 「でも、ミスティちゃん乗れるかしら?身長がちょっと気になるとこだけど…………」 「んー、たぶん平気だよー」 自分の胸の位置に来るミスティの頭をぽんぽんとマドカが撫でる。 すでに「ちゃん」付け。 と言うのも、あってすぐ『おねえちゃ〜ん』とミスティがやって抱きついてきたのだ、すぐ懐いた。 マドカも、懐かれることは嫌いではなかったし、何よりミスティは可愛かった。 カンナを巡るライバルか、と初めは身構えたが、子供だから仕方ないと思ったし、誰にでも同じような対応をする。 要するに人懐っこいだけか、との結論に至った。 カンナは無愛想だけど嫌われてるわけではないようだし……… 「ねぇねぇ、早く行こうよー、楽しそうだよー」 と、はやる気持ちを抑えきれないのか、その場でかたかたとかかとを揺らしてミスティがみんなを急かす。 春美はよいしょ、と95枚のゴールドフリーパスポートが入ってる紙袋を持ち上げた。 すると、後ろの方から優雅に歩いてきたカンナが春美から紙袋を奪う。 「あっ………」 「人目があるからな、俺が持とう」 「………ありがとうございます……」 紙袋の取っ手を左手に通し、肩にかけるようにして持つ。 そして、気にするな、と言うかのように右手をひらひらと振る。 そして、春美もスカートをひらめかせて後に続いて入園する。 ここで、五人の名前と、背格好の説明をしよう。 まずは『美景 春美』。 普段は長い黒髪を三つ編みにしているのだが、今は自由にふわりとなびかせている。 薄い桜色の長袖ワンピースを身に纏い、左手に金色の小さな腕時計を着けていた。 また、上下一対のワンピースを、腰の位置でぎゅっと縛り、背中側でちょうちょ結びにする。 さらにフェイクファーの長袖の上着を防寒用に羽織る。 そして、胸元に黒い揚羽蝶のブローチを着けて、完成である。 ゆったりとしたワンピースを腰の位置でぎゅっと締めて、さらに胸元のブローチによって豊満な胸が、たとえ重ね着をしていたとしても強調される。 彼女が動くたびにふわりと、鼻孔をくすぐる甘い香りがほとばしり、近くを歩いていた男性を思わず振り向かせた。 そして次にミク。 フルネームは『神月 美紅』で『こうづき みく』と読む。 肩の位置ですぱっと切ってるボブカットで、身につけている物はピンクのアンダーシャツ。 その上にデニムのGジャンを羽織っている、前のファスナーは閉じずに開いたままである。 下は単なるGパン、ファッション雑誌は読むものの、それほどファッションに興味のないミクの性格が顕著に表れていた。 だが、3サイズは不明。身体測定で計っているはずなのだが、なぜかその情報を知るものは極端に少ない。 親友のマドカですら、ミクの胸のサイズを知らないという有様だ。 しかも、その胸は春美より豊かなのだ。 明らかにミクは春美より年下のように見えるのに、恐るべし、最近の子供……… そして、次はミスティ。 男なんだか女なんだかよく分からないが、一人称が『ボク』だったので少年なのだろう。 ミスティは、一番下に赤いTシャツ、その上に紫色のジャンパーを羽織っている。 下は七部ズボンで明らかに寒くないと言ったらはり倒されそうな格好をしている。 しかもそれに加えて今は12月、下手したら空から雪が舞い降りてきたっておかしくないのだ。 しかし、ミスティ本人はそんな事気にする様子もなく、嬉しそうにミク、春美、マドカ、そしてカンナの間を行ったり来たりしている。 次は、マドカ。 フルネームは『時任 円』で『ときとう まどか』 高校の頃、ミクに陰湿な虐めをしていたグループのリーダーだったのだが、学校の校門でミクとカンナが話しているのを見て、一瞬にしてカンナに惚れてしまった。 結果、今では親友である。 ミク自身がカンナと付き合っているわけではない、ただ、カンナはミクが幸せになる事を望んでいる。 会ったその時のカンナのセリフからそう結論づけて、マドカはミクを苛めるのをやめた、やめさせた。 そして、カンナのセリフの中にある、深い意味にも何となく気付き、そして『美紅』を知る唯一の人間でもある。 最近は美紅の胸が気になるらしい。 高校の頃からずっと、ミクは巨乳と言われていた、校内No1である。 ただ、そのサイズを知る者はいない、なぜなら当の本人が触らせてくれないからである。 故に今、マドカの『知りたい事ランキング』に、ミクの胸のサイズがここ数年トップを維持していた。 ちなみに今日つけてる服はチェックのミニスカに、茶色のダッフルコート。 白いタイツを履いて足の防寒対策はバッチリである。 この前買ったクロスのペンダントを首に掛けてお出かけスタイル完了である。 後は少し化粧をしているが、特に代わり映えしないので割愛する。 そして、最後にカンナ。 身長183cm、美形。 二人目の男である。 趣味は遊ぶ事、と言うより娯楽が好き。 最近は麻雀やビリヤード、ボーリングやカードなどもする。 つり目の三白眼、と言うのも背が高い為で。大抵見下ろすような形になるので自然にそうなってしまうのである。 彼は悪くない。 身に着けてる衣服は、中に何か隠してるんじゃないか、と思われても仕方ないほどゆったりとした真っ黒のコート。 どこぞのエージェントか、と思って振り返る人と、カッコいい人、と思って振り返る人が半々くらいかもしれない。 どうでも良いかもしれないが、この五人組、やたら顔が良い。 おそらく毎日鏡と睨めっこしているのだろう、芸能界に入って、テレビ映えしそうな顔のオンパレードである。 その中で1人、マドカは雑誌のモデルをした事があるが、今はしていない。 なぜなら、自分より親友のミクの方がスタイル良いからだった。 「きゃぁああああぁぁあぁ〜」 「きゃ〜〜〜ははははははは〜」 二つの悲鳴が見事に重なり合う。 プシュー、と音を立てて、世界最大のジェットコースター『エル・トール』は出発地点に戻ってきた。 「もー、マドカおねえちゃんしっかりしてよ〜」 「わ、わらひ、もうらめ………」 「え〜?でもまだ2回目だよー?後3回は乗ろうよー」 「う………うえぇ………」 半分泣き出しそうになっているのは、上記した『エル・トール』に半ば無理矢理、引きずられるように乗せられたマドカだ。 そしてその隣でミスティは何とも楽しそうに天使の笑みを振りまいていた。 「…………マドカ、絶叫系苦手だったのね………」 「…………いや、コレは苦手だからと言うレベルでは……」 ミクの呟きに春美が返す。 そして目の前にそびえ立つコースターを見上げた。 『エル・トール』 全長3253m、高さ144mの位置から、傾斜70度の坂を一気に落ちるのが最初だ。 最高速度は時速200kmを越える、バケモノコースターである。 しかし、事故を起こした事は一度もない。 と言うよりも、このスターダスト・レインボウ・パーク無いで起こった事故と言ったら、ミラーハウスで出口だと思って勢い良く壁にぶつかるとか。 ゴーカート同士がぶつかってクラッシュする、と言ったその程度であった。 安全性はとことん追求する、誰もが笑顔で帰っていくような、そんな楽しい場所であり続けたい、と言う制作者の望みの結果であった。 「た、たひゅけ………」 順番待ちをしていた他の利用客を尻目に、フリーパスでそそくさと先に乗った。 最初はマドカもノリノリだったのだが、一週を終えて帰ってきた瞬間、立てなかった。 瞳孔が開いて、クチをぱくぱくと開閉させる事しかできなかった。 しかし、それを見て何を思ったのか、ミスティは。 「ぼくもう一回のろ〜っと」 と、マドカの隣に座って、もう一週。 ミク、春美、カンナは他の利用客に席を譲って、一足先に降りていた。 コースターから思いっきりあふれ出る絶叫に、複雑そうな笑みを浮かべながら。 まぁ、『楽しんでるなら良いか』と心の中でマドカを哀れんだ。 「うぇ、うえぇ………ふえぇええぇ」 「ほらマドカ、しゃきっとしなさいしゃきっと」 「だ、だってぇ…………」 膝がガクガクと盛大に、凄まじく、もの凄く笑っていた。 エル・トールに乗る直前に用を足していたため、失禁なんて言う最悪の事態は避けられたものの、立つ事すらままならない状態だった。 よたよたと、マドカに肩を貸しながらコースターから離れて、ベンチに腰掛けさせる。 そして、ふとコースターを見ると、なるほど。 すぐ隣にトイレと売店。 しかも売店には下着まで売ってる、計算ずくか……… それ以前に、失禁してしまうほどのコースター作った奴の顔が見たいくらいだった。 「ミスティ、なにか飲み物………あ、飲み物はお金いりますよ?はいコレ」 と、春美はミスティに千円札を握らせ、売店へと向かわせる。 すると、コーンポタージュを五本買って戻ってきた。 「はい、どーぞ」 えへへ、とにこやかに笑うミスティの顔に、マドカは思わず苦笑しながら礼を言った。 「ありがと」 缶を受け取って、ぷしゅっと開ける。 コーンポタージュ独特の良い香りが鼻孔をくすぐる。 そして、一つ溜息をこぼして、缶に口を付けてごくりと飲み込む。 「あったかい…………」 「ねぇ、ねぇ、もう大丈夫?じゃぁもう一回乗らない?」 と言ったミスティに、すかさず三人が『コラ』と言った。 「同じのばっか乗ってちゃダメでしょ。遊園地はコースターだけじゃないんだし、他の客もいるんだから………」 「そうですよミスティ、他のアトラクションも回って、その後また乗ればいいでしょう」 「同感だな。不満だろうが………まぁ、これ以上こっちを酷使するな、怯えてるぞ?」 と言ってカンナがベンチに座ってるマドカを指さす。 瞳孔が開いた状態で唇を青くしてぷるぷると震えている。 「………はぁ〜い、じゃぁ………また後で」 ほっ、とミスティ以外の四人が全く同じタイミングで息を吐いた。 「えっと、じゃぁ………」 しかし、安心するのは早すぎた。 スターダスト・レインボウ・パークは、広い。 ミスティが飽きる事は、たとえ10年かかったって有り得ないほど、遊ぶところはあるのだ。 「ギャーーーーーーーーーッ」 「キャハハハハハ」 再び、悲鳴が二つ。 スターダスト・レインボウ・パークの目玉のアトラクション。 『デス・リボン・レボリューション』 ジェットコースターに並ぶ、メインのアトラクション、いわゆるホラーハウスである。 しかも、その中は一つの学校になっている。 コレもまた、『学校のホラーハウスを作った』のではなく、『学校をホラーハウスにした』としかか思えないほどリアルだった。 さらに、どれほどのお金を使ってるのだろうか、ただのホラーハウスではなく、天井が存在する。 天井には満月がホログラフで常に同じ位置で映し出され、ホウホウと言うフクロウの鳴き声と、野良犬の遠吠えが断続的に聞こえてきた。 つまり、一つの大きな建物の中に、学校が丸々一つ入ってる形になっている。 そして、そのアトラクションのルールと仕掛けが、またリアルだった。 ただ入って出るのではなく、校内をある程度回って、鍵を集めなければならない。 音楽室の鍵や、家庭科教室の鍵、体育館の鍵や、体育倉庫の鍵、職員室等々。 ………アトラクションの事はどうでも良い、それよりはまず、そのアトラクションに参加している二人の様子が気になるところだろう。 再び、ミスティ・マドカのペア。 腕に抱きつかれて、上目遣いでお願いされてしまったら、無下に断る事などできやしない。 哀れ、マドカはミスティに振り回される結果になった。 「いっっっゃあぁぁあぁぁぁぁぁあぁぁぁあ〜〜〜」 ホログラフ………映像に決まってると判っているはずなのに、それでもマドカは脇目もふらず廊下を突っ走っていた。 そしてその隣を楽しそうに併走するミスティ、息切れ一つしていない。 追いかけてくるのは人体模型。 理科室に入って、職員室の鍵を探している真っ最中、ミスティが人体模型に触ろうとして。 そして、動き出した。 突然ガタン、と音がする。 そして、ゆっくりと人体模型が動き始めた。 声のない悲鳴を上げて、マドカは脱兎の如く理科室を飛び出した。 で、今現在、人体模型はその腹部から内臓を飛び散らせながら追ってきている。 ご丁寧に、スピーカーからはびちゃっ、びちゃっ、と言う効果音が断続的に聞こえてくる。 それから数十分、他の利用客の悲鳴と、マドカの声が、凄まじく響き続けた。 「はっ、はぁっ、はひっ、はぁっ、はぁっ、はぁっ、はぁっ、はぁっ、はうっ………」 既に死にそうなマドカの額を、濡らしてきたタオルで汗を拭き取る。 「汗だくね………マドカ………風邪引くわよ?着替え買ってきたら?」 といって、ミクがホラーハウスの隣の公衆トイレと売店を指さした。 計算ずくか…………というか、また下着まで売ってるし。 恐怖に漏らすかもしれないというまで作り込む必要が何処にあるのだろうか、と思ったが、言うまでの元気はマドカにはなかった。 「はぁ、はふー、はふ〜…………」 何度か深呼吸をして、ようやく呼吸を整える。 「………着替えてきます………」 と言ってベンチから起きあがり、売店で上下一式買ってトイレの中に消えた。 「…………ミスティ、楽しかった?」 「うん」 「………人間には刺激が強いみたいね、やっぱり此処は」 「だから人気なんじゃないのか?」 「まぁ、そうかもしれないけれど………あのマドカがあそこまで………」 苦笑しつつ視線をトイレに向けていると、マドカが出てきた。 チェックのミニスカの代わりに赤いミニスカート。 白いタイツの替わりに黒のニーソックス。 汗を吸った青のワイシャツの代わりに白のワイシャツを着けて、ダッフルコート。 がらりと衣装を変えて、ひとまず風邪をひく事は無さそうだ。 「………ただいま……」 「おかえり」 四人の声が重なる。 「………あのさ、あたしとマドカは自由に回ってきても良いかな?」 「えっ…………?」 少し考えるような仕草の後のミクの言葉に、ミスティは思わず驚いた。 「ほら、ミスティそんな顔しない、春美にカンナもいるじゃない。わたし達は、わたし達で回ってみるから、そっちは三人で回って、ね?」 ミクの言葉にほんの少し寂しそうな顔をしたが、すぐ笑顔になって頷いた。 「ありがと、じゃ、後で集合しようね。パレードもあるみたいだし、花火も見るし……」 それじゃ、と言って、マドカの手を握りながらミクは人混みの中に消えた。 「…………はしゃぎすぎたかなぁ?人間のお友達って久しぶりだったんだもん………」 ポツリと呟くミスティの頭に、春美とカンナがそっと手を置いた。 「確かに、自分と相手は違うと言う事を自覚しなくてはな。急ぐ事はない、そのうちお前も出来るだろ」 「そうですよ、そのうち、焦る事はないです」 そして、二人はミスティの頭を帽子越しになで、ミスティは、嬉しそうに笑った。 「ありがと、ミク…………元気なのは良いけれど、さすがにあそこまで引っ張り回されるとは思ってなかったわよ私………」 はぁ〜、と心底安堵したように溜息を漏らすマドカの肩を、ポンポンと優しく叩く。 「ミスティはただの子供じゃないから仕方ないわよ、それにあの子人見知りしないし……」 「ふーん………あんたと同じ?」 「………そ、あたしと同じ、春美も、カンナもね」 なんの気兼ねなしに訊いた言葉、帰ってきた言葉に思わず絶句する。 「…………いや、ちょっと、ひょっとしてあんた気付いてなかったわけ?」 『こくり』 「あー………てっきり気付いてるモノと………だってほら、あたしら呼び捨てしてるでしょ?基本的にあたしら同等なのよ」 「………ミスティも?」 「『ちゃん』って呼んであげてね。呼び方突然変わったらあの子困るから。そうね、あの子も一緒、だけど成立はあたしらとはちょっと違うけど………」 「けど………?」 「………いや、なんでもない、さてと、何処いこっか?」 と、ミクが会話を切り上げてそう尋ねた瞬間、ベンチに座っていた男達が不意に立ち上がって二人を通せんぼした。 あからさまにイヤそうな顔をするが、目の前の男達は気付かずにへらへらと笑いながら言った。 「なぁ、君ら二人だけ?よかったら遊ばん?」 The・ナ ン パ! しかし、二人はこの手のナンパは慣れていた。 そして、二人はにこりと微笑んだ。 そして男達は、おっ、っと思いながら顔をほころばせた。 マドカはモデル経験者、ミクはそう言った経験はないがそもそも彼女は人間ではない。 『神獣』 人より遥かに上のランクの存在。 人でないのに人と同じような姿を持ち、そして人を遥かに超えた身体能力を兼ね備えている。 美貌もまたしかり。 基本的に絶世の美女として歴史に残っている人物は神獣だった、と言うオチなのだが、そこら辺は関係が無いので割愛する。 「ごめーん、あたし、体目的で近づいてくる男って嫌いなの〜」 「ごめーん、ミクが嫌いって言うなら私もきらーい、ミクが嫌った人間ってろくな人間いないしー」 『ねー』 と二人で顔を見合わせて満面な笑みでボロクソ言って、男達をかき分けるように立ち去ろうとする。 すると、微笑まれて脈有りか?と思った瞬間あのセリフだったため凍結していた男達が一斉に解凍した。 「んだとコラぁッ」 男の1人がマドカの右手を掴もうとした。 すると、男の右手がマドカの左手首を掴んだその時、踵でくるりと一回転をし、男の体の下に己の体を滑り込ませ、見事な一本背負いを決めた。 「一本、それまでっ」 「Vっ」 ピースでにこやかにマドカが勝利のポーズを取る。 ところが、投げ飛ばしただけでは致命傷を与えるに至らなかったようだ。 マドカが投げ飛ばした男を仲間の男が助け起こし、じりじりと迫ってくる。 「てめぇ、このクソアマぁ………」 「マドカ…………」 「ミク…………」 じりじりと迫りよる男達から、じりじりと後ずさりしながら。 二手に分かれて逃げ出した。 「逃がすなっ!絶対○○○して、○○○○して、○○で○○、○○の○○にしてやる!!!!!」 聞くに堪えない下劣な罵詈雑言、18歳未満禁止の言葉の限りを尽くし………… 三十秒後、全員捕まった。 「あっはっはっはっは。あー、面白かった、たまにはああいうのと遊ぶのも良いわねー」 「はっ、ふっ、はぁ〜………ふぅ………そうね、相変わらず息一つ乱さないのね………」 てくてくと歩きながら嬉しそうに笑うのはミク。 その隣で胸に手を当てて深呼吸し、息を整えながらマドカは呆れながら言った。 「んー、まぁね。こんなコトしてても神獣だから、やっぱ人間より体力はあるし………ミスティ見ればわかるでしょ?」 ミクにそう言われ、なるほど、と言った感じに苦笑した。 「ミスティちゃんも元気いっぱいよねー、もう年寄りの体力じゃぁついていくのが精一杯ね」 「何言ってんのよ、花の高校三年生がそんな事言ってて言い訳?」 「…………やばいなぁ………」 「危険よ〜?」 一瞬沈黙。 「ふふふ………」 「ははは………」 「ふふふふふふ………」 「はははははは………」 「くふふふふふふふ………」 「ふははははははは………」 『って………』 『怖いわっ!』 十二月のとある一日、遊園地のある場所で、他のお客が沢山居る中、高笑いする女子高校生が二人。 もの凄い希有の目で見られたとさ。 時計の時刻は、既に午後5時を回っていた。 すでに日は沈みかけ、観覧車のネオンも既に点いている。 「は〜、楽しかった〜、でももうちょっと遊びたかったなー。今度またこよーね、今度はもっと沢山で来れると良いなぁ……」 右手を春美、左手をカンナに握られて、嬉しそうに行進するミスティ。 端から見たら、仲むつまじい親子にしか見えないその光景。 しかし、その三人で某国の太平洋艦隊と真正面からぶつかって、あっさり勝てるほどの力を持っている事を、想像出来る人などいるだろうか。 いないだろう。 そもそも彼らの名前は伝説や神話の類にしか現れない、実際目の当たりにした人間などは数えるほどしかいないのだ。 『神獣』 それが彼らを統括する呼称。 万物の霊長は人間、確かにそうだろう。 ただ、知らない故に幸せなのだから。 この世界に、想像を絶するほどの力を持ったものが存在している事を。 そして、彼らは、決して支配する事を望んでなどいない事さえも。 「あ、ミク〜、マドカおねえちゃんお帰り〜。あのね、もうすぐパレードと花火なんだって、一緒に見よっ、ねっ?」 と、抱きついて上目遣いに懇願するミスティに、マドカは苦笑気味で困惑する。 (この子が神獣………か、ただの人なつっこい男の子にしか見えないんだけどね…………) と、思わず頭に手を置いて撫でたとき、突風が吹いてミスティの帽子が吹き飛ばされた。 「あっ、ぼくの帽子………」 すると、マドカの目に飛び込んできたのは、見た事もない雪のような白銀の髪、シルバーブロンド。 ところが、次の瞬間さらに驚く事が起こった。 「ぼくの帽子〜」 風の気の向くままに転がっていく帽子を追いかけるミスティのその髪の毛。 その髪の毛が、すっと音もなく銀髪から金髪へと変わっていったのだ。 「なっ………えっ?あっ………えっ?」 驚きの声を上げるマドカの口を背後からぴたりとミクが押さえる。 「静かに、みんな時計見てて気付いてないから………」 そう言ってミクは早く帰ってくるようにミスティを手招きする。 「えへへ、ごめんね」 帽子を拾って戻ってくる途中、再びミスティの髪の毛が金髪から銀髪へと代わった。 「ど、どういう事?」 「つまり…………そうね、お風呂一緒に入れば判るわよね」 「?」 頭に疑問符を浮かべるマドカをさらりとかわし、ミクはミスティの頭をなでなでした。 それにマドカも一つ溜息をこぼしたももの、反対側、ミスティを挟み込むように立って、肩に手を置いてぎゅっと抱き寄せた。 そんな光景を後ろから見ているカンナと春美。 「やれやれ………」 「可愛さというものは、誰からも愛される為にあるようなものですね」 微笑みながら言う春美の言葉に、そうだな、とだけカンナは返す。 すると、不意に目の前を白いものが横切る。 「………雪………?」 「そうか、もう12月ですからね、明日はクリスマスですし………」 「そうか、そうだな………この様子だと、ホワイトクリスマスになりそうだ」 視線の先で、マドカが『雪』を、ミスティが『Jingle Bell』を口ずさんでいるのを、ミクがシャーペンで指揮していた。 そして、そんな光景を、他の客達もクスクスと楽しそうに見て笑っていた。 そう、明日はクリスマス。 何か良い事、ありますようにと。 恋人達にとっても一大行事。 そして、神獣の中でも特に辛い過去を持つミスティにとっても。 とっても、とっても大切な一日。 そして今日も、今までのミスティの生きてきた日々の中でも格別に、忘れられ無い良い日になったのだろう……… ――雪やこんこ 霰やこんこ―― ――降っては降っては ずんずん積る―― ――山も野原も 綿帽子かぶり―― ――枯木残らず 花が咲く―― ――雪やこんこ 霰やこんこ―― ――降っても降っても まだ降りやまぬ―― ――犬は喜び 庭駈けまわり―― ――猫は火燵で丸くなる―― 澄んだ声は、高らかに鳴り響き、花火の轟音でもかき消える事はなく聞こえる。 白い雪は、ひらひらと舞い降りる妖精のように。 白く暖かいミスティの肌に触れ、ゆっくりと溶けた。
『メリー・クリスマスっ♪』 |