天津彦根と天津日高
序文
古事記上巻において、いわゆる日向三代の神名中に現われる名辞「天津日高」を何と読むのか、日本古典文学大系『古事記』などを見ると、これをアマツヒコと読んでいるが、一方で、本居宣長『古事記伝』など、アマツヒダカと読んでいる場合も少なくない。
平成になってからの論考を見ても、太田善麿「「天津日高」小考」や大脇由紀子「天津日高の継承」は、アマツヒコを支持しており、矢嶋泉「「天津日高」をめぐって」は、アマツヒダカを主張している。
おおよそ、アマツヒコと読む場合の論拠は、日本書紀に「天津彦」とあることや継体記の「丸高王」など「高」をコと読む事例があるという点にあり、アマツヒダカの根拠は、「天津日」が訓読みならば「高」も訓で読むのが自然であるというところにある。
こうしてみると、両説それぞれに然るべき論拠もあり、どちらを是とすべきか断案を得るまでには至っていないというのが現状であろう。
そこで、名前の変遷という、これまでとは、やや別の視点から、この問題を考えてみようというのが本稿の企図である。
(なお、本稿における記紀の引用は、日本古典文学大系本に拠った。ただし、字形・字体は正確に再現できていないものがある。)
第一節 「火折彦火火出見」
はじめに、記紀に見える日向三代の神名を抜き出してみると次のようになる。
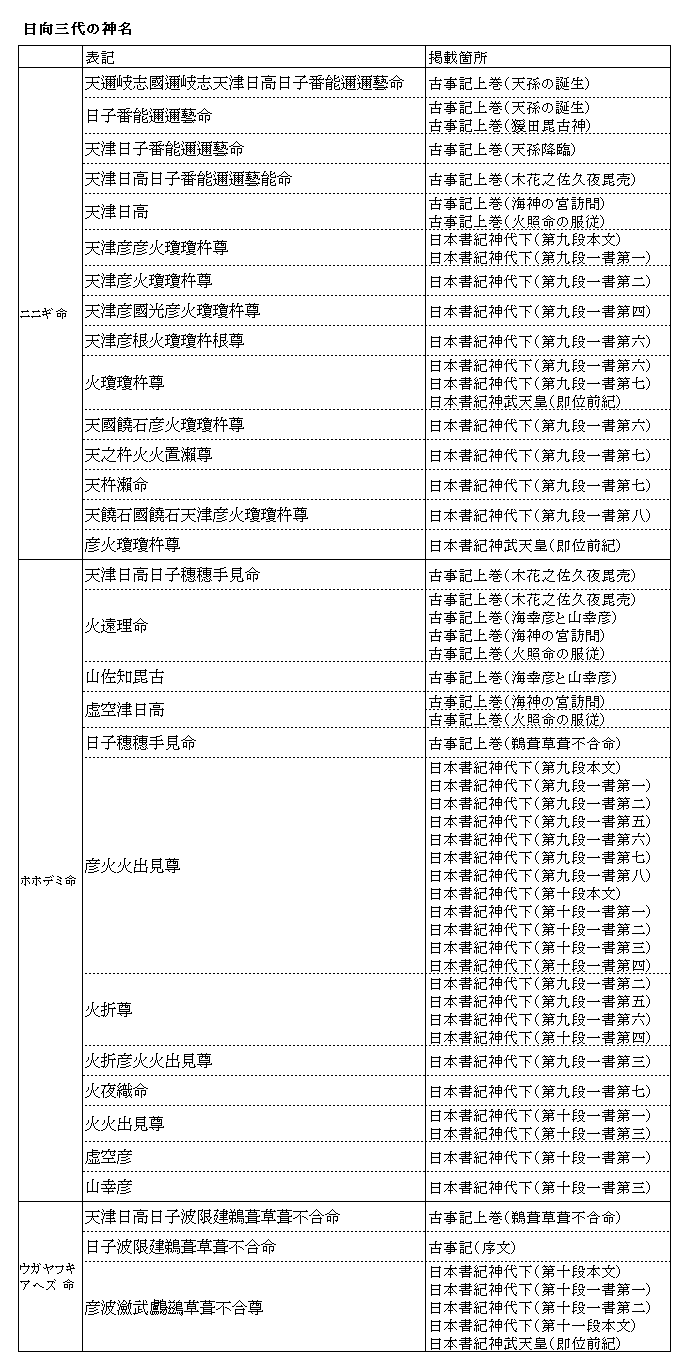
これら、さまざまに表記されている中で最初に注目されるのは、ホホデミ命の「火折彦火火出見」という神名である。
その構成要素である「火折」と「彦火火出見」は、それぞれ単独でも神名として通用しており、その場合の両者の関係は、兄弟とされる場合もあれば、同一神の「亦の名」とされている場合もある。
○ 兄弟とされている例
・日本書紀神代下(第九段一書第五)
次
に火炎の衰る時に、躡み誥びて出づる兒、亦言りたまはく、「吾は是天神の子。名は火折尊。吾が父及び兄等、何處にか在します」とのたまふ。次に火熱を避る
時に、躡み誥びて出づる兒、亦言りたまはく、「吾は是天神の子。名は彦火火出見尊。吾が父及び兄等、何處にか在します」とのたまふ。
・日本書紀神代下(第九段一書第七)
次に火夜織命。次に彦火火出見尊といふ。
○ 同一神の「亦の名」とされている例
・古事記上巻(木花之佐久夜毘売段)
次に生める子の御名は、火遠理命。亦の名は天津日高日子穗穗手見命。
・日本書紀神代下(第九段一書第二)
次に生む兒を、彦火火出見尊と號す。亦の號は火折尊。
・日本書紀神代下(第九段一書第六)
次に火折尊を生みまつる。亦の號は彦火火出見尊。
このように、両様の伝えがある中で、「火折彦火火出見」という神名は、「亦の名」で結ばれた「火折」と「彦火火出見」を、さらに接着した形となっている。
本稿では、この結合された神名を合成神名と呼ぶことにする。
また、合成される前のそれぞれの神名を素神名と呼ぶことにする。
おそらく、生成の順序としては、
複数の素神名 → 兄弟関係 → 「亦の名」で結合 → 合成神名
という経過があったのであろう。
それからもう一つ、素神名に美称(好い意味を持った言葉)などが付加された形の神名を特に装飾素神名と呼ぶことにしたい。
例えば、
火火出見 = 素神名
彦火火出見 = 装飾素神名
という具合である。(「彦」については、一般に男子の美称と考えられるが、かつては、「命」などと同様の称号として用いられる場合もあったと推測される。この点については、以前、「記紀天皇名の注釈的研究」という小論の中でも触れてみたことがある。神名に付された「彦」も両方の可能性が考えられるが、ここでは、仮に美称と考えておくことにする。)
これとは逆に、神名の一部だけを取り出して他を省略した形も見られる。
・古語拾遺
天祖彦火尊、海神の女豊玉姫命を娉ひて、彦瀲尊を生れます。(新撰日本古典文庫『古語拾遺』による。)
この場合の「彦火」は「彦火火出見」の略称、「彦瀲」は「彦波瀲武鸕鷀草葺不合」の略称とすべきであろう。
ところで、筆者は、前掲小論の中で“前補後元名”という名前の類型を考えてみたことがある。
これは、従来から存在する名前に美称や地名を増補して形成された名前であり、増補にあたっては、付加された名辞が前置され、元からの名前は後置されるという特徴を持っている。
例えば、雄略天皇の「大泊瀬幼武」の場合、「幼武」という実名の前に「大泊瀬」という美称・地名が付加された形をしている。
このように美称・地名を付加することによって、その人を称賛する意味合いがあったらしい。
装飾素神名も、この“前補後元名”と、ほぼ、同じ概念であるが、後から述べる「根」の場合のように、名前の最後に付加される美称もあるので、ここでは、それらも含めて、装飾素神名という名称にしてみた次第である。
第二節 「天津彦根火瓊瓊杵根」
上記のような合成神名という概念を導入した場合、次に注目されるのが、ニニギ命の「天津彦根火瓊瓊杵根」という神名である。
この神名も「天津彦根」と「火瓊瓊杵根」とに分解可能である。
前者の「天津彦根」は、天照大神と素戔鳴尊の誓約(ウケヒ)の際に生まれた男神であり、例えば、日本書紀神代上(第六段本文)では、
既にして素戔鳴尊、天照大神の髻鬘及び腕に纏かせる、八坂瓊の五百箇の御統を乞ひ取りて、天眞名井に濯ぎて、■然に咀嚼みて、吹き棄つる氣噴の狭霧に生まるる神を、號けまつりて正哉吾勝勝速日天忍穗耳尊と曰す。次に天穗日命。是出雲臣・土師連等が祖なり。次に天津彦根命。是凡川内直・山代直等が祖なり。次に活津彦根命。次に熊野櫲樟日命。凡て五の男ます。(■
=齒+吉)
と記されている。
なお、古事記上巻(天の安の河の誓約段)にも同様の神話があり、「天津日子根」と表記されている。
記紀を見るかぎり、天津彦根命と火瓊瓊杵尊とは、叔父・甥の関係に位置づけられており、「亦の名」で結びつけられる事例は存在しないのであるが、「天津
彦根火瓊瓊杵根」という合成神名が残されたことからすると、かつて、同一神とされることがあったのではないかと想定されるのである。
さて、「天津彦根火瓊瓊杵根」という形は、唯一、日本書紀神代下(第九段一書第六)に見えるものであるが、この名前から「根」を除いた「天津彦火瓊瓊杵」・「天津日子番能邇邇藝」という形は、日本書紀神代下(第九段一書第二)や古事記上巻(天孫降臨段)にも見られる。
この「根」を除いた形も「天津彦根」に由来するものであろう。
というのも、名前の最後に付く「根」は、着脱可能な美称であったと考えられるからである。
その類例を一覧表にすると次のようになる。
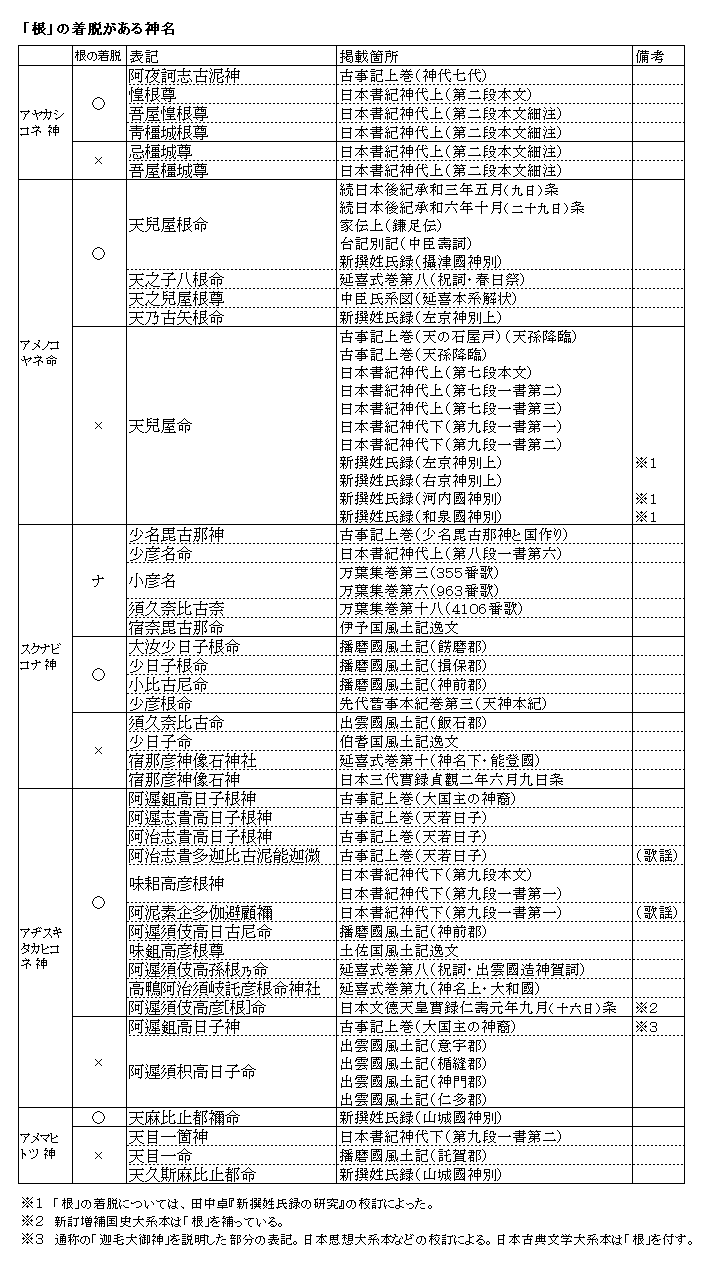
このうち、天兒屋命については、『古事記伝』(八之巻)に、
他書には、多くは兒屋根と根字を添て書るを、此記書紀などには此字無く、又泥は稱名にて、稱名は略ても云る例これかれあるなどを思へば、根字なきをば、古夜と訓べきかとも思へど、屋を夜泥と云こと、今の俗語のみならず、萬葉集四巻などにもあれば、なほ古夜泥と訓べし
とある。
引用文中、「萬葉集四巻」云々については、779番歌に「板盖之 黒木乃屋根者 山近之 明日取而 持将参来」とあることを指しているのかも知れないが「屋根」とあって、「屋」をヤネと訓む用例とは言えない。
ただ、諸橋『大漢和辞典』を見ると、「屋」という漢字には、“室を覆うもの”という意味もあるので、「屋」をヤネと訓んでも不当ではない。
それはともかく「泥は稱名にて、稱名は略ても云る例これかれある」という指摘は、そのとおりであろう。
こうした事例から類推すると、「天津彦火瓊瓊杵」の「天津彦」は、「天津彦根」から「根」が落ちた形と考えられるのである。
(これに関連して一言触れて置きたいのが「天津子」という神名である。
この神が天津彦根命と同一神か否か、はっきりとしないが、出雲國風土記<意宇郡>には、「天乃夫比命の御伴に天降り來ましし伊支等が遠つ
神、天津子命」という記述があり、日本古典文学大系本の頭注では、「他に見えない。或は、天津日子命で、天菩比命と同時に生れたとする神か。」と記されて
いる。
もし、そのとおりとすれば、「根」の脱落した形が出雲國風土記にも存在したことになる。
それから、もう一つ、古語拾遺には、「天祖吾勝尊、高皇産霊神の女栲幡千千姫命を納れて天津彦尊を生みませり。」という記載がある。
ここに見える「天津彦」は、上述の「彦火」や「彦瀲」などと同様の略称であろう。)
第三節 「天津彦彦火瓊瓊杵」
さて、「天津彦火瓊瓊杵」という形が「天津彦根」に由来するものだったとして、さらに「彦」が追加された「天津彦彦火瓊瓊杵」という形は、どこから生じたのであろうか。
ここで注目されるのは、「火瓊瓊杵」に対して、「彦」が前置された「彦火瓊瓊杵」という装飾素神名が存在することである。
合成の素材として「天津彦」と「彦火瓊瓊杵」を選び、単純に足し合わせると、「天津彦彦火瓊瓊杵」となる。
形式的には、これで「天津彦彦火瓊瓊杵」の生成を説明できるのだが、「彦彦」という連続した重複をそのままにしたと言うのも気が引けるところである。
感覚的に言って、「彦」は、一つあれば充分であろう。
初期天皇名などに多く見られる「○○彦○○」という形も、「彦」は、一つだけであって、重複は見られない。
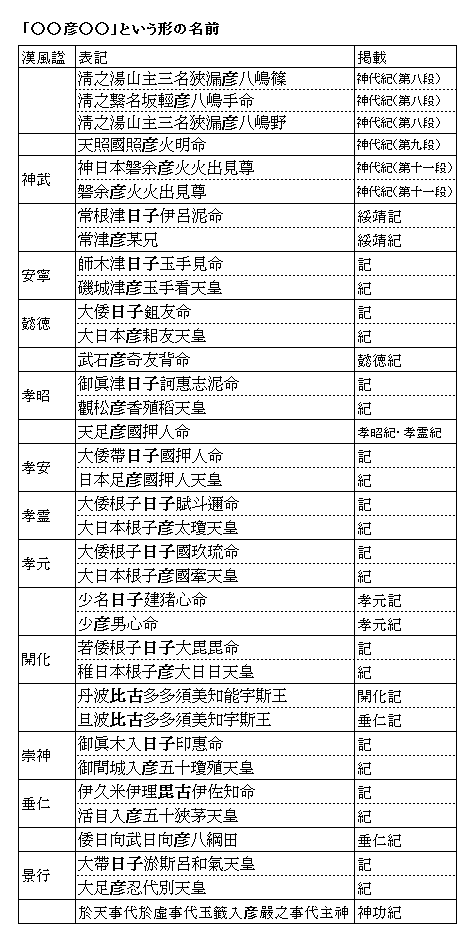
日本書紀において、このような重複が見られるのは、「天津彦彦火瓊瓊杵」だけである。(蛇足ながら、「彦」が離れた場所に重出する事例は、いくつか存在する。神名としては、「天津彦國光彦火瓊瓊杵」、人名としては、孝霊天皇皇子の「彦五十狹芹彦」、「若日子建吉備津日子」、神功摂政前紀に見える「内避高國避高松屋種」などである。)
「彦彦」という連続重複が特殊な事例であることは間違いない。
それゆえ、合成の過程で「彦彦」が自然に形成されるとは考え難いのである。
しからば、重複発生の理由は何処に求められるのか。
そこで思い当たるのが、古事記の「天津日高日子番能邇邇藝」という表記である。
この表記は、おそらく、帝紀・旧辞の段階で、すでに、こう記されていたものと想定される。
日本書紀の編者は、その「日高」をヒコと読み、「日高日子」を機械的に「彦彦」と変換したのであろう。
そして、日本書紀編者と同時代人であった太安万侶も、また、「日高」をヒコと読んでいたと考えられる。
太安万侶は、古事記序文で
辭理の見え叵きは、注を以ちて明らかにし、意況の解り易きは、更に注せず。
という編集方針を述べているが、問題の「日高」に注を加えなかったことからすると、「日高」は「意況の解り易き」ものであったに違いない。
「天津日高」をアマツヒコと読むことは、当時の人々にとって、半ば常識となっていたのであろう。
もっとも、これは、あくまでも特殊な読み方であり、「天津」と結びつかない「日高」は、ヒタカと読まれていたようである。
例えば、日本書紀の中に見える「日高」を抜き出すと、次のようになる。
・日高見國(景行天皇二十七年二月<十二日>条 ・同四十年是歳条)
・太子に日高に會ひぬ。(神功皇后摂政元年二月条)
・日高皇女(天武天皇十一年八月<二十八日>条)
これらの読みは、明らかに、ヒタカ、あるいは、ヒダカである。
古事記序文には、
亦姓に於きて日下を玖沙訶と謂ひ、名に於きて帶の字を多羅斯と謂ふ、此くの如き類は、本の隨に改めず。
ともあって、慣用的な表記をそのまま採用したことを述べているが、そのことは、当然、「天津日高」にも適用されたのであろう。
この点、使用する文字に意を用いた日本書紀では、「日高」→「彦」という変換が行われたと考えられる。
第四節 「天津日高」
記紀編纂の頃には、アマツヒコと読まれていたであろう「天津日高」であるが、当初からアマツヒコと読まれていたかどうかは疑問である。
アマツヒコの表記としては、「天津日子」の方が自然であり、殊更に「天津日高」としなければならない理由が見当たらないからである。
「天津日高」の表記が発生した当初、その読みは、やはりアマツヒタカであったのではないだろうか。
ヒコという名辞と比較して、ヒタカという名辞には馴染みがないが、全く類例がないわけではない。
古事記中巻(応神天皇段)には、天之日矛の物語があり、そこには、
故、更に還りて多遲摩國に泊てき。即ち其の國に留まりて、多遲摩の俣尾の女、名は前津見を娶して、生める子、多遲摩母呂須玖。此の子、多遲摩斐泥。此の子多遲摩比那良岐。此の子、多遲麻毛理。次に多遲摩比多訶。次に清日子。三柱
という系譜が見える。
この系譜中に登場する「多遲摩比多訶」の読みは、タジマヒタカ以外考えられない。
そして、タジマヒタカが存在するからには、アマツヒタカも存在して、何ら不思議はない道理である。
古事記上巻(海神の宮訪問段)に見える、「天津日高」・「虚空津日高」も、それぞれアマツヒタカ・ソラツヒタカと読まれていた段階があったのではないだろうか。
もし、そうだとすると、これらの名前は、「多遲摩比多訶」が固有名詞であったのと同様に固有名詞であったと想定される。
記・海神の宮訪問段では、海神が火遠理命を見て、
此の人は、天津日高の御子、虚空津日高ぞ。
と言う場面がある。
これは、豐玉毘賣の父である海神が娘の結婚相手の素性・名前をズバリ言い当てたものと解釈するのが良さそうである。
娘の婚姻に先立って、相手の名前を確認する場面は、記・須佐之男命の大蛇退治段にも見られる。(櫛名田比賣の父、足名椎が須佐之男命に対して「恐けれども御名を覺らず。」と問う場面がある。)
さらに、記・根国訪問段にも、須勢理毘賣の父、須佐之男命が大国主神を見て「此は葦原色許男と謂ふぞ。」と言い当てる場面がある。
それはともかく、ニニギ命の名前に戻ると、「天津日高日子番能邇邇藝」は、「天津日高(ヒタカ)」と「日子番能邇邇藝」の合成神名であったのだろう。
その後、いつの頃かは不明であるが、「高」をコと読む事例に引きずられ、「日高」をヒコと読む慣習が生まれたと考えられる。(人名で「高」をコと読む事例としては、神功摂政前紀の「内避高國避高松屋種」、応神記の「高目郎女」、継体記の「丸高王」などがある。)
それに伴い、固有名詞であった「天津日高(ヒタカ)」は、「天津日高(ヒコ)」という美称に変化していったと推測されるのである。(「虚空津日高」の読みも同様の経過を辿ったに違いない。また、「天津日高」がアマツヒコと読まれるようになると、「天津日子根」から「根」が脱落した形の「天津日子」との区別も曖昧となり、ニニギ命と天津日子根命の結びつきは、忘れ去られていったと想像される。)
このような変化の結果、「天津日高日子番能邇邇藝」は、日本書紀において「天津彦彦火瓊瓊杵」と表記されるに至ったと考えられる。
また、この美称となった後の「天津日高(ヒコ)」を付加して成立したのが、古事記に見える「天津日高日子穗穗手見」と「天津日高日子波限建鵜葺草葺不合」であろう。
従って、両者の類型は、合成神名ではなく、装飾素神名ということになる。
この二つの神名が古事記にだけ見られ、日本書紀に出現しないのは、上記二神名への「天津日高(ヒコ)」の付加が比較的新しい時代に行われたことを示唆しているように思われる。
第五節 神名の形成過程
さて、「天津彦彦火瓊瓊杵」がアマツヒタカに由来する合成神名だとすると、「天邇岐志國邇岐志天津日高日子番能邇邇藝」は、如何なる神名とすべきであろうか。
これは、「天津日高日子番能邇邇藝」に「天邇岐志國邇岐志」という美称を付加した形と見て間違いあるまい。
そうすると、「天邇岐志國邇岐志天津日高日子番能邇邇藝」は、装飾合成神名という類型に整理されるであろう。
同じく、日本書紀の「天饒石國饒石天津彦火瓊瓊杵」という形も「天津彦火瓊瓊杵」に美称が付加された装飾合成神名となろう。
また、「天津彦國光彦火瓊瓊杵」という形の場合は、やや判断に迷うところであるが、「天津彦國光彦」を「天饒石國饒石」などと同様の一団の美称と考えて、装飾素神名に分類しておきたいと思う。
およそ、「天國饒石」という形も含めて、「天」と「國」が一対になった美称は、合成神名が形成された後に付加された比較的新しい美称であると考えられる。
最後に残った、「天之杵火火置瀨」と「天杵瀨」については、今のところ思い当たる節もなく、とりあえず素神名として整理しておくことにしたい。
ここで、ニニギ命の名前の形成過程をまとめると、次のようになる。
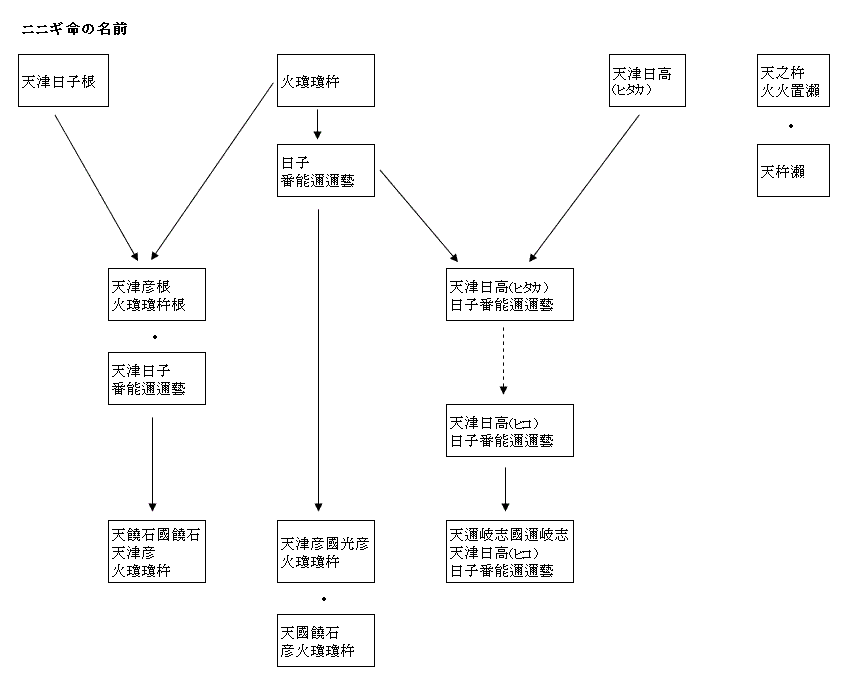
これと同様に、ホホデミ命、および、ウガヤフキアヘズ命の名前もまとめてみると、次のようになる。
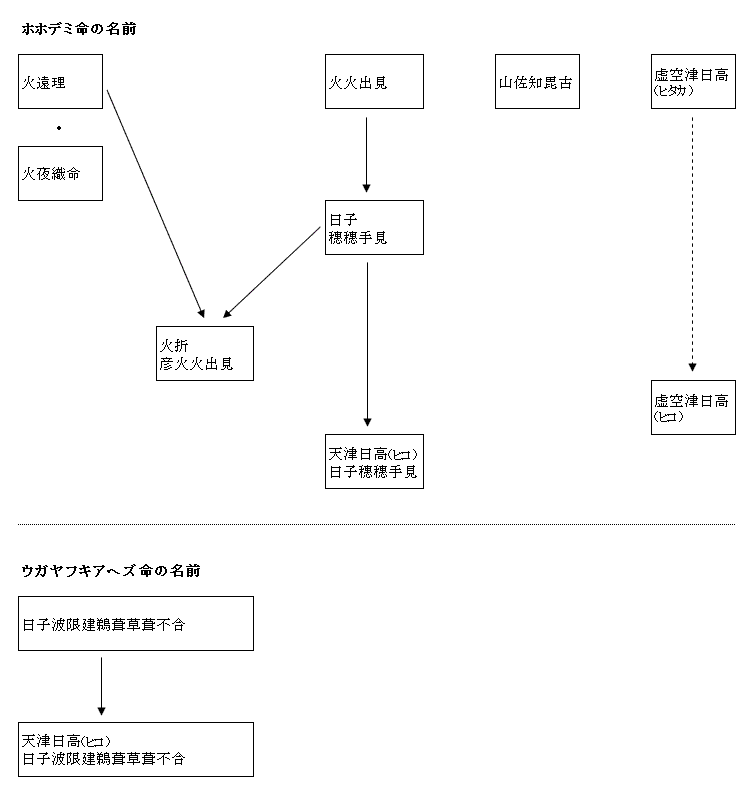
ニニギ命の神名中に現われる「天津日高」の読みは、元来、アマツヒタカであったと考えられる。
その後、「日高」がヒコと読まれるようになると、「天津日高(ヒコ)」は、固有名詞ではなく、一般名詞の美称であると認識されるようになったらしい。
ホホデミ命・ウガヤフキアヘズ命の神名に付加されたのは、美称となった後の「天津日高(ヒコ)」であろう。
要するに、「天津日高」の読みと意味合いには、変遷があったと推測されるのである。
余録1 「天忍穗耳」
本稿では、もっぱら日向三代の神名を考えてきたが、その一代前、オシホミミ命の名前についても、若干の考察を加えておくことにしたい。
この神も多くの名前を持っている。
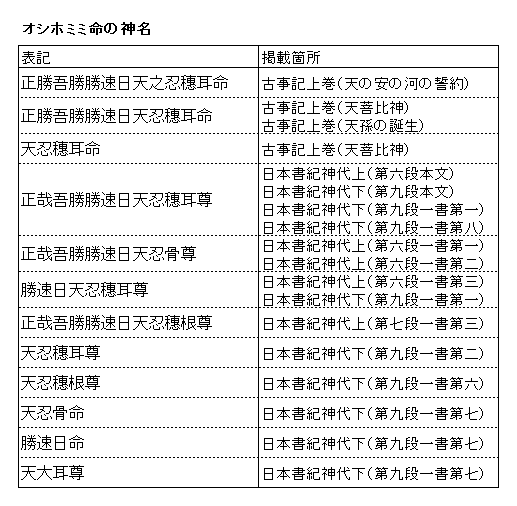
このうち、「勝速日」と「天大耳」については、日本書紀神代下(第九段一書第七)に、
一に云はく、勝速日命の兒天大耳尊。
とあって、父子関係で結ばれている。
おそらく、元来、別々の素神名であった「勝速日」と「天大耳」が父子関係で結び付けられたのであろう。
記紀には、両者が「亦の名」で結び付けられた例は見られないが、「勝速日天忍穗耳」という形が見られる。
これは、「勝速日」と「天忍穗耳」の合成神名と見て間違いあるまい。
そうすると、「正哉吾勝勝速日天忍穗耳」は、合成神名に「正哉吾勝」という美称が付加された装飾合成神名ということになろう。
もっとも、日本書紀神代下(第六段一書第三)に、
已にして素戔鳴尊、其の左の髻纏かせる五百箇の統の瓊を含みて、左の手の掌中に著きて、便ち男を化生す。則ち稱して曰はく、「正哉吾勝ちぬ」とのたまふ。故、因りて名けて、勝速日天忍穗耳尊と曰す。
とあることからすれば、「正哉吾勝」は、美称と言うよりも、素戔鳴尊の“言挙げ”と言った方が正確かも知れない。
さて、ここで、名前の形成過程をまとめると次のようになる。
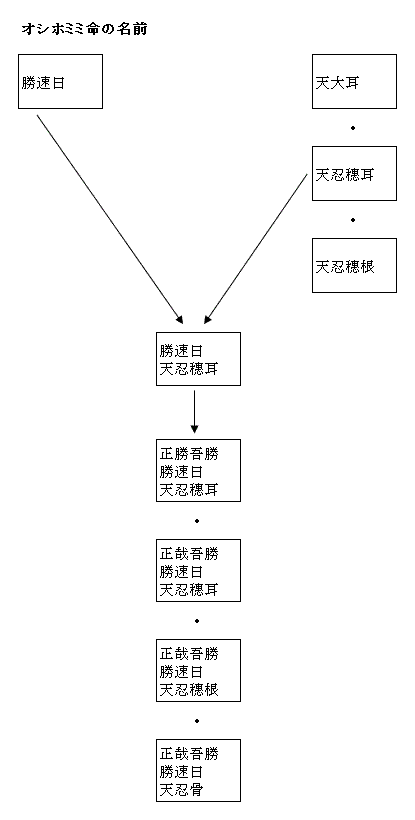
こうして見ると、名前の最後、「耳」と「根」の交代が見られる。
「根」は、上述のとおり着脱可能な美称であり、「耳」も美称とすると、「天忍穗耳」・「天忍穗根」は、装飾素神名に類別されるであろう。
ただし、「天忍穗」という形は、見ることができない。
「耳」と「根」が交替可能であることは確かであるが、他の場合と同様に脱落可能とすべきか否か、なお、検討を要するところである。
(『古事記伝』<七之巻>には、「伊勢外宮に、忍穗井と云井の名もあり」という注が加えられている。
この「忍穗井」がオシホミミ命の神名から取られたものとすれば、「耳」の脱落した形とも考えられよう。
しかし、その井戸の名称は、別に起源を持つようである。
そもそも、「をしほ井」という名称は、南北朝の頃には存在しており、風雅和歌集
巻第十九<神祇歌>には、「をしほ井をけふ若水にくみそめて御あへたむくる春はきにけり」、「世々をへてくむともつきし久方のあめよりうつすをしほ井の水」という二首が収録されている。
ところが、それよりも早く成立したとみられる神宮雜例集
巻第一<御井社事>などには、「天忍石乃長井乃水」、「天忍水」、「天忍井水」といった井戸に関係する名称が出現するものの、肝腎の「忍穗井」という形は見ることができない。
この状況から推測すると、外宮の「忍穗井」は、上記「天忍井」などが転訛したものと考えた方が自然である。)
また、「天大耳」と「天忍穗耳」を比較すると、「大」と「忍穗」が交替可能であったことになる。
この点、『古事記伝』(七之巻)では、
忍穗耳は、大々耳にて美稱なり、忍の大なることは、上の忍許呂別の所【傳五の八葉】に云り、穗も大なり、大の意を省て富とのみ云る例多し、中にも書紀に三穗之碕とある地名を、此記には御大之前と書るなど、此によく合へり
と述べて、「忍」と「穗」の双方が「大」に通じることを主張している。
一方、日本古典文学大系『日本書紀』では、
大耳は、オホシミミと訓む。オシホをオホシと転写した本があり、そのオホシに大の字をあてたのであろう。
という注を付している。
いずれにしても、「大」と「忍穗」の読みが近似していることは間違いない。
その原形は、はっきりしないが、同じ言葉の異伝であろう。
それから、もう一つ、取り上げておきたいのが兄弟の名前である。

このうち、「天之菩卑」と「熊野忍蹈」について、さきほどの『古事記伝』(七之巻)は、
天之菩卑能命、【能字を添えたることめづらし、】此も本右の穗耳と同言にて、菩は大なり、卑は美と通ひて、その美は右に云る耳の略なり・・・又書紀に、次の熊野久須毘命を、忍蹈命ともあるは、忍穗耳と正しく同言なる例なり、
と述て、「菩卑」・「忍蹈」が「忍穗耳」と“同言”であることを指摘している。
さすがに「菩卑」の場合は、やや遠く感じるが、「忍蹈」と「忍穗耳」が、ほぼ同じであるというのは、そのとおりであろう。
「忍穗耳(オシホミミ)」と「忍穗根(オシホネ)」の間に「忍蹈(オシホミ)」という形が入ると、その変化が、より自然に感じられる。
余録2 神話と神名
オシホミミ命からウガヤフキアヘズ命までの素神名を見てみると、その内包する名辞の意味と、登場する神話の内容との間に明らかな対応が認められるものがある。
(1)「勝速日」= 天の安の河の誓約(ウケヒ)
誓約(ウケヒ)における素戔鳴尊の勝利と「勝速日」という名前は、不可分のものと考えて良かろう。
神名に前置された「正哉吾勝」に至っては、素戔鳴尊の“言挙げ”そのものである。
(2)「火遠理」= 火中出生譚
火が燃え進む状態に因んだ「火須勢理」と火勢が弱まる状態に因んだ「火遠理」は、一連の名前であり、火中出生譚があってこその名前である。
(3)「日子波限建鵜葺草葺不合」= 海辺の産屋における出生
「日子波限建鵜葺草葺不合」という名前が、そのまま出生譚を要約した内容となっていることは、誰の目にも明らかであろう。
(4)「山佐知毘古」= 海神宮訪問の前段(幸易え)
「海佐知毘古」と「山佐知毘古」が「各佐知を相易へて」釣針を失くすという筋書きは、海神宮訪問譚の導入部分を構成している。
以上、四つの素神名は、その名前と神話との間に明らかな対応関係が認められる。
次に、神話の中に直接登場しないものの、名前の意味から見て関連が想定されるものがある。
(5)「虚空津日高」= 虚天での出生
ホホデミ命は、古事記上巻(海神の宮訪問段)において、「天津日高の御子、虚空津日高」と呼ばれていたが、日本書紀神代下(第十段一書第一)では、
若し天より降れらば、天垢有るべし。地より來れらば、地垢有るべし。實に是妙美し。虚空彦といふ者か
と語られている。
ここでは、「虚空彦」が、天より降れるものでもなく、地より来れるものでもないことを述べている。
一方、日本書紀神代下(第九段一書第二)では、
則ち高皇産靈尊の女、號は萬幡姫を以て、天忍穗耳尊に配せて妃として降しまつらしめたまふ。故、時に虚天に居しまして生める兒を、天津彦火瓊瓊杵尊と號す。
という一文が見られる。
こちらでは、天と地の間に「虚天」という場所が設定されており、そこでの出生が語られている。
以上、二つの記述を合わせて考えると、天のものでも地のものでもない「虚空津日高」は、「虚天」に生まれた子ではないかと疑われる。
第九段一書第二の原形は、「天津彦火瓊瓊杵」ではなく、「虚空津日高」が誕生する筋立てになっていたのではないだろうか。
それから、もう一つ、特定の地域との結び付きから推測して、対応する神話を想定できるものがある。
(6)「天津彦根」・「火瓊瓊杵」= 天孫降臨神話の伊勢と日向
「天津彦根」と「火瓊瓊杵」を合成して「天津彦根火瓊瓊杵根」という名前が形成されたであろうことは、すでに述べたとおりである。
そこで、名前の合成が行われた理由を考えてみると、その原因は、両者がよく似た内容の神話を持っていたところに求められるのではないだろうか。
具体的には、天孫降臨神話である。
古事記上巻の邇邇藝命段、日本書紀神代下の第九段(ただし、大国主神の国譲りの部分、および、山陵の記事を除く。)を見てみると、その中に伊勢と日向の地名が散在していることに気づく。
○ 伊勢(伊勢・志摩)の地名
・佐久久斯侶伊須受能宮
(記・天孫降臨)
・伊勢の狹長田の五十鈴の川上
(紀九段一書第一)
・外宮の度相
(記・天孫降臨)
・佐那那縣
(記・天孫降臨)
・阿邪訶
(記・猨女の君)
・島の速贄
(記・猨女の君)
○ 日向(南九州)の地名
・竺紫の日向の高千穗の久士布流多氣
(記・天孫降臨)
・日向の襲の高千穗峯
(紀九段本文)
・槵日の二上
(紀九段本文)
・筑紫の日向の高千穗の槵觸峯
(紀九段一書第一)
・日向の槵日の高千穗の峯
(紀九段一書第二)
・日向の襲の高千穗の槵日の二上峯
(紀九段一書第四)
・日向の襲の高千穗の添山峯
(紀九段一書第六)
・笠沙の御前
(記・天孫降臨、木花之佐久夜毘賣)
・吾田の長屋の笠狹碕
(紀九段本文)
・吾田の長屋の笠狹の御碕
(紀九段一書第四)
・吾田の笠狹の御碕
(紀九段一書第六)
・長屋の竹嶋
(紀九段一書第六)
・神阿多津比賣
(記・木花之佐久夜毘賣)
・鹿葦津姫
(紀九段本文)
・神吾田津姫
(紀九段本文)
・神吾田鹿葦津姫
(紀九段一書第二・三)
・吾田鹿葦津姫
(紀九段一書第五)
・豐吾田津姫
(紀九段一書第六)
・吾田津姫
(紀九段一書第七)
・竹屋
(紀九段一書第三)
一方で、天津彦根命は、現在、多度大社(桑名市多度町)の祭神となっている。
この神社は、延喜式巻第九(神名上)「伊勢國桑名郡十五座」のうちに
多度神社 名
神大
として見えている。
また、新撰姓氏録(右京神別下)には、
桑名首 天津彦根命男、天久之滿比乃命之後也。(田中卓『新撰姓氏録の研究』による。)
とあって、伊勢地方との関わりの深さを窺わせるものがある。
こうして見ると、天津彦根命は、天孫降臨神話のうち、伊勢に関わる部分と密接な関係を持っていたのではないだろうか。
かつて、天津彦根命を主人公とする伊勢への降臨神話が存在したとしても、それほど不思議なことではあるまい。(なお、伊勢降臨神話の存在に言及した論考
としては、青木紀元「降臨神話の展開」や松前健「大嘗祭と記紀神話」がある。ただし、前者は、皇祖神の降臨、後者は、オシホミミ命の降臨を想定してい
る。)
もし、そうだとすると、もう一方の日向降臨の主人公は、火瓊瓊杵尊ということになろう。
以上の対応関係をまとめてみると、次のようになる。
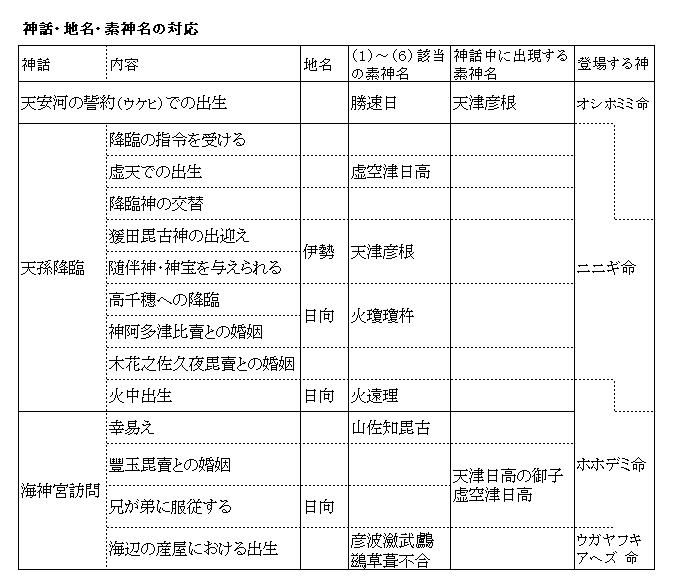
この一覧表から想像すると、天津彦根命は、日神の子であり、伊勢へ降臨する神であったのではないだろうか。
そのため、オシホミミ命の兄弟とされる一方で、ニニギ命と同一神とされる場合もあり、「天津彦根火瓊瓊杵根」という合成神名が生じたのであろう。
また、虚空津日高は、虚天で誕生した後、降臨し、海神宮を訪問する神であったように見える。
従って、当初は、ニニギ命とホホデミ命の二柱分の役割を担っていたのであろうが、その後、いずれかの時点で、ホホデミ命と同一神と観念されるようになり、降臨神の役割を失ったらしい。
その変化に合わせて、父神の天津日高は、ニニギ命と同一神とされ、「天津日高日子番能邇邇藝」という合成神名が形成されたように思われる。
この合成については、「天津彦根」に由来する「天津彦火瓊瓊杵」という、よく似た形の合成神名が存在していたことも影響を与えたのではないだろうか。
あくまでも、推測の域を出るものではないが、本稿では、以上のように考えておきたい。
参考文献
日本古典文学大系『古事記・祝詞』(岩波書店、1958年)
日本思想大系『古事記』(岩波書店、1982年)
新潮日本古典集成『古事記』(新潮社、昭和54年)
『本居宣長全集 第九巻~第十巻、古事記伝 一~二』(筑摩書房、昭和43年)
太田善麿「「天津日高」小考」(『梅澤伊勢三先生追悼 記紀論集』、続群書類従完成会、平成4年、所収。)
大脇由紀子「天津日高の継承」(『古事記年報』39、平成9年)
矢嶋泉「「天津日高」をめぐって」(『青山学院大学文学部紀要』31、1989年)
日本古典文学大系『日本書紀 上・下』(岩波書店、1965~67年)
新撰日本古典文庫『古語拾遺・高橋氏文』(現代思潮社、1976年)
新訂増補國史大系『續日本後紀』(吉川弘文館、昭和58年、普及版)
「家傳 上」(『群書類従・第五輯 系譜・伝・官職部』、続群書類従完成会、昭和57年、訂正三版五刷、所収。)
田中卓『新撰姓氏録の研究』(国書刊行会、平成8年)
佐伯有清『新撰姓氏録の研究 本文篇』(吉川弘文館、昭和37年)
「中臣氏系圖」(『群書類従・第五輯 系譜・伝・官職部』、続群書類従完成会、昭和57年、訂正三版五刷、所収。)
佐竹昭広 木下正俊 小島憲之『萬葉集 本文編』(塙書房、昭和38年)
日本古典文学大系『風土記』(岩波書店、1958年)
鎌田純一『先代舊事本紀の研究 挍本の部』(吉川弘文館、昭和35年)
新訂増補國史大系『交替式・弘仁式・延喜式 前篇』(吉川弘文館、昭和56年、普及版)
新訂増補國史大系『日本三代實録 前篇』(吉川弘文館、昭和58年、普及版)
新訂増補國史大系『日本文德天皇實録』(吉川弘文館、昭和56年、普及版)
『二十一代集 第八、風雅和歌集』(太洋社、大正十四年)
「神宮雜例集」(『群書類従・第一輯 神祇部』、続群書類従完成会、昭和58年、訂正三版五刷、所収。)
青木紀元「降臨神話の展開」(『日本文学研究資料叢書 日本神話』、有精堂、昭和45年、所収。)
松前健「大嘗祭と記紀神話」(同著『古代伝承と宮廷祭祀』、塙書房、昭和49年、所収。)