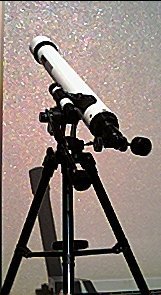| 大学時代は私の天体観測の空白期間である。天文への興味を失ったわけでは無いが、専門の物理学の勉強にいそしんでいたから、それで知的好奇心は充分に満たされていた。大学を卒業して就職し、再び趣味として天体観測をやろうとしたときに、友人からカートン光学の6cm屈折赤道儀、商品名「コメットシーカー」を譲り受けた。これが私にとって初めての赤道儀である。天文を始めてから、赤道儀を手に入れるまで、実に10年の歳月を要したことになる。細かいことだが、ラック&ピニオン式のドローチューブも初めてだった。
そうは言っても、私の天体写真の技術と情熱は大したことが無いから、写真をたくさん撮ったということは無い。たまに珍しい天体が現れると、ちょっと撮ってみたという程度である。 天体写真にはもっぱらPENTAXのSMCタクマー300mmの望遠レンズを使用した。これは肉眼では見えない、暗い彗星を撮影することを目的として買った。5万円だったと思う。300mmでF4だから、レンズの口径は75mmもある、それは見事なレンズだった。理論上は12等級の彗星まで姿を捕らえることができるはずだった。
この望遠レンズと6cmの屈赤の組み合わせは、回数は少ないが、いくつかの大きな成果をもたらした。小林−バーガー−ミロン彗星、はくちょう座新星、ウェスト彗星など全てこの機材の組み合わせで撮影した。これらについては別項「過去の会報から」に記したとおりである。 特にウェスト彗星は大きく見えたときだけではなく、地球から離れつつあり、かなり暗くなったときに、この望遠レンズに姿を現した。この撮影に成功したときは、本当に嬉しかった。300mm望遠ならではの、貴重な成果だったと思っている。 なお、望遠レンズを付けたカメラを同架すると、当然重量が重くなるから、始めから付属していたバランスウェイト1つではバランスが取れない。そこでバランスウェイトをもう1つ購入し、それでバランスを取った。今、考えると過積載だったのではないかと思うが、当時は手動ガイドが当たり前だったから、じゅうぶん実用になった。 最近になって、星への興味を取り戻して、また望遠鏡を買おうと思ったとき、真っ先に考えたのは、この6cm屈赤のように、小さいがしっかりした赤道儀が欲しいということだった。しかし、時代は変わって今はこのような商品は売られていない。まことに残念である。 300mm望遠レンズは今でも家にあるが、カビだらけになっている。カメラボディもシャッターが壊れて使えなくなっている。カメラは35年以上、望遠レンズは30年以上も昔のものだから、使えなくなるのも仕方ないが、今これらの機材が使えれば、それなりに役に立つと思うと残念でもある。
|
 この望遠鏡は当時としては珍しく、6cmの口径でありながら、焦点距離は710mmと短かった。したがって、光学性能は特筆するほどではなく、まあ普通に見えた、といったところである。初めて手に入れた赤道儀ということもあって、これは眼視観測よりも、天体写真のガイド鏡として使われたという記憶が強い。
この望遠鏡は当時としては珍しく、6cmの口径でありながら、焦点距離は710mmと短かった。したがって、光学性能は特筆するほどではなく、まあ普通に見えた、といったところである。初めて手に入れた赤道儀ということもあって、これは眼視観測よりも、天体写真のガイド鏡として使われたという記憶が強い。
 この赤道儀は私の次の機材の購入のときに、友人に2万円で売ってしまった。いま手元にあったら、まだ使えただろうか。
この赤道儀は私の次の機材の購入のときに、友人に2万円で売ってしまった。いま手元にあったら、まだ使えただろうか。
 私は多分、天文趣味の限界に突き当たったのだと思う。これほど大きな望遠鏡をもってしても、天体というのはそんなに良くは見えないものだ、ということを知ることによって、観測者としての自分に限界を感じたのではないか。私は、その後観測をやめて天文計算の分野に入っていった。そのことを思うと、そう断ずるしかない。
私は多分、天文趣味の限界に突き当たったのだと思う。これほど大きな望遠鏡をもってしても、天体というのはそんなに良くは見えないものだ、ということを知ることによって、観測者としての自分に限界を感じたのではないか。私は、その後観測をやめて天文計算の分野に入っていった。そのことを思うと、そう断ずるしかない。 口径が8cmなのはいいとして、焦点距離が91cmと、ちょっと短めなのが気になった。口径8cmなら120cmの焦点距離が、昔の標準である。これでちゃんとした像が得られるのだろうか、いいや最近はレンズの研磨技術が進歩して、これで充分なのに違いない、など様々な思いが交錯したが、ネットのショップで注文した。4万円ちょっとの価格だった。後で知ったことだが、ヨドバシカメラでは、もっと安く買える。orz
口径が8cmなのはいいとして、焦点距離が91cmと、ちょっと短めなのが気になった。口径8cmなら120cmの焦点距離が、昔の標準である。これでちゃんとした像が得られるのだろうか、いいや最近はレンズの研磨技術が進歩して、これで充分なのに違いない、など様々な思いが交錯したが、ネットのショップで注文した。4万円ちょっとの価格だった。後で知ったことだが、ヨドバシカメラでは、もっと安く買える。orz