

 |
■鉄人28号FX (1992年 日本テレビ系) 何と最古の日本ロボットアニメ「鉄人28号」とストーリー的には繋がっているのである。 前作で主人公だった正太郎少年も父親となり、その息子、正人が本編の主人公・28号FXの操縦者なのだ。 かつてのライバル、ブラック・オックスが登場するのもポイント高し。 |
| ■闘士ゴーディアン (1979年 テレビ東京系) 番組自体はとてーもマイナーなような気がするが、他に類を見ないその合体方法がとても画期的なのである。 なんと大中小の3タイプのロボットが、小さい方から大きい方のロボットへ、順々に体内に入るように合体し、徐々に巨大になっていくのだ! 当時発売されたこれの超合金もその合体方法を再現しており、いたく感動した覚えがあります。 |
 |
 |
■魔法騎士レイアース (1994年 読売テレビ系) ロボット・・・というより魔神なんですが(汗)。 自ら意思を持ち、操縦者の魔力を増幅させる、肉体の延長と考えた方がいいのかもしれません(ニュアンス的に「魔神英雄伝ワタル」の龍神丸に近いかな)。 しかし主役の魔神「レイアース」「セレス」「ウインダム」の3体は合体することが出来るし、「FTO」「GTO」という完全機械タイプのロボットも登場しました。 純粋なロボットアニメではないにもかかわらず、相変わらず参戦要望が高い。 |
| ■勇者特急マイトガイン (1993年 名古屋テレビ系) 主人公が超大金持ちで、スポーツ万能、知能明晰のスーパーヒーロー。石油がすべて枯渇してしまい、鉄道テクノロジーが発達した舞台設定。キャラ名をはじめ、番組タイトルさえも日活アクション映画がモチーフ。 ヒロインが貧乏・・・・。 等々、すべてが個性的かつ斬新な野心作。 勇者シリーズの中でも特に固定ファンが多そうな作品だけに、参戦したら喜ぶ人も多いのでは。 「だからドリルはよせと言ったんだ〜」 |
 |
 |
■光速電神 アルベガス (1983年 テレビ東京系) なんと既にゲーム化はされているのである。 と言っても’84年に出たLDを使用したセガのアーケードゲームで、場面に応じてボタンを押していく単純なものだが、まあ何と言うか、よくコレをゲーム化しようなんて思ったもんである(失礼だな)。 |
| 亜空大作戦 スラングル (1983年 テレビ朝日系) 確かプラモはアオシマから出ていました。 それだけでなんか悲しい気が(アオシマファンの方すいません)。 特殊部隊「ゴリラ」が、様々な秘密任務を遂行する、SF版「スパイ大作戦」を意識した番組。 渋い。 |
 |
 |
■熱血最強 ゴウザウラー (1993年 テレビ東京系) エルドランシリーズ最終作。 前作「ガンバルガー」が不評だったのか、今回は原点に返って「ライジンオー」と同じ学校モノ。 また「ジュラシックパーク」の影響か、当時恐竜がブームであったため、登場マシンはすべて恐竜がモチーフとなっています。 ところでゴウザウラーって学校の一部だし、18人全員が搭乗するので、精神コマンドは18人分用意することになるのか!? ※「スーパーロボット大戦NEO」に参戦が決定しました。 |
| ■超時空要塞マクロスII (1992年 OVA) 満を持して登場した超有名作の続編だが、なんとマクロス正史ではなかったこと(と言うかパラレルーワルド扱い)になってる作品。 あんまりだ! ちなみに同シリーズでは既に「マクロス」「マクロス7」「マクロスプラス」が参戦しており、この「II」も充分参戦の可能性はあるんでないかな〜と思う今日この頃。 |
 |
 |
■UFO戦士ダイアポロン (1976年 TBS系) 主人公タケシがアポロン星人で、アメフトのような容姿のダイアポロンの中で巨大化するという設定が凄すぎ。 さらに主役級5人が孤児院で生活すると言うのが悲しすぎ。 ちなみにけっこう人気があったらしく、再編集された「ダイアポロンII」が制作されています。 |

 |
■ブロッカー軍団IV マシーンブラスター (1976年 フジテレビ系) うっひゃあ!出ましたね!マシンーンブラスター。 主役級ロボが複数登場する・・・ってのは当時としては画期的だったのですが、超能力を題材としているせいか、必殺技もこれまた「武者固め」とか「不動組み」とか、運動会の組み体操ばりの無茶なものばかり・・・。 異色中の異色スーパーロボットだ。 |
| ■宇宙魔神ダイケンゴー (1978年 テレビ朝日系) 宇宙魔神と言うからには大英の「大魔神」をモチーフにしているのでしょうか? とにかく怒るとフェイスオープンして牙をむき出したり、火を噴いたりする様は確かに「魔神」でした。 声優でありアニソン界の大御所である堀江美津子が初の声優参加した作品でもあります。 |
 |
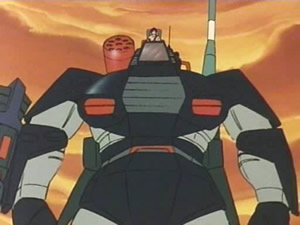 |
■太陽の牙ダグラム (1981年 テレビ東京系) 高橋良輔が初めて世に送り出したリアル・ロボットアニメの旗手。 ガンダムのヒットを受けて制作された感は否めないが、緻密な設定や、あくまで一兵器として描かれたコンバットアーマーのデザイン。主人公クリンが、地球連邦評議会長である父にそむき、己の信じる正義のためデロイア独立戦争に参加するという衝撃的なストーリー等で好評を得、実に75話と長期放映されました。 「♪もう戻れない〜もう帰れない〜」というOPが物悲しかった。 |
| ■特捜機兵ドルバック (1983年 フジテレビ系) 「♪星のピアス〜虹のバンダナ」というコッパズカしいOPしか印象のないアニメ(ォィ)。 1999年、宇宙流民イデリア星人が、地球侵略を開始。 苦戦する地球連邦軍の中で、ヴァリアブルマシンを駆るドルバック部隊が立ち上がる! ということで「ドルバック」とはロボの名前ではなく部隊の名前だったりします。 |
 |
 |
■マグネロボ ガ・キーン (1976年 テレビ朝日系) 鋼鉄ジーグに続くマグネロボシリーズ第2弾。 と言う割にはジーグとは知名度、人気の点で雲泥の差があるような・・・・。 珍しい男女混合主人公で、猛と舞の2人が「スイートクロス!」の掛け声と共にガ・キーンに融合し、ビルドアップが完了する。 ちなみに名前のガ・キーンとは、合体するときに「ガキーン!」と音がする・・・・からではなく、「GATHERING・KEEN」(結合する・鋭さ)が由来である。 |
| ■魔神英雄伝ワタル (1988年 日本テレビ系) ロボットアニメ+ファミコンゲームの融合・・・って感じで、子供だけでなく大人のアニメファンにも大人気を博した番組。 主人公ワタル(ロボではなく主人公の名前が番組名になってます)の乗る「龍神丸」は神龍の化身である魔神。 自ら意思を持ち、ワタルの呼びかけにより空間からその姿を現す。 キャラがもともとSDサイズなので「スパロボ」の世界でも違和感なく溶け込むと思いますが、「リアルサイズのロボットがSDになってこそのスパロボ」という意見も・・・。 |
 |
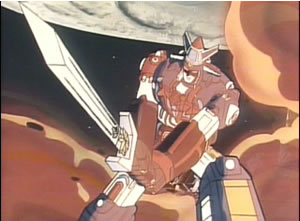 |
■機甲艦隊ダイラガーXV (1982年 テレビ東京系) とにかく合体ロボも行き着くところまで行き着いたか・・・・と思わせる作品。 なんと15台のメカが変形・合体!パイロットも15人! もしゲームに登場したら15台分のメカのパワーアップをしたり、15人分の精神コマンド用意すんの!? |
| ■巨神ゴーグ (1984年 テレビ東京系) ゴーグは異星文明の産物なので、厳密に言えばロボットではないのだが(イメージとしてはゴーレムっぽい)、途中で人間の与えたバズーカ砲をぶっ放したりして、決戦兵器としての側面も見せてくれます。 敵役でキャノン砲を装備したゴーグ型兵器も登場した。 |
 |
 |
■勇者指令ダグオン (1996年 名古屋テレビ系) 勇者シリーズ第7弾。 前作までとは打って変わり、複数の美形高校生たちを主役に据えることで、独自のファン層(て言うか大きなおねいさん)に指示された。 また「ウルトラマン」を初めとする特撮ヒーロー作品の要素を取り入れていることでも話題になったようです。 |
| ■超攻速ガルビオン (1984年 テレビ朝日系) 21世紀に地球人の好戦性を恐れた異性人が地球にバリアーを張り、そのため航空機関が絶滅し、車中心の社会になったと言う世界設定(んなバカな)。 というわけで敵味方共に車からロボに変形する異色アニメですが、あまり人気がなかったらしく、未完のまま放送終了しました。とほほ。 |
 |
 |
■元気爆発ガンバルガー (1992年 テレビ東京系) 前作ライジンオーのヒットに気をよくして(?)制作された「エルドラン」シリーズ第2弾。 内容はコミカル路線で、悪く言えばジャリ向き。 主人公たちが忍者で、正体がバレると犬にされるというのもなんとも(パーマン!?)・・・。 「ライジンオー2」とも言える次回作「ゴウザウラー」で原点回帰されるの早すぎ。 ※「スーパーロボット大戦NEO」に参戦が決定しました。 |
| ■サクラ大戦 (2000年 TBS系) ゲームから派生した作品が、アニメを経由してゲームに逆輸入されたら面白い話なのだが、「太正時代」という架空の時代を舞台にしているので、その辺の時間軸の辻褄合わせが大変そうです。 作品自体は超メジャーで、ゲーム、アニメに留まらず、劇場版やドラマCD、歌謡ショウなど、様々なメディアミックス戦略を行っております。 ところで光武って宇宙行けるの!? |
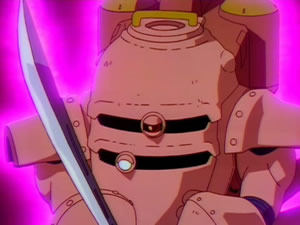 |
 |
■思春期美少女合体ロボ ジーマイン (1999年 OVA) すでにタイトルが腰砕けだが、これでもサンライズ作品なんである(しかも初の完全オリジナルOVA!)。 その割にはえらくマイナーな方向へ追い込まれているような…。 1970年代の日本を舞台にする等、目の付け所は良いのだが、それらがすべて消化不良に終わった、誰も褒める人がいない悲しい作品。 |
| 198X Vol.11 INDEXへ戻る | 198X TOPへ戻る |