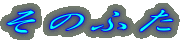
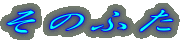
| 八百万の神々が疲れを癒しにくる湯屋 ともあれ、映画の「八百万の神々が疲れを癒しにくる湯屋」という設定にもどろう。この湯屋が、極めて組織的にしかもスマートに運営されているということに、感心した方も多いだろう。それは千尋がハクに伴われて湯屋にもぐりこもうとする場面の賑やかさにある。「いらっしゃいませ」という陽気な呼び声は、訓練され、かつ湯屋の繁盛を心から願っているように聞こえる。続く場面で湯屋の活気で、従業員たちが生き生きと仕事をしている様子が伺える 湯婆婆の人柄から推定すれば、従業員は湯婆婆に専制的に支配され奴隷のようにこき使われているのかと思えば、「ここで働かせてください。」という台詞があるのだから、働いて給料をもらうのである。千尋を子豚や石炭に変えてしまう脅かしはあるが それは千尋が人間であるからなのだろう。いずれにせよ彼らは、働いているのであって奴隷ではない。 リンは「いつかはここを辞めて、海の向こうにいくのだ」と語り退職することも可能なのである。 同時に彼ら従業員は、湯婆婆のシンパというわけでもないようだ。かとおもえば、番台蛙は、河の神が残した砂金を「会社のものだ!」と叫んでいる。湯屋は会社だったのだ。 こうなれば湯婆婆の態度は、決して極悪の魔女ではなく、例えば「クリスマスカロル」のスクルージ、あるいは「ベニスの商人」のシャイロックのような強突張りの経営者ということになろう。まして、「どうして、『働きたい者には仕事をやる』なんて誓いを立てたんだろう」と後悔しているところをみると案外、悪い魔女ではないようだ。 湯婆婆は、会社の社長であり、しかもかなり優秀な経営者である。湯屋の経営のため養豚場まで、経営しているのである。そこでは、多くの従業員が生き生きと日々の仕事に従事している。 とはいっても彼らに絶対的な自由があるわけでもない。湯婆婆の眠っている間に、羽振りのいい客を引き込んで、金を手に入れるという程度の自由性はある。 |