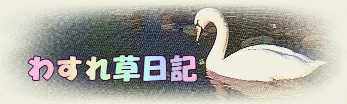
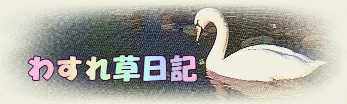
|
◆春はいつのまにか◆  今年は蕗の薹がたった3っつ。しばらく待ってもそれっきりでした。昨年蔓延った蕗を沢山根こそぎ引き抜いたからかもしれません。枝垂れ梅が、まだ小さな蕾の中に、  ポツンと離れて一輪づつ花開いて寂しそう。すっきりと伸びた木蓮の細い枝の先はしっかりと新芽が膨らんできています。辛夷はもうしばらくで蕾がほころびそうです。毎年繰り返す事を毎年新しく発見したような驚きを覚え不思議です。だから生きていられるのかも。 ポツンと離れて一輪づつ花開いて寂しそう。すっきりと伸びた木蓮の細い枝の先はしっかりと新芽が膨らんできています。辛夷はもうしばらくで蕾がほころびそうです。毎年繰り返す事を毎年新しく発見したような驚きを覚え不思議です。だから生きていられるのかも。夜中に強風が吹くと、クリスティーの甘え鳴きの声がして気になって眠れません。懐中電灯を持って犬小屋まで見に行くと、クリスティーが  吃驚して顔をあげます。とうとう鳴き声の主を見つけました。私が寝ている部屋の窓の下にあるパイプの枠にビニールを被せた簡易温室です。留め金のビスが緩んでキイキイ音を立てていたのです。 吃驚して顔をあげます。とうとう鳴き声の主を見つけました。私が寝ている部屋の窓の下にあるパイプの枠にビニールを被せた簡易温室です。留め金のビスが緩んでキイキイ音を立てていたのです。 小さなビニールの中の棚にはスミレをいれて冬越しさせました。地植えにしておくと、品種によっては翌年、庭中探しまわっても1株も発見できないときがあったので、この冬から数株づつ鉢植えにして保存することにしました。朝夕、開閉しているうちに、いくつかは花を咲かせたのがありました。早速写真に撮りました。 04 .2 .27 ◆「蛇にピアス」と「蹴りたい背中」◆ 殆ど関心がない芥川賞ですが、今の二十歳の人がどんなことを小説に書くのか興味が湧きました。「文芸春秋」3月号を発売と同時に買ってきて読みはじめると、「蛇にピアス」は出だしの数行で拒絶反応、翌日続きを読もうとしても前に進めず辞めてしまう…これの繰り返しが毎晩続き、いつのまにか文春を買ったことすら忘れていたら、授賞式のニュースと共に”文春3月号追加発売”の広告です。2人揃って史上最年少受賞者の”女の子”というのに人々の関心が集まったのは判りますが、理解しようとしても入り口から入り込めない世界で、長くもないのに読み通すのにかなりの努力が必要となりました。  私が受賞者と同じような年頃のころ、石原慎太郎が「太陽の季節」で受賞。今回の2作品については「現代における青春て、なんて閉塞的なものなのだろうか」と腹立たしげなコメントをしています。先の見えない今日の若者達の生態を反映した作品です。でも池田満寿夫の「エーゲ海に捧ぐ」は、これの何処が芥川賞なのぉ?と呆れたことがあります。その翌年はガラリと変わって、「蛍川」(宮本輝)が受賞。これは好きでした。「芥川賞ってよく判らないねぇ。」と言えば「アンタが判ってくれなくてもいいんだよ」って今度の作品の中で声がします。 以下は「撲たれた背中」です。 お風呂場で犬を洗ってやっているうちに、犬が動かないので自分が犬の周りをぐるぐる移動して、洗うのに夢中になって勢いよく立ったら、タイルの壁から突き出ていた蛇口の先を思いきり突き上げてしまいました。それも背骨で。昔、母は孫2人を洗ってやっているうちに同じ事をして、痛々しい紫色の打撲痕がしばらく消えませんでした。話しをしたら、友達のYさんも猫を洗っていてしたことがあるそうです。「判る判る、イッタイよねぇ!!」と、今も痛む背骨を擦りながら自分のドジが情けなくて笑うしかないのです。 04 .2 .25 ◆♪「冥土」の裏門叩いて丸山ぶらぶら◆ ♪遊びに行くなら花月か中の茶屋〜、これは長崎の”ぶらぶら節”ですが、2年前、なかにし 礼が「長崎ぶらぶら節」で直木賞をとって以来、吉永小百合  主演の映画で知る人も多くなったようです。先日親戚の法事が長崎であり、遠くから親戚も集まりました。長崎で生まれ子供の頃この地を離れ遠くに住む人にとっては「長崎」の響きは懐かしいものがあると思います。法事の前日遠方からきた親戚が、お昼を食べそこなったというので午後3時ごろ中華料理店で皿うどんを食べて、次の夕食のための腹ごなしにぶらぶらしようと夕暮れの街に出かけました。 主演の映画で知る人も多くなったようです。先日親戚の法事が長崎であり、遠くから親戚も集まりました。長崎で生まれ子供の頃この地を離れ遠くに住む人にとっては「長崎」の響きは懐かしいものがあると思います。法事の前日遠方からきた親戚が、お昼を食べそこなったというので午後3時ごろ中華料理店で皿うどんを食べて、次の夕食のための腹ごなしにぶらぶらしようと夕暮れの街に出かけました。50年前は子供だったので思案橋から先は行った記憶がないと言うので、それではと散策、花月の前に着いたときは陽も落ちて真  っ暗でした。通りから石畳の露地の奥の玄関までお迎えのタクシーが入っていきました。その花月の前までド派手な傘(からかさ)に提灯が二つ下がった明かりが幾つも並んでいるのでよく見たら、そんなデザインの街灯でした。ぶらぶら節の赤い字が、まだ映画の宣伝をしているような雰囲気です。「中の茶屋」が近くにあるはずだと っ暗でした。通りから石畳の露地の奥の玄関までお迎えのタクシーが入っていきました。その花月の前までド派手な傘(からかさ)に提灯が二つ下がった明かりが幾つも並んでいるのでよく見たら、そんなデザインの街灯でした。ぶらぶら節の赤い字が、まだ映画の宣伝をしているような雰囲気です。「中の茶屋」が近くにあるはずだと 坂を登り細い迷路のような道を右へ左へ。夜だから余計に判りにくく、通りすぎて梅園天満宮の鳥居に来てしまい、あれ?やっぱりあそこらしいと後戻りをしたり。 坂を登り細い迷路のような道を右へ左へ。夜だから余計に判りにくく、通りすぎて梅園天満宮の鳥居に来てしまい、あれ?やっぱりあそこらしいと後戻りをしたり。ここではじめて、唄の文句で「冥土の裏門」と覚えていたのが本当は「梅園裏門」だったのを知りました(^_^;)。梅園身代わり天満宮にお詣りした出征兵士は皆無事に帰還したと書いてありました。坂の途中の家で明かりが灯っていない古い門灯を見つけました。家の造りを見ると昔はお茶屋さんだったようです。今は丸山の面影を残すものは「花月」だけになりました。坂の街長崎は一気にどこどこを目指して・・・・ということが出来る街ではありません。本当にぶらりぶらりと行きつ戻りつ歩く街です。
ハタチ過ぎといえばもう半世紀近く前の事になります。古い記憶は往々にして、いつの間にか事実と全く違った記憶に変化しているのに気付かず、後生大事に信じ込んでいたりすることがあるものですが、この記憶についてはいつも思い返していたので、ほぼ確かだと思います。当時は唯一軒しかなかった古い塚原温泉で一泊し、翌早朝から一日山歩き。夕方、由布岳から小雨に煙る湯布院に下り、その日の宿を探しました。濡れた登山靴を引きずって、人影のない道でやっと野良仕事帰りのおじいさんに出会いました。  「すみません、この辺りに旅館はないでしょうか」と聞くと、「ちょっと先に建ったばかりの金鱗湖旅館があるけど、気をつけて行きなさいよ。かなり高いという噂だから」。お蔭で心構えが出来た私達女二人は礼を言って、煌々と明かりがついた檜造りの御殿のような玄関をくぐりました。番頭さんが出て、直ぐ旅館の主人に代りました。主人はしばらく私達二人の上から下まで眺めて考えていましたが、「女中部屋が空いているけど、それでよければ。」と言いました。塚原温泉は混浴で、女中さんが「今、男の人が居ないから」と知らせてくれて、別棟にある薄暗い大きな浴槽でリラックスできなかったのに比べると、天国のようでした。温泉は無色透明、胃腸に良いからと、飲めるように柄杓が置いてありました。大きな浴槽のほかに、新しい木の香が匂い立つ白木の舟の浴槽が、ポコンと床(ゆか)の上に置かれていたので入ってみました。 翌朝窓の障子をあけたら硝子の向こうは真っ白で何も見えません。一瞬、「ここは何処?私は誰?」状態になりました。女中部屋が雲の中に浮いているのかと思った程です。この池に温泉が湧出して、明け方にかけて気温によってはこのような現象が起こることを知りました。その季節、気温はかなり低かったのでしょう。 今から13年ほど前、高校卒業以来初めて会う級友と博多駅で待ち合わせて、金鱗湖旅館に泊まることにしました。その頃は旅館は名前も外観も洋風のペンションに変わっていました。真夜中に熟睡している友人をそっと起こしました。月明かりが静かに金鱗湖一面に立ち上る湯気を浮かび上がらせていました。絵が好きな彼女はいつも小さなスケッチブックを持っていましたが、感動してその場でスケッチを始めました。 二つの金鱗湖をいつも懐かしく想い出します。 04. 2. 8. |
||