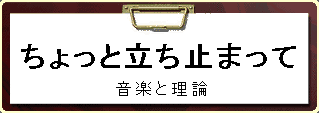
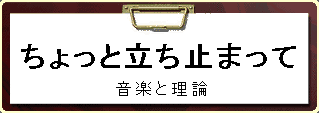
◇ 「音楽は理論や技術ではない」─ そのとおりです。音楽はその美しさや力強さで、人の心とともにあるからです。しかし、理論や技術が全くないところには音楽もありえない、このことも事実です。たしかに、理論や技術は音楽にとって目的ではありませんが、欠くことができません。
◇ 音楽理論は数学や科学のようには表せません。経験や直感がどうしても入り込んでくるからです。だからこそ音楽なのでしょう。しかしそれでも、
論理を秩序立てて集積することは、 ある程度可能です。実際、過去の偉大な作曲家たちも、作品を作るにあたりこのことを頭に置いていたのです。彼らは知っていたのです。歌詞を使わない、もしく部分的にしか使わない音楽における、理論の必要性を。長大な曲であれば、なおさらであることを。なにより音楽そのものを。
◇ おそらく音楽は、人の幸いとともにあるのでしょう。そして音楽は目に見えません。
◇ 目に見えるものが全てではありません。幾何学でさえ、本当の三角形は目に見えません。思想・信条も目に見えません。目に見えないものについて、正しいかどうかを判断するのは大変なことです。目に見える社会生活なら、法律に照らして正否を判断すればいい。現実はある意味で単純です。しかし、たとえば思想・信条についてはそう簡単にはいきません。
ひとつの思想・信条が人の幸いとともにあるためには、次の三つの条件が必要でしょう。
(1) 理論的構成を持つこと。
(2) 社会性や普遍性を備えていること。
(3) 正しい実践を伴うこと。
そうでなければ、そうした思想・信条はうのみにしない方が賢明でしょう。
◇ このことは、音楽についても同じようにいえると私は考えています。
(1) 理論的構成を持つこと。
(2) 伝統性と普遍性を兼ね備えること。
(3) 新鮮な創造性を伴うこと。
◇ ここで、私を含め、ワーグナーの音楽が好きな人にとっては、耳の痛いことを書かなければなりません。ヒトラーがワーグナーの音楽の熱烈な傾倒者であったことは周知の事実です。ホロ・コーストにワーグナーの音楽はどう関わったのでしょうか。ワーグナーの音楽がヒトラーを鼓舞したことは間違いありません。ワーグナーの音楽は正しかったのでしょうか。音楽は音楽にすぎない、と考える人も多いでしょう。しかし、少なくとも私たちは、単にワーグナーの音楽が好きだというのではなく、このことについて疑問を持つべきです。もしかしたらワーグナーの音楽は、張本人とまではいわないまでも、共犯者であったかもしれない。
ならば、その理由は ……。
(1) ワーグナーのとりあげた民話が、ドイツ民族にとって本当に豊かな伝統であったのか、どうか。
(2) その民話を、「楽劇」という様式に発展させる際に、何らかの問題点がなかったのか、どうか。
…… 疑問であり、今後の研究が待たれます。
日本では平気でワーグナーの音楽が流れますが、ヨーロッパでは、今なおワーグナーの音楽の演奏を禁止している劇場が多いそうです。
◇ 荒唐無稽なるものをもって、人の心を乱してはならない。いたずらに災いの種を播いてはならない。これは、創造に携わる者の、自らへの戒めです。判断するのは最後は自分です。音楽理論は、その判断する際の、一本ではありますが大切な柱なのです。