森有正――感覚がめざすもの、辻邦生、筑摩書房、1980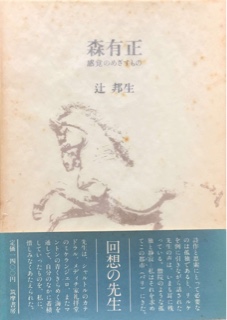
ある人物の生き方を普遍的な思想として理解することは易しいことではない。私の場合、思想の内容をその人物に固有な境遇や体験へ還元してしまいやすい。必要なことは思想を思想家へ戻すことではなく、受け手である自分の中へ広げることであるのに、それがなかなかできない。しようとしても、まず思想家の置かれた境遇と自分の境遇を比較することからはじめてしまう。 ある思想家の思想を理解するためには、その著書を読めばいい。評伝や年譜は読まずに著作だけを読むことができればなおいい。そうすれば著作に表れた思想だけを読み込むことができる。ところが実際には、何の本でも読み出すときには余計な知識とそれに助長された偏見をすでに抱いているもの。帯や奥付は、そうした偏見を読みはじめる直前にまで植えつけようとする。 ともかく、思想を思想として受けとめる、簡単そうでいてそれが難しい。思想家を個人的に知り、師として仰いでいれば、なおさらだろう。辻邦生が森有正について書くとき、その人物評は、小説家らしい細やかな観察と恩師に対する奥床しい尊敬に彩られた美しい肖像画となっている。 その一方で、森の思想や作品の解題となるとどこか歯切れが悪い。辻の随筆や小説で感じるような、透き通った山の清水をするすると飲み干すような清涼感があまり感じられない。 森有正のエッセーにおいては個人的体験と創作が虚実ないまぜになっている。また、エッセー、すなわち森の作品は『バビロンの流れのほとりにて』を起点にして時を重ねて成長していく。私は今、たどりついた思想が森自身の言葉で要約される晩年の講演や対談などから読みはじめることもできる。これに対して、同時代に、しかも個人的に身近にいた辻の場合は、思索を同時進行で見届けていたために、海図を持たない船に乗せられたように、思想の全体像をつかみきれないもどかしさがあったのかもしれない。 例えば、森のエッセーはたんに欧州文化の深奥を探る旅ではなく、自己へ帰る思索の旅なのだという理解に辻が至るのは、意外に遅い。その第一の理由は、辻が森に近すぎたということにあるに違いない。ただ、それだけではないようにも思われる。同じ言葉を用いる表現者であっても、小説家と思想家という違いが根本的な立場の相違となっているように思われてならない。 辻はすでに作家としての第一作を発表してから、「自分が作品を書く根拠」を求めてヨーロッパを彷徨した。その旅のさなか、パルテノン神殿を前にして、「人類が発生し、何百万年して滅亡してゆくその歴史の全体を包み、人間を高いものへ方向づける「秩序」こそが、美なのだ」という思いが光のように彼の心をとらえた。その光を小さな種のように胸にしまい彼はパリに戻り、さらに読書と思索をつづけた。そしてようやく見出す。 私は、それまで、この世界を、私と対立し、私と別個の存在、と思っていた。つまり自分とは、この世界のなかにおかれた一個の偶然的な存在にすぎない、と思えたのである。 辻にとって≪私の世界≫は彷徨の終点であり、創造の出発点である。彼は≪私の世界≫を材料に、美と秩序を備えた作品世界を建築していくだろう。 これに対して森にとって≪私の世界≫は初めから意識されているように見える。『バビロンの流れのほとりにて』で森が試みるのはむしろ≪私の世界≫の解体。森にとっては≪私の世界≫から魂の彷徨がはじまる。 森はパリで初めてみるノートルダムに感動するものの、その感動を否定する。それは見聞きしていた「あの」ノートルダムを見て感動したに過ぎないと感じたから。「名所」巡りは、その後ずっと森の批判の対象になる。「さすが」という日本語を対象の価値を無批判に受け入れる語として否定的に捉えていることも、この考えと関連しているかもしれない。 そこで森は、感動を自分の「純粋感覚」へと還元するよう試みる。その作業は平凡な感動を純粋な体験へ還元し、そこで得られた純粋な感覚をよく吟味された言葉で表現する、すなわち定義することによって普遍的な経験、思想へ昇華するまでの一連の内省。その精神の苦闘はコルドバのゴシック教会を見た時に一気に解決される。 異なる場所の異なる建築を通じて、森は己のなかに己だけのノートルダムを見出す。このノートルダムは「あの」パリのノートルダムではない。この教会にはもはや名前はない。名前のない街の名前のないただの美しい教会。この美しさを森は自分自身で名づける、定義づける。それが経験であり、その定義が思想。 辻の言う≪私の世界≫と森の言う「経験」を比べると、自己を中心とした創造と解体の違いともとれるし、解体も創造も表現の一つだとすれば、表現の方向性が異なると言えるかもしれない。辻は≪私の世界≫から溢れ出す美を小説という作品へ蒸留する。森は「純粋感覚」を思索という炎で煮詰めて、最後に残る経験という結晶を析出する。言ってみれば、思想における異なる化学反応の実験方法と見ることもできるかもしれない。 感覚から経験を析出する実験は一度ではない。あらゆる対象に対して実験は行われ、また何度でも行われる。 森のエッセー集は、そうした思索の反復。だから似たような表現が繰り返し登場し、うんざりしてくることさえある。同時に言えるのは、森が一度の「経験」で満足せず、弛まず思索を続けることでさらに深い「経験」に到達していく道程が、エッセー集成の第一巻だけでも体感できるということ。 ところで辻は、森を思索者であるより、表現者として見ていたようにみえる。辻は森の文章について、「見事な散文と、そして豊かな尽きることのない映像の輝きとを、頁ごとに、胸をときめかせ、芳醇な酒に酔うように読みふける」と形容している(「感覚がめざすもの」)。 私に言わせれば、芳醇なのはむしろ辻の文章のほう。森の文章はより荘重で重苦しい雰囲気さえ漂う。辻の文章を明るい澄んだ色のブレンデッド・スコッチ・ウィスキーにたとえられるとすれば、森の文章は、磯の香りやシェリー樽の香りが強く残るシングル・モルトのように、思索の発酵臭が強く残る。 辻と森を比較すると、違いは方法論だけではない。方法を実践する態度にも大きな違いが感じられる。辻は≪私の世界≫から作品を生み出すために、その動きは外へ向かう。その動きは≪私の世界≫を発見した喜びと新しい作品世界を生み出す喜びの二重の歓びに増幅されて外交的、肯定的、楽観的な旋律を帯びる。一方、自己の体験の奥深くへ降下していく森の手法は、内省的、自己批判的、悲観的な様相を呈する。 辻の作品がすべて楽観的であるというつもりはない。世界のあり方を積極的に肯定する姿勢が、つねに底流にあることを指摘したいだけ。現状肯定という言い方をするとむしろ否定的な響きがある。しかし辻が世界の今あるあり方を肯定するのは、問題を見過ごしたり、忘れたつもりで無理に前向きに考えたりするようなことではない。さまざまな政治的、社会的な問題を見据えたうえで、それを解決していく人間の潜在能力を含めて肯定する姿勢。 辻の世界肯定の姿勢は、森の死後に書かれた文章によく表れている。敗戦国から船でパリへ向かった森の時代と、辻が追悼文を書いた1980年の間には大きな隔たりがある。その隔たりを辻は積極的にとらえようとする。飛行機で短時間にパリへ行けるようになり、日本は経済的には欧米諸国を圧倒するようになった。 そのような状況において、ヨーロッパ文化から学ぶことがなくなったとは辻はもちろん言わない。まだまだ学ぶべきことは多い、と彼は考える。それでも経済的に豊かになり、技術の進歩による旅行時間の短縮や、生活感覚においても心理的な距離感が格段に短くなったことを考えれば、もう森が選ばざるをえなかった孤独で悲壮な方法を用いる必要はないのではないだろうか。辻はそのように考えている(「ある試みの終わりーーコスモポリタンとエトランジェ」)。 このような肯定的な時代の受けとめ方は、辻の個人的資質だけによるものではないだろう。1980年代には、確かに物質的に豊かになること、日本国外へ人やモノが出て行くことを積極的に肯定する雰囲気があった。それは必ずしもジャパン・アズ・ナンバー・ワンという独善的な自己評価ばかりではなかったはず。これまでのやや屈折した憧憬からではない、同じ目線からよいところを学ぶという段階にようやくたどり着いたという一種の安堵感もあったのではないだろうか。 もっともその後の十年間は巷間「失われた」などと自嘲的に呼ばれているように、辻の期待に応える展開になったとは言いがたい。辻の展望が甘かったというつもりはない。むしろ彼のような考え方は、経済的、社会的に不安な現在にこそ求められているのではないかと思う。実際、彼は90年代に入って加速したグローバリズムについても、否定的にではなく、あえて肯定的な側面に光を当てて「世界文化混淆(アレクサンドリア)」と呼んでいる(「春にパリで思ったこと」『海峡の霧』)。こうしたところは、≪私の世界≫をつねに明朗に広げていった小説家、辻邦生らしい。 辻邦生らしいと言えば、森の死後に見た夢には恩師森への思いを含めて、本書を通じてこれほど辻邦生らしさが表れているところもないように思われる。彼は森の訃報を聞いた後、森が棺の中で「いたずらっぽい笑顔で、ウインクされる」夢を見たという。さらに離婚した前婦人が亡くなった後には、「先生が前婦人と一緒に腕を組んで、ギリシア神殿のような建物に向かって歩いてゆかれる」夢を見たのだという(「あとがき」)。 この挿話から、辻邦生が森有正を心から敬愛しながらも、森に欠けていると残念に思っていたこと、辻自身が生きるなかで大切にしていたことが、よくわかってくる。そうして、すでに亡くなっている森有正が、生前幸福に過ごすことができなかった前夫人と、森と辻自身が「経験」と≪私の世界≫をそれぞれ見出す舞台となった神殿へ腕を組んで歩いていくという夢が、すでに美しい小説の一場面となり、読者である私の心に映し出されてくる。 |
碧岡烏兎 |