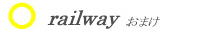石川県の私鉄保存車
北陸鉄道
北陸鉄道は金沢市に本社を置く県内最大手の私鉄ですが、鉄道に関しては現在、石川総線、浅野川線の2路線になっています。過去にあった金石線、小松線、加南線、能美線、金名線などは廃止となっています。名鉄の資本が入っていますが、電車やバスのカラーは独自デザインになっています。
保存車「しらさぎ号」

撮影:山中温泉ゆけむり健康村(2018.9.2)
北陸鉄道 クモハ6010形(6011号)

撮影:山中温泉ゆけむり健康村(2018.9.2)
加南線(大聖寺〜山中間)の急行用に1963年に作られた“日本初のアルミカー”。「しらさぎ号」と命名されています。
前年に製造された「くたに号」をベースにした2扉転換クロスシート、扇風機付のデラックスな観光用電車で、富山地鉄10020系や長野電鉄2000系と同じ側面スタイルをもつ日本車輌製です。もっとも「くたに号」が並行カルダン駆動の高性能車だったのに対し、「しらさぎ号」は在来品を流用した釣り掛け駆動車で、車体と動力とはアンバランスです。
1970年に国鉄北陸本線に加賀温泉駅が開業するなどの影響もあり、1971年に加南線は廃止となりました。せっかくのロマンスカーも北陸鉄道では使う場所もなく、大井川鉄道に譲渡されてしまいました。
時は流れて2005年、加賀市に合併されて山中町の名前が消える前に、町の歴史の証人として保存すべく、大井川鉄道から譲渡され、道の駅を永住の地としました。
保存車「しらさぎ号」

撮影:山中温泉ゆけむり健康村(2018.9.2)
北陸鉄道 クハ6060形(6061号)
クハのほうは、建物に顔を合わせるようになっているため、写真が撮れません。なんとか、顔つきだけは撮ることができました。
正面に前照灯のほかに、両脇にライトが増設されています。大井川鉄道時代の施工でしょうか。
保存車

撮影:能美市立博物館(2018.9.2)
北陸鉄道 モハ3760形(3761号)
石川総線で使用されていた戦後型17m級車両で、広瀬車輌製。モハ5100形を名乗っていましたが、機器更新などでモハ3760形に改番され、幾度かの車体更新を経て、正面貫通扉付き、ノーシルノーヘッダー、固定窓Hゴムの北陸鉄道の旧形車によくある顔つきに変わりました。
保存車

撮影:能美市立博物館(2018.9.2)
北陸鉄道 ホム1形(1号)
元は1914(大正3)年に九州の筑豊地区の炭鉱で石炭を運ぶために作られた貨車で、戦後は西武鉄道、近江鉄道で使用され、1967年に北陸鉄道入りしたそうです。
北陸鉄道では線路のバラストを運ぶために使用され、能美線沿線にあった砕石工場の引き込み線に置かれていました。1980年に能美線が廃止となり、バラスト輸送もトラックに移行、この車両は2007年に廃車となりました。その後個人に引き取られたものの、能美線ゆかりの車両ということで、博物館が引き取ったそうです。(現地説明板による)
尾小屋鉄道
尾小屋鉄道は、小松駅を起点に尾小屋(尾小屋鉱山)に至る非電化の軽便鉄道で、軌間762mm、営業キロ16.8kmでした。起点の小松を除くと沿線に目立った人口集積地や観光地はなく、貨物輸送で成立していた鉄道のようです。
鉱山の閉山と道路の整備による車の増加などにより、1977年に廃止となりました。
その後、小松バスと名前を変え、現在はバス事業中心の経営となっています。北陸鉄道とは系列関係にあり、やはり名鉄資本です。
現在保存車は2ヵ所にあり、いずれも動態保存車です。特に小松市粟津の「なかよし鉄道」では週3日間の定期運転も行われています。
ポッポ汽車展示館
動態保存車

撮影:ポッポ汽車展示館(2018.9.2)
尾小屋鉄道 蒸気機関車5号
戦後1947(昭和22)年製とされるCタンク蒸気機関車。狭軌の蒸気機関車としては大型だそうです。立山重工業製。
尾小屋鉱山の閉山後、大きなスノープローを付けて除雪用になっていたそうです。
現在、尾小屋鉱山資料館に隣接する展示館で先頭に立って保存されています。
動態保存車

撮影:ポッポ汽車展示館(2018.9.2)
尾小屋鉄道 ハフ1形(1号)

撮影:ポッポ汽車展示館(2018.9.2)
開業時に用意された木製の2軸客車で、1917(大正8)年に名古屋電車製作所で製造されたもの。両端はオープンデッキ。
後に外板を鉄板張りに改造していますが、それ以外は原形をとどめています。
動態保存車

撮影:ポッポ汽車展示館(2018.9.2)
尾小屋鉄道 キハ3形(3号)

撮影:ポッポ汽車展示館(2018.9.2)
1966年の増備車で、遠州鉄道奥山線からの譲受車。1954年製なので、それなりに新しく、また在来車より大型のボギー車で重宝されたそうです。エンジンはいすゞDA45型。
遠州鉄道ではキハ1803でしたが、その180を塗りつぶして3としています。
なかよし鉄道(粟津公園)
動態保存車

撮影:粟津公園(2018.9.2)
尾小屋鉄道 キハ1形(1号)

撮影:粟津公園(2018.9.2)
尾小屋鉄道最初の半鋼製ボギー気動車で、日本車輌で1937年製。
当初は平妻スタイルでしたが、後に切妻スタイルに改造され、独特な顔つきになりました。
現在、定期運転は通常はこの車両が担当しています。公園内に引かれたレールの上を1往復するのが基本で、途中には踏切やカーブ、ポイントもあり、また子供たちを楽しませるための小細工も施されています。
動態保存車

撮影:粟津公園(2018.9.2)
尾小屋鉄道 ホハフ1形(3号)
元三重交通の客車ですが、遡ると中勢鉄道開業時の1921(大正10)年製の客車。元は窓の小さい角張った車両でしたが、近代化の改造の結果、上部がHゴム支持の窓に改造されました。
車体にはホ8と表記されています。
通常は車庫内に保管されています。
動態保存車

撮影:粟津公園(2018.9.2)
尾小屋鉄道 ホハフ1形(8号)
元三重交通(←北勢電気鉄道)の客車で、1925(大正14)年製。元はダブルルーフの木造客車でしたが、1970年に鋼製車体に載せ替えられ、窓の上部がHゴム支持の、当時としては近代的な車体に生まれ変わりました。
通常は車庫内に保管されています。
動態保存車

撮影:粟津公園(2018.9.2)
尾小屋鉄道 DC12形(1号)
戦後の1952年に蒸気機関車に変わり製造されたディーゼル機関車。一部蒸気機関車の足回りを流用して作られたそうです。
通常は車庫内に保管されています。
三菱DF2L型エンジン

撮影:粟津公園(2018.9.2)
粟津公園に入口付近に置かれたエンジンです。恐らくディーゼル機関車に搭載されていた三菱製のDF2L型エンジンだと思われます。
説明板には、尾小屋鉄道そのもののことが書かれています。
参考文献
- 西脇恵(1968)「北陸鉄道(私鉄車両めぐり77)」鉄道ピクトリアル連載
- 宮沢元和(1968)「尾小屋鉄道」(鉄道ピクトリアル68-7増)65-75
- 朝日新聞社(1973)「世界の鉄道'74」