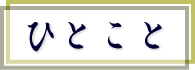
寺報第81号より
合掌。芒種の候。間もなく梅雨入り、今年も熱中症には気をつけましょう。喉が渇く前に水を飲む。ビールはNGだそうです。
先号で「お寺に来る人たちの顔を仏さまは見ておられます。仏さまに顔を覚えられたらラッキーです。功徳を譲り与えられるのですから。」とお伝えしましたら「仏さまに顔を覚えてもらえたら嬉しいです」と言いながらお参りに来られた方がおりました。この素直さが素晴らしく、思わず仏さまに「この人の顔を覚えて下さい!」とお願いしてしまいました。何よりもお寺の敷地に入り、仏さまの前にいることが大切なのです。「気」というか「空気感」というか、巷ではパワースポットなどと言われたりしますが、このような場所にはそれなりの「気」が充満しているもので、それを体に浴びることで功徳が具わったりするのです。お経を聴くだけで毛穴からその功徳が入ってくると言われますがまさしくそれです。これからの時代を考えるとたぶん・・・きっと・・・おそらく近い将来、オンライン参拝なるものが始まると思います。私自身それを予想していて頭の中でシミュレーションも行っています。体が不自由な方にとってそれは逆に有り難いことかもしれませんし、遠方の方や海外に居る方も参加出来るツールです。良いものか否か、分かりませんが、時代の大きな流れというものは中々変えられません。私としては率先して行いもしませんが否定もせず、いつでも対応できるようにしたいと思っています。ただ、先述のようにその「気」から頂く功徳があることは伝えておきたいと思っています。私は身延山久遠寺に行くと背筋が伸びます。何というかそれこそ空気が違うのです。その中でも一番好きな場所は「御廟所」という場所で日蓮聖人が当時居住されていた付近です。皆さんも参拝してみて下さい。他とは違う空気の流れを感じるかも知れません。因みに六月十五日~十七日には身延山で開創法要が行われますので是非とも参拝してみて下さい。
さて話がガラッと変わりますが、現在ウチには十七才のフランス人女子高生が住んでいます。鶴嶺高校の交換留学生をホストファミリーとして預っているのですが、家族が一人増えたようでとても楽しく日々を送らせて頂いています。フランス語は「ボンジュール」「メルシー」「ウィ」くらいしか知りませんから英語で会話を、などと意気込んで勉強までしていたのですが、「日本語の勉強になりませんから日本語で話して下さい」と言われてしまいました。今では普通に生活するのに困らないくらいペラペラです。まさに恐れ入谷の鬼子母神!つい先日は浴衣を自分で着て花火を観に行きました。その努力と根性、度胸に感服です。会話が弾んでくると「え!マジ?ヤバい!」とか挟んできたり、無茶ブリすると手のひらを広げ「結構です」などと返したりもします。本堂の仏具や装飾品に感動したり、お経を不思議そうに聴いたり、唱題行の時は大太鼓の音にビックリしていました。習慣や文化の違いに戸惑いつつも今ではすっかり慣れ、日本が好きな国の一つになってくれたようです。当初、留学生の受け入れについては、かなり悩みましたが今は良かったと思っています。ただ一番大変だったのは奥方様だと思います。感謝しています。奥方様もきっと良かったと思ってくれていると思います。たぶん・・・きっと・・・おそらく・・・恐ろしくて聞けない・・・誰か、聞いて・・・


今年は庭にある白い花が妙に綺麗に見えました。我が家に家族が一人増え、一輪の綺麗な花が咲いたように感じた気持ちが、その様な景色に見えさせたのでしょうか・・・この縁に感謝しつつ彼女が将来世界の平和に貢献するような人材になってくれたら嬉しいな。彼女が背筋の伸びるところはどんな場所だろう?
人には背筋が伸びる場所が一つくらいあったほうが良いかも知れません。それは自分を律する大切な場所のはず・・・大切にしたいものです。 あ・・・そう言えばもう一つ私の背筋が伸びる場所が有りました。奥方様の前では何故か背筋が伸びます・・・大切にしたいものです・・・
今日もお題目を唱えて皆々様の幸せを祈りたいと思います。
南無妙法蓮華経



副住職の一言 〈 名前 〉
先日、初めて『世界がもし百人の村だったら』という話しを読みました。世界の人々を百人だけの村に縮小して考えるものです。全世界の人々を百人として考えると「女性が五十二人、男性が四十八人」「七十五人には家があるが、二十五人には家がない」などをイメージしやすく表現しています。ところで、この地球上に生きている生物の種類を百種類に凝縮すると、「学名」という世界共通の名前が付けられている生きものはたったの八種類しかいなく、残りの九十二種類には名前がないそうです。名前とは存在そのものを表わすもの、自分が自分であることの証明であり、自分以外の人たちが自分を認知するために必要不可欠なものです。かのマザーテレサは愛情の反対語を「無関心」「無視」と言いましたが、そう考えると名前があるということはそれだけでこの上ない愛情の証であると言えます。 『アイユ』という人権啓発誌に掲載されていた中学一年生の實原朋恵さんの作文には「名前で呼ばれるのはその人の権利であり、名前で呼ぶことで責任感という義務が生じる」「名前で呼ぶことは責任ある態度なのだ」とあります。
お釈迦様はお弟子さん一人一人に向かってそのお名前をお呼びし、語りかけられました。私もその御姿に倣い、日々お会いする皆様そのお一人お一人を〇〇さんとお名前でお呼びすることが、かねてからの目標です。責任を持って精進して参りたいと思います。
改めまして、私は信隆寺副住職 木村佳奨(キムラケイショウ)と申します。今後ともよろしくお願いいたします。
南無妙法蓮華経 (拝)
ご報告
この場をお借りして皆様に感謝を申し上げます。当山改修工事ご寄付を有難うございます。先ずは本堂の北側漆喰の雨漏りから修繕を始め、西の塀の工事にも着工できればと思います。引き続きご協力の程、よろしくお願い申し上げます。合掌。
お知らせ
- 6月5日
- 大東亜戦争終戦八十年戦没者慰霊法要
- 7月13~15日
- お盆棚経 日程は事前にお知らせします。
- 7月27日
- 新盆 盂蘭盆施餓鬼法要
- 8月13日~15日
- お盆棚経 施餓鬼法要の日に貼り出します。
- 毎月7日 9時~12時
- 有志にて清掃奉仕 本堂の清掃や仏具のお磨き、庭の草むしりなど、仏さまに給仕奉公し、心の垢も落とします。(有志募集中)
清掃後、お茶飲みしておしゃべり致します。
