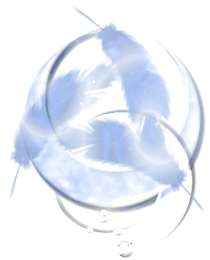 |
CRESCENT MOON 綺麗な月の夜だった。 指輪の旅から一年余り。ホビット庄は、今やすっかり落ち着いた生活の中にある。 そんな平和で静まり返った庄の片隅で、かすかに響く水音があった。 「冷たすぎはしませんか?」 気遣う声に、フロドは肩越しに振り向いてそっと微笑んだ。 「大丈夫だよ、サム。これくらいの冷たさがかえって丁度いいくらいだ。それより、こんな夜中に悪かったね」 夢見の悪さにうなされて、水でも浴びてさっぱりしようとしたところを、サムに見つかってしまったのだ。 「何を言うんですか。こんな時こそオレを頼ってくださいといつも言ってるじゃないですか」 遠慮深い主人を押し切って、風呂に水を張って無理やり手伝っているサムは、水桶で掬った水を、滑らかな背中にそっとやさしく掛けてやった。 小さなランプと窓から射しこむ月明かりだけに照らされた浴室。 フロドの華奢な背中は夜目にも白く輝いて、サムは時折目のやり場に困るほどだった。 「どうした、サム?」 「い、いえっ、何でもありません」 不埒な思考に止まった手を慌てて動かしながら、サムは奪われる視線を何とか引き離した。 最近の主人は、なんだか昔から知っている主人と違う気がする。 時々遠くを見ている眼差しやちょっとした仕草が、妙に人の目を惹きつけるのだ。そしてそれは、目にした者に守ってあげたい気持ちと同時に奪ってしまいたい衝動を起こさせる。 心が騒いでしょうがない。 なぜこの人はこんなにも儚げで今にも消えてしまいそうなのだろうと……。 だけど、それは今に始まったことではなかったのかもしれない。 いや、本当はもっと前から、あの指輪の旅の半ばから、サムは気づいていた。そして、そんな主人に目を奪われる自分は、もっとおかしいと…。 でなければ、フロドの潤んだ瞳や細い肩、少しかしげたうなじや白い背中に、こんなに胸が苦しくなるはずがない。 まして、今の自分は妻子有る身。主人に邪な思いを抱くこと以前の問題なのだ。 しかし…、 「サム?」 意識しまいとすればするほど手は震えて、サムは指が肩先に触れた拍子に、とうとう水桶を取り落としてしまった。 「あ、ああっ…、旦那、すみません……っ」 「いや、それよりどうしたんだい、サム。今日のおまえはどこかおかしいよ。いや、今日だけじゃない。このところずっと上の空みたいだ…」 「旦那…」 すべてを見通すような深い緑の瞳にみつめられて、サムは観念した。 気づかれていたのだ。 自分の邪な気持ちが、自覚する前から知らず知らず行動に現れていたなんて、サムは身が縮む思いだった。 「許してください、フロド様。オレは、オレは…」 「サム…サムや。そんなに辛そうな顔をしないでおくれ。おまえにはいつも笑顔で暮らしていて欲しいと思っているのに」 首を垂れてすっかり意気消沈してしまったサムの頭を、フロドはやさしく抱き寄せた。 だが、滑らかな肌の感触に、サムの胸は一層ざわめいてしまう。 「旦那、旦那…、フロド様……」 自分ではどうしようもないのだと訴えると、フロドは抱きしめたサムの耳元に囁くように言った。 「大丈夫。わかっているよ、サム。おまえが悪いんじゃない。それはきっと指輪のせいだよ」 「指輪…?」 「そうだよ、あの指輪だよ。私にはちゃんとわかっている。なぜなら、私もまた指輪に心を引き裂かれた身だからさ。おまえの苦しみはよくわかる」 そう、たぶん誰よりも… 「フロド様」 サムはまさかと驚き目を見開いた。 「考えたら、あの旅から帰ってからずっと、私達はちゃんと話し合ったことがなかったね」 フロドは、以前ガンダルフから聞き覚えた指輪の力について語った。 指輪の及ぼす力は、保持者によって様々だという。 サウロンによってもたらされた指輪は、それぞれに強い力で保持者を支配した。 何かに執着している者にはより一層の執着を強い、それ以外の者には指輪そのものに執着を強いる。 持つ者の胸の奥、自分さえ気づかない欲望を引きずり出すのが恐ろしさの所以だった。 ドワーフの金や宝石への貪欲さがいい例だろう。 ましてフロドの手にあった指輪は特別なものだったのだ。 「おまえも、ほんの僅かな時間とはいえ、保持者だったことにはかわりはない。あれは失われた後でさえ、私達を縛る邪悪なものだ」 指輪によって刻まれた傷は、ナズグルの傷よりも深いことを、フロドはもう知っていた。そして、それが遠からず自分をここより他の地へ連れ去ってしまうことも。 「ではオレは…」 サムは思った。 ――――― オレはフロド様に執着を… 「何ということだ…」 サムは呆然と宙を見た。 「オレは確かに旦那のことが好きだった。だって旦那は優しくて、ほかのどんなホビットの連中とも違って輝いていたから…。でも、それがこんな風になるなんて」 歪められたからこそ焦がれる気持ちはサムをよけいに苦しめた。 身体の中で、フロドを求めて溶岩のように熱い何かが溢れてしまいそうだ。 「いいんだよサム。おまえのせいではないのだから」 フロドは憂えた瞳で、苦しげな顔のサムを見つめて言った。そして、湯船からそっと立ち上がり薄布を纏うと、サムの手を引いて居間の暖炉の前に導いた。 暖炉には燃え残りの炭が残っていてまだほんのりと暖かい。その前に敷かれた毛足の長い絨毯に座って、フロドはサムに呼びかけた。 「おいで、サム。おまえの心を引き裂こうとするものは、私がすべて消してあげるから…」 「旦那…でも……」 「いいから。これは私にできる精一杯だよ。おまえに受けた恩を、こんなことでしか返せない…」 「フロド様」 微笑むフロドの前に、サムはふらふらと膝をついた。 薄布の隙間から見える肌は艶かしく、抗いがたい衝動を覚える。サムはコクリと咽喉を鳴らしながら、この感覚は、以前にも経験した覚えのあることを思い出した。 そうだ、あのキリス・ウンゴルで、指輪を手にフロドを見たときと同じ感覚だ。 あのときも今と同じように、目の前の大事な主人を身も心もすべて奪って自分だけのものにしてしまいたい欲望に駆られた。 すぐに指輪を手放して、久しく忘れていたというのに、なぜまた囚われてしまうのか。 サムは一度捕らえた者の心を蝕む指輪の恐ろしさを思い知った。そして自分の欲深さをも…。 フロドは、そんなサムの葛藤を和らげるように、ただやさしく微笑んでいる。 「フロド様…すみません」 サムは、これから自分が犯す罪をすべて許そうとするフロドに詫びながら、淡く開いた唇にそっと口付けた。 「サム、サム…ん、……んぅ…」 重ねた唇を深くしながら、サムの無骨な指がフロドの身体をまさぐっていく。止められない欲望のままに主人を貪るサムの目には、うっすらと涙が滲んでいた。 冴えた月の光だけが、慰めるように照らしている。 それは、フロドがホビット庄を永遠に去る数ヶ月前の出来事だった。 |
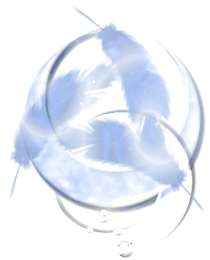 |