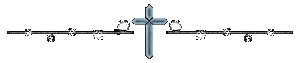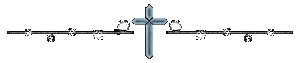真夜中の共犯者
兄を美しいと思うようになったのはいつの頃からだろう。
朗らかで真っ直ぐなボロミアを好ましく思う者は多い。
ファラミアの自慢の兄、ボロミア。誰よりも誇り高いゴンドールの大将。
偏屈な父に偏愛されるボロミアを、羨ましいと思うより前に、憧れや思慕の念がファラミアの中にあった。
ファラミアの中で、ボロミアはそれほど崇高な存在だったのだ。
だから、自覚はなかった。まして、ボロミアの生き様に高潔さを感じても、彼をそういう意味で“美しい”と思うなど……。
あの、王の末裔が玉座に再び就くまでは……。
ファラミアが、自分の兄と王がいかがわしい関係にあると知ったのは偶然だった。
閣議の折、具合が悪そうに途中退席した兄を見舞おうと伺った兄の居室に、王が居合わせたのだ。
今思えば、以前から王のボロミアを見る目は異常だった。
普段は穏やかに人を導く王が、ボロミアと二人でいるときだけは、なぜか獰猛な獣の雰囲気を纏うのだ。
最初は気のせいだと思った。しかし、兄の部屋でその場面に遭遇したとき、ファラミアは己の直感を確信した。
気分が優れないと言ったボロミアは、確かにベッドに横たわっていた。しかし、その恰好はあまりにも淫らで、ファラミアはこれが本当にあの慎ましく騎士道精神に溢れた我が兄かと目を疑うほどだった。
仰向けに仰臥したボロミアは、腕をひとくくりに頭上で縛られ、大きく寛げた胸を喘がせていた。見れば下履きまで取り去られた下肢は開かれ、ベッドの両柵に括り付けられている。
王の身体は、その間にあった。割開いた下肢をさらに己の身で割くように動いていた。
不規則に、強く、緩く、時には捏ねるように揺れ動く。その度に、ボロミアの唇からは信じられないような虚喜の声があがっていた。
ファラミアは、部屋の入り口で佇んだまま、一歩も動けなかった。どうやってその場を離れたのかも覚えていなかった。
ただ、兄が恐ろしく遠いところに行ってしまったような気がした。
数日は平穏な日々だった。
いつものように騎士団の会議と装備の点検、市中の巡回をしてすごす日々に、ファラミアに平静な心を取り戻していた。だが、あれは夢だと思うにはあまりにも衝撃的な光景だった。
「ご機嫌が優れないようですね」
所用で王宮に赴いたファラミアが内苑を歩いていると、見かけた王が親しげに声をかけてきた。
「先日は夕食をご一緒にと思っていたのに突然帰られたから、あなたまで具合が悪くなってしまわれたのかと心配しましたよ」
「いえ…。そういうわけでは…」
自分に見られたとは微塵も思っていないのか、それともわざとはぐらかしているのかわからない王の態度に、ファラミアはどう接すればいいのかわからず言葉を濁した。
あれから、何度も兄を犯す夢を見た。
背徳は甘い毒のようにファラミアを蝕んでいく。
だから、王に、「あなたも、彼を抱いてみたいと思いませんか?」と言われたとき、それを言い当てられたような気がして、ファラミアは思わず叫んでいた。
「私は、あなたとは違う!」
「どう違うのです」
王は挑発するよにファラミアを流し見た。その目は心の奥底まで見透かすように鋭く冷たかった。
「あなたが彼を見る目はただの兄弟愛とは思えない」
「私は…、私は兄上を尊敬しているのです。あなたの邪な欲望と一緒にしないでいただきたい。あのようなことをして…っ。恥ずかしいとは思わないのですか!?」
「あなたもボロミアを知ればわかる」
王は、ファラミアの罵倒にただ静かに笑って言った。
「明日の晩、ボロミアの部屋に来られるがよい。そうすれば、あなたの本当の望みがわかるはずだ」
そうして、再び訪れた兄の居室で、ファラミアは己の胸の奥深く潜んでいた昏い欲望に向き合うことになったのだった。
王に責められるボロミアの花芯を夢中で貪ったファラミアが正気にもどったのは、ボロミアが果てた後だった。
さんざん王に責められて達したボロミアは、意識朦朧としたまま横たわっていて、上気した身体からは、滴るような色香が漂っている。
その悩ましい姿を前に、理性を取り戻しつつあるファラミアが倫理観や道徳心に喘えでいると、
「今度は、弟君に犯される悦びを教えてさしあげよう」
と言って、王が座を譲った。その目が、おまえの番だと言っていた。ここまできて、逃げることは許さないと…。
もとより、そのつもりはなかった。
兄を犯すという倒錯的な悦びが、ファラミアの思考を支配していた。
「ボロミア…」
虚ろな意識を無理やり呼び戻して、最初から丁寧に愛撫していく。
喉元から胸にキスをおとしながら、僅かに開いた下肢の間に手を差し込む。ボロミアは慄いて身を捩った。
「あ、ファラミア…や…」
力ない腕で押し戻そうとするのを押さえつける。
自分を見る目が、明らかに嫌悪と恐怖を湛えていることを見て取って、昨日までの兄弟の関係が終わりをつげたのがわかった。
残酷なことをしていると思う。こんなことは兄への裏切りだ。
だが、ファラミアはそんな目を見てもやめるつもりはなかった。
さっき啜ったボロミアの蜜の甘さが、まだ舌に残っていて、もう一度味わいたいと欲している。
花芯を含もうと唇を寄せると、ボロミアはますます嫌がった。見かねた王が、上半身を拘束する。
「今更何を恥ずかしがることがある? さきほどまでのご自分の狂態を忘れたわけではあるまいに」
「……っ」
意識がそれた隙にすらりとした脚を開かせて、ファラミアは兄の花芯をねっとりと舐め上げた。
「あああぁぁ……っ」
感じやすい身体が、直接的な刺激に跳ねる。全体を含んですすり上げ、先端の穴を舌で抉ると、すぐに震えて蜜を滴らせた。
「あ……あぁ、いや…だ、もう…許して……」
甘い掠れ声が切れ切れに懇願する。
嗜虐芯を煽る声だった。普段の慎み深い仮面の下に、こんな淫猥な顔を隠し持っていたとは。
――― もっと暴いてやりたい…
もっと泣かせて、よがり狂うほど感じさせて、快感に咽び泣く姿を見てみたい。
ファラミアの中で、兄はもはや兄ではなかった。
気が付けば、ボロミアは後ろ手に縛られて、その身体を抱きかかえるように座った王に胸を嬲られている。
よほど感じるのだろう。広げた手のひら全体で乳首ごと揉まれるたびに、ファラミアの口の中でボロミアの欲望が跳ねた。
「いや…っ、も……あ、ああ…はぁ…っ」
力なく首を振るボロミア。きつく目を閉じ、すすり泣くような声を漏らすまいと精一杯唇を噛み締めて、だが堪えきれずに喘ぐ。
そんな艶めかしい姿を堪能し、もう少しで達するところまで追い詰めて、ファラミアは次の標的に取り掛かった。花芯の奥、ひっそりと存在する、もう一つの花…。
さきほど王に散らされたばかりだと言うのに、もう花弁は慎ましく閉じてしまっている。
脚を抱えてそこがすべて見えるように曝け出されると、花は羞恥に震えるボロミアを裏切って差し込んだ指をやんわりと呑み込んだ。
「よせ…っ、ファラミ…ア…っ!」
花の中は、思った以上に熱く、柔らかく、それでいて絞るようにきつく、ファラミアはその感触をもっと味おうと、さらに指を増やして深く突き入れた中で蠢かせた。
「あああ…あ、い、いや…ぁ…」
「兄上…、中が熱いですよ…」
触ってもいないのに、前からは蜜が零れ落ちている。
「はしたないですね。兄上はこんな処で感じているのですか。そう言えば、さきほどもここだけで達ってしまわれましたね」
「くぅ…うう…」
「ほらボロミア、ちゃんと答えなさい。ファラミア殿が聞いていらっしゃるのだぞ」
思慮深い賢弟の顔を脱ぎ捨てて、兄を犯す悦びを享受するファラミアに満足したのか、王が面白がって加勢した。
やがて、丹念に花筒を探っていた指が一番弱い箇所を掠めたのだろう。ボロミアは声もなく仰け反って果ててしまった。
「ここがイイ処なのですね」
嬲られて慎みを無くした蕾から、先に注ぎ込まれた王の欲望が滴り落ちた。
「おやおや、こんな粗相をして…。ファラミア殿は初めてでいらっしゃるのだから、綺麗にしなくてはな」
王が、また何やら思いついたのだろう。何をされるのかと怯えるボロミアをよそに、寝室の奥の扉を開けて言った。
「ファラミア殿、こちらへ」
促されるままに、ボロミアを抱いて向かう。
扉をくぐると、狭い廊下の先に、間口の狭い浴室があった。
「さぁボロミア、そなたの身体を洗ってあげよう」
「い、いやだ、アラゴルン…っ」
有無を言わせぬ強引さで、ボロミアは浴室に四つん這いにさせられた。
「こ…んな……っ、あ、あああ…っ!」
開かせた脚の間に絶えず暖かい湯をかけながら、王が二本の指で奥に溜まった体液を掻き出す。そうしながら、丹念な指使いはわざと執拗にポイントを突いて、ボロミアを泣かせた。
中をくつろげようと抜き差しされる動きに腰が震える。
石鹸をあわ立てたファラミアに両手で感じやすい胸を、股間をぬるぬると嬲られて、ボロミアの膝はガクガクと今にも崩れそうだった。
「いや……ぁ…あ、駄目、だ…あ、ああ……っ」
開かれた花筒の中にまでお湯が入る。
「どうしたのです兄上。またイきそうなのですか? いいですよ。何度でも気持ちよくさせてあげますから、さぁ、イッて見せてください」
「いや、いやだ……もう…」
これ以上はつらいと懇願するのを無視して、二人の男はボロミアの身体を執拗に弄った。
「あ、あ……あッ―――ぁ……」
王の指に一際深く犯され、ファラミアに胸の突起をきつく摘まれた瞬間、うわずった声を上げてボロミアは浴室の床を汚していた。
それを見届けて、王がヒクつく奥から指を抜く。
すかさずファラミアは自分の欲望を兄の蕾へ捩じ込んだ。
「くう…んっ、ううっ…」
突然の挿入にも、中の媚肉はファラミアを柔らかく包み込むように迎え入れた。
「ああ、暖かい…。今私は兄上の中にいるのですね…」
得も言われぬ感動が湧き上がり、ファラミアは夢中で腰を動かした。抱き起こされて、さらに深く繋がったきつさに喘ぐボロミアの胸を、今度は王が嬲り始める。
石鹸のぬめりをかりて、突起をつぶしたりひっぱったりしたあと、胸全体をぬるぬると手のひらで揉み上げられる。乳首をクリクリ転がされると、余計に中のファラミアをヒクヒクと締め付けてどうしようもなく感じてしまった。
「ボロミア、ステキだ…」
ファラミアの雄は、締め付けられるたびに容量を増す。
「このまま中にたっぷり出してさしあげますからね」
「い、いやだ…っ、ファラミア……それだけは…、なら…ぬっ」
血のつながった弟に犯されただけでも気が狂いそうなのに、これ以上はとても耐えられそうもなかった。
だが、そんなボロミアの意識も、媚肉の柔らかな箇所を何度も擦られるうちに遠ざかっていく。
胸を、花芯を、奥の媚肉を、男たちはたっぷりと愉しんだ。
「ほら、ボロミア、イきますよ」
「ぁ……っあ、ああ……んん…っ、もう、もう許し…はあああ……っ」
大きくグラインドして中のファラミアも達した時、灼熱の奔流に媚肉の隅々まで犯されて、ボロミアもまた何度目かわからない絶頂に登りつめていた。
事が終ると、憔悴したボロミアを寝かせたベッドの脇で、王とファラミアはボロミアの寝顔を肴にして飲んだ。
「これで、私の言っていたことがわかりましたか?」
すべてを見届けた王が、ファラミアに尋ねた。
グラスに濃い葡萄酒を手ずから注ぐ王に、ファラミアはもう反論するつもりはなかった。
「ええ。どうやら私も王と同じように兄を愛してしまったらしい」
認めてしまえば、すべてが楽になる。
昏い笑みを浮かべるファラミアに、王は静かに頷いた。
「ではこれからは私たちは共犯者だ」
獣じみた雰囲気を纏った王は、もうそれを隠そうともせずファラミアに言った。
「そう、私たちは共犯者だ…」
ボロミアを愛し、穢し、犯して愛おしむ共犯者。
知ってしまったからには、昨日までの弟という位置に甘んじることはできない。
自分は兄を、あの敬愛する兄を犯す男でいたいのだ。
ファラミアの中には、兄の辛そうな泣き顔を思い出して熱くなる倒錯的な欲望だけがあった。
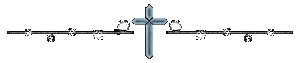
春が来たので予定どおりアップです。ファラミア参戦〜〜〜(笑)
今更ボロミアかわいそうなんて言う読者はここにはいませんよね?
これからいったいどうなっていくのやら(ていうか続くのか…!?)
さくら瑞樹著
− 戻る時はブラウザでお戻りください −