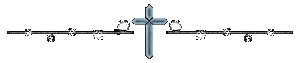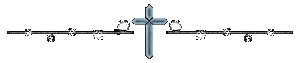夜のしじまに落ちて
世界は新たな王を迎えて、時代は春を謳歌していた。
ゴンドールでは、先の戦で壊れた建設物や道路、農地の復興に余念がなく、新王政は次々に持ち込まれる様々な懸案事項について、難易を問わず即座に検討し、新王の下、穏やかな治安と秩序を維持していた。
王は、言わずと知れた流浪の王で、しかし長年の経験と資質を活かして政権に従事するこの王を、人々は口々に称え、城内で彼に傾倒しない者は一人としていなかった。
ただ一人、彼の傍に仕える執政官を除いては…。
「ボロミア…」
真夜中。
自室に引き下がったボロミアの許を、毎夜訪れる黒い影がある。
スラリとした長身を豪奢な衣で包んだ姿を、蜀台の明かりが照らし出す前より、ボロミアはそれが誰かわかっていた。
ゴンドール国王、アラゴルンだ。
自分のベッドの中で物思いに耽っていた若い執政官を見越したかのように、王はその耳元に唇を寄せて目を眇めながら言った。
「ボロミア、もうお休みか?」
優しげな声音。そしてそれとは裏腹に、射るような、怜悧な視線。
──たったのそれだけでボロミアの意識は覚醒し、疲れの取れない身体がぴくん、と跳ねて微かな反応を示す。
「どうもまだ眠れそうになくてな…。よければ少し付き合ってほしいのだが」
昏い気配を漂わせ、今夜も王はボロミアに迫った。
ボロミア以外誰も知らない薄暗闇の中、獰猛な獣はその本性を現す。
──夜が深まるにつれて馨り立つ、自分の中の濃厚な雄の匂いに酔いしれながら。
「…めてください……っ…」
「そうではなかろう? この雨の匂いや風の音。貴方だって眠れないはずだ…」
掠れた声に、獣の唸り声が重なる。
全てを見越した上での、確信犯的な物言い。
言い訳するのも馬鹿馬鹿しいぐらいに的を射ているだけに、その言葉に捕らわれたまま動けない。
ボロミアは、全ての意味でこの新しい王の奴隷だった。
王は、日中の甘い飴と夜毎の手酷い鞭を使い分け、ボロミアを己の性に奉仕させる。
最初は、お互いに失ったものを補うような感覚だった。
ボロミアは、一度生を奪われたことから夜毎見る悪夢を追い払うため。そして王は、そんなボロミアを再び失わないことを確認するための。
しかし、いつの頃からか、この行為は王の中で獣性を増し、ボロミアはそれに引きずられるように肉体を作り変えられていた。
本気で抗っているのに、心底嫌だと思っているのに。
…結局最後にはその喉元を、柔らかな腹部を、飢えた獣に晒しているのだ。
「ほら、いつものように素直になるがいい」
長い指がボロミアの頬を優しく撫で、ぎゅっと噛み締められた唇をからかうようになぞる。
ズボンを下着ごとボロミアに下させると、王は有無を言わさずに弾け出てきた強張りをぽってりと厚い唇へと押し込んだ。
それからギシギシとベッドを軋ませながら、ボロミアの喉奥めがけて緩慢に腰を突く。
呼吸もままならなくなるような王のその動きに、ボロミアは涙を零して耐えていた。
激しい嘔吐感に喉が狭まる所を、否応無しに猛ったそれに犯され嬲られる、この感覚──。
「うぐぅ……んッ……んふっ……」
柔らかいボロミアの髪を撫でるように見せかけながら、実はそこから逃れられないよう戒めている王の手。
形良い唇から一定の間隔でズルズルと自分のが見え隠れする様を、楽しげに見つめている。
ぬくもった唾液に塗れ、てらてらといかがわしげに光っている自分の「そこ」。
時折甘えた子犬のように鼻を鳴らす仕種。
息苦しさゆえか、咥えしゃぶりながら縋る視線を投げかけてくる、潤んだ瞳。愛しい者を最も酷く犯す悦び。
そんな媚態に刺激されて、王の下腹には次第に重い射精感が込み上げてくる。
「もう、結構だ。だが本当にしゃぶるの上手くなった。…なぁ、ボロミア?…」
含ませた時と同じに、脚の間から強引に顔を上げさせた王は、潤んだ瞳をしたボロミアを覗き込んだ。
「──我慢できないのなら、もう乗ってもかまわないぞ。今夜だけは特別に…」
手酷い王の言葉の後、ただもうどうしようもなくて、ボロミアは自らの着衣を脱ぎ始めた。
月明かりだけの室内に浮かび上がる、ボロミアの硬く締まった健康な肌。
だがそれは、夜毎王に愛され続け、匂い立つような色香を纏っていた。
「ほら……早く」
緩慢な動作でベッドを這うと、ボロミアは王の顔を跨いでおずおずと腰を落としてゆく。
羞恥に頬を染め、洩れてしまいそうな声を殺して、その恥部を余すところなく晒した。
「今日もよく我慢できた……。とは言え、やはりもう、こんな小さなものでは物足りないか…」
割り開いた下肢の中心、そこにボロミアの快楽と羞恥の源があった。
「次からもっと、大きいのに替えてあげようか?」
「……っ、王……アラゴルン…早く…出…して…」
「おや?……出してもいいのか?…それとももう、イってしまいそう……?」
王はボロミアの震える声に含み笑いながら、桜色の内股をそっと撫で上げた。
目線をその奥にやれば、甘く熟れた秘肛から細い紐が垂れて白い太腿に括りつけられている。
「もっ………早く、外……して…っ…」
王の吐く息を敏感な場所で感じ、拡げられた内股が震え始めた。
ベッドヘッドの柵に縋りつき、露になった脚の間を舐めるような王の視姦に耐えている。
けれど贄となった身体はそんな場面でも悦び、堪えきれぬとばかりに後穴をひくつかせていた。
「強がってはいるが、前からも涎が垂れているぞ……私にこうやって見られて…感じてるのだろう?」
小指大の張り型を奥の奥まで押し込められた状態で日中をやり過ごすのが、ここ最近のボロミアに科せられた勤めだった。
前立腺の付近では終始射精しっぱなしの状態になってしまうため、わざと限界まで奥に押し入れられた玩具。
引き出すための紐さえあるこの淫猥な玩具は、大きはさほどないものの、ボロミアの意識を散漫にさせるのには充分な刺激を生み出す。
執務室で誰にも会わずにいられるならまだしも、今日のように弟のファラミアが尋ねて来るときはそうもいかず、ボロミアは極限まで忍耐を強いられる。
所構わず一日中陰部を掻き乱すこの性具の所為で、ボロミアは日に何度も下帯を替えなければならなかった。
そして今も、身体の奥にそれを埋められたままのボロミアの脚の間はあさましく勃起して、先端をとろとろに濡らしていた。
「違っ…ぅ…んッ……ぁ、ふぅっ……」
下肢の付け根を両方の手でさわさわと刺激され、とうとうボロミアの唇から甘い嬌声が零れ出た。
そして王の目の前で、紐を食い締めるようにしてそこがきつく絞られた。
「うむ…いい眺めだ。……だがもう少し楽しませてくれ、我が執政官殿」
そう言って淫猥に舌舐め擦りをした後、羞恥で慄くそこに、王はおもむろに己の舌を這わせた。
「ひ…っ!……やめ…っ…、やめ…あ……っ…」
己の恥部を息が触れるような近さで直視される羞恥。
そして、蛇の生殺しのようなぬるい刺激ばかりで疼き続けていた場所に突如加えられた、蕩けるほどに激しい刺激。
極まりを求め続けている身体にとっては、そのどれもが残酷なまでの甘い喜悦にしかならない。
「ん、…っ……アラ…ゴルン、……あ、ひぁ…ッ…」
入り口を執拗に舐め嬲られて、手のひらがまろい臀部を揉みしだくと、一層淫らに腰が揺れ踊る。
速いピッチで収縮を繰り返して喘ぐそこを抉じ開け、今度は先端を尖らせた舌が熱く練れた中に押し入ってきた。
ぴちゃっ………っちゅ……ぴちゃ………
「ひ、ひぁっ、あああ……ッ…!」
長時間に渡って玩具に嬲られていた粘膜は、ボロミアの心を容易く裏切った。
柔らかく解れた後穴を犯す舌に悶え、絡みつくように締めつけながらその甘い刺激を尚も深くまで貪ろうとしている。
欲しがり続ける熟れた場所をぬめぬめと舐め上げられ、蕩け出しそうな快楽がたちまち沸騰する。
「…アラゴ…ル…も…っ…あ、はぁああ…っ!」
太い舌に縦横自在に犯されて、快楽の蜜を啜り上げられる。
責め続けられる秘肛の感覚に、ボロミアの中心も弾けてしまいそうなくらいに反りを強めた。
「ボロミア……もう、前も…後ろも……とろとろじゃないか…ん?…このままイケるんだろう? そなたは後ろのお口の方が気持ちいいみたいだからな」
そんな王の卑猥な言葉に、ボロミアは必死に頭を振リ続ける。
「い、いや…だ、…それだけは……ッ」
後ろだけでイクことを強制する王に、最後の理性が抵抗する。
「…うそを言うな。そんなわがままを言うとおしおきしなければならんぞ?」
「あ……っ……ん…ぁ…」
王はとろとろに蕩けたそこに、ぴっしりと揃えた2本の指を、ぬぶぬぶと音を立てながら出し入れし始めた。
張り詰めた前にはけっして触れず、差し込んだ指を開き、その間に自らの長い舌入れてたっぷりとあやしてやる。
「ん、あぁあぁ……ひッ!……ぃ、んぅ……あッ…あぁッ…」
熟れた柔肉を節くれだった長い指で存分に擦り上げられるという心地好さ。
さらに、過敏な粘膜を長く太い舌で嬲られる悦楽。
ボロミアは、身体の芯から蕩け出しそうな快感にほとほと酩酊していた。
濃厚な王の性技。おそらく、野を流離う長い月日が彼に教え込んだであろう技は、それまで貴族特有の上品で淡白な行為しか知らなかったボロミアに、悪い毒のような濃密な性交を教え込んだ。
昂ぶり切った身体に加えられる濃密な愛撫と、被虐の性を擽る手酷い言葉の数々。
王は、元から過敏なボロミアの性感を巧みに操って、己の好みに勝手に染め上げたのだ。
初めての時から、ボロミアはおぞましさに竦み上がるそこを猛らせては、必ず秘肛に指を咥えさせたままで無理やり射精に導かれた。
時に自分の指を深々と挿し込んだまま、吐精の悦びに一人悶え泣いたこともある。
ボロミアの性は、王によって、最早前への直接の刺激だけでは物足りない、貪欲なものに作り変えられていたのだ。
「…あ……っ……ひ、あぁ……ッ…!」
煽られ続けた性感が今にも弾けそうで、今のボロミアが洩らす言葉に意味のあるものなどない。
ただひたすら絶頂を欲して腰を揺すり、咥え込んだ王のなめずる舌と指を締め上げるだけの性奴と化している。
「ボロミア…ここがイイのだろう?」
ぬる…っとその後口から口を放した王は、深く挿入した指先で探り当てた性具をそのまま器用に摘んで弄び始めた。
勿論、ボロミアがその刺激で達してしまわないように加減しながら、ボロミアの感じる処ばかりを攻める。
内部の激しい振動を無理やり意識させられる攻めに、ボロミアの膝は今にも崩れそうだ。
「あ…っ…、ん、ぅ……あッ…ん…」
身体の中心を走り抜けていく絶頂に近しい喜悦に、ボロミアはがくがくと首を振るだけで何も答えられない。
「…って、もう聞こえてはいない、か……」
王はそう苦笑しつつも先走りを垂らし続ける亀頭を初めて口内に含み、後穴を攻める指を増やした。
鋭過ぎる刺激に思わず逃げを打った腰を引き寄せ、前も後ろも音を立てて嬲り続ける。
「ひ…、ア…ラゴル…や……ああああー……ッ!」
激しく胴震いをしながら、ボロミアが至福の笑みを浮かべて絶頂を迎えようとしたその時。
「おっと、おしおきだと言っただろう?」
突然、亀頭の窪みを抑えられ、熱い欲望が無理やり塞き止められた。
「イイ子だから、出さずにイってごらん?」
口調はやさしく、しかし王は恐ろしいことを言う。
「そ、そん…なっ」
いやだと必死に頭を振るが、許してもらえないことはわかっていた。言い出したことは必ずヤラせる男なのだ。
窪みから塞いでいた親指が外れると、すぐさま細い紙縒りのようなものが差し込まれる。
「あ、あぁっ、はああ―――……っ!!」
尿道をわざとゆっくりと犯されて、下腹部が耐えられずに痙攣した。ひくひくと蜜を漏らして悶える果実。花芯深く紙縒りを何度も出し入れされて、ボロミアはその度に擬似射精の絶頂を味わされ身悶えた。
喉をそらして痙攣するような絶頂感を味わうたびに、花筒の奥に含んだ異物を無意識に締め上げさらに狂うことになる。
「や、やぁああ…っ!」
もう勘弁してくれと羞恥心をかなぐり捨てて懇願するボロミアに、王は細くそ笑んでさらなる追い討ちをかけた。
「ほら、そなたの下のお口がキスをねだっているぞ」
かわいらしいな と言って、王は深く舌を差し込んでディープキスをするように熱く潤んだ花筒を探った。まるで応えるようにヒクついて締め上げ、さらに奥に引き込もうとする動きに、太い舌先がゆっくりと入り込んでいく。
ズルズルと狭い花筒の中を太い舌が這いずると、ボロミアは無意識のうちに腰を淫らにうねらせた。
「ひ、ひぃぃ・・・んっ! あ、ああ…っ」
集中的に蕾の奥の快楽の泉を嬲られる。同時に紙縒りを差し込まれた花芯の内側からも同じ泉を攻められて、ボロミアは頭が一瞬真っ白になった。
「―――イッッ……グッ…ンンンンンン―――ッ!」
それは想像を絶する苦痛と快楽だった。
「ん…ちゃんと今日も、言いつけ守っていたようだな。……さすがは真面目な執政官殿だ」
限りなく無臭に近いような精液の濃さと多さに、王はボロミアが自分の言いつけを遵守していた事を知る。
ひとまずご褒美の代わりに、深い絶頂の余韻に耽るボロミアの内股の肉に甘く噛みついた。
「っ…あ……」
思わず自分が洩らした声の濡れ具合に、僅かに戻ったボロミアの理性は叩きのめされる。
一日の内に何度も下帯を履き替えなければならない程に身体を熱くさせながら、ボロミアは射精する事を許されていなかった。
並大抵の理性では押さえられない、原始の熱い衝動。
それを堪える理由は、ただ一つ。
己の王、アラゴルンにあった。
隷属という言葉が相応しいまでに、王に陥れられたボロミアだった。
普段のプライドの欠片も残らぬほどの恥辱の果てに待つ、王との激しい性交。
ボロミアの身体はほんの短い間に、すっかり骨抜きにされていた。
穏やかな顔つきにおおよそ似つかわしくない老獪なテクニックと、強靭な体力。
鋭い爪と牙を巧みに操り、時に隠しながら、甘く激しくボロミアを翻弄する王の獣性。
ボロミアという清かな蕾は、王を待ち侘びて濡れそぼるほどに淫らに花開いていた。
「あ……っ…、は…ぁッ…」
絶頂の余韻にざわめく柔肉の隙間を縫って、ようやく玩具が引き出される。
単に引き出されるだけだが、過敏な粘膜を刺激されるのには何の変わりもなく、ボロミアのそこは再びあさましく喘ぎ始めた。
「ほらほら、執政官殿。…そんなに締めつけては出せないではないか」
未だ忘我の淵にいるボロミアは、無意識のうちに後穴から抜け出ようとする悪しき性具を締め付けていた。
淫猥な蠕動を呼び起こしながら、奥へ奥へと飲み込もうとしているかのように。
「ボロミア、欲しいのだろう?私が……ん?」
好色な光を帯びて艶めく瞳がボロミアを見つめる。
答えない相手に王は、そのまま秘肛に指先を突き入れると狭まるそこを強引に開かせ、紐を引っ張りつつ性具を吐き出させた。
「もう、こんな時にまで手間掛けさせて。…ほら、ボロミア。貴方の弟君が、あそこで見ておられるのだからちゃんとなさい」
「………っ!」
促されて視線をやった先に、いるはずのないファラミアの姿を認めて、ボロミアは一気に全身を羞恥に焼かれた。
部屋の隅、蜀台の火がようやく届くところに、彼の弟は立っていた。いつからそこに居たのかそれさえ気づかないほど乱れていた自分を、ボロミアは激しく呪ったがもう遅い。
「兄上…」
だが、自分を恥じる兄をよそに、弟ファラミアは王と同じ欲望に濡れた瞳でボロミアを捉えていた。
「さぁボロミア……?」
王は、固まって動けないボロミアを抱え起こすと、ファラミアに見せつけるように脚を開かせた。そのままゆっくりと腰を持ち上げ、少しずつ落としながら熟れた入り口に先端を擦りつける。
「……っ…あ………」
強張りが触れた瞬間の甘い刺激に秘肛は緩み、くぷっ、と一気に先端を飲み込んでしまった。
「─どうだ? 美味いか?」
日頃は忠実な執政官であり兄であるボロミアの壮絶な媚態──というよりは、"痴態"。
心とは裏腹に、王の剛直を蕩けるような表情で迎えようとしているこの瞬間も、その一幕にすぎない。
王の欲望を咥え込んだ白い下肢は、その全てをファラミアの視線に晒すように割り広げられていた。
「っ……あ…イヤ…っ…ファ…ミア…見ないで…はぁあっ……」
半開きの唇の端からは唾液がとめどなく零れ、白い喉笛に何本もの筋をつくった。
凄まじいまでの充溢感。
熟れた柔肉に触れる熱い脈動。
屹立した熱の杭を咥え込み悦んでいる、淫らな自分を余すところなく晒す恥辱。
そして、それを実の弟の目の前であげつらわれるという羞恥。
「イイのだろう? ほら、前もこんなに喜んでいる。さっきイッたばかりだというのに。はしたない執政官殿だ」
「嫌…だっ……言わないでぇ…っ…!」
恥ずかしさに身を捩れば、力強い腕に縫いとめられ、ますますボロミアの悦楽を抉った。
「は…あああっ……と、とけ…る……っ」
「では、そなたの弟君にもこの甘い蜜を味わっていただかねばな」
一瞬、何を言われたかわからないボロミアのすぐ目の前に、ファラミアの顔があった。
「ファラミア…なにを……っ!」
うろたえるボロミアをよそに、王に促されたファラミアは、ゆっくりと顔を沈めると、王の剛直を咥え込んで悦びの涙を流すボロミアをそっと口に含んだ。
挿入した瞬間から先走りを滴らせるほどに勃起していたそれが、弟の口腔でびくびくと震える。
「…いっ…いやぁあああっ、ファラミ…ア…ッ!」
弟の口中でいきり立つものを緩くキツク吸われ、ときに甘噛みされ、堪らない刺激がボロミアを襲う。
男の最大の弱みであるそこを嬲られる快感は、弟にされる羞恥と相まって、瞬時にしてボロミアを追い詰めた。
それを堪えるためにきつく秘肛が引き絞られ、咥え込んだものを締めつける結果となって、ボロミアの快楽は一気に深まっていく。
「実の弟君に愛される感覚はどうだ? ん? ボロミア?……ヨくってヨくってたまらないようだな」
言葉と共に、王がゆっくりと律動を開始した。
それを待っていたように、ファラミアが咥え込んだ兄の欲望をさらに攻め始める。
後を犯されながら前を弄られ、ボロミアの弱みは今や二人に容赦なくよって貪られていた。
甘く熟れた後穴の中を擦り上げる王のそれ。ときに蕩けた秘所にまで舌を這わせて兄の悦楽を貪るファラミアに、ボロミアはいつしか我を忘れてすすり泣いていた。
生も死も、悦楽さえも支配される。
己の全てを捧げてこの王に使える悦びだけが支配する世界。
それが今のボロミアの全てだった。
「ボロミア…我が愛しい執政官よ。忘れるな。そなたはこのアラゴルンのためだけにあるのだ」
耳元に何度も囁かれる言葉に洗脳されて、揺さぶられるままにガクガクと頷く。
もう、この関係がどんなに歪んでいようがかまわない。
王の執着が尋常でないというのなら、王に殉じる自分もまたそうなのだろう。
今はただ、快楽という王の鎖に縛られて、落ちるところまで落ちてしまいたい。
深く潜り込んだ王の楔が、心地好く絡みついてくる柔肉の感触に先走りを滴らせ、ボロミアの中で硬度と反りを強めて猛ってゆく。
「……もっと……あ、ああっ…アラゴルン………っ!」
身の内深くで王を締め上げながら、ボロミアは堪えきれずに己の腰を揺すった。
己の動きでも最奥に届くが、そんな弱い刺激ではもう足りないのだ。
弓形に反り返った王のそれで、思うが侭に奥の奥まで擦り上げられたい。
いっそ舌の根が痺れる程、壊れるまで突き上げられたい。
そして、蕩けきった最奥を王の精液でぐちょぐちょに濡らして欲しい…。
「アラゴルン………ッ──」
花筒奥深くに王の迸りを受けると同時に、弟の口腔に放っていた。
最後の蜜まですすり上げようと蠢く口中に、白い内股が痙攣する。
荒い息も整わないうちに身体を返されたボロミアは、潤った秘所を指で開かれて、遠くなる意識を引き戻された。
「今度は、弟君に犯される悦びを教えてさしあげよう」
夜は、まだ闇の底深くボロミアを呑込んだまま、いまだ明ける気配はなかった。
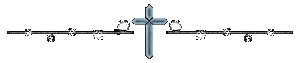
初書きアラボロでこの内容…。
我ながら病は重いと実感してます。
ボロミアは可愛いから、よけいに苛めてしまうのです。
世のボロミア好きならわかってくれますよね、ね?
さくら瑞樹著
− 戻る時はブラウザを閉じてください −