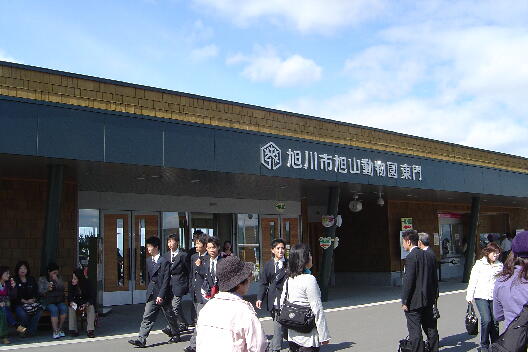�k�C���i�m���E�����E�x�ǖ�E������ʁj�̗�
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�o�@�ʐ^�͂��ׂĎ����B�e�����v���C�x�[�g�ʐ^�ł��@�p�@�@�@�@�@�͖�@�P��
�y�X�P�W���[���z
�H�c�i�P�O�F�O�T���j�@JAL1187�ց@���@�����ʁi�P�P�F�T�O���j
�����ʋ�`�i���j�@���@�������u�����@���@�ԑ��@���@�����������ԉ��@���@�Η��@���@�I�V���R�V���̑�@���@���̟�シ���
�@���@�m���܌@���m���E�E�g���i���j
�y��Q���ځz
�m���E�E�g���i���j�@���@�m�����i�C���r��đD�����q�E���~�j�@���@�t���y�̑�@���@�@�m�����R�Z���^�[�@���@�m�����f���H�@
���@
�m�����@���@�W�ÃT�[�����p�[�N�@���@�����@���@�����R�@���@�����i���j
�y��R����z
�����i���j�@���@�I���l�g�[�@����@���@�m�y�@���@�T�z�����]�[�g�@���@�돟���@���@�㓡���j���p�ف@���@�x�ǖ�i���j
�y��S����z
�x�ǖ�i���j�@���@�v�����@���X�̓��@���@���l�ό��i��^�فE�l�G�ʂ̋u�E�j�@���@�p�b�`���[�N�̘H�i�P���ƃ����[�̖E
�Z�u���X�^�[�̖E�e�q�̖j�@���@���R�������@���@�����`�@
����i�P�V�F�P�O���j�@JAL1112�ց@���@�H�c�i�P�W�F�T�O���j

�y�����L�@��P���z�@�@�X���Q�R��
�@�����ʋ�`������߂��������u�����ɍs�����B�@�W�]��ɓo��ƂR�U�O�x�J�������]�͂������k�C���E�ł������ǂ��ɗ����ƌ���
�����𖡂�
�@���܂��B�@�G�߂��I�����Ђ܂�肪�A����̗Έ�F�̑����̋u�����F�ɐ��߂ĐS��a�܂��Ă���܂��B�@����ɁA�n�}�i�X�̐Ԃ�
��������
�@�ԂƋ��Ɍ}���Ă���āA�k�̑�n�̗��̎n�܂�������Ă����̂ł��B�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����ʋ�`�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Ђ܂��̔�
 �@
�@
�@�ԑ�����m���Η��܂ł̓��͍��ɃI�z�[�c�N�C�A�E�ɟ����i�g�[�t�c�j�̊Ԃ�ʂ鍑���Q�S�S�����ŁAJR���Ԑ������s���ĊC��
���𑖂��Ă��܂��B
���̃��[�J�����̖k�l�w�͉f��u�S�����@�ۂ��ۂ�v�̃��P�Ɏg��ꂽ�w�ō����l�C�̊ό��X�|�b�g�ɂȂ��Ă��܂��B�@�u�S�����@
�ۂ��ۂ�v�͍���
�{���̊��Љw�i�����Ƃ炦���j��y���w�Ƃ��Ď�ɓ�x�ǖ쒬�Ń��P���ꂽ���̂ŁA��l���̍��q�� �A�Ȃ̑�|���̂� �A�L�����q
�炪�o�������b��
��ł��B�@����JR���Ԑ��œy�A���A�j��DMV�i�f���A���E���[�h�E�r�[�N���j�Ƃ����A�����ɃS���^�C���ƓS�̎ԗւ����āA���H
�Ɠ��H�̗�����
�s�ł���o�X�̂悤�ȏ�蕨�̎����I�c�ƒ��ł��B�@����P�T���A�d�Ԃ̉^�]��ƃo�X�̉^�]��A����Ɏԏ������̂ŏ�q�����
�P�Q���ł��B
�@���{�̑�P���͐É����x�m�s�̊x��S���ŁA�Q�O�O�U�N�P�P������JR�k�C���̋Z�p���͂̂��Ƃő����Ă��邻���ł��B�@JR���Ԑ�
�ɂ̓m���b�R����
�����T���Ґ��ŁA�ԑ��`�m���Η��Ԃ𗬕X�����Ȃ���ꎞ�Ԃ����đ���d�Ԃ�����~�͑�D�]�������ł��B
�@���̉ʂĂ��Ȃ��L���I�z�[�c�N�ɗ��X�������܂��B�@���X�������Ɍ��������𗬕X�����ƌ����A��P�T�Ԃ���P�O���Őڊ݂�
������ڊݏ�����
�����܂��B���̓�����C�͑�ጴ�ɕς��D�������Ȃ��Ȃ�ƌ������玩�R�͑z�����z�������E�ł��B
�@���̃I�z�[�c�N�C�ɖʂ����C�݂̍��l�ɂ́A�Tm�Ԋu���炢�ɍ��������������낦��ꂽ�ފƂ�����ł��܂����B�@����ނ��Ă�
��Ƃ̂��Ƃł���
���A�Ƃ̕��тɐ�߂��Ȃ��A���L�����������܂͑z���O�ł����B�@�����͖����ō����ނ��̂������ł��B
�@�����i�g�[�t�c�j�͐��[�Q�D�T���A���͂Q�V�����̋D���ŁA���������ɖ�W�����̍ג��������ł��B���a�R�R�N�ɖԑ������
���Ɏw�肳��A
�Q�O�O�T�N�����T�[�����̓o�^���n�ƂȂ������ł��B�����ƌ̊Ԃ͏����������ԉ��ƌ����A���{�Ŏn�߂Č����ԉ��Ɏw�肳�ꂽ
�ꏊ�������ł��B
���ĂɃN�������A�Z���_�C�n�M�A�q�I�E�M�A�����Ȃǂ��炫�n�߁A�Ăɂ̓G�]�X�J�V�����A�G�]�L�X�Q�A���F�Ƃ�ǂ�̓V�R�̂���
����A�~����
��Δ����T�O�O�O�H�ȂǓn�蒹���Ζʂߐs�����Ƃ��낾�����ł��B�@�Ȃ��A�E���̎����ɍ炭�u�Ђ���������߁v�͏H�{�I�q
�l�̌��ŁA����
�̓y��ɍ炭�u�͂܂Ȃ��v�͍c���q�܉�q�l�̌��ł��B�@�P�����ōc���܂̌��������鏊�͂ق��ɂȂ��ł��傤�B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�k�l�w�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ԑ��`�m���Q�S�S����
�@ �@
�@
�@�m�����������̌����A�m���E�Η����͐l���P�R�C�O�O�O�l�̏����Ȓ��ł��B�@�Η������班���m�������ɐi�ނƉ����ʁi�I���l
�x�c�j�삪�����
���B���̐�ɂ͎Y���̂��߂ɐ��܂ꂽ��ɖ߂��Ă���ƌ�������}�X���A�Q��𐬂��ďd�Ȃ荇���悤�ɟ�㒆�ł����B�S�g���t��
����Ɖj���ł���
�������邵�A���łɎ��̂ƂȂ��Đ�݂ɗ��ꒅ���������P�O�O�����炢�͋��܂����B�ł̓J���������ɂ��������̔���{�ŋ���
�ň����グ�悤��
���A�������Ă�����i���ς��܂����B�@�m�������ɂ͂X�Q�{�̐삪����A��Q�C�O�O�O�����̍������N�A���Ă���̂�������
���B
�@�I�V���R�V���̑�͈ȑO�͓��H����̏㑤�ɂ������̂ŁA�����낷�悤�ȑꂾ���������ł����A���͐������藎����̂���������
�ς��ɂȂ��Ă�
�܂��B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Q��𐬂��ğ�シ����@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�I�V���R�V���̑�
 �@�@
�@�@
�@���E���R��Y�ɓo�^���ꂽ�m���̓A�C�k��̃V���G�g�N�i�n�̉ʂāj����t����ꂽ���O�ł��B���̔����ɂ̓G�]�V�J�Q�����A�F
�P�T�O�`�Q
�O�O�����Z��ł���A�L�^�L�c�l�A�G�]�V�}�t�N���E�A�Ȃǂ������Z��ł��܂��B�����̓G�]�}�c�A�g�h�}�c�A�_�P�J���o�Ȃǂ̌�
���тŕ���
��Ă���A�����̒��ԓ_���炢�܂ł͓������邪�A��͗��H���s���ꍇ�ɂ͎R�ɕ������邵���L��܂���B���������āA�m�����܂�
�͊C�H��D
�ōs�������Ȃ��̂ł����A���͒f�R�őD�𒅂���ꏊ���L��܂���B
�@���E��Y�ɂ͕�����Y�A���R��Y�A������Y������A���{�̕�����Y�͕P�H��E�@�����E�����E�����h�[���ȂǂP�P�ӏ����w�肳
��Ă��܂�
���A���R��Y�͉��v���E���_�R�n�E�m���̂R�ӏ��݂̂ł��B�Ȃ��A������Y�͓��{�ɂ͂���܂���B
�@�m���̎��R���c�����̂́A�i�V���i���g���X�g�^���̂��A�ł��B�@���̉^���̓C�M���X�Ō��^���o�����^���ŁA�M���̏��L���Ă�
������Ȃ�
���r�����ɂȂ����Ƃ��݂�Ȃ��������o�������ĕۑ��������̂��n�܂�ł��B�@�Η����̓��J�������u�P�O�O�u�^���v����A
�m���̌���
�Ɠ�������肽���ƌĂт����A����ɓ����ĕ���͌��݂S�W�C�O�O�O���i�m�����R�Z���^�[�ɑS���̖��D���˂����Ă���j������
���Ă��܂��B
�@����W�C�O�O�O�~�ł��B��ԍŏ��̉���҂͐V�����s�̓�l�ŁA���������͈ꐶ�y�n�͎��ĂȂ������m��Ȃ����ǁA�����̋L�O��
�Ɖ��傳��
�������ł��B�@���w�Z�T�N���̃N���X�ł��̉^����m�����q���������A�y�n���Ă��s���Č��邱�Ƃ͂Ȃ����낤���ǂƁA���R��
���^����
�^�����Ă�������������t���Ă���܂����B�@�����������J�������S���ɋL�O�̃o�b�`�𑗂����Ƃ���A�q�������͂������o�b�`
��ɏ�����
���܂����ƌ����Ă܂��A�W�C�O�O�O�~���W�߁u�����o�b�`�͂���܂���v�Ǝ莆�����đ����������ł��B�@�@�@�@�@�@�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�摜���N���b�N����Α傫���摜�ɂȂ�܂�
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�m���܌̈ē��Ł@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��ɉf�闅�P�x�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�쐶�̗Y������������
�@�m���܌��i�N���b�N����Ύʐ^������܂��j�͔����̂�⒆�S���ɂ���A�V��������������Ă��܂����S�����ƂX�O���|�����
���B���Y��
�Ȑ��X�Ƃ����A�Â��Ȍΐ��ł��B���̓N�}�T�T�ɕ����A����L�c�l���l�Ԃ�������Ȃ��ł̂�т�Ɛ������Ă��܂��B�@�F��
�o������
���͓��R�֎~�ł����A���X�ŌF�����̃x�����݂��o�����Ă��܂����B�@���E���R��Y��悩��͓��������łȂ��A���A�ԁA��
�̈����
���o���͋֎~�ł��B�@�r���̐�ɌF���o�č�������Ă���Ƃ̏��ŃJ�����}���������Y�������Ă��܂������A�������͌��邱�Ƃ�
�o���܂���
�ł����B
�@�E�g���͉F�o�C�Ə����A�A�C�k��̃E�g�D���`�N�V����t����ꂽ�����ł��B�m���ό��D�̏��ꂪ���艷��X������܂��B�m��
��������
���P���Ƌ��ɒm���ό��̋��_�ƂȂ�ꏊ�ł����A���~���ɂ͗��X��������X�ł��B
�@�[���Ɋς��m���̓��v�͎�̂����i�ł����B�@�h�̗����������ł��i��ŖуK�j�ȂǏo�Ă��܂����j�B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�m���E�E�g���`�̗[���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�h�̗���
 �@
�@
�y�����L�@��Q���z�@�@�X���Q�S��
�@���H�ɂ͓����Ȃ��m���������@�ό��D�ŊC���猩������\��ł������A�C���r��Č��q�̂��ߎc�O�Ȃ��璆�~���܂����B�@�����E
�g��������ł�
�G�]�V�J���W���ɐi�o���A�_�Y����H���r�炵����A���H��яo���ɂ���ʎ��̂����������̂ŁA�W�����ׂĂ��t�F���X�ň͂ނ�
�Ƃ�2006�N�Ɍ�
�肵�܂����B�t�F���X�͍���3m�ł��̋�����3628m�ɂ����������ł��B
�@�m�����R�Z���^�[�ɍs���܂����B�m���̃i�V���i���g���X�g�^���ɋ��^���A��t�������l�S�W�C�O�O�O�l�̖��D�����ʂɐ�������
�Ă��܂����B�@
�@�ĂуE�g���ɋA���Ēm�������z�����P�ɍs���܂����B�V���G�g�N�i�������ɑ�n�Ȃ��j�ƌ���ꂽ�m���̗��P�x�̐����o��
���͕��̒ʂ蓹
�ŁA�P�N�̑唼�͖��ɕ�����ƌ����A�g�h�}�c�A�_�P�J���o�Ȃǂ̎}�������ɂ͂Ȃ��A�����݂̂ɏ����c���Ă���l���݂ē~�̌�
������z������
�����B
�@�J���}�c���Y�z�̍B���p�ɑ�ʂɐA�т���܂������A���ł͒Y�z���Ȃ��H������̑�����p�C�v�ɕς�����̂ŁA�m���̕Ǘp�Ɏg
������x�ł��B
�����͂P�O�����{����͒ʍs�~�߂������ł��B�@�m������o�肫��Ɩڂ̑O�ɍ����C�����u�Ăč��㓇�������܂��B���㓇�͒�����
�P�Q�R��������A
���P����͂R�U�����������ł�����ԋ߂��Ƃ���͂P�U�����ŁA�{�y�Ԋ҂��ꂽ���ɂ͂��̓��Ƃ̊Ԃɋ����˂���v�������܂��B
�@���㓇�͍]�ˎ���ɏ��O�˂����Տ���u���A���Z���̃A�C�k���g���Č��Ղ��s�������ŁA�P�T�O�N�O�ɂ����I�a�e���œ��{�̗�
�L�ƌ��܂�����
�ł��B�I��̂P�T�Ԍ�ɓˑR���V�A�����N�U���A�Z�l�͑S�Ă̍��Y��u���ď��D�œ����Ă����̂ł��B�@�����ɋA�����Ǝv������
�ɂ����U�O�N��
��A���Ȃ��̂ł��B�@�𑨓��A�F�O���A���������݂͂ȓ����悤�ȉ^���ɂ���܂����A��ԋ߂��[���z�����琅�����܂ł͂R�D�V
�����ł��̊Ԃ�
�C�Ń��V�A�̑D�ɏe������\�߂���Ă���̂�����ł��B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�m�����b�ی��@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�������ɑя�Ɍ����铇�����㓇�B�P�Q�R��������ʐ^�̉E�[
����[
 �@
�@
�@�m�������������Ƃ��ɂ��鏬���Ȓ����l���U�C�S�O�O�l�̗��P���ł��B�����C�����u�ĂĖڂ̑O�ɍ��㓇�����鋙�ƂƊό��̒���
���B�����̗R
���́A�A�C�k��́u���E�V�v�i�Ⴂ�Ƃ���E�b�̍��̂���Ƃ���j�������ł��B
�@�q�{���r�{�̃t�W�e���r�h���}�u�k�̍�����v�̕���͕x�ǖ�s�ł����A���j�����Z�ԉ��Ƃ��ă��P�Ɏg��ꂽ�Ƃ��������P
���ɂ���܂��B
�̂͒m�������̋��͏H�̍������I���Ət�܂Ŕ��N�����Ȃ��A���H�ł͍s���Ȃ������̕l�ӂ̔ԉ��ƌ��������ŖԂN�ԕۊǂ���
�����B�l�Y�~
�ɖԂ���������̂�h�����߂ǂ̔ԉ����P�O�C�ȏ�̔L���������̂ł����A���̔L�ɉa����邽�߂����ɁA�ԉ��ɂ͔ԉ���i��
�����j�ƌ�
�ꂽ�j����l�œ~�̔��N�Ԃ������Ő������܂����B
�@�X�ɋv�킳��̉f��u�n�̊U�Ăɐ�������́v�̌���͌ː�K�v�́u�I�z�[�c�N�̘V�l�v�ł��B�@���̏����̂��炷���́A�Ɋ���
�n�ɐ��܂ꂽ
���c�F�s�������ł��L���Ȑ��������߂đ𑨂ɓn��܂��B�w�͂̍b�゠���đD�����ɐ���܂��B�e������u�D�����O�ɉł�����
���v�ƌ����
�F�s�͂��ƌ������܂��B�Ⴂ���t�̐��b������͉̂ł���̎d���Ȃ̂ł��B�F�s�͎O�l�̎q������Ă�̂ł������j��g�͋��ɏo
�ė��X�ɗ���
�Ď��ɁA���j�͏��W�ߏ��Đ�n�Ŏ��ɂ܂��B�A���Ă����̂͐��낪�����������̈⍜�ł����B�O�j�͌R���H��ɒ��p�����
���B�푈���I��
��\�A�����㗤���܂��B�E�C�̉\����сA���D�ŃE�g���ɓ����A��܂��B���̌�A������Ă������ɂ��o���Ȃ��F�s�ɔԉ��ŋ�
�߂Ȃ����Ƃ�
�b�����܂��B�ԉ��ł̋ꂵ�������̒��ōȂ��a�C�ɂȂ�A���̎�҂��˔ɏ悹�Đ�̓����z���Ē��܂ʼn^�ڂ��Ƃ��܂��B�������A
��҂܂ő���
�����Ă͂����Ȃ��Ǝv�����F�s�́A��҂Ɉ����Ԃ����Ď����ЂƂ�Ŕw�����ĕ�������̒��ōȂ͗₽���Ȃ�܂��B
�@����Ȓj�̐����l�������œǂX�ɂ��������A�f�扻�����̂͏��a35�N�̂��Ƃł��B2�����Ԃ̃��P�̕���͓��R���P�ł����B
���P���P�ł�
���܂�̉����̂��߃G�L�X�g�����Ăׂ��A ���P���̐l�X���吨�o�������̂ł��B ���̢�I�z�[�c�N�̑D�̣���X�ɂ��쎌��Ȃ���
�̂ł����A�ǂ�
���������肵�Ȃ��̂ł��B���P���I�������ɗ��P������������܂����B ���̕ʂ�̓��̑O��A�V�����̢�T���o���P�棂�����������
�ł��B �X�ɂ�
�������Ďi�t�q��J���q����Ɂ��ʂ�̓��͗����`�Ɖ̂��Č������Ƃ����܂��B�@�Ȍ�A�k�C���e�n�Ţ�T���o���P�棂͌��R
�~�I�ɉS���A
��P�O�N��ɐX�ɋv�킪�u�m������v�Ƃ��ēo�^�����̂ł��B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@���������̐������Ɣ[���z���͂R�D�V�����@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�u�k�̍�����v�́@���̔ԉ��Ƃ��ă��P�Ɏg��ꂽ��
 �@
�@
�@�W�ÃT�[�����p�[�N�ׂ̗ɁA�W�ÃT�[�����Ȋw���i�N���b�N����Ύʐ^������܂��j������܂��B���̉Ȋw�قɂ͍��E�}�X�̒��Ԃ�
���\��ނ�����
����Ă��܂����A�ǂ�������Ԃ̋��ŗL��Ƃ������Ƃ̂ق��͂悭������܂���ł����B�f������������܂��B
�@�W�Â��璆�W�ÁE��q���Ɛ��Ɍ��������͒����̓��H�������A���̗����͖w��ǂ��q���n�тł��B���P���ɂP�w�N�^�[���̖q���n
���K�v�Ȃ̂���
���ŁA�Ƃɂ����̑�n����ł��B�J���~�肻���ŋ��ɂɋ��������Ă���Ƃ��낪���������̂ŁA�q���n���肪�ڂɕt���܂�
���B�����q���͓~
�̉a�p�Ɋ������A���[����Ɋ����āA����𔒂����̃r�j�[���Ŋ����Ă���܂����B�������ɂɎ����A����̂��A�q���n�ɐ�
�R�ƕ��ׂĂ���
�Ă���܂��B
�@�@�@�@�@�@�@�@����Ɍ�������͐Ⴊ�ς����������H�̋��E����������́@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�̖q���n
 �@
�@
�@��q���̒����̗R���̓A�C�k��́u�e�V�J�E�K�v�i��Ղ̏�j�ŁA�~�ɂ̓_�C�������h�_�X�g��������Ɋ��̒n�ł��B���̂���
��ɂ͔_�ƌ�
�C���R�N���A�y�n�̓^�_�Œ������Ă����ƌ����ꏊ�����邻���ł����A�~�̐������v���Ƒ�ςȑ�n���Ǝv���܂��B�q��
�n�͓y�n�̋�
�E�̈Ӗ�����������̂��A�h���тƂ��ďc��������ɁA�Y��ɗт��c���Ă��܂��B�l�H�q���������Ղ̖ڂ̂悤�ɐ��R�Ƃ����A�i
�q��̋�悪
������Ƃ����܂��B�@���̒n�ɏ��D�̔�����b�q���Z��ł���Ƃ̂��Ƃł����B�@���c�S���E����������q������̂���
��̂悤�ł��B
��q��������̖q���n
 �@
�@
�@�����ɍs���r���ɖk�C���n�}�̂悤�Ȍ`������������܂����B���O�͕�����܂���B�@�����͈��������������ɂ���A��
7000�N�O�̉ΎR
���ɂ���ďo�����E�n�ɁA�������܂����J���f���ł��B���͂Q�O�����A�ő吅�[�Q�P�P���A�����ɒf�R�̏����J���C�V��������
��܂��B����
�E���o�̉͐삪�����̂ɔN�Ԃ�ʂ��Đ��ʂ̕ϓ������Ȃ��ƌ����Ă��܂������A�ߔN�̒����Ō̓쓌�W�L���ɂ��邳���܂��Z��
�^�[���ʎ���
���̂��ɗ��o���Ă��邱�Ƃ��������������ł��B�̎��͂͒f�R�������A�ΐ��ɂ͗�������֎~�Ƃ���Ă���̂ŌΖʂɂ͋߂Â�
�܂���B
�@�����͌ΐ��̓����x�������A���E�ꂫ�ꂢ���ƌ���ꂽ�o�C�J���̓����x�S�O��������S�P�D�T���ł����B�������A�ߔN��
�����ł͓���
�x�Q�O���ʂɗ����Ă��܂��B�}�X������������Ƃ�A�������ꂽ�W�����ɂ���ă~�W���R�������āA�A���v�����N�g��������������
�ł͂Ȃ�����
�����A�����͒������Ȃ̂������ł��B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�k�C���̒n�`�̂悤�ł���B���̌@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����@�@���ʂ́u�J���C�k�v���i�_�̎R�j�v�i�����x��W��
858m�j
 �@
�@
�@�����̂��ɂ��闰���R�́A���c�����̈��c�P���Y��1877�N���痰���̍̌@���J�n���A�A���̂��߂ɖk�C���œ�ԖڂƂȂ�S
���𗰉��R�`
�W���Ԃɕ~�݂��܂������A���@�ɂ�莑�����͊���9�N���1886�N�ɑ��Ƃ��~�����ꏊ�ł��B�����ΎR�̓����ɗ������܂܂�ċ�
��ȓ��������A
�߂��ɑ��͂܂����������Ă��܂���B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���H�ɔ�яo�����L�^�L�c�l�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����R
 �@
�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@���H�ɔ�s�@�̒����牽�C�Ȃ��ʂ����������̂悤�ł��B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����̃z�e���̗[�H
 �@
�@
�@�����͎��͂R�O�����A�ő吅�[�S�T���̒W���J���f���ł��B�̐��ʂɂ͕W���P�R�V�O���̗Y�����x������A��������������
�܂܂�܂��B
���ʓV�R�L�O���̃}�����͗L���ł��B�~�͑S�ʌ��X���A���J�T�M�ނ��A�X�P�[�g�A�X�m�[���[�r���Ȃǂ̃E�B���^�[�X�|�[�c����
��ł��B
�@�ΔȂ̉���X�̂��ɁA�k�C���ő�̃A�C�k�R�^���i�A�C�k�̏W���j������A�ː��R�U�ˁA��P�R�O�l�̃A�C�k�������ؒ����i��
�ǂ�̔�����
�y�Y���X������܂��B�A�C�k�̓`�����x���������鉉����́u�I���l�`�Z�v��A�`���������Љ�鎑���فi�A�C�k�����L�O�فA�X
�ƌ��Y�p�فj
������܂��B���|�X�̓X��ŃA�C�k�ߑ��̎h�J����D���ō���Ă��������ɕ����܂�����A�u����͋V���ɏU����������̂ŁA����
�܂łɖ�Q��
���Ԋ|����R�O���~�قǂ�����́v�������ł��B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�A�C�k�̓y�Y���X�E�W���Ɓu�I���l�`�Z�v�Î����x���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ߑ��̎h�J�����Ă��������B
 �@
�@
�A�C�k�Î����x�i���̏d�v���`�����������w��j
 �@
�@ �@
�@
�y�����L�@��R���z�@�@�X���Q�T��
�@�����̃z�e�����U���ɏo�q����ό��D�ɏ���ĉ���X�����Q�O���A�Ί݂̃`���E���C���ɂ���}�����W���ώ@�Z���^�[��
�s���ĂV���ɋA
���Ă��܂����B����30�N�A�D�y�_�w�Z�̊w������\�����A�����V�����R�}�x�c�p�Řa�l�ł͂��߂ă}���������A�a���u�}��
���i�{���j�v��
���݂ƍ̏W�L�^�\�����̂������ł��B�吳10�N �����̃}�����͍��̓V�R�L�O���Ɏw�肳��܂����B�@���a53�N�ɂ� �`���E��
�C���Ƀ}�����W
���ώ@�Z���^�[���ł��A���ʓV�R�L�O���̃}������W�����A�ی슈�������Ă���Ƃ���ł��B�}�����̓A�C�k��Ńg�E���T���y�ƌ�
���A�_�̌��
�i�݂��܁j�ƌ����Ӗ������邻���ł��B���a�U������������̂ɂP�T�O�N�|����ƌ����Ă��܂����B�@�ŋ߂ł� �͌���k�đ嗤
�ɂ��}����������
���Ă��邱�Ƃ��������Ă��邻���ł��B
 �@
�@ �@
�@
�@�I���l�g�[�ɍs���܂����B�I���l�g�[�͎��͂Q�D�T�����A���ϐ��[�R���̉ΎR�ɂ���ďo�����W���̉��~�ł��B�A�C�k��ł׃J
���x�i�̏��_�j
�ƌ����A�I�R�^���y�A���_�ƂƂ��ɖk�C���O���̈�Ƃ���Ă��܂��B�Ζʂ͍��X�ƐF��ς��邱�Ƃ���ܐF���̕ʖ���
����܂��B
�@ �@�@�@�@�@
�@�@�@�@�@
�@�k�C���ƌ����A�ΐ��ł��B�̐l�E���l�̑�͖{���͐ΐ��i�͂��߁j�ŁA�����P�X�N�Ɋ�茧�ɐ��܂�A���w����Ɂw��
���x��ǂ�ŗ^
�Ӗ쏻�q��̒Z�̂ɌX�|���A�w������x�ɒZ�̂\���܂��B�@���w�̎��ފw�ƂȂ�A���w�Őg�𗧂Ă錈�ӂ������ď㋞���^��
��v�Ȃ�q�˂�
�����B��Ƃ������O�͗^�Ӗ�S�����������Ƃ����Ă��܂��B�P�X�̂Ƃ��x���ߎq�ƌ������܂������e�Ɩ����}�{���A��Ƃ�
�n�R�̂ǂ���
�����B���ىw���̋`�Z��K�ˈ�Ƃ̋���ŊJ�𑊒k���܂����������ł��܂���ł����B�@�����̏a�����ɖ߂�A�a���q�퍂�����w�Z
�ɑ�p�����Ƃ�
�ċΖ����܂��B�g�̔���Œ����������Ə����ꏬ���������n�߂܂��B�Q�P�̂Ƃ��V�������J����ƍȎq���̎��ƂɎc���A����
�Ɉڂ��Ė퐶��
�w�Z�̑�p�����ƂȂ�܂��B�����ŕБz���̏����E�k�q�b�q�ƒm�荇���܂��B���������̕��Q�̗����n�܂�̂ł��B���ّ��
���蔟�ق𗣂�
�܂����A���ّ؍݂P�Q�O���قǂ̊ԂɁu���R�̍��ɕ����E�E�E�v�ȂǂR�Q������܂��B�@�D�y�Łw�k��V��x�ɓ��ЁA����ɏ�
�M�Ɉڂ�w���M
����x�̋L�҂ƂȂ�܂��������ɑގЂ��܂��B�Q�Q�̂P���ɂ͉Ƒ������M�Ɏc���A�����{������l���H�Ɍ������A���H�V���Ђɋ�
������̂ł���
�R���ɂ͑ގЂ��Ă��܂��B�����ɋA����c�ꋞ��̉����Ő������A�u���C�̏����c�v�u���͂ނ�ɕ��w���Ђāc�v�Ȃnj�ɒm��n
��̂��܂߁A246
������w�����x�ɔ��\�����̂ł��B
�@���i������낿�傤�j�͐l��8,3�O�O�l�A���̖ʐς�1,4�O�Okm2����A���쌧�قǂ̍L���̓��{��L���ʐς������ł��B��
����m�y�̊�
�̍Œ����������͖�P�P�������邻���ł��B���̗����͖w�ǂ��q���n�тŁA���q�̂ق��ɂ�A�W���K�C���A�g�E�����R�V�A�r�[
�g�i�����卪�j�A
�哤�A�����A�������A�X�C�J�Ȃǂ��͔|����Ă��܂��B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���̕��q�n�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�������n��A���Ŋ��������Ă���
 �@�@
�@�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���n��̍앨�Ŋ����i�W�߂ăr�j�[���V�[�g�������Ă���j�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�L��Ȕ_�n
 �@�@
�@�@
�@�\���ɂ���R�ʌi������ׂ��j�́A�W��810m�ɂ���A�k�C���̌ł͍ł��W���̍����ꏊ�ɂ���������ł��B�~�ɂ͑R��
�ΕX��R�^��
�܂肪�J�Â���A�C�O���[�i�X�̉Ɓj���ɍ��ꂽ�X��̘I�V���C���l�C�ł����A�Ăɂ͕X�������ł���ʂ��đ���u�X�̃W���b
�L�v�Ńr�[��
�����܂��Ă���邻���ł��B
�@���N�̍Œ�C����������߂ĂO�x����āA�y��������0.2�������������ł��B���x�ł͍�����������ƌ������Ƃł����B������
�͂܂��R�O����
�����Ă��܂����A���̂�����̍����̒��Ԃ̉��x�͂P�V���ʂŒ����̃V���c�Ə㒅���K�v�ł��B���{�ŋL�^���ꂽ�Œ�C���́A��
�a53�N2��17
���ɓ����y��������q���ŋL�^���ꂽ-41.2���������ł��B
�@���R��t�̌̋��u���������v�ŋx�e�̌�A�x�ǖ�Ɍ��������B��x�ǖ�̓e���r�u�k�̍�����v�̕���ɂȂ����Ƃ���ł��B�@
�r�{�ƁA�q�{
����NHK�̒��҃e���r�h���}�u���C�M�v�̐��쒆�Ɉӌ��̈Ⴂ����ԑg���~��āA�x�ǖ�̎R���ɓ���p���Ő������Ă��܂����B��
�̂����q�b�g
�����f��w�L�^�L�c�l����x��w�A�h�x���`���[�t�@�~���[�x�Ǝ����悤�Ȃ��̂��Ƃ����t�W�e���r����̈˗��ŁA�q�{�����A����
�J���O���̃e
���r�h���}�w�呐���̏����ȉƁx���q���g�ɏ��������̂ł��B�B�e�͎�ɘ[���n��ōs���܂������A���P�͈͂��L���A�x�ǖ�̖�
��S���ɒm��
���܂����B�P�X�W�P�N����Q�O�O�Q�N�́u�k�̍�����2002 �⌾�v�܂łQ�R�N�ԕ�������܂����B
�@����̏h�Ɂu�x�ǖ샊�]�[�g�E�I���J�v�Ɍ������܂���������Q�T�O�����o�X�͑����Ă��܂����B
�y�����L�@��S���z�@�@�X���Q�U��
�@�x�ǖ�̖閾���ʐ^�́A��������l�y�m�A���l�x�i�Q�O�T�Q���j�A�\���x�i�Q�O�V�V���j�A�x�ǖ�x�i�P�X�P�Q���j�A�O�x�ǖ�x
�i�P�U�Q�S���j
�ł��B�閾���̒��́A�����Ⴍ�����ĐÂ��ɓ��̏o���}���܂����B
�@�x�ǖ�Ƃ������x���_�[�����v���o�����炢���ł͗L���ł����A��P�P�O�N�O�ɖk�C�����L���J�n�����@���o���āA�u�t�@�[��
�x�c�v�̑n�n
�҂ł���x�c���n�����̒n�ɊJ���̌L�����낵�܂����B���j�A�x�c���Y���͖�T�O�N�O�ɁA�����p�Ƃ��Ẵ��x���_�[�͔|���J�n
���A���͂��悻
1.2�w�N�^�[���ɂ܂Ŋg�債�܂����B�x�ǖ�n���S�̂ł��s�[�N���ɂ̓��x���_�[�͔|�_�Ƃ�250�ˈȏ�A�͔|�n�悪230�w�N�^�[��
�ȏ�Ɋg�債
�܂������A�������Ζ����瑢����悤�ɂȂ��ĉ��i���}�����͔|�͋}���ɐ��ނ��������ł��B���a�S�W�N���ɂ̓��x���_�[�͔|�_
�Ƃ͂قڃt�@
�[���x�c�݂̂ƂȂ�܂����B���N�ō͔|���~�߂悤�Ɖ��l�Ɩ������̔N�A���a�T�O�N�ɁA���{���L�S���̎ʐ^�R���e�X�g�ŗD��
�����A�t�@�[
���x�c�̃��x���_�[�ʐ^���J�����_�[�ŏЉ���ƁA�ό��q��J�����}�����K���悤�ɂȂ�܂����B�@���ł͔N�ԂU�O�O���l��
���̕x�ǖ��
���邻���ł��B���x���_�[�̋G�߂͏I����āA����͉Ԃ����邱�Ƃ͏o���܂���ł����B���ꂪ��Ԃ̐S�c��ł��B
�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�x�ǖ�~�n�̖閾���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�x�ǖ�E�l�G�ʂ̋u
 �@
�@
�@���l�͋u�˕��i�ƉԂ̕��i���l�C�̊ό��n�ł��B�A�C�k��Ńs���G�C�ƌ����A�������Ă���Ƃ����Ӗ������邻���ł��B�l���P
�P�C�S�O�O�l�A
���̖ʐς͂U�V�VKm2�ł��B�@���ɂ͔����⒱�̐X�A�V�h�̋u�A�l�G�ʂ̋u�A�O�c�^�O�̎ʐ^�فE��^�قȂNJό��n�������A�N�ԂP
�Q�O���l������
����K���ƌ����܂��B�ߔN�͓���A�W�A����̗��s�҂������ƕ����܂����B��^�قɂ͔��l�̎l�G�������ɕ߂炦���������ʐ^��
����܂����B
�@�x�ǖ�x�O���Y��ȕ��i�B�@�����̗��B�@�p�b�`���[�N�̘H�i�N���b�N����Ύʐ^������܂��j�ƌ�����قȂ����_�앨���̃R��
�g���X�g���Y��
�ł��B���̂�����̍앨�͂̓W���K�C���A���A�r�[�g�i�����卪�j�����������ł��B�r�[�g�͍����L�r�Ɠ����悤�Ɏ��̃A���R�[��
�R���Ƃ��Ďg��
��悤�Ƃ��Ă��邻���ł��B�@���Y�����Ԃ�CM�Ɏg��ꂽ�P���ƃ����[�̖��̓|�v���̖ŁA���ɂ͏��a�T�P�N�ɃZ�u���X�^�[
��CM�Ɏg��ꂽ
������܂����B
�@���l��ō��ꂽ���l�w�B�@�����̉w�O�̃r���́A�ǂ̃r�����O�ǂɔ��l���\��A�O�p�`�̃f�U�C����������Ă��܂��B
�܂��r���̊O��
�ɂ͌��z�N�𐼗�̔N���ŋL�^���Ĉٍ��I�ȕ��͋C�Őv����Ă��܂��B�@���n�����w�Z�͎O�p�����i�Ƃ�X�q�j�̂��鏬�w�Z
�ł��B
�@���l�����k�l���w�Z �� �V����������w�Z�Ƃ��Ēm���Ă��܂������A�S�Z���k19���ł����̂œ�������A���܂͕Z���ƕ�
���܂����B���̊w
�Z�͓~�ɂȂ�Ɛ��k���X�L�[�ʊw���邱�Ƃł��m���Ă��܂����B�@�@�@�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@CM�Ɏg��ꂽ�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@����߂��̔�
 �@
�@
�@����s�͐l���R�U���l�A�k�C���ł͎D�y�s�ɂ��ő傫�Ȓ��ł��B�����Q�S�N�i�R���ɓԓc�������A�����̂��J��̎n�܂�ł��B
���R�������i�N���b�N����Ύʐ^������܂��j�́A����s�̈��R�Ƃ����R�ɍ��ꂽ�̂ł��̖�������܂��B�u���������R�ɋ߂��`��
���Ă��炤�v��
�����R���Z�v�g�ő����Ă��܂��̂ŁA�K���X����̐����g���l���̒��ŃA�U���V�������邵�A�k�ɔ��F�A�y���M���Ȃǂ���������
�^�C���Ƃ����A
�a�𐅒��ŗ^������Ƃ�����K���X�z���Ɋς邱�Ƃ��o���܂��B�I�����E�[�^�����P�T���̍����ɒ���ꂽ���[�v��n���ĎU����
�܂��B�I�����E
�[�^���̉ʕ����͌����ł��B�B�̂Qm�ʊO�ɒu�����R�̂����ʕ��͒|�Ƃ������Ă��ď��Ɏ��܂��B�@�������炢���ꂽ�Ƃ�
��ɖ_�𗧂ĉ�
����˂��h���Ēu���Ă����ƁA�ѕz�������Ă��ē����Ԃ̂悤�ɂ��đS�̂ɔ킹�āi�[�͗����Ȃ��悤�ɑ��Ŏ����Ă��܂��j�茳��
�����ʕ���
�������A�����Ǝg�����ѕz�������Ď�荞�ނ̂ł��B�܂��܂��ق��ɂ��y���݂͈�t�ł��B
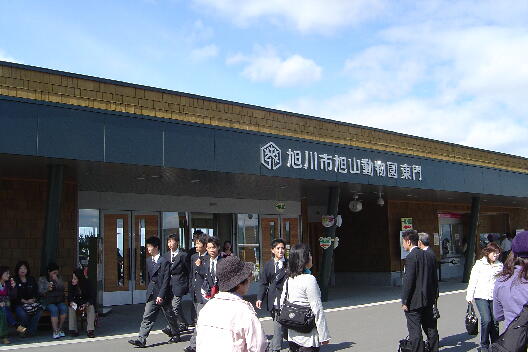
�߂�

�@�@�@�@

 �@
�@
 �@
�@
 �@�@
�@�@
 �@
�@
 �@
�@
 �@
�@
 �@
�@
 �@
�@
 �@
�@
 �@
�@
 �@
�@
 �@
�@
 �@
�@ �@
�@
 �@
�@ �@
�@
 �@�@�@�@�@
�@�@�@�@�@
 �@�@
�@�@
 �@�@
�@�@
 �@
�@
 �@
�@