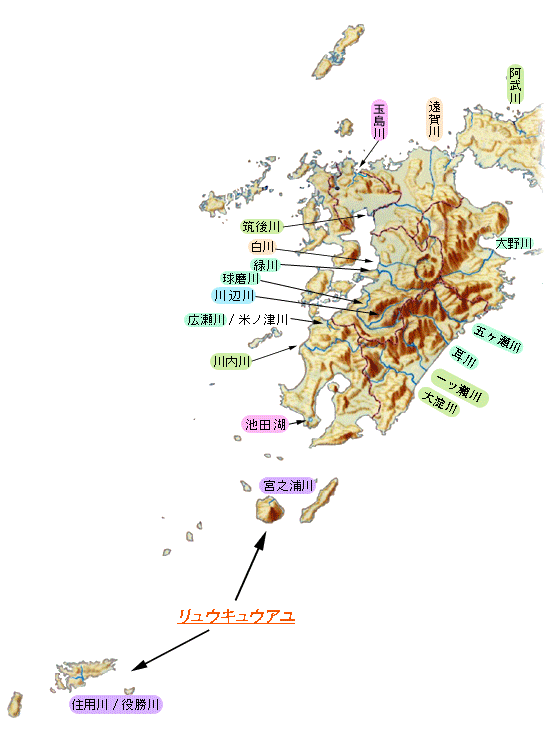鮎釣りに訪れたことのある川
大野川:阿蘇外輪山を源とし大分平野を通って別府湾に注ぐ。H16、1級河川の水質ベスト5に入った清流。流域には多くの磨崖仏が見られる。中流の犬飼町では毎年五月五日家族連れなど1万人が参加するドンコ釣大会が名物で、犬飼大橋下流では、「こいのぼり」ならぬ「どんこのぼり」百匹以上が泳ぐそうだ。 もちろん、鮎も名物。
五ヶ瀬川:高千穂の峰より下り延岡で日向灘に注ぐ。体長36.5cm、体重600gがこの川の記録。
延岡駅では「鮎の蒲焼弁当」が旅人に人気とか。子持ち鮎飯という新名物も登場。
耳川:上流の山深き椎葉は平家落人伝説の里。「ひえつき節」は落人哀歌。
渓流の珍味といわれるカワノリはこの辺りが南限。
玉島川:はるか神話の時代、神功皇后が新羅遠征に際し、釣り竿を上げると、細鱗魚が釣れた。皇后が「めずらしき物なり」と述べた事より”めずらの国”と言われるようになったが、訛って松浦になったという。この故事よりアユに鮎の文字をあてるようになったともいわれる
筑後川:筑紫次郎の名で呼ばれる大河。阿蘇外輪山を源とし大分を抜け、佐賀平野を貫流して、有明海に注ぐ。大分・日田の辺りは三隈川(古くは日田川)といい、そこで捕れる鮎を日田鮎/別名金口鮎と称し、西国で、其の風味最も賞すべきものありといわれた。
三隈川では、闇夜の川で鮎を手づかみする「鮎押し(アイオシ)」漁が今も活きている。
球磨川:巨鮎の川としてあまりにも有名。町をすっぽり包む名物の川霧の中、
球磨川下りで四十八瀬をめぐり
尺鮎に思いをはせる。人吉の鮎寿司も。
JR九州の駅弁ランキング1位は、新八代駅などで販売する「鮎屋三代」。鮎屋三代は炊き込みご飯の上に、球磨川で捕れた天然のあゆの甘露煮を載せた弁当。
広瀬川:小河川だが野アユは多く、独特の建網漁が行われる。
屋久島杉の原始林を抜けて流れる
宮之浦川と奄美の住用川には南国の鮎
リュウキュウアユが住む。沖縄でのリュウキュウアユ復活計画に期待。