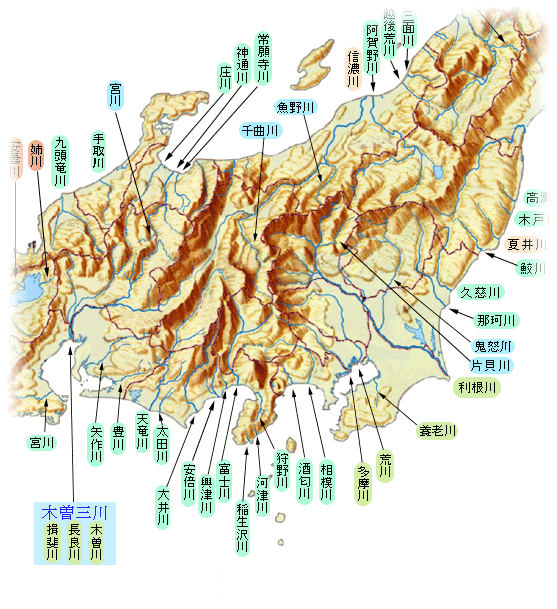:鮎釣りに訪れたことのある川
:鮎釣りに訪れたことのある川
久慈川:かつて水戸烈公が誇ったというのが常陸太田市を抜け久慈川本流に注ぐ里川の鮎。今は本流の袋田、太子あたりへ友釣に訪れる釣人が多い。
那珂川:大きな堰やダムが無いので、鹿島灘から栃木の奥深くまで天然アユが遡上する。
上流域の烏山町では、450年の伝統をほこる日本一の野外歌舞伎「山あげ祭」(国重要無形民俗文化財)が毎年7月の第4土曜日を含む金・土・日曜日の3日間にわたり開催される。
鬼怒川:日光連山からの水を集めて流れ、かつては巨鮎の川と呼ばれ大型の鮎が掛かることで有名だった。
利根川:奥利根は姿・形、味・香りのいずれも優れた大鮎の川として知られていた。大正末に支流の片品川に次いで本流岩本地先に発電所堰堤が建設されたとき、”奥利根は死んだ”と垢石は嘆いた。利根大堰の完成で利根の鮎は本当に葬り去られた。
が、群馬で「日本一のアユを取り戻す会」が’03年より活動を始めた。
養老川:以外にも千葉にも鮎の川がある。杉、桧にかこまれた養老渓谷に鮎は育つ。
多摩川:江戸時代は幕府の御用鮎として名を轟かせたせいか、昭和半ばまで江戸っ子は奥多摩の鮎が一番と思っていたそうだ。近年鮎が戻ってはきたが、多摩川は過去の川。
相模川:かつて大鮎の川として知られたが、昭和25年の相模ダム竣工とともに好漁場は水底に沈み、昔話となった。
支流の中津川も香りと味の良い鮎が釣れる川であったが、2000年の宮ヶ瀬ダムの完成でここも死んだ。
酒匂川:首都圏近郊の川なので相模川とともに釣人が多い。
文豪幸田露伴がドブ釣に足繁くかよったころの面影はもはや無い。
河口から8キロほど上流に報徳橋がある。報徳橋下流すぐ右岸が二宮金次郎(尊徳)の生誕地で、尊徳記念館がある。今も各地に報徳XXという名称があるが、これらは尊徳の「報徳の教え」と関連している。
神通川:岐阜県の川上岳を源流とする宮川は高山市を抜け、富山県境で断崖絶壁の壮大な峡谷を抜けた後、神通川と名を変え富山市で富山湾へと注ぐ。
支流の宮川はかつて飛騨国で最も鮎の漁獲が多かった川である。富山県境に近い宮川で山下福太郎が昭和七年に1尺3寸(39.4cm)百七十匁(637g)の大鮎を釣ったという記録がある。1匹は塩漬け、もう1匹はアルコール漬けにして保存してあったという。
庄川:富山湾へとうとうと流れ、明治・大正までは、
「麦屋節」に”鮎は瀬につく鳥は木に止まる、人はなさけの下に住む♪”と唄われたように鮎が多かったところ。
今は昔。
九頭竜川:昔は大変な暴れん坊といわれた。急流が多く、ここに住む鮎は身が引き締まり、その美味と香りは遠方まで知られたという。この川独特の取り込み技は「九頭竜返し」の名で知られる。
魚野川:昭和の初め信越線が開通した頃、三国峠を越えて奥利根の職漁師が大挙して押しかけた。越後の漁師は利根の漁師から狩野川式友釣を学んだ。
かつてこの流域はツツガムシ病が多く発生する所としてそれを知る者に恐れられた。抗生物質が広く使われるようになり、それも忘れられようとしている。
千曲川:島崎藤村の小説「千曲川のスケッチ」に登場する一膳飯屋<揚羽屋>は小諸市にあり、いまも「郷土料理」といわれる昔の小諸地方の料理と地酒が、安い料金で堪能できる。鮎の背ごしや塩焼き、それになんと鯉こくならぬ”鮎こく”を食べさせてくれるとか。
姫川:知る人ぞ知る翡翠の郷。縄文時代から北は北海道、青森から南は熊本、福岡まで翡翠の玉が運ばれた。全国各地の遺跡から糸魚川・西頸城産のヒスイが発見されている。4000年前の人はどのようにしてヒスイの玉を運んだのだろう。



















狩野川:近代友釣技法発祥の地。明治〜昭和にかけて数百人の川漁師が各地に遠征して狩野川釣法を伝えた。現在の友釣のルーツである。
5月の解禁から12月初頭まで釣人の絶えることが無く狩野川銀座の異名をもつ。
河津川:天城峠から河津へ流れる小河川で、伊豆の踊り子の舞台でもある。戦前に井伏鱒二が太宰治や亀井勝一郎らを伴い鮎釣によく訪れた川でもある。今は両岸が護岸で固められて川自体の風情はないが、天然遡上が多く良形が釣れる。
興津川:小河川であるが、広重の東海道五十三次に描かれるなど古くからその名は知られている。
東海道の川の中にあって、興津川の鮎は香りと味は海道一といわれた。狩野川と同様に11月末まで鮎キチが川に立つ。
安倍川:全国的には、鮎の川よりは”安倍川餅”でよく知られる。狩野川とともに名手の多かった所。
大井川:越すに越されぬ大井川。水のない広い河原にかつての面影を残すのみ。
天竜川:昔は諏訪湖まで尺鮎が遡った暴れ天竜も十数ヶ所のダムでおとなしくなってしまった。
支流気田川の中ほどに火伏せの神・秋葉神社がある。その昔秋葉講でお参りした帰り、尺に近い鮎の焼き枯しが一番の土産だったと古老が話していた。
豊川:上流で寒狭川と名を変えるあたりに、声のブポウソウで名高い鳳来寺がある。
矢作川:塩の道・足助街道に沿って支流の足助川が流れる。かつて塩の宿場町として栄えた足助は、良質の竹に恵まれ、優れた矢と足助竿を生み出した。
足助竿での取り込み技は「矢矧の振り子抜き」と呼ばれる。
木曽三川:いうまでもなく名を馳せた木曽三川だが、木曽川も揖斐川もダムと堰でズタズタにされ、長良川だけが10年前まで自然の川の様子を保っていた。1994年に河口堰が竣工して長良川も死んだ。悲しいかな木曽、飛騨の鮎の川は放流鮎に頼るのみ。
木曽三川の鮎の物語は、いまや遺跡として埋もれつつある。
郡上鮎は、もはや幻。