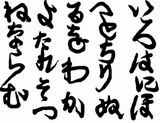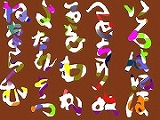|
ロシアは世界の情報を得るため、また覇権のため、言語の習得には熱心な国であったらしい。ロシアの国立図書館には世界中のどんな小さな部族でもその言語の辞書が揃っていると聞いたことがある。
ロシアにおける日本語教育の歴史は古く、江戸時代の1705年には初めての日本語学校がサントペテルベルグに設立されている。
ロシアの日本語学校の初代日本人教師は漂流民の「デンベイ」という人である。
このことを今回井上靖の小説「おろしや国酔夢譚」を読んで知った。その本の序章に「デンベイ」のことが書かれている。
「おろしや国酔夢譚」という小説は
江戸末期(1782)、伊勢の商人大黒屋光太夫を始めとする一行が、江戸ヘ向かう途中嵐にあって漂流、アリューシャン列島のアムチトカ島に流れ着いて、苦節9年で日本に帰国した話である。
私はその展開に魅かれてたった二晩でこの本を読んでしまった。
この物語は映画化(緒方拳主演)され、話題を呼んだという。
ロシアの学生たちも「コウタイフ」と言う名で彼のことを知っていた。 デンベイは、大黒屋光太夫一行の漂着より90年も前に漂着してきた人である。どちらも日本は鎖国の時代である。
デンベイの時代のロシアは、日本への航路もまだ開かれていない時代で彼はついに帰国を果たすことができなかった。
大黒屋光太夫たちはロシアにとって5回目の漂流民で、その頃は日本への航海路も調べられていて、彼はエカテリーナ2世に嘆願し、ロシア政府によって念願の帰国を果たしている。16人の一行中、生き残ってロシア本土を踏んだ5人のうち3人だけが帰国している。
洗礼を受けた2人はイルクーツクで日本語教師になり、ロシアで没した。
ロシアは大黒屋たちを送り届けるにあたって、日本との国交を開く手がかりを求めたが日本の鎖国のガードはかたく、「長崎港入国許可証」をもらっただけでロシア側は空しく帰国せざるをえなかった。
日本に帰った大黒屋光太夫のその後は江戸で半幽門の生活を余儀なくされ一生を終えたという。ついに郷里伊勢の土を踏むことはなかった。
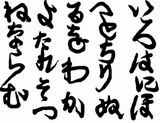
話をデンベイに戻すことにする。
デンベイは大阪商人の息子で、仲間と30隻の船団を組んで、米、酒、緞子、砂糖などを積んで江戸に向った。
途中暴風雨に遭い、28週間も漂流した末カムチャッカに流れ着き、そこでクリール人に囚われの身になった。
囚われて一年したころ、ロシア人のアトロフという人物と運命的な出会いを果たす。
このアトロフはカムチャッカ半島を発見した人である。
その頃ロシアは、毛皮や魚が大量に獲れるシベリアに目をつけ、次第に東新して領土を拡張していった。
原住民を支配し、当時のヤクーツクの町には、もうシベリア局が設けられている。
そして新たな土地発見のために次々と探検隊を出している。
アトロフは、1695年にシベリア探検の根拠地であったヤクークツから極東の町アナディルに城砦司令官50人隊長として派遣され、カムチャッカ半島の探検隊長の任にもついたのであった。
「アナディル」という所は「マガダン」よりさらに北東端に位置し、ベーリング海に面した地である。
その頃、ヤクーツクからアナディルまではソリなどで約半年の行程であったという。
現在はマガダンからアナディルまで小型ヘリコプターが飛んでいる。
余談だが、現在のアナディルはおしゃれで西洋風の美しい街になっているという。
というのも、アナディルを管轄する知事は世界で有名なプロサッカーチームのオーナーをつとめている大富豪で、彼の政治力と財力とでアナデイルの街は整備されたと聞く。
ロシアの金持ちは日本とは桁が違う。
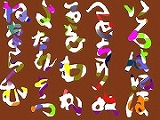
アトロフのカムチャッカ探検は、1997年から1699年まで3年にわたって行われた。
そのカムチャッカで彼はデンベイに出会うわけである。
彼は原住民カムチャダール人の村に異国の漂流民が囚われの身となっていることを聞き、連行させてみると、アトロフがまだ見たこともない風貌をした男が現れ、覚えたカムチャダール語の言葉で語ったという。
ロシア人に保護された「デンベエ」を取り調べた出先機関の役人は2種の報告書1702年にシベリア局に出している。。
しかしその報告書はその後2百年も官庁の倉庫に眠ったままであった。
1891年に史学者エヌ・オグロブリンが「1701〜1705年ロシアにおける、最初の日本人」という論文が発表されて、はじめてデンベイは世に知られることとなった。
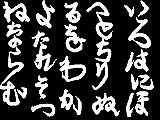
1701年の末に、デンベイはアトロフにともなわれヤクーツクに行き、やがてモスクワに移される。
そこで日本の地理的位置、金山、銀山の場所、政治、軍備、宗教、風俗を詳しく調べられている。その報告書が上部に提出され、これが直接日本人が話したロシアにおける最初の日本資料となった。
またこの年、デンベイはピョートル一世に謁している。
ピョートル一世は、国費によるデンベイの生活保障を約し、日本語学校を開設してデンベイを
そこの教師になることを勅令で命じている。
デンベイはロシア語を習得したあと1705年、サントぺテルベルグに開設された日本語学校の教師となるのである。
学生は軍人の子弟ばかりで、数はすくなかったが、終生日本語を研究する義務を負わされた人たちだった。
デンベイは1710年洗礼をうけロシアで生涯を閉じたがその没年はわかっていない。

その後、ロシア政府は日本語教師を増やすため、今後カムチャッカ海岸に漂流する日本人がいたら,その中から1名をペテルベルグに送るようにヤクーツク代官に命令を降ろしている。日本人漂流民はロシアにとって貴重な人材だったわけである。
またその待遇もかなりよかったらしい。
第2回漂流民は1701年に紀州の「サニマ」で彼もペテルルブルに送られ日本語教師になっている。「サニマ」はデンベイの死後1734年まで日本語を教え続けた。
第3回漂流民は1729年に薩摩から大阪に向かう途中漂流民になった「ゴンザ」と「ソウザ」でやはり日本語教師となっている。二人は女帝アンナ・ヨアンノウナに謁している。
第4回漂流民、南部藩出の竹内徳兵兵衛一行は1745年千島列島オネコン島に漂着し、1745年にはペテルブルグで5名が日本語教師になっている。
また他の4名もイルクーツクで日本語教師になっている。
その中で、さすけという人は「ニボンのコトバ」という露和辞典を作っている。
その頃のロシアは日本および日本近海への関心が急速に高まっていた。
太平洋探検に必要な通訳を東部シベリアに確保するために、1754年イルクーツクでも航海学校の中に日本語学校が開設された。
その6年後の後の1761年の記録には日本人教師7名、学生15名とある。このイルクーツクの日本語学校は62年間続けられ日本語の通訳を育て続けた。
大きく言えばロシアの極東政策の一翼を担ったわけである。
この時代、漂流民から日本語教師になった人々は、ついに日本の地を踏むことはなく、多くは正教の洗礼をうけロシアの地で没している。
そのころ日本は長い鎖国の時代であった。
おそらく日本人のことであるから、彼らは誠心誠意日本語教育に尽くしたことと思う。
しかし彼らの望郷の念を思えば胸が痛む。
真摯な日本語教育の大先輩に敬意を表したいと思う。
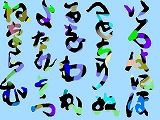
余談であるが
日本人が多くのロシア人たちを救った歴史もある。
時代は下がり1936年12月。
マガダンからウラジオストックに向かったソ連貨物船「インティギルガ号」が乗客、マガダンの漁業労働者、囚人など1000余名を載せて航海中に嵐に会い、北海道宗谷岬付近で座礁沈没した事件があった。
その時の犠牲者は700人にものぼったが、暴風雨の中を北海道猿払村の人々が官民一体となって救助をつくし、約400名が救助された。
今も宗谷岬にはロシア人たちの鎮魂の記念碑が建っているそうである。
(この文は井上靖の「おろしや国酔夢譚」から抜粋しています。
興味のあるかたは是非お読みになってください。)
日本にある 伝兵衛友の会

|