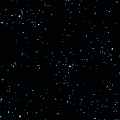例えば、"我々は、何処から来て、何処へ行くか"と云った根本的な問いに対し、星から来て、
星に還るのだ、というような言い方をするといった具合である。
我々の体を構成している総ての物質は、宇宙から来ているわけであるから、尤もな、答えだと
言い得よう。然しながら、それら宇宙を構成するに至った物質は、何処から来て、何処へ行く
のか、という根源的な問いに対しては、口を噤まざるを得ない。答えが、今の所、出せないこと
が、明からだからである。と共に、我々の精神は、広大な宇宙の真っただ中に、根拠地も無く
存在し得るほど強靭ではないからだ。従って、通常、我々は、答えの出ない質問に対しては、
それ以上の問いを控え、口を噤むのである。これも、一種の知恵であろう。
然るに、こんなことでは、問題を先送りし続けるだけだというのも、また、事実である。今回、テ
ラ・アーツ・ファクトリーが、上演した「ヒロコ」は、通常の芝居が、目指す、観客との一体化とい
うカテゴリーから、距離を置いた作品である。その結果、芝居が、撥ねた後も、納得がいかな
い。観劇後、何時まで経っても、違和感が、拭えないのだ。異化が、成功した証である。
無論、表面上の意味を追い、作劇法をテクニカルな意味で追うことは可能である。しかし、この
作品の真の意図は、其処には無い。寧ろ、通常、我々が、納得したつもりになっていることの、
根底を疑い、事実というものが、如何に分かりにくく、また、錯綜し、複雑に絡み合って、実際、
本当には、何が起こってきたのか、それは、本当に、起こったことだったのか、ということをも、
疑って掛かり得ること。其処には、何一つ確固としたものなど無い、という残酷な迄の事実性を
明らかにすることにあったのだと考える。
例えば、タイトルの「ヒロコ」だが、作中人物の誰とも、関係が、無いばかりか、モデルになった
人物たちとも、関係が、無さそうである。恐らく、この名には、心を開く、とか世界に対して、否、
世界の虚無性そのものに対して、真っ向から、向き合おうとした者の、夢の残滓のようなもの
が、こびりついているのだと思う。舞台は、一幕三場。
女性ばかりが、演ずる一場では、其々の、出身地に関する地場情報・地域的特性などが、語
られる。場面、場面は、一対一のダイアローグを積み重ねながら、オムニバス形式で語られて
ゆく。
それは、様々な世代の観客と演者の相互確認とギャップの確認作業のようにも思われる。更
に、深読みするならば、一場では、言葉とイメージの乖離が、提示されていると言っても良い。
但し、この段階では、それらは、単に示唆される形を採っている。
だが、深読みだの、言葉とイメージの乖離だの、言ってみても、本当に、現代日本の問題を抉
り出したとは言えない。今の日本の日常、我々、一人、一人が、語るに足るだけの人生を、本
当に持っているのか? グローバリゼーションが、叫ばれる時代、我々の知識・経験は、正しく
ボーダーレスになっている。しかし、その空疎な情報実態を日々感じ、虚しさに、のたうってい
る人間が、どれほど、この国に存在するか? 中味の無い人間ばかりが、大手を振って歩いて
いる。この情けない現状を女たちは、生活の言葉で、淡々と語るのだ。
暗転後の二場では、様々な世代の男性が、登場する。其々の、世代に、プロフィールを質問す
ることから始まり、彼らが、何をし、それが、世間から、如何様に見られたか、しかも、実態は、
どのようであったのかが、少しずつ明らかにされてゆく。
つまり、二場では、表象と現実の乖離、言葉やイメージが、紡ぎだす情報と事実との間に横た
わる深淵が、更に明らかになって行く。
質問の含意と回答の妙が、世代・時代・社会的地位や状況に纏わりついたステレオタイプのイ
メージに対応する。既存のイメージは、現実に生きる人間との、微妙なずれやギャップ、見られ
たイメージ通りに演じる、登場人物の主体的作為に由って割れるコンセンサスの底、知的な意
志や行為によって変質する「現実」を通して、多数の人々を操作しようとして為されるプロパガ
ンダや擬制とその解体を窺わせる。
マスメディアが報じる、心地よいイメージだけで語られ、報じられる「世界」と事実の深淵を垣間
見せるのだ。それと同時に、男たちの、存在からの乖離そのものが、示唆されていると言えよ
う。
クライマックスは、三場である。ポリフォニックに、語られる其々の生、その背後に通底音のよ
うに、響く砂川紛争伊達判決。判決は、日本政府が、米軍駐留を許したことを憲法九条第二項
前段に於いて禁止された戦力保持に当たると判断、違憲との結論を出し、刑事特別法の罰則
そのものが、憲法31条に違反するとした。1959年3月30日のことである。
ポリフォニックに語られる言葉の群れを総て、理解することは、殆どの人々にとって、不可能な
ことであろう。しかし、それで良いのだ。芝居の狙いは、其処にこそ、在ったのだから。恐らく、
この芝居の真の狙いは、世界は、簡単に分からない、ということを、重層する科白の虚々実々
を提示して、提起することであった。更に、「ヒロコ」の表記に注意を向けるならば、以下のよう
な想像も可能である。カタカナ表記の意味するもの。それは、ヒロシマ・ナガサキの子であり、
更には、ヒロヒトの赤子である、と。
三場で伊達判決を背景に語られる、其々の人物の声が、ポリフォニックに重なるのは、このよ
うに考えれば、偶然ではない。否、必然である。それは、被曝時の阿鼻叫喚であり、ウラン型
核爆弾、プルトニウム型核爆弾使用後のABCCの対応への抗議であり、大日本帝国憲法下唯
一の主権者であった、天皇・裕仁の戦争責任回避という欺瞞そのものへ突きつけられた、無
数の声なき声の謂いであり、日本の対米従属を決定的ならしめたメルクマール・砂川事件最
高裁大法廷判決への、圧殺された、これまた無数の抗議であったからである。
真に実験的な演劇を追求する、この劇団ならではのチャレンジとして、評価したい。
以下は、評者の加える蛇足的解説である。興味のある方に読んで頂きたい。
伊達判決を受けて、アメリカは、慌てた。安保改定阻止を目指す左派勢力に時間を与えては、
アメリカの対日支配にマイナスの影響を与えると考えたからである。時の駐日大使、ダグラス・
マッカーサー2世は、60年の安保条約実質改定へ向けて、伊達判決廃棄を画策する為に、外
務大臣であった藤山 愛一郎に最高裁への跳躍上告を促す圧力を掛け、更には、最高裁長
官であった田中 耕太郎との密談を交わした。田中は、統治行為論を採用、司法の独立を蔑
ろにしたばかりでなく、多くの犠牲の上に成り立った我が国の憲法に対する判断を忌避し、日
本を歴史的汚辱にまみれさせた。
日本にも漸く日の出を見掛けた民主主義は、最高裁判断に依り、自ら、墓穴を掘ったのであ
る。この結果、必然的に、権力による民衆圧殺の歴史が、表舞台へ飛び出してきた。日本共
産党の路線転換や山村工作隊の位置ずけ、評価を巡って、新左翼の源流も登場し、その流
れは、連合赤軍事件へも連なる。「ヒロコ」では、圧殺された民衆の象徴として、1972年、迦葉
山で総括対象の一人となって亡くなった大槻 節子さんの日記も織り込んだ。従って、タイトル
に関しては、永田 洋子の読みも出てくる。
多少、アイロニカルに言うのであれば、最高裁長官であった、田中 耕太郎は、日本の進路を
過らせたにも拘わらず、勲一等旭日桐花大綬章と文化勲章を受章している事実を指摘した
い。それも、当然であろう。日本は、東京大空襲など、日本の焦土化を立案・指揮し、東京大
空襲だけでも、数時間で下町住民10万人以上を嬲り殺しにした、カーチス・ルメイに勲一等旭
日大綬章を与える国だからである。(現在形であることに注意して欲しい)勲章を欲しがる連中
など、光る物を集めるのが、大好きな、烏と同レベルだと笑って済ませる人なら兎も角、有り難
がる人々にとっては、大きな意味を持つ事実であろう。
ところで、演劇とは、想像力の場である。多様な解釈が、其々の、演者・受容者の中で、オリジ
ナリティーを持って、ドラマツルギーを構成し得た時、それは、成功した作品となる。それ故に、
演劇は、最も人間的な芸術形式であり、世界中で古くから上演されてきたし、現在のようなハイ
テク社会でも、その命脈を保っている。命の多様性を持つとは、絶えざる新陳代謝をすること
である。それは、生きる行為そのもの、日々の営為そのものである。そして、それが、想像力
によって為される時、其処に湧き上がってくるものをこそ、アウラと呼びたい。演劇における実
験とは、マンネリを打破し、生の根源たるアウラを再起せしむるべく提起される新陳代謝その
ものである。
|
|