2A3シングルアンプ製作
2A3シングル(亜紀誕生記念アンプ)
 <このアンプについて> 製作2004.6〜8月頃
<このアンプについて> 製作2004.6〜8月頃
この2A3シングルアンプは、真空管アンプ全4作目にしてこれまでの知識をまとめる意味として、更に
球を交換することによる音の違いを楽しめる物を作る為、そして最も肝心な下の子の誕生記念と
して製作しました。
あえて、メジャーな2A3を採用した理由は銘柄や構造の異なる球を調達しやすいことがあります。
(相談にのっていただいた、いつもお世話になっているboiaudioのあきすけさんに感謝)
電源回路には、今回整流管を採用しました。基本設計は傍熱管の5AR4とし、差し替えで5U4G等の直熱整流管の音も楽
しめる設計です。
2人目の子供(亜紀)が生まれ、これまで以上に子供中心の生活になります。時間の掛かる製作そのものは、
しばらくおあずけでしょう。球の交換だけならお手軽に楽しめます。
そんな訳で製作したアンプです、これまでの集大成としてトランス等の部品も特性の良い物を採用しました。
(値段や見た目ではありません)
前回の6AH4GTsingleは、「お金を掛けずにクロストークが良い」がコンセプトでしたが、今回は最高の音
を目指しました。(f特、クロストーク、歪み、波形等)
デザインも、後述しますが一般的な配置ではなく少し工夫しました。これで、シングルアンプ3つ(5極管、駄
球3極管、直熱3極管)、プッシュプルアンプ1つ(50BM8)と揃いましたので、様々なアンプの音の違いを
楽しめるようになりました。
特性まとめ
<目標とした特性等>
はっきりいって、最高の特性をめざしました。キッパリ!!(^_-)-☆
・周波数特性が良いこと。
・クロストーク特性が良いこと。
・小さなスピーカーでもたっぷりのしまった低音が出ること。
・レイアウトに少し特徴を出すこと。
・球の交換で音の違いを楽しめること
<設計・概要>
・初段、ドライブ段は内部抵抗の低い球を使い、特に高域の周波数特性を良くする。
・出力段は、自己バイアス。(ちょっと弱気かな)
・初段、ドライブ段間は直結。(Cが省けますし、帰還も掛けるので安定性が良くなります)
・NFBは適度に使用。
・レイアウトは一般的なシングルアンプとは変えました。
左手前に整流管を配置し、自己主張出来るようにしました。
出力トランスは右に並べました。結果として前後の重量バランスも良い。
(但し配線に少々コツ必要、6AH4singleアンプで経験済みの配置)
<設計・詳細>
・初段・ドライブ段ロードライン
初段5678は、プレート電圧57V、プレート電流3mA、負荷抵抗51kΩとしました。初段は直流負荷抵抗
=交流負荷抵抗なのでロードラインは1本です。
ドライブ段5687は、プレート電圧132V、直流負荷抵抗20kΩです。交流負荷抵抗は2A3が自己バイアス
の為グリッド抵抗を270kΩと高く設定出来ましたので18.6kΩとなり、ロードラインもそれほど違い
ありません。
よってドライブ段の高域周波数特性も十分あるはずです。(同様な回路の6AH4single
ではドライブ段までの周波数特性も測定してあります。)

・出力段ロードライン
Ep=285V、Ip=52mA、RL=3.5KΩと設定し設計しました。

・回路図(手書きですみません)
電圧は設計時の予定電圧です。
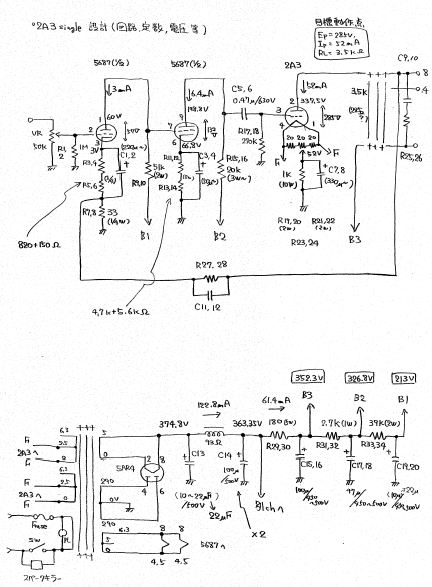
整流管の違い
その後、直熱管の5U4Gに差し替えてみました。電源投入時の動作に関して、少し心配していました。
(初段・ドライブ段が直結、2A3に対しても少し負担が大きいか?)しかし、実際に立ち上がり時の
過渡電圧を測定すると、それほど高圧にならないことが分かり安心しました。
ダイオード整流
ですと、もっと高い電圧になり問題になりそうです。
(実測で、5687には最大270V程度、2A3プレート330V程度となった)
<製作>
製作記事作成中
<このアンプについて>で少し書きましたが、一般的な配置から少し変えてみました。
変えたといっても、結局は同類って感じですが。。
理由・方針
・みんなと同じじゃ、面白くない。
・ST管の横一列配置ではなく、整流管を離して左手前に。整流管が自己主張できるようにしました。
・アウトプットトランスを右側に並べました。前後のトランスの間にカソード電圧のモニタ端子を置いています。
こうすることで、端子が隠せます。
また、全体の重量バランスも良くなりました。一般的な配置ですと、重心がかなり後ろ側に偏ってしまいます。
・今回は、シャーシの塗装をすることにしました。穴あけ後に、やすりがけとアルミ用スプレーです。
下地処理剤や仕上げのクリアは省略しました。色にもよるとは思いますが、処理無しでも問題無しです。
シャーシ加工完了

塗装完了

虎の子のビンテージ2A3(RCA)

<特性>
しばらく無帰還でエージングを兼ねて聴いていました。しかし、どちらかというと
DF(ダンピングファクター)がある程度あったほうが私には合うようです。特にブックシ
ェルフ型のスピーカーでは顕著です。
既に製作済みのアンプでDFが2〜3程度の物があるので、音の違いを楽しむためにも今回はDF6
程度まで持っていきました。(このあたりは、個人の好みの問題だと思います。もちろん帰還の有無や帰還量
で調整可能です)
結果として、低音にも力の有る(かたまりで押してくる感じ)なアンプに仕上がり
ました。
ノイズはもともと無帰還でも少なかったのですが、帰還をかけたことで更に静かなアンプになり
ました。スピーカーに耳を付けてもハムは全く聞こえません。
波形(容量負荷でもまあ大丈夫でしょう)
一応、負帰還用の抵抗にCをパラって軽く対策してあります。(カットオフ300kHz程度)
100Hz

1kHz

10kHz

10kHz(8Ω+0.1μF)

10kHz(8Ω+0.47μF)

10kHz(Open)

10kHz(0.1μFのみ)

10kHz(0.47μFのみ)

update 2004.10.20


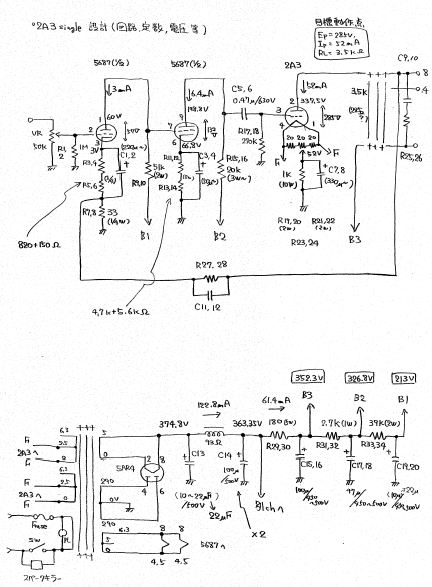
 <このアンプについて> 製作2004.6〜8月頃
<このアンプについて> 製作2004.6〜8月頃










