| Ready to fly NEMO | |||||
| 組立参考資料 2007.11.20 一部修正 |
|||||
| <ご注意> この組立参考資料は、私が複数機製作した経験から、 個人的にまとめたものです 製造元および販売店等には、一切の責任はありません また、この参考資料をもとに製作されたことによる トラブル等については、”自己責任”にて対処されますよう よろしくお願いいたします * |
|||||
| 組立に使用する 補助材料等 |
 |
||||
| プラスチック用接着剤とグラステープと爪楊枝・・・ 3M製「Scotch 強力接着剤」通称”ねりわさ” ”スーパーX”なども使用できるけど、 この接着剤は極めて作業性が良いですね * そのほか、プラスドライバー(小) M3ナット回し φ1.2mm~φ1.5mmドリル カッターナイフ、はさみ等・・・ |
|||||
| 部品確認 1 |
|
||||
| 主翼 | |||||
| 胴体(2分割です) (バッテリーハッチは、撮影のため取り外しました) |
|||||
| 搭載メカ類 (プロポレスの場合は、送信機が入っていません) |
受信機、アンプ(スピードコントローラ) バッテリー、充電器 (その他、サーボx3個) |
||||
| 水平尾翼 | 垂直尾翼 | ||||
|
|
|||||
| シール 1 | |||||
| シール 2 | 説明書 | ||||
| 部品確認 2 |
|
||||
| 左から ①プロペラ ②カーボンロッド(主翼ねじ止め用) 長短各1本 ③ラダーリンケージロッド (長いほう) ④エレベータリンケージロッド (短いほう) ⑤エルロンリンケージロッドx2 ⑥主脚ピアノ線 ⑦尾輪用ピアノ線 ⑧ペラ止め用パイプ ⑨ ヾ M3ナットx3個・・・写真は2個ですが3個が正しいです ⑩ ヾ M3平ワッシャー ⑪モーター止めねじ、 ⑫小ねじ4本・・・・エレベータ&ラダーホーンの止めねじ ⑬主翼止め用輪ゴム ⑭両面テープ・・・(使用しませんでした) ⑬マジックテープ (バッテリー固定用) |
|||||
|
|||||
|
|
|||||
| 左から ①スピンナー ②主輪(2個) ③尾輪 ④主翼止め用カーボンロッドにかぶせるキャップ(4個) ⑤エレベータ&ラダーホーン(2組) ⑥主輪止め用カラー(2個) ⑦主輪止め用ブッシュ(2個) ⑧尾輪止め用ブッシュ |
|||||
|
|||||
| モーターの取り付け |
|||||
| 最初にコネクターを通しておく | モーターの固定 付属のねじでモーターケースを取り付ける (M2X8) |
||||
| モーターがしっかり固定できない場合は ケース上部も固定する (このねじは添付されていません) |
モーターケースが、がたつく場合は 適当な厚さの、ペーパー等をはさむと しっかり固定できる |
||||
| サーボにグラステープ巻きつけ (3個とも) |
|
※サーボのホーン位置は このままでかまいません |
|||
| エレベータ/ラダー サーボの取り付け) |
|||||
| サーボ取り付け面に接着剤を塗布 (点付けで良い) |
サーボ(2個)を接着する | ||||
| 水平尾翼の取り付け | |||||
| 水平尾翼を仮組みして、 組み合わせをチェックしておく |
水平尾翼の当たり面の両面に プラスチック接着剤を薄く塗布する * ※数分間、乾かしてから接着する (溶剤を飛ばして接着する方法です。 一度張り合わせると、ほとんど動かせません) |
||||
| 胴体後部の貼り付け | |||||
| 仮組みして組み合わせと、 当たり面ををチェックしておく |
胴体後部の当たり面の両面に プラスチック接着剤を薄く塗布する (水平尾翼面にも塗布) * ※数分間、乾かしてから接着する |
||||
| 水平尾翼に ホーン取り付け |
|||||
| 水平尾翼にエレベータホーンをねじ止めする (M1.5x4 2本* この小ねじは、木ねじのように、 先端が細くなっていないので ねじ込みに少々難儀します。 φ1.2mmドリルであらかじめ通しておくと 作業性が良くなります * 接着剤で貼り付けてしまってもOKです * |
水平尾翼の裏面 | ||||
| 水平尾翼に折癖をつけておく | 水平尾翼の動翼面を数回上下させる | ||||
| 垂直尾翼に ホーン取り付け |
|||||
垂直尾翼にもホーンを取り付ける |
垂直尾翼に折癖をつけておく | ||||
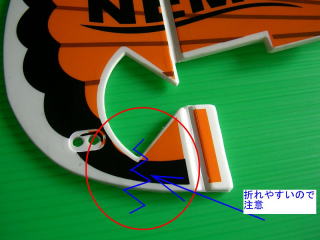 |
|||||
| 折れ曲がりやすいので、注意してください | 折れ曲がっりやすい箇所に グラステープで補強しておくのも良いでしょう |
||||
| 垂直尾翼接着 |  |
||||
| 垂直尾翼を仮組みして、 組み合わせをチェックしておく |
垂直尾翼が胴体の溝に干渉する場合は 胴体側の溝を、尾部側に10mm程度 カッターナイフやピンセット等で広げると その後の作業がやりやすくなります |
||||
| 垂直尾翼の当たり面の両面に プラスチック接着剤を薄く塗布して すぐに接着する (注意)★この工程は接着剤塗布後 速やかに組み立てること もし接着剤を乾かしてから接着すると 組立途中で動かなくなってしまって とんでもないことになりますのでご注意ください |
|||||
| 胴体後部を裏面からみたところ1 | |||||
| 主翼固定用カーボンロッドの差込 | |||||
| 前側に長いほうのカーボンロッドを差し込む ※シールを貼ったあとで固定するので、 ここではまだ接着しないこと |
後ろ側に短いほうのカーボンロッドを差し込む |
||||
| 主脚/尾輪組立 | |||||
| カラー、主輪をピアノ線に通し ブッシュをプラスチック接着剤で固定する ※接着剤がはみ出さないように注意 |
同様に、尾輪を組み立てる ※接着剤がはみ出さないように注意 |
||||
|
|
|||||
| ロッドストッパーで固定する方法もあります (ロッドストッパーは入っていません) | |||||
| エルロン・サーボの 取付け |
|||||
| エルロンサーボの側面に接着剤を塗布 (点付け程度) |
エルロンサーボを主翼のミゾに押し込む ケーブルの途中をグラステープで固定する (グラステープは入っていません) |
||||
| エルロン・リンケージ | |||||
| エルロン・リンケージロッドを取り付ける ※リンケージロッドがきつい場合は サーボ・ホーンの穴をφ1.2mmドリルで広げる |
エルロンロッドについているホーンは ”ねじ”になっています ねじ込めば、舵角を増やすことが出来ます |
||||
| メカの搭載 | |||||
| 受信機裏面にマジックテープを貼りました | アンプと受信機のコネクタ接続 | ||||
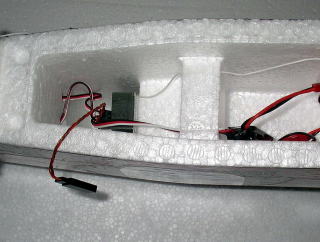 |
|||||
| エルロンコネクタは、延長ケーブルを使いました (延長ケーブルは入っていません) |
受信機の固定位置 | ||||
| プロペラ取付け | プロペラシャフトにペラ止め用パイプを通して M3ねじで(軽く)固定する <重要>※プロペラシャフトは、 スラスト方向(軸方向)に わずかな隙間が必要です。 締めすぎないようにして下さい |
||||
| スラスト方向(軸方向)に隙間がないと、 モーターに大きな負荷がかかり、 最悪の場合モーターが焼きつくことがあります。 隙間調整がうまく出来ない場合には、 ペラ止め用パイプを、使わないほうが無難です * **** ペラ止め用パイプを使用しなくても、機能上問題ありません *** * |
|||||
| カウリングを取り付ける マグネット止めになっています |
ペラを取り付けて M3平ワッシャー M3ナットで締め付ける |
||||
| スピンナーの先端部をはずして M3ナットで締め付ける そのあと、スピンナー先端部を取り付ける |
スピンナー先端部は 少し強めに引っ張れば外れます |
||||
| シールの貼り付け |
 |
||||
| シールを別々に切り取る ※裏紙はまだはがさないこと |
|||||
| 主翼上面に、霧吹きしておくと、シールの位置を 少し修正する時にはがしやすくなります |
主翼に貼る大きなシールは裏紙のみ、 真ん中をカットしておく |
||||
| 霧吹きした主翼にシールを位置決めしたあと 真ん中から裏紙を剥がして半分貼り付ける |
同様に、残りの半分と、E-SKYシールも貼る 最後に、古タオルなどでシールの中央から 外側に水を押し出すように拭いて行く |
||||
 |
|||||
| シール貼り付け参考写真 ケースの写真などを参考に貼り付けると良いでしょう |
|||||
| 主翼止め カーボンロッドの接着 |
|||||
| 主翼止め用カーボンロッドの 穴にかぶったシールは カッターで小さい切り目(X)を入れる |
カーボンロッドを通す | ||||
| カーボンロッドを少し引き出して 接着剤を塗布する |
カーボンロッドを差し込んで 先端部に少し接着剤を塗布して キャップをかぶせる |
||||
| カーボンロッド2本(キャップ4個)を接着した状態 | |||||
| 主脚の取付け |  |
主脚を取り付ける | |||
| 尾輪取り付け | |||||
| 尾輪を胴体に差し込む | ※水上機する場合、尾部フロート取り付け部に、 グラステープを張る |
||||
| エレベータ/ラダー・リンケージ |
|
||||
| エレベータ・リンケージ | ラダー・リンケージ | ||||
| バテリーの固定 | バッテリーとバッテリーボックスに 両面テープを貼る |
||||
| バッテリー収納部 カバーの取付け |
 |
||||
| 主翼のゴム止め |  |
 |
|||
| 主翼を輪ゴムで止める 輪ゴムは4本使用する |
主翼が浮いたり、傾いたりしないように 主翼のエンボスを胴体の穴にしっかりと差し込む |
||||
| 完成!! | |||||