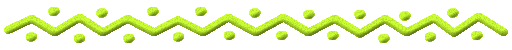
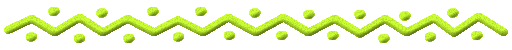
![]()
しん子おばさんというのは、ママの妹です。私の自慢のおばさんです。なんたって、国際線のスチュワーデスをしているのですから。
英語は、ペラペラだし、スタイルだっていいし、流行の服をきているし、おばさんというよりは、おねえさんのよう。そう、五才しか違わないのに、ママとはとは大違いです。
しん子おばさんは、時々、ぶらっと泊りにきます。いつも連絡もなく、突然くるのです。わたしは、いつでも、しん子おばさんのことは、大歓迎。でも、ママはちょっと、違うみたい。シン子おばさんが来ると、ママはちょっとごきげんななめになるのです。
その日も、おばさんは、突然やってきました。
「ああ、疲れた。もう、年だから、スチュワーデスも疲れるわ。あれで、なかなか重労働なんだから・・。あら、メグちゃん、元気だった?」
そういって、私の頭をなぜました。
「ボーイフレンドできた?」
「やだー。私、まだ、8才になったばかりなのに」
「そうか、まだ、そんなだったっけ。それじゃ今回のおみやげは、ちょっと早すぎたかな」
おばさんは、いたずらっぽく、にやっと笑いました。
「え、なに、なに、おみやげあるの」
わたしは、身をのりだします。
「なにいってるの。期待していたくせに」
おばさんは、笑って、わたしがまるごとはいっちゃいそうなほど、大きいトランクをゆっくりとあけました。
「今度は、どこにいってたの」
わたしは、トランクの中の香水の匂いにどきどきしながら、おばさんに聞きました。
「インド。カレーのふるさとよ」
「へえ。すごい」
おばさんは、トランクの中に頭をつっこんで、おみやげをさがしています。なかなかみつからないようです。
「まったく、整理整頓てものができないのね。あんたって人は」
そこに、お茶をもって、ママがやってきました。
「え、お茶だけ。ケーキかなにかないの」
おばさんは、口をとんがらせました。
「とめてあげるだけでも、感謝しなさい」
ママは、軽くおばさんをにらみました。
「ママ。シン子おばさん、おみやげを買ってきてくれたんだって」
わたしが言うと、ママはかたをすくめました。
「また、おかしなものじゃないの。この前の栓抜きなんか、一度つかったら、こわれちゃったし。それに、この前のアロハ、派手すぎてきれないわよ。」
ママは、しん子おばさんには、いつもこんな言い方をします。でも、ママが、どんな言い方をしても、しん子おばさんは平気な顔をしています。
「あった。あった」
おばさんは、やっと、トランクから、顔をあげました。
「これ、これ」
おばさんは、薄汚れた茶色い包みから、小さなガラス瓶をだしました。お化粧道具のようです。
「何、それ」
ママがききます。
「これは、マニキュア。インドのまじない師が売っていた、高価なマニキュアよ」
「へえ。でも、それ、みどり色じゃない」
「そう、みどりのマニキュアなの」
「まあ。やだ。ばかばかしい。あんたは、そうやって、いつもやくにたたないものばかり買ってくる」
ママは、おおげさに、ため息もつきました。
「いいじゃない。ねえさんにあげるんじゃなくて、メグにあげるんだから」
おばさんは、私に指をだすように言いました。
「これは、そんじょそこらのマニキュアじゃないんだから。インドのまじない師がいうにはね。心がきれいで、欲のない素直な人の爪にぬると、ぬったところから、芽が出て、花が咲くんだって。マニキュアの花よ」
「うそー」
私は、思わず、手をひっこめようとしました。
「私も、うそだと思ったの。でも、そのまじない師の爪にぬったらね、私の目の前で、本当に芽がでて、花がさいたのよ。とっても小さな、赤い花がね。すごくきれいだったんだから。ほら、いたくもかゆくもないから、やってみようよ」
おばさんは、そういうと、やさしく私の手をとって親指にマニキュアをぬりました。もっと他の指にもぬろうとすると、ママが、こわい顔で止めました。
「やめて。変なこと教えないで。みどりのマニキュアなんて、なんだか、気持ち悪いじゃない。自分の指でやればいいでしょ」
「私の指では、さんざんためしたわ。でも、だめなのよ。やはり、心の汚れてない人っていったら、わたしの回りでは、メグちゃんぐらいしか思い浮かばないのよ」
おばさんは、私の親指のマニキュアが早くかわくようにと、ふうふうと息をふきかけました。
「きれい。マニキュアってきれい」
私は、自分の親指の爪をみながら、つぶやきました。マニキュアをするのは、生まれて初めてです。それは、すきとおるような、きれいな、きみどり色でした。朝の露をいっぱいすった、やわらかな草の色でした。こんなきれいな草色なら、本当に花が咲くかもしれないと、わたしは、うっとりしました。
「だまされたのよ。しん子は、よくだまされるから。そんないんちきまじない師の話を、まにうけるなんて」
ママは、そんなふうに言って、つまらなそうにキッチンのほうにひきあげていきました。 おばさんは、そんなママの背中にアカンベーをしました。
「これだから、夢をなくした中年女はいやだね」
おばさんが、そう言って、わたしにわらいかけました。こういう時、わたしはどうしたら、いいのでしょう。ママと、おばさんの間にはさまって、ちょと、複雑な気分です。
「ああ、やっぱり、メグでもだめか」
おばさんが、あきらめかけた時、私の親指の先がむずむずしてきて、爪にぬったみどりのマニキュアが、少しふくらみました。
「お、おばさん」
わたしの胸は、どきどきしてきました。
「ね、いんちきじゃなかったよ。ほら、見て見て」
マニキュアのみどりいろが、おできぐらいにふくらんでいきます。
「え。わあ、うそー」
おばさんは、アイシャドウをたぷうり塗った目をおおきく見ひらいて、わたしの親指をみつめました。
二人の目の前で、みどりのふくらみが、プツンとわれて、小さな、小さな、針の先のような芽が顔をだしたのです。
「やったー」
おばさんは、そういって、私の手をとってとびあがりました。
「夢みたい。魔法みたい」
私は、もう一方の手の指で、その親指の芽にそうっとさわりました。芽は、小さくても針金のようにかたく、しっかりとしていました。
「だめ。そうっとしておいて。これから、花がさくんだから」
おばさんが、真剣な声でいいます。ただならぬ二人の様子に、ママもやってきました。ママが、わたしの指を見たときには、芽から、かわいい双葉がでた所でした。
「どう、ほ・ん・と・だったでしょう」
おばさんは、得意そうにいいます。ママは、始め、声もでないと言う様子で、私の親指もじいーっと見ていました。
「世の中、不思議なことってあるものね」
ママは、やっとのことで、それだけ言いました。
みるみるうちに、双葉は、四つにふえ、茎のさきには、かたいみどりのつぼみまで、つけました。どうやら、マニキュアの花は、成長がとても早いようです。この分なら、あっというまに花がさくのでしょう。
「あ、言い忘れたけど、このマニキュアの花には、もうひとつ秘密があるのよ」
おばさんは、わたしの親指のさきから、目をはなさずにいいました。
「秘密って」
わたしは、親指をゆらさないようにと、手に力をいれてました。でも親指は、そうしても興奮で、小刻みに震えてしまうのです。
「この花のあとにできる実のことなの。それこそ、不思議な力をもった実なんだって」
「不思議な力?」
「うん。その実を口にふくんで、ひとつだけねがいごとを言って、飲み込む。そうすると、どんなねがいでもかなうんだって。その実のおかげで、億万長者になった人もいるんだって。それから、なおらないと言われていた病気がなおった人も」
おばさんは、わたしとママの顔をのぞきこみながら、いいます。
「まさか」
ママは、目をぱちくりさせます。ママの目の前で、みどり色だったつぼみが、だんだん赤くなって、ふくらんでいきます。
「信じないのは、かってだわ。でもわたしは、もう、ねがいもきめてあるんだ」
おばさんが、きっぱりとそう言うと、ママは、少しあわてました。
「ちょっとまって。信じないなんて、言ってないでしょう。そうね。花がさくだけでも信じがたいことが本当になったんだから、その、ねがいごとっていうのも、案外、かなうかもね」
ママがそこまで言った時です。花びらがひらいたのです。つぼみの時は、血の色のように濃い赤が、花びらになると、淡いきれいなしゅういろです。どこかで、こんな色のビーズをみたっけ、私は、そんなことを考えました。でも、ママやおばさんは、もう、ねがいごとのことで夢中のようです。
「ね、しん子。そのマニキュアは、メグにおみやげにくれたものでしょう。それじゃ、その実もメグのものじゃない」
ママが、そんなことをいいだしました。
「そりゃ、マニキュアはメグにあげたけど、実はわたしにくれるわよね。ね。メグ」
おばさんは、わたしに笑いかけます。
「だめよ。ママにくれるのよね。メグ。もし、ママにくれたら、ママ、もっとひろい家に住みたいってねがいをかけるの。そうすれば、メグ、あなたも、広いお庭で遊べるわ」
「だめよ。そんなの。ずるいわ。ねえさんは、始め、全然、信じてなかったくせに」
「それと、これとは、話は、別よ。あんたには、わからない家庭の悩みってやつがあるんだから。その実、ママにちょうだいね」
ママと、おばさんは、にらみあっています。私は、ひやひやしてきました。
「ねえさんは、いつもそうやって、ずるいのよ。横取りの名人だわ」
「ちょっと、なによ。私が、いつ横取りなんかした」
「しょちゅう、していたわよ」
しん子おばさんは、口をとがらせて言いはりました。ママも顔を真っ赤にして、鼻をぴくぴくさせています。これじゃ、こどものけんかと同じです。
そんな間にも、マニキュアの赤い花は、しおれてきました。てんとう虫の羽のようにうすい花びらが、見るまにくしゃんとなっていきます。
「ああ。かれちゃう」
私は、思わずそう言いました。あまりにも早くしおれてしまうので、残念だったのです そんな時です。ママは、突然、しん子おばさんにむかって、おがむように手をあわせました。
「おねがい。ね、しん子、一生のおねがい。その実、私にちょうだい。もっと広い家に住みたいのよ。メグにピアノをかってあげられるような広い家に。宏さんの給料じゃ、とても、そんな家に住めないわ」
私は、びっくりしました。こんなに真剣な表情のママは、始めてです。でも、私は、心の中で、叫びました。
(やめてよ。ママ。そんなママ、みたくないよ。カッコワルすぎるよ。)
「いやよ。そんなかっこうしたって、だめよ。私だって、結婚のことをお願いしようと思ったんだもの。いいじゃない。ねえさんは、こんなかわいい、子供がいて、しあわせじゃない。それ以上は、ぜいたくよ」
しん子おばさんも。こわい顔をしてゆずりません。
「それなら、メグに決めてもらおうじゃないの。このマニキュアは、メグのおみやげでしょう」
ママは、提案しました。
「いいわ。そうしましょう」
しん子おばさんも、うなずきました。
とたんにわたしは、とってもまずい立場になってしまいました。いったいどうしたらいいのでしょう。どちらにあげても、どちらかからは、うらまれてしまう。
ママは、横から、わたしをにらみます。しん子おばさんは、とっておきの笑顔で、わたしを見つめます。
絶体絶命です!。
「あ、赤い実だ」
マニキュアの花は、しおれて、赤いちいさな花をつけました。ちょっと大きめのビーズの玉のような、きれいな花でした。
「メグちゃん」
「メグ!」
ふたりが、わたしの手をひっぱります。右からは、ママ。左からは、シン子おばさん。 わたしは、その瞬間、ふたりともきらいになりました。だって、わたしの気持ちなんかちっとも考えてくれないんだもの。
わたしは、ふたりの手をふりはらうと、夢中で、親指の先から赤い実をとりました。そして、さっさと口のなかにほうりこみました。
「きゃー」
「まあー。なんてことするの」
ふたりが、なにやら、さけんでます。
「ママとしん子おばさんがけんかしないで、仲良くしますように。それから、こんなマニキュアのこと、もう、忘れて」
わたしは、小さな声で、そういって、思い切って赤い実をのみこみました。赤い実は、かぜ薬のようににがい味がしました。
*
「ああ、飲んじゃった」
ふたりとも、この世の終わりといったほどがっかりした顔をしました。
「メグ、何おねがいしたの」
ママが、こわばった顔で聞きます。
「うん、そのね、あの・・・・」
「何よ。早く言いなさい」
おばさんも、さいそくします。
「あのね。おねがいするの、忘れちゃった。だって、ママもおばさんもとってもこわい顔をするんだもの」
わたしはうそをつきました。
「なあんだ」
ママは、ぺたんと床にすわりこみました。
「ああ、期待して、なんだか疲れちゃった。」 おばさんも残念そうです。
しばらくの間、ママもおばさんもつかれはてたように、ぼうっとしていました。
実をとった後、マニキュアの花はどんどの小さくなって、いつのまにか、ただのマニキュアにもどってしまいました。さっき、あんなきれいな花が、咲いていたなんて、うそのようです。わたしたちは、みんな、みどりのマニキュアの魔法にでもかかって、まぼろしでもみたのかと思うほどに。
「そうだ。今晩は、みんなで、おすしでも食べにいこうか。いつもねえさんにお世話になってるばかりだから。今夜は私がおごるわ」 しんこおばさんが、突然いいだしました。
「おすし。いいわね。この所食べてなかったから。昔、しん子とよく食べにいったけね。あなた、小さいときから食いしんぼうだったから」
「そう、そう、やせの大食いね。ねえさんは、すぐふとるけど」
そういって、ママとおばさんは、仲よさそうににっこり笑い合いました。
(赤い実の力だ。二人とも急になかよくなっちゃった。やっぱり不思議な力があるんだ。これは、ちょっとすごい)
私は、心の中でそう思い、にんまりとしました。もう、二人ともマニキュアのことなど忘れたように世間話しをしています。私は、テーブルの上にころがっているみどりのマニキュアをすばやくつかみました。
(もう、だれにもわたさない。これ私のおみやげだもん)
そう言って、手の中のマニキュアを、ぎゅうとにぎりしめました。
:
わたしの机の中には、あれから、ずっとみどりのマニキュアがはいっています。もう、一年近く、はいっています。でも、あの日以来、わたしが、マニキュアをぬってみても、花どころか、芽もでてきません。何度ためしてもだめなのです。
赤い実の不思議な力を知ってしまったわたしは、きっと欲張りになってしまったのでしょう。あの日のママやしん子おばさんみたいに。だから、マニキュアをぬっても、花が咲かないのです。
ただ、ママとしん子おばさんは、人がちがったように仲良くなりました。あれから一度もけんかしません。パパも、びっくりするくらい。
そう、マニキュアの力は、本当にすごいのです。
なかよくなったママとしん子おばさんみるたびに私は、複雑な気分です。こんなによくきく力だったのなら、もっとほかの願いをかければよかったと思ってしまうのです。
ピアノもほしかった。犬もかいたかった。もっと早くはしれるようになりたい。テストがなくなるってのもいいな。願いは、次から次へとうかんでくるのです。
「どうして、あんなことお願いしたんだろう」
机の中のみどりのマニキュアをみるたびそのことだけが、残念でたまりません。でも、こんな欲張りなことを考えいたら、私の爪からマニキュアの花は、一生、咲かないでしょう。
いつかまた、私が欲張りでなくなるその日まで、緑のマニキュアはなくならないであるでしょうか。でも欲張りでなくなった私は、赤い実をのみこんでどんな願いをかけるのでしょう。
私は、マニキュアのびんのすみきった緑色の中に、小さなため息をおとすのでした。
![]()
Copyright(C) Jnunko Akahane 1993
 トップページへもどる
トップページへもどる