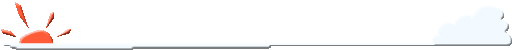
| 平成16年「障害者週間」 啓発事業講演会 「やさしい街・やさしい人」 平成16年12月7日 講師 石井 めぐみ(女優) 略歴 1958年生まれ 早稲田大学教育学部卒業 1979年松竹映画「夜叉ケ池」デビュ- 「噂の刑事トミーとマツ」 「おんな太閤記」出演 「オレたちひょうきん族」 レギュラー出演 1996年 長男の子育て ドキュメンタリー番組 「ゆっぴぃのばんそうこう」 (フジテレビ系放映) 現在 NHK教育テレビ新番組 「福祉ネットワーク」出演中 於 京田辺市立 中央公民館大ホール 主催 綴喜二市二町「障害者週間」 啓発事業実行委員会 |
||
| 平成11年9月に重い障害を持った長男ゆうとが亡くなって5年になりますが、この重い障害を持った息子からそれまで気がつかなかったこと関心のなかったことをたくさん教えられました。亡くなってしばらくは、そんな気は起きなかったのですが、それを伝えていかなくてはという気になって今日もお話しします。私の話の中から、普段お役に立つようなことを一つでも二つでもつかみ取っていただけたらと思っています。 まず、ゆうとは平成3年2月6日に計画出産というかたちで生まれました。計画出産というのは、出産予定日までに、医者と親とで産む日を決めて、その日に合わせて陣痛促進剤を用いて出産することです。そのとき私は体も小さいし、三十を超えていましたから、医者のいる昼間に産もうという、こちらの都合で計画出産という形をとりました。 前日から入院して点滴をしたらすぐ陣痛が始まりましたが、とっくにうまれてきてもよい時期がきても1日経っても赤ちゃんが出てこないんです。そこで引きずり出すようにして生まれました。赤ちゃんの泣き声がきこえないまま、救急車で国立小児病院に運ばれ、1週間で自分が退院して初めて赤ちゃんに会いに行きました。会おうとすると、看護婦さんが、とにかく先生の話を聞いてからにしてください、と止めるんです。 ゆうとは、肺の中に羊水をつめたまま生まれて来てしまいました。このような事故は、計画出産で時々起こるもんなんです。本来は、生まれてくる準備が赤ちゃんの側で出来ると、信号をお母さんに送るもんなんです。計画出産の場合、赤ちゃんの都合は関係なしに、子宮から急に追い出されそうになるものですから、赤ちゃんは出る準備が出来ていないもんで、あばれるんだそうです。あばれた時に羊水をガバガバのみこむのです。その羊水がお腹の中だけでなく肺の中までびっちり入ってしまったんです。産道を通るときから肺呼吸に切り替わるんですが、肺にまで羊水が入っているものですから、呼吸が出来なかったんです。呼吸ができないと、酸素が脳に送れませんから、脳の細胞がどんどん死んでいくのです。そういうことで、ゆうとの脳細胞は9割以上死んで重い障害になると言う話しを先生の口から聞いたのです。 その時はじめて「障害」という言葉を自分に身近な言葉として聞いたのです。それまでは、「障害」と言う言葉を深く考えたことがなかったのです。そこでMICU(新生児集中治療室)まで見に行きました。そうしたら50cmに満たない体の口の中や鼻の中や体中にチューブやコードがたくさん付いていたんです。最初見たときは、とても人間とは思えなくて、SFかなんかのサイボーグかなんかに見えてとても触ることができなかったんです。「先生このチューブはなんですか、とても苦しそうなんですが」と聞くと「この赤ちゃんはとても自力で呼吸出来ないので人工呼吸器なんです。」と言われました。 自分で呼吸が出来ないほど重い「障害」なんだと思って頭の中がパニックになってその日はどうやって帰ったか覚えていないんです。最初は、どうしてこんな重い障害を持っているのに助けたんだろうとか、いつあのチューブが外せるんだろうとか、死んだらどこへ埋めるんだろうとか。いろんなことが頭の中をぐるぐる回ったんです。 ものすごく落ち込んだのですが、3日目くらいには、気を取り直して、大きな本屋さんへ行き、ゆうとに関係しそうな本を何十冊も買ってきて読んだんです。その中の一冊に小さい時から刺激や訓練を与えれば、場合によったら健常児になるかも知れないということが書いてあったんです。そこで、自分は、その訓練をしてゆうとの障害を克服しようと決心したんです。 人工呼吸器を付けたままでも出来る限りいろんな刺激を与えました、動かせるところは何度も動かして、音や声を聞かせ触ったりしに病院へ行きました。そうしたら、1ヶ月で人工呼吸器を外せるまでになったんです。でも、まだ口からミルクを飲むことができなかったんです。本来の赤ちゃんなら吸着反応があって、口元になにか近づけたら吸う動作をするのですが、そういうことがまったくなかったんです。ですから、鼻のチューブから直接胃の中にミルクを入れていました。そこで、この鼻のチューブをとらなくちゃと思い今度は口からミルクを飲む訓練をしたんです。そうしたら、2ヶ月ほどして30CCのミルクを1時間かけて飲むことができるようになったんです。先生にはしかられましたが、それにもめげないで、なんとか、自分の家で面倒看たいので何度もお願いして4月の13日に退院することができました。 退院はできたもののゆうとは、鼻からチューブはつけたままだし、つばや疸を飲み込んだりはき出したりできないし、体温の調節もできなかったのです。部屋を35度に保っていないと体の体温が下がってしまうんです。それでも、家に帰ってきたのでよろこんで一生懸命面倒を看ました。 そこでテレビ局などで、情報を聞いて訓練する場所を東京だけでなく大阪や地方に足をのばし月曜から金曜まで訓練にあけくれました。そればかりか、1日に複数行けるときはスケジュールを組んでびっちり訓練をしました。そうすると先生もびっくりするほどよくなることもあったんです。 ところが1歳になったころガクンと調子が悪くなったんです。ゲーゲー吐いたり自分で呼吸を止めようとするんです。病院に行って診察をうけても特に病名がわからないのです。そうしたら、「なにか、ストレスを与えていませんか?」と先生に言われてハッと気が付いたんです。いつも訓練訓練だし、しかも普通は、お母さんのにこやかな顔を見て育つものなんですが、その時の私は、そんな余裕はありませんので、多分、目はつり上がって鬼のようだったんです。私は、障害が治っていくゆうとを好きだったので、障害児のままのゆうとを認めていなかったのです。それなら、このままゆうとが亡くなったら、この子は一体何の為に生まれて来たのかわからなくなってしまう。訓練訓練の辛い思いをするために生まれてきたことになってしまう。せっかく生まれて来たのに、障害を持ったままのゆうとをそのまま愛することができなければ、ゆうとの幸せにはつながらない。ようやく、そのことに気がつきました。 。 それからは、訓練を全て整理して、楽しみながらできるところを探しました。東京の多摩市にある訓練センターをみつけることができました。そこで、楽しく笑っている障害児を見てこれだと思い、家も多摩市に引っ越しして楽しく過ごすことができました。 私は、ゆうとからいろんなことを学びました。私一人だけの時は、みんな近寄って話しかけてくれるんですけど、鼻にチューブをつけた普通より長い車椅子に乗ったゆうとと一緒の時は、だれも話しかけてくれないばかりか、顔をそむけて遠ざかってしまうんです。それは、みんな重度障害者のことを知らないからだと思いました。そこで、よく知ってもらう必要を感じました。人は誰でも知らない物や事に対しては臆病になります。できるなら関わりたくないものなのです。でも、ちょっと知れば、あるいは知ろうと思えば、知ろうという気がおきれば、そんなに難しくないと思ったのです。 それで、生まれる前からのビデオが20巻もあったのでゆうとのことをなんとか、テレビで放送してもらえないかと思いました。そう思ったのには、もう一つ理由がありました。ダウン症の子供の腸が癒着していたのですが、その両親の賛同が得られなかったので、手術が遅れ、やっと賛同できたときには、体力がなくなっていて間に合わなかったということを聞いたからです。最初の時に手術をすれば十分助かったのですが、両親は、この子は障害児なので、将来希望がないのでそうっとしておいてくださいということだったのです。どうしても、障害のある子供を持った親には通るべき関門があると思うんです。一度は、こんな障害を持って一生を過ごすならいっそひと思いにと言う感覚に陥る瞬間はあるものです。それでも、我が子なんですから、一生懸命育ててみれば、いろんな楽しいことや喜びを与えてくれるんです。 ゆうとでも、指をチュパチュパと吸っているのを見たときは本当にうれしかったのです。それであのテレビを見てもらえれば、そういう普通ならなんでもないことが、喜びになるということを知って欲しかったのです。そもそも不幸とか幸せとかは、その人の考え方感じ方でかわるものなんです。幸せになろうとしたら、なれるんです。番組が終わって8年以上経つんですけど未だに手紙がとどきます。それは11万通を越えました。 困っていそうな方を見つけたら、ほんの一瞬でもよいですから立ち止まってみてください。そして目を合わせて見てください。そうしたら助けて欲しい場合は声をかけやすいんです。さっさと歩いて目を背けられると声を掛けられないのです。もし助けが必要でなかったら目をそらすはずです。そのときは何もなかったように通り過ぎてください。 2段以上の段差があるところは、車椅子ででかけられないのです。それでも、ちょっと助ける人がいるだけで、でかけることができるようになるんです。助けてくれる人がいれば、とりあえず行けるところまで行こうかという気になるのです。障害者の人が出てゆけるようになると、他のお年寄りや子供やいろんな立場の人がいて当たり前になるんです。日本は先進国のなかでハード面だけでなくソフト面が最も遅れているんです。障害者は20人に1人の割合で生まれているんです。この人達が、みんな街に出てきたら、もっともっとたくさんの障害者が街にでてきてもおかしくないんです。 多摩市や国立市では、たくさんの障害者が街にでていますし、障害者用駐車場では、障害者以外は駐車していません。また、エレベーターでも、障害者以外の方は乗っていないんです。他の街では、健常者が障害者用の駐車場に駐車したりエレベーターにのったりします。ですからこのような街では、車椅子をエレベーターにのせるのが大変です。このように障害者にやさしい街では、ベビーカーや妊婦やシルバーカートのお年寄りさらには歩行器を利用した人も暮らしやすいのです。 いろんな人が立場の違う人がお互いのことを考えることができるということが大切なんです。ほんのちょっとプラスの気遣いをすることで、もっともっと暮らしよい街づくりができると思うんです。 今日はお忙しいなか、お付き合いくださり、どうもありがとうございました。 |
トップページへもどる