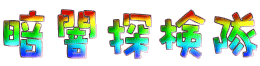守護天使たちは海に来ていた。 色々な出来事もあり、疲労している時に、隣人である忠治が海にいかないかと誘いに来たからである。 行くと決まり、そして海に行く当日。 忠治はなんと貨物トラックに乗って現れた。 貨物部にソファーやら絨毯やら冷蔵庫やら。 クーラーや、テレビやゲームも置いてあった。 どこから電気を供給するか悟郎が訪ねると、忠治は笑って言った。 『まぁ、いろいろ改造してあるからね』 とだけ答えた。 トラックの中を見た守護天使たちは大いに驚いた。 そんなこんなで、彼女たちは海に来ていた。 ただ、ちびっこトリオの、モモ、ナナ、ルルは、海岸を歩いていて、洞窟を見つけていた。
「ね、ねぇ、やめようよ、暗いし・・・・・」 そう言っているのはモモ、ちびっこトリオの最年長である。 控えめで赤面症の彼女は、常にルルとナナに振り回されてしまっている。 「何言ってるぉ〜?こんな所に洞窟があるなんて、お宝の匂いがするぉ〜」 と言っているのはルル、真っ暗な洞窟に好奇心を刺激されたのか、瞳をキラキラと輝かせている。 「そしたら、ご主人様に見せて、頭なでなでして貰うんだ〜♪」 嬉しそうに言うのがナナ、悟郎に褒められる場面を想像してうっとりとしている。 「で、でも・・・・暗いし・・・・・」 『モモお姉ちゃん怖いの?』 口調は違うがナナとルルの言葉が重なる。 「そ、そんなこと・・・・・・・ありません・・・・・・・けど」 最後の方は聞こえないほど小声になっている。 「よ〜し、それなら暗闇探検隊、出発らぉ〜」 「お〜」 いつの間に暗闇探険隊などと言う名前が決まったのかはわからないが、三人は一緒に洞窟の中に入っていった。 「うわ〜、真っ暗らぉ」 「本当だ、何にも見えないね・・・・・・・」 眼前に持ってきた自分の手も見えないほどの闇に思わず声を漏らす彼女たち。 「ふっふっふ〜、こんな事もあろうかと・・・・・」 ルルは懐中電灯を取り出した。 『おぉ〜』 ナナとモモが思わず手を叩く。 パチパチパチパチ ルルはニコニコと笑みを浮かべながら懐中電灯のスイッチを点ける。 パッ、と暗闇が削られ、ほんの一部が光に照らされる。 「け、結構広いですね」 モモが言う通り、洞窟はけっこう、と言うかかなり広く見えた。 自分たちが今居る場所はちょっとした広間になっていて、天井までは大体5メートルくらいありそうだった。 ルルは懐中電灯の光を移動させる。 前方に三つの前に進む道があった。 「右かなぁ?」 「左だとおもうぉ」 「も、モモは、真ん中だと・・・・・」 3人の間に火花が散る。 仕方が無いからじゃんけんをすると、ナナが勝った。 「わ〜い、ナナの勝ち〜♪ さっ、右にレッツゴ〜」 意気揚揚と先頭を歩くナナのうなだれたルルとモモがついてゆく。 その後も、幾度かの分かれ道をじゃんけんで決めたり、石を放り投げたり。 3人は順調に進んでいった。 ふと、いきなり洞窟が淡い光に包まれた。 洞窟を抜けたのかと3人は思ったが、違った。 「壁が・・・・・・光ってる?」 モモが不思議そうに洞窟の壁面を撫でると、手が光る。 光ゴケのようだ、壁一面に群生している光ゴケが淡い光を放っていた。 それを見たルルが、何を思ったか両手を壁の光ゴケにごしごしとこすりつける。 不思議そうに見ているナナとモモの方を振り返ると。 「シャイニングゴッドフィンガ〜らぉ〜」 ルルは一体何歳なのでしょう。 「あっ、面白い面白い、ナナもやる〜っ」 と、ナナもルルと同じように壁に手 ・・・・では無く、顔をこすりつける。 「見てみて〜、光る顔〜」 ナナの顔が光っている、はっきり言って怖い。 そのあとも、3人は、特にナナとルルは光ゴケを体にこすりつけ、気づいた時には全身からオーラの如く光を放つ2人が居た。 「コレなら懐中電灯いらないぉ」 と、ルルは電灯をしまう。 3人は再び進み出した。 オーラを放ちながら。 この洞窟はどうなっているのやら。 洞窟にありがちのコウモリの急襲が無い。 それどころか、コウモリが居ると言う痕跡すらなかった。 途方も無く広い大間に、枝分かれした道。 光ゴケの群生に・・・・・・ さらには、洞窟の奥。 光ゴケの群生地よりもっと先に進んだところである。 その場所の壁面は、まるで何かで磨き上げられたかのようにツルツルであった。 「わぁ〜、凄いよ、鏡みたいにツルツルしてるよ〜」 ナナが嬉しそうに壁面を撫でる。 何がそんなに嬉しいのかはわからないが、磨き上げられた壁面は、撫でられるたびに、きゅッきゅと小気味いい音を立てる。 すると、何を思ったか、ルルは爪を立てる。 「ルルたんもナナね〜たんみたいにいい音を出すぉ〜」 と、爪を立てたまま壁面をこする。 キィ〜、キュルルルルルルィィイキュイィイイ〜〜〜〜〜 盛大にアノ音が赤い文字で流れる。 しかも、3人が今居る場所は洞窟である。 洞窟の中では音が篭り、壁面に反射し、四方八方からイヤな音が三人に襲い掛かる。 3人は耳を抑えて悶絶した。 10分後3人は目を覚ました。 未だに耳に残るアノ音を忘れようと、仕切りに3人は頭を振り舞わす。 すると、音は忘れたが、今度は頭を振りすぎてふらふらと千鳥足になった。 バランスを保てない。 モモが倒れる。 その上にナナが倒れこむ。 さらにその上にルルが座り込む。 3人は痛む頭を押さえ、必死に頭痛が止むのを待った。 何やってんだかこの3人は。 どうやら、全く新しい発見に、3人のテンションも上がっているらしく、いつもはやらないような事をやってしまっている。 3人が洞窟の中に入って数時間後。 洞窟がかすかに振動する。 3人が怪訝そうに顔を見合わせる。 「大丈夫かなぁ・・・・・・・?」 「も、戻りましょうか?」 「帰り道わかんないぉ」 ルルの一言で洞窟の中の気温は一気に氷点下以下まで落ちた。 「ど、どうするんですかっ、帰り道わかんなかったら、モモ達帰れないですよっ」 珍しくモモが声を荒げる。 「だ、だって、ルルたんはモモね〜たんが道を覚えてると思ったから・・・・・」 ルルが目を潤ませながらナナを見る。 「な、ナナは、ルルが道覚えてるかと・・・・・」 その言葉を聞いて、モモがぺたりとその場に座り込む。 「も、モモね〜たん? そ、そうらぉ、懐中電灯が有ればなんとかなるかも知れないぉ」 ルルは懐中電灯を取り出し、スイッチを点ける。 数回の点滅のあと、懐中電灯は沈黙した。 洞窟を沈黙が覆う。 と、嗚咽の混じった声でモモが口を開いた。 「だから、だからここに入るのはイヤだったんですっ、出られなかったらもうご主人様に合えないんですよっ」 【ご主人様にあえない】 その言葉にルルもナナも瞳を潤ませる。 「ご主人たまぁ〜〜〜〜〜」 「合えないのはイヤだよぉ〜」 『わ〜〜〜〜ん』 3人は鳴き声の大合唱を始めた。 「あの・・・・・・・」 『わ〜ん』 「ちょっと・・・・・・・・・」 『うわ〜ん』 「あの、なぜ泣いているんです?」 『え〜・・・・・ん?』 聞き覚えの無い声に3人は泣くのをやめ、声のした方向を見る。 相変わらずの暗闇で何も見えない。 「え〜っと、ここがこうなって・・・・こうだから・・・出来ました」 その声はそう言ったその直後に、声の主が持っていた明かりが洞窟内を明るく照らした。 声の主は女性だった。 年齢は17歳前後であろうか、開いているのか閉じているのかわかりにくいその瞳のおかげで、とても柔和で優しい雰囲気を出していた。 「こんなところで、何をしているのです?」 女性がなおも尋ねる。 『そちらこそ』とは3人は言わなかった。 「あ、あの、迷っちゃったんです。入ったは良いけど出られなくなってしまって・・・・・・・」 モモがしどろもどろになりながらそう言う。 「そうですねぇ、あなた達のような小さなお子さんにはこの洞窟は迷います・・・・と言うより、出れなくなるでしょうね・・・・・・・・・・」 女性は、片手で明かり――ランタン――を持つと、もう片方を頬に当てて困ったような表情をする。 「どうすれば出られるぉ?」 ルルが言うと。 「戻るより先に進んだ方が良いですよ、こちらへ」 と、彼女はくるりと体の向きを変えると歩き出す。 3人も女性の後をとことこと付いて行く。 女性に連れられ、行き付いたところを見て、ちびっこトリオの3人は絶句した。 行き着く先、洞窟の最下層は海の中。 ガラス越しに海の中が眺める状態になっている。 さらに、非常識な事に。 「家・・・・・・・・・?」 洞窟の中に家が建っていた。 「さぁ、遠慮せずに、どうぞ」 彼女がそう促がすと、モモたちも恐る恐る家の中に入る。 「おじゃまします・・・・・・」 その3人を女性は笑顔で迎える。 一室に案内すると、ティーポットからお茶を注ぐ。 お茶の良い香りが洞窟探険で疲れたちびっこトリオの鼻腔をくすぐる。 とどめに、女性は3人の目の前にケーキを差し出した。 甘いケーキの誘惑に負け、3人はとうとうお茶とケーキに手を伸ばした。 3人が食べ終わるのを待って、女性が口を開いた。 「さて、聞かせてもらえます?どうしてこの洞窟に?」 ナナが答える。 「え、えっと・・・・・洞窟探険で、お宝があるかな・・・・って」 はぁ、と彼女が溜め息を漏らす。 「お宝はありませんよ。もぅ、この洞窟はただでさえ入り組んでいますから、私が来なかったあそこで骨になりますよ?」 『骨・・・・・・』 3人の背筋に冷たい物が流れる。 (現に年に五人ほど行方不明になっていますし) と、彼女は心の中で付け足した。 「ところで、貴方たちの名前は?」 女性がそう訊くと、3人は素直に答えた。 「モモです」 「ナナだよ」 「ルルたんらぉ」 「なるほど、モモちゃんに、ナナちゃんに、ルルちゃんですね」 彼女は一人一人顔を見て名前を覚える。 と、ふとモモの何かを訴える視線に気づいた。 「あっ、ごめんなさい、私はフィン、と言います」 「フィン・・・・・・?」 「えぇ、『フィン・フィッシュ・ブランフォード』がフルネームです」 「フィンさん・・・・・・?」 フィンがうなずく。 「そう呼んでください」 と言って、フィンがニッコリと微笑んだ。 先ほども書いたが、フィンの表情は常に柔和で、見るものを穏やかにさせてくれる。 フィンの笑顔は、ちびっこトリオ達も例外無く虜にした。 と、その時、洞窟内の、家が揺れた。 『きゃぁっ』 「これは・・・・・・」 ちびっこトリオが悲鳴を上げ、フィンの表情が険しくなる・・・・と言ってもさほど変わりないが。 「今の振動は・・・・・・・・・・・?」 「上では大騒ぎだぞ、フィン」 フィンの言葉に答える者が居た。 長身で、白銀の髪の毛、つり目で、きつい印象があるが、ちびっこトリオはそれほど怖いと言う感じは受けなかった。 「あら、ジョン?いらっしゃいませ、珍しいですね」 「マスターからの指示だ、即急に上に・・・・・・この娘達は?」 ジョンがちびっこトリオに気づいて言う。 「洞窟に迷い込んできたみたいです。ほおっておいたら大変だと思ったのでお招きしましたんですけど・・・・・・・」 「そうか、なら問題はないな、先ほども言ったが上は大変だ、手伝え」 「上が大変って?どうなっているんですか?」 フィンが訊くと、ジョンが複雑な表情を浮かべる。 「いや、色ボケ巨大ガニが、女性の海水浴客の水着奪って暴走してるんだ」 「なんです?それ」 フィンが呆れ顔と口調で言った。 「言ったとおりだ・・・・・が、マスターは『カニ鍋〜』と言っているぞ、手伝いに行くんだが・・・・・・・・・」 言葉を区切ってジョンがちびっこトリオを見る。 「留守番、頼めるか?」 ジョンが言うと、ちびっこトリオはこくこくと首を縦に振った。 「じゃぁ、頼むぞ、あ・・・・・家の中のものは適当に使って良いぞ、上が落ち着いたら迎えに来るから、まぁのんびりしててくれ」 ジョンはそう言うと、くるりと回れ右をして、家の奥に向かう。 その後をフィンも髪を揺らしながら付いて行く。 2人の後姿を見ながら、ちびっこトリオが相談を始める。 「そういえば、ここからどうやって出るんだろう・・・・・・」 「ひょっとしてあっちに出口があるのかなぁ?」 「ついていってみるぉ?」 と、3人はジョンとフィンの後をこっそりとつけて行くことにした。 家の奥に、池があった。 池と言うより、外の海に直接繋がっているだろうが。 ジョンとフィンは水の淵に立った。 何をするんだろうと、3人が壁から顔を半分だけ出して見ていると、フィンとジョンがその池の中に飛び込んだ。 「あっ!」 思わず声を上げてしまう、3人は慌てて口を抑え、池に近寄る。 池を覗き込むが、2人の姿はどこにも見えなかった。 3人はふと、洞窟に入る前に聞いた言葉を思い出した。 『ここの海に鮫が1匹だけ居る。まぁ、怖いだろうが、危険は無いから心配する必要は無い』 「心配する必要は無いって言ったのに・・・・・・」 「あの二人、さめたんに食べられちゃったぉ?」 「そんなぁ・・・・・・」 目の前で起こった出来事に3人は涙を流す。 10分後、呆然と水面を覗き込んでいた3人の目の前に水柱が上がる。 水滴が三人に降りかかる中で、水の中から一糸まとわぬ姿のジョンとフィンが現れた。 「あら?あなたたち、どうしてここに?」 フィンが不思議そうに3人を見つめると、さっき泣いたカラスがもう笑った。 「よかったっ、食べられたんじゃなかったんだねっ」 「心配しました・・・・・・」 「さめたんに食べられちゃったかと思っちゃったぉ・・・・」 3人の様子にフィンが苦笑する。 ジョンだけはなんだか不機嫌顔である。 「誰が食うか・・・・・・」 「あっ、そういえば、どうなったんですか?」 思い出したかのようにモモが訊ねる。 「上は終わったよ、カニはバラバラにして、今はカニナベの準備真っ最中だ」 ジョンがあっさりと答える、いつの間にやら服を着ている。 「さて、帰りますか」 フィンが言う、フィンもいつのまにか服を着ている。 髪は濡れたままだが。 「そうだな、カニナベの準備も手伝わんといけないし・・・・・・」 ジョンがちびっこトリオの頭を撫でる。 「どこから帰るか・・・・・・・・・・・」 ジョンが言うと、フィンが困ったような表情を浮かべる。 「そうですねぇ、この子たちが居るからここから行く訳には行きませんし・・・・・」 フィンが池を一瞥して溜め息をついた。 「仕方ない、作ったは良いけどつかってない直通エレベーターを使うか」 と言うと、ジョンが壁の一部分を押し込む。 すると、プシュゥッ、と空気が抜ける音がして、目の前の扉が左右に別れる。 「地上に直通エレベーターっ♪ 使ってない奴〜」 「はい、では、送り届けるのお願いしますね」 「ちょっと待て」 池のほうに歩いていこうとするフィンの襟首をジョンが掴む。 「どこに行こうとしてるのかなぁ〜?フィンさん」 「え、いや別に」 ジョンが睨むが、フィンは目をそらす。 「ね〜、速くいこ〜」 ジョンが振り返ると、エレベーターの中に乗り込む3人の姿が移った。 「ほら、ああ言ってる事ですし、では、よろしくお願いしますっ」 ジョンがフィンをつかむ手を離した瞬間、フィンは一瞬で跳躍し、池の中に飛び込む。 水面から首だけ出して、 「では、先に上に行ってますね」 と言ってフィンは水の中に消えた。 あっ、と言うちびっこトリオの目の前で、ジョンが乗り込み、エレベーターの扉を閉める。 エレベーターの内壁にジョンが手の平を当てると、少しの揺れの後に、エレベーターが動き始めた。 「たく、あいつ、速い方を取りやがって・・・・・・上でとっちめてやる」 ブツブツと呟くジョンの服を、クイクイとちびっこトリオが引っ張る。 ジョンが視線を下に向けると、何かを訴え掛けるような3人の顔があった。 ふっ、と息を吐いて、ジョンがかがんで視線を合わせる。 「なんだ?」 「あ、あの、フィン・・・・・・さんは水に飛び込んでしまいましたけど、大丈夫なんですか・・・・・?」 ジョンが3人の顔を見渡すと、軽く吹きだした。 「コレで出るより、泳いで出たほうが俺たちに取っちゃ速いんだ。だから何も心配する事はない」 コンコンと、ジョンがエレベーターの壁を叩く、すると今度はナナが言う。 「で、でも、ここって海の中じゃ・・・・・」 「ん?あぁ、水面下500メートルくらいだったかな?」 『ごっ、500メートルっ!?』 3人が同時に声を上げる。 「息が合ってるな、500メートルと言っても大したことはないぞ」 ジョンが笑う、その様子を頬を膨らませて3人が睨む。 「それに、ジョンたん、ルルたんと同じような感じがするぉ」 ルルが言うと、ジョンが意外そうな顔をして微笑む。 「まぁ、俺も・・・・・・・・・・と、そろそろ着くぞ」 ジョンがそう言うと、ちびっこトリオが感じていた【下に押し付けられるような感覚】が徐々に薄れて行った。 直後、今度は軽い浮遊感がし、入ってきたドアが空気が抜ける音と共に開かれる。 数時間ぶりの外の光の眩しさに3人は顔を覆った。 腕で顔を覆っている3人の背中をジョンが押して出るように促がす。 エレベーターは、海の近くの崖の上に地面から飛び出た状態で止まっていた。 3人を中から出すと、ジョンも降りると、何かのボタンを押す。 すると、音もなく扉が閉まり、エレベーターは地面へと消えた。 その後には、どこからどう見てもエレベーターがあるなどと判るようなものではなかった。 「す、すごいですね」 「凄いよ〜、全然わかんないよ〜」 モモは驚き、ルルとナナは地面をポコポコと叩いている。 叩いた感触も地面と全く変わらないように作られてあるため、無理もない。 ふと、モモが崖から下方を見る。 そこには・・・・・・・ 「あっ、ご主人様が居ます」 『えっ!?』 地面をしきりに叩いていたルルとナナが起き上がって、モモの側に立ち、同じように下方を見る。 『ご主人様〜〜〜〜〜〜〜っ』 3人が声を上げてしきりに腕を振るが、悟郎が全く気づく様子はない。 じれたルルが、ジョンに訊く。 「ここから降りるには、どうすればいいぉ?」 ジョンが奥の森を指して言う。 「そこから降りれるぞ、20分ほどかかるが」 聞くが否や、くるりときびすを返しルルとナナが走り去ろうとする。 「ちょっと待て」 ジョンがルルとナナの襟首を握って動きを止める。 二人は不満気に振り向いてジョンの顔を睨む。 「速く降りたいんだよな?」 ジョンが聞くと、2人はうなずく。 視線をモモに移すと、意を理解したモモもうなずく。 それを確認したジョンは、手を離して、モモを手招きする。 モモが不思議そうにジョンに近寄ると、ジョンはモモを右肩に担いだ。 「えっ?あの、あのっ?」 突然のジョンの行動ににモモは戸惑う。 「良いから、こっちの方が速い」 モモを担ぐと、ジョンは何も持っていないかのように軽がると立ち上がる。 「きゃっ」 落ちそうになるモモをジョンはしっかりと抱える。 「さて、お前たち二人は・・・・・・」 ジョンは2人を並ばせ、腰に左腕を回し、小脇に二人一緒に抱える。 「では、行くか、三人ともしっかりと掴まってろよ」 ジョンに抱えられている状態なのにどうやって捕まると言うのか、とりあえずジョンは言うと、崖下の砂浜の方へ体を向ける。 「あ、あの・・・・ちょっと?」 ずりずりとジョンがあとずさる。 「そ、それってまさか」 体を曲げ、足に力を入れ、ジョンが駆け出す。 「まさか、まさか、まさかっ!」 モモを背負って、ルルとナナを両腕に抱えながら、ジョンは高い崖の上から崖下の砂浜に助走をつけて飛び出した」 『キャァ〜〜〜〜〜〜っ』 三人の見事なまでの黄色い 「ハッハァ〜〜」 ジョンは嬉しそうにそんなことを言う。 「は、速いよっ。か、風が、強いよぉ〜〜〜〜」 「お、落ちちゃってるぉ〜、落ちたら地面に激突して潰れたトマトの出来上がりらぉ〜」 「イヤ〜、降ろして〜、離して〜。いや、降ろさないで〜、離さないで〜」 普通に感想を言うナナや、何気に恐ろしい事を言っているルル。 落下の恐怖に訳のわからないことを言っているモモなど、3人の反応は人それぞれであった。 また、落下の最中に、気を失うことができなかった事が、三人にとって幸せだったのか、不幸だったのかは、わからない。 3人の叫び声により、辺りに居た海水浴客は崖の上から飛び降りてくるジョンの姿を見つけた。 崖から急降下するジョンの落下速度は、ものすごい速さになっている。 ふと、ジョンは肩に抱えたモモに何かを耳打ちする。 ジョンから何かを耳打ちされたモモは青ざめ、ぎゅっとジョンの体にしがみつく。 すると、ジョンはモモの体を支える腕をゆっくりと放す。 そして、ジョンはその腕で地面に指し、何かを唱える。 『地に宿る重力よ、我に力を貸し与えたまえ・・・・・・・』 ジョンが唱えると 指先が光った。 数瞬の後、指先の光が消えると 再びジョンはその腕でモモを支える。 「悪いな、怖かったか?」 「あ・・・・・・・たり・・・・・・前です」 腕を放され、必死でジョンにしがみついていたモモが、鳴き声の混じった声で答えた。 「さて・・・・着くぞ、各自衝撃に備えろ」 と 言われたとしても何をすれば良いのやら、モモは肩に抱えられ、ルルとナナはジョンの小脇に抱えられ。 この状態でどうやって衝撃に備えろと!? と 3人は思ったが、あえて声に出さなかった。 声に出せなかった、と言ったほうが正しいのかもしれない。 そして、長い落下時間の終着点。 地面との対面が4人を待ち受けていた。 衝撃に備えろ、と言われたものの、何もすることができない3人は、とりあえずその瞳を硬く閉じる事にした。 来るであろう衝撃に備えて・・・・・・ 3人を抱えていたジョンは、3人の様子を交互に見るとクスリと笑った。 3人の予想に反して、着地の衝撃は全く無かった。 それどころか、衝撃どころか、着地の感覚すら無かったのである。 不思議に思って、まず気づいたのがモモであった。 ゆっくりと閉ざしていた瞳を開ける。 モモの目の前に、夕焼けの太陽に黄昏色に照らされる砂浜が映った。 ちなみに未だに肩に担がれている状態ではあるが。 ジョンはモモに気付いてか知らずか、担いだまま、抱えたまま、すたすたと砂浜を歩き始めた。 可愛い女の子3人を抱えたジョンは、あたり一体の海水浴客から当然の如く注目された。 その海水浴客の好奇の目に晒されながら、 (好奇の目に晒された理由が、3人の小さな可愛い少女を抱えていた所為でもあるが) 平然とジョンは砂浜を歩く。 すると、ジョンが歩いている方向から、悟郎と、他の守護天使たちが血相を変えて走ってきた。 「あっ、ご主人様っ」 モモが言うと、ジョンは黙って腰をかがめ、砂地にモモを下ろした。 小脇に抱えたナナとルルも同様に砂の上に下ろす。 『ご主人様〜』 嬉々としてナナとルルとモモの3人は悟郎に飛びつく。 その3人を、悟郎はやさしく受け止めた。 「俺の役割はコレにて終了・・・・・・と」 ジョンが言うと、悟郎が顔を上げてジョンの顔を凝視する。 そして言った。 「君が、この娘たちを守ってくれたんだね、ありがとう」 ジョンは目を丸くして驚く。 そして微笑んだ。 ジョンが何かを言おうとして口を開きかけると、突然砂浜に大きな声が響いた。 『お〜い、そんなところで何してる〜、カニナベできたぞ〜』 声のした方を見ると、フィンが頭の上で両手を振ってこちらを見ていた。 そのフィンのすぐ側で、小さな少女がぴょんぴょんと嬉しそうに飛び跳ねている。 そしてさらにその横で少女の頭をぐりぐりと撫でる、男がいた。 おそらく彼がさっきの声の主であろう。 そしてその側にはとてつもなく大きいナベが有った、これでカニを料理しているのであろう。 その3人を見ると、ジョンは、ふ、と笑った。 そして、ちびっこトリオの頭を撫でて、悟郎の目を見て、言った。 「今日は大サービスだ、カニナベ食べ放題、速く行かないとなくなるぞっ」 ジョンの言葉に触発され、守護天使の中の一人が疾風の如くUターンして鍋の方に走る。 「ちょっとクルミっ、アンタだけ食べるのは許さないわよっ」 「早い者勝ちれす〜」 「コレも運命かな・・・・・・」 各々が好き勝手に呟き、自分勝手に鍋の方に歩いていった。 ナナとルルも、そしてモモも、悟郎の服を引っ張って、『速く行こう』と催促する。 その様子に、悟郎は苦笑しながら、もう1度ジョンに頭を下げ、皆と同じ方に歩き出した。 ジョンはふたたび微笑んだ。 夕暮れの海は、黄昏色に染まり、銀色のその髪は、金色に染まる。 彼は夕焼けの太陽を見た。 果てしなく広がる海を、一色に染めるその大きな存在。 それに負けない存在が、彼には存在した。 彼は瞳を閉じ、何かを念じた。 果てしなく広大な海に、その思いを飛ばす。 瞳を開けると 彼は呟いた。 「カニ・・・・・・俺も大好物なんだよね」 そう言うと、彼は走り出した。 |