倭建命の年齢設定をめぐって
緒言
古事記における倭建命は、何歳の時に西征・東伐の旅に出発したものとして描かれているであろうか。
この点、日本書紀の日本武尊の場合は、次のとおり具体的な年齢が記されている。(記紀の引用は、日本古典文学大系本による。
ただし、引用にあたっては、字体を再現できず、別の字体に置き換えるなどしたものがある。)
○景行天皇二十七年十月(十三日)条
日本武尊を遣して、熊襲を擊たしむ。
時に年十六。
○同二十八年二月朔条
日本武尊、熊襲を平けたる状を奏して曰さく、・・・
○同四十年七月(十六日)条
天皇、群卿に詔して曰はく、「今東國安からずして、暴ぶる神多に起る。亦蝦夷悉に叛きて屢人民を略む。誰人を遣してか其の亂を平けむ。」とのたまふ。・・・
○同四十年十月(二日)条
日本武尊、發路したまふ。
○同四十年是歳条
既にして能褒野に崩りましぬ。時に年三十。
すなわち、景行27年に16歳で西征したことになっている。
従って、景行40年の東征時には29歳のはずであるが、同年是歳条の薨去時には「時に年三十」とある。
もっとも、同条の末尾には、
故、時人、是の三の陵を號けて、白鳥陵と曰ふ。然して遂に高く翔びて天に上りぬ。徒に衣冠を葬めまつる。因りて功名を録へむとして、即ち武部を定む。是歳、天皇践祚四十三年なり。
ともある。
ここから推察すると、景行四十年是歳条には、実は、景行40年~43年にかけての記事がまとめられており、その中で、日本武尊の薨去は、景行41年、30歳の時のこととして想定されていたのかも知れない。
なお、日本古典文学大系本の「是歳、天皇践祚四十三年なり。」の頭注には、
日本武尊の崩御が四十三年であることを示す。尊の東征中の個個の事件を年時に係けるのが困難だったため、東征開始の年時と、崩御の年時とのみを記したのであろう。
という解釈が見られる。
こちらが正解とすれば、景行43年、30歳で薨去ということになり、景行27年=16歳という設定とは、2歳ほどのズレが生じることになる。
計算違いか、数字の書き間違いか、何かしらかの錯誤があったことになろう。
いずれにせよ、日本書紀の年齢設定は、西征=16~17歳、東征=29~30歳(場合によっては32歳)ということになる。
ここで、古事記の方に目を転じてみると、次のような記述がなされている。
○景行天皇(小碓命の西征)段
是に天皇、其の御子の建く荒き情を惶みて詔りたまひしく、「西の方に熊曾建二人有り。是れ伏はず禮无き人等なり。故、其の人等を取れ。」とのりたまひて遣はしき。此の時に當りて、其の御髮を額に結ひたまひき。
○景行天皇(小碓命の東伐)段
天皇既に吾死ねと思ほす所以か、何しかも西の方の惡しき人等を擊ちに遣はして、返り參上り來し間、未だ幾時も經らねば、軍衆を賜はずて、今更に東の方十二道の惡しき人等を平けに遣はすらむ。此れに因りて思惟へば、猶吾既に死ねと思ほし看すなり。
○景行天皇(倭建命の薨去)段
是に倭に坐す后等及御子等、諸下り到りて、御陵を作り、即ち其地の那豆岐田那より下の三字は音を以ゐよ。に匍匐ひ廻りて、哭爲して歌曰ひたまひしく、
なづき田の 稻幹に 稻幹に 匍ひ廻ろふ 野老蔓
とうたひたまひき。是に八尋白智鳥に化りて、天に翔りて濱に向きて飛び行でましき。智の字は音を以ゐよ。爾に其の后及御子等、其の小竹の苅杙に、足■り破れども、其の痛きを忘れて哭きて追ひたまひき。(■=足+非)
古事記には、紀年もなく、年齢も書かれていないのであるが、西征の段に「其の御髮を額に結ひたまひき。」という記述が見える。
すでに本居宣長『古事記伝』(二十七之巻)が、
此は書紀崇峻巻【蘇我大臣馬子が、諸皇子及群臣を勸めて、物部大連守屋を討ところ】に、是時厩戸皇子束髪於額而隨軍後とありて細注に古俗年少兒年十五六間束髪於額、十七八間、分爲角子、今亦然之とあるが如し、かくて此は御齡の十五六に坐ことを如此申せるなり、
と注釈しているように、西征時には、15~16歳であったと認識されていたようである。
このことは、先ほどの日本書紀の設定とも符合している。
次に東征時の年齢についてであるが、古事記の東征の段には、「返り參上り來し間、未だ幾時も經(あ)らねば」と語られている。
※ 日本書紀においても、景行天皇四十年七月(十六日)条の日本武尊の奏言に、「熊襲既に平ぎて、未だ幾の年も經ずして、今更東の夷叛けり。」とある。
しかし、日本武尊の西征は、景行27年10月~28年2月のことであったから、12年ほどの歳月が流れており、通常、「未だ幾の年も經ずして」とは言えない状況である。
にもかかわらず、「未だ幾の年も經ずして」という文言が残ったのは、景行紀の紀年が割り当てられる以前に、そのような伝承が古くから行われていたことの痕跡であろう。
してみると、東征は、西征後、間もなくのことであり、16歳前後の少年のままの出征であったことになる。
ところが、続く薨去の段になると、突然、「倭に坐す后等及御子等」が現われて、白鳥と化した倭建命を追いかけている。
こちらの記載内容からすれば、倭建命は、東国への出征以前に複数の「后」と結婚し、複数の「御子」を儲けていたことになる。
この状況は、到底、15~16歳の少年のものとは思えず、むしろ、30歳前後の壮年とする日本書紀の設定と符合している。
以上のように、古事記の場合は、東征物語の最初と最後において、年齢の設定に食い違いが生じている。
このような齟齬は、最初から意図して作られたものではあるまい。
そもそも、倭建命の物語が幾つかの征討物語を集成したものであろうことは、多くの人が指摘しているところである。
例えば、井上光貞『日本の歴史1 神話から歴史へ』は、
「倭建」という名は、大和朝廷の勇者という普通名詞であり、この物語は、大和の勇者の数々の物語が、ながい年月を経るうちに一人の英雄に形象化されたものであろう。
と述べている。
年齢に注目した場合、物語が現在の姿に落ち着く以前に、少年皇族の物語と壮年皇族の物語が別々に存在していた段階があったと考えた方が自然であろう。
その少年皇族の物語と壮年皇族の物語は、それぞれどのような内容であったのか。
少しばかり推理をめぐらせてみることにしたい。
第1節
記紀が編纂された前後の時代、男子の成人と結婚は、何歳頃に行われていたのか。
その様子を、ある程度、窺い知ることができるのは、聖武天皇の場合であろう。
[聖武]=「和銅七年六月、立為皇太子。于時年十四。」(続紀:聖武即位前紀)
[聖武]=「皇太子加元服。」(続紀:和銅七年六月)
すなわち、14歳で元服している。
ただ、聖武天皇の場合は、他と比較して、若干、早めであったかも知れず、例えば、平城天皇の場合は、15歳で元服したことになってる。
[平城]=「皇太子加元服。」(続紀:延暦七年正月)
[平城]=「寳龜五年生於平城宮。」(後紀:平城即位前紀)
また、文武天皇の場合は、元服とは記されていないものの、15歳で即位しており、関連があるものと思われる。
[文武]=「受禅即位。」(続紀:文武元年八月)
[文武]=「天皇崩。」(続紀:慶雲四年六月)
[文武]=「文武天皇。三首。年二十五。」(懐風藻)
記紀が編纂された頃の14~15歳は、元服をする年齢であったようである。
おおよその感覚として、15歳前後で一人前という共通認識が形成されていたのであろう。
次に結婚であるが、聖武天皇の場合は、元服後、2年ほどで結婚していたようである。
[光明]=「天平応真仁正皇太后崩。・・・勝宝感神聖武皇帝儲弐之日、納以為妃。時年十六。・・・崩時春秋六十。」(続紀:天平宝字四年六月)
[称徳]=「天皇崩于西宮寝殿。春秋五十三。」(続紀:宝亀元年八月)
聖武天皇と光明皇后は同い年であり、16歳で結婚し、18歳のときに孝謙(称徳)天皇が生まれている。
※
なお、聖武天皇には、もう一人、県犬養宿禰広刀自という「夫人」もいた。
続紀(天平宝字六年十月条)には、「夫人正三位県犬養宿禰広刀自薨。・・・聖武皇帝儲弐之日、納夫人。生安積親王。・・・又生井上内親王・不破内親王。」とあり、やはり、皇太子時代に結婚していたことが知られる。
しかも、所生第一子と思われる井上内親王については、水鏡(巻下、光仁天皇)に、「寳龜三年に帝井上の后と博奕し給ふとて、・・・この后御年五十六になり給ひにき。」と伝えられている。
この記述が正確であれば、井上内親王は、養老元年の生まれとなり、孝謙(称徳)天皇よりも1歳年上ということになる。
従って、聖武天皇と広刀自との結婚は、14歳の立太子以降、16歳頃までのこととなる。
ただし、水鏡の語る年齢がどこまで信用できるものであるのかは、よく分からない。
さらに、聖武天皇以外の場合でも、おおよそ、17~18歳の頃には結婚していたように見える。
例えば、草壁皇子の場合は、19歳のときに元正天皇が生まれている。
[草壁]=「高天原廣野姫天皇、・・・天命開別天皇元年、生草壁皇子尊於大津宮。」(書紀:持統称制前紀)
[元正]=「太上天皇崩於寝殿。春秋六十有九。」(続紀:天平二十年四月)
また、文武天皇の場合は、19歳のときに聖武天皇が生まれている。
[文武]=「是年、夫人藤原氏誕皇子也。」(続紀:大宝元年是年)
天武九年生まれの元正天皇や大宝元年生まれの聖武天皇は、おそらく、第一子であろう。
ここから逆算すると、草壁皇子と文武天皇は、いずれも、17~18歳の頃には結婚していたことが推測される。
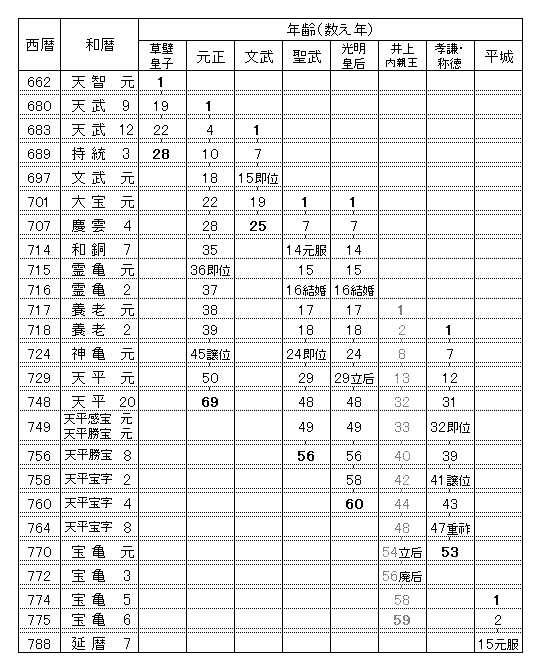
その当時の元服年齢が15歳前後とすると、即座に結婚したというわけではなく、2年前後の間隔をあけて結婚をしたということになろうか。
ところで、日本書紀(崇峻天皇即位前紀)には、
是の時に、厩戸皇子、束髪於額して、軍の後に隨へり。
という記事があり、「束髪於額」(ひさごはな)の細注には、
古の俗、年少兒の年、十五六の間は、束髪於額す。十七八の間は、分けて角子にす。今亦然り。
とあったわけであるが、この髪型の変化と記紀編纂の頃の様子とを比較してみると、「束髪於額」というのは、元服をする年齢に相当し、「角子」(あげまき)というのは、結婚をする年齢に相当しているように見える。
未だ、「年少兒」(わらは)と言われながらも、一人前の男子として認められるようになるのが、
15~16歳の頃であり、結婚適齢期が17~18歳の頃であったのだろう。→ 補注1
この年齢感覚は、聖徳太子の時代を越えて、もっと古くから存在していたように想像される。
おそらく、倭建命の物語が形成された当時に遡ってみても、16~17歳の少年は、一人前になったばかりの未婚の男子であって、そろそろ結婚適齢期に差しかかる頃合いの人物として認識されていたに違いない。
第2節
以上のように推定したうえで、古事記の東征物語の各要素を少年皇族の物語と壮年皇族の物語に分類してみると、次のようになると思われる。(日本書紀の東征物語も、大筋においては、古事記と変わらないが、上述のとおり、少年皇族の物語の痕跡は、古事記の方に、より色濃く残っている。)
[01] 天皇から東征を命ぜられる。
爾に天皇、亦頻きて倭建命に詔りたまひしく、「東の方十二道の荒夫琉神、及摩都樓波奴人等を言向け和平せ。」とのりたまひて、吉備臣等の祖、名は御鉏友耳建日子を副へて遣はしし時、比比羅木の八尋矛比比羅の三字は音を以ゐよ。を給ひき。
西征譚が少年皇族の物語であることは、間違いのないところであり、そこから引き続き東征を命ぜられたとする古事記の設定は、少年皇族のものとした方が自然である。
[02] 伊勢神宮で姨の倭比賣命に心情を吐露し、草那藝劒と御囊を授けられる。
故、命を受けて罷り行でましし時、伊勢の大御神宮に參入
りて、神の朝廷を拜みて、即ち其の姨倭比賣命に白したまひけらくは、「天皇既に吾死ねど思ほす所以か、何しかも西方の惡しき人等を擊ちに遣はして、返り參
上り來し間、未だ幾時も經らねば、軍衆を賜はずて、今更に東の方十二道の惡しき人等を平けに遣はすらむ。
此に因りて思惟へば、猶吾既に死ねと思ほし看すなり。」とまをしたまひて、患ひ泣きて罷ります時に、倭比賣命、草那藝劒那藝の二字は音を以ゐよ。を賜ひ、亦御?を賜ひて、「若し急の事有らば、茲の囊の口を解きたまへ。」と詔りたまひき。
この心情吐露の部分で、「返り參上り來し間、未だ幾時も經(あ)らねば」と語られているわけであるから、この部分は、少年皇族の物語に含まれていたとすべきであろう。
[03] 尾張の美夜受比賣の家に立ち寄り、さらに東国へ向う。
故、尾張國に到りて、尾張國造の祖、美夜受比賣の家に入り坐しき。乃ち婚ひせむと思ほしかども、亦還り上らむ時に婚ひせむと思ほして、期り定めて、東の國に幸でまして、悉に山河の荒ぶる神、及伏はぬ人等を言向け和平したまひき。
ここで、「乃ち婚ひせむと思ほしかども、亦還り上らむ時に婚ひせむと思ほして」というのは、結婚適齢期には少し早いという感覚が反映されているのかも知れない。
前後の話との続き具合からしても、少年皇族の物語とするのが相応しいように思われる。
[04] 焼津で騙され火攻めに遭うが、倭比賣命から授けられた品を使って危機を脱する。
故爾に相武國に到りましし時、其の國造詐りて白ししく、
「此の野の中に大沼有り。是の沼の中に住める神、甚道速振神なり。」とまをしき。是に其の神を看行はしに、其の野に入り坐しき。
爾に其の國造、火を其の野に著けき。故、欺かえぬと知らして、其の姨倭比賣命の給ひし囊の口を解き開けて見たまへば、火打其の裏に有りき。是に先づ其の御
刀以ちて草を苅り撥ひ、其の火打以ちて火を打ち出でて、向火を著けて燒き退けて、還り出でて皆其の國造等を切り滅して、即ち火を著けて燒きたまひき。故、
今に燒遣と謂ふ。
ここでは、[02]の倭比賣命から授けられた品物が重要な役割を果たしており、少年皇族の物語の続きとすべきであろう。
[05] 走水の海が荒れ、后の弟橘比賣命が入水する。
其れより入り幸でまして、走水の海を渡りたまひし時、其
の渡の神浪を興して、船を廻らして得進み渡りたまはざりき。
爾に其の后、名は弟橘比賣命白したまひしく、「妾、御子に易りて海の中に入らむ。御子は遣はさえし政を遂げて覆奏したまふべし。」とまをして、海に入りた
まはむとする時に、菅疊八重、皮疊八重、絁疊八重を波の上に敷きて、其の上に下り坐しき。是に其の暴浪自ら伏ぎて、御船得進みき。爾に其の后歌ひたまひし
く、
さねさし 相武の小野に 燃ゆる火の 火中に立ちて 問ひし君はも
とうたひたまひき。故、七日の後、其の后の御櫛海邊に依りき。乃ち其の櫛を取りて、御陵を作りて治め置きき。
ここで、急に「后」が出てくるのは、唐突である。
系譜によると、弟橘比賣命との間には、若建王という皇子もいたことになっている。
この部分は、壮年皇族の物語に由来すると想定される。
[06] 東(あづま)の荒ぶる蝦夷と山河の荒ぶる神等を言向け、帰路、足柄坂で「阿豆麻波夜」と歎く。
其れより入り幸でまして、悉に荒夫琉蝦夷等を言向け、亦山河の荒ぶる神等を平和して、還り上り幸でます時、足柄の坂本に到りて、御粮食す處に、其の坂の神、白き鹿に化りて來立ちき。
爾に即ち其の咋ひ遺したまひし蒜の片端を以ちて、待ち打ちたまへば、其の目に中りて乃ち打ち殺したまひき。故、其の坂に登り立ちて、三たび歎かして、「阿豆麻波夜。阿より下の五字は音を以ゐよ。」と詔云りたまひき。故、其の國を號けて阿豆麻と謂ふ。
ここで「あづまはや」と歎いたのは、やはり弟橘比賣を思ってのことであろうから、壮年皇族物語の続きとすべきであろう。
[07] 東(あづま)から甲斐へ入り、酒折宮で歌を詠む。
即ち其の國より
越えて、甲斐に出でま
して、酒折宮に坐しし時、歌曰ひたまひしく、
新治 筑波を過ぎて 幾夜か寝つる
とうたひたまひき。爾に其の御火燒の老人、御歌に續ぎて歌曰ひしく、
かがなべて 夜には九夜 日には十日を
とうたひき。是を以ちて其の老人を譽めて、即ち東の國造を給ひき。
この歌の中に見える新治や筑波などの地名は、「あづま」の領域に含まれるものであり、壮年皇族の物語からの続きとすべきであろう。
※
倭建命の物語の中に見える歌謡の多くは、元来、物語とは無関係に成立したものと思われるが、この場面に関しては、歌の唱和が主題であり、当初から歌謡が存在していたものと推定される。→ 補注2
[08] 甲斐から科野へ抜け、科野の坂の神を言向けて尾張へ戻る。
其の國より科野
國に越えて、乃ち科野の坂の神を言向けて、尾張國に還り來て、先の日に期りたまひし美夜受比賣の許に入り坐しき。
尾張へ戻ったのは、美夜受比賣と結婚するためであり、少年皇族の物語に戻ったとすべきであろう。
[09] 美夜受比賣と結婚する。
是に大御食獻りし時、其の美夜受比賣、大御酒盞を捧げて獻りき。爾に美夜受比賣、其れ意須比の襴意須比の三字は音を以ゐよ。に、月經著きたりき。故、其の月經を見て御歌曰みたまひしく、
ひさかたの 天の香具山 利鎌に さ渡る鵠 弱細 手弱腕を 枕かむとは 我はすれど さ寝むとは 我は思へど 汝が著せる 襲の裾に 月立ちにけり
とうたひたまひき。爾に美夜受比賣、御歌に答へて曰ひしく、
高光る 日の御子 やすみしし 我が大君 あらたまの 年が來經れば あらたまの 月は來經往く 諾な諾な諾な 君待ち難に 我が著せる 襲の裾に 月立たなむよ
といひき。故爾に御合したまひて、
これは、少年皇族の結婚物語とすべきであろう。
古事記においても、日本書紀においても、美夜受比賣との間に子をなした記述はないが、それは、倭建命が結婚後、間もなく薨去したことと無縁ではあるまい。
[10] 草那藝劒を美夜受比賣の許に置いて伊服岐山へ行く。
其の御刀の草那藝劒を、其の美夜受比賣の許に置きて、伊服岐能山の神を取りに幸行でましき。
これも前からの続きで少年皇族の物語とすべきである。
[11] 山中で判断を誤り、山の神に打ち惑わされる。
是に詔りたまひしく、「茲の山の神は、徒手に直に取りてむ。」とのりたまひて、其の山に騰りましし時、白猪山の邊に逢へり。其の大きさ牛の如くなりき。
爾に言擧爲て詔りたまひしく、「是の白猪に化れるは、其の神の使者ぞ。今殺さずとも、還らむ時に殺さむ。」とのりたまひて騰り坐しき。是に大氷雨を零らして、倭建命を打ち惑はしき。此の白猪に化れるは、其の神の使者に非ずて、其の神の正身に當りしを、言擧に因りて惑はさえつるなり。
伊服岐山の神に打ち惑わされたのは、草那藝劒を置いてきたことが原因であり、少年皇族の物語の続きである。
[12] 美濃から伊勢へ向う。
故、還り下り坐して、玉倉部の淸泉に到りて息ひ坐しし時、御心稍に寤めましき。故、其の淸泉を號けて、居寤の淸泉と謂ふ。
其處より發たして、當藝野の上に到りましし時、詔りたまひしく、「吾が心、恒に虛より翔り行かむと念ひつ。然るに今吾が足得歩まず、當藝當藝斯玖當より下の六字は音を以ゐよ。成
りぬ。」とのりたまひき。
故、其地を號けて當藝と謂ふ。其地より差少し幸行でますに、甚疲れませるに因りて、御杖を衝きて稍に歩みたまひき。故、其地を號けて杖衝坂と謂ふ。尾津の
前の一つ松の許に到り坐ししに、先に御食したまひし時、其地に忘れたまひし御刀、失せずて猶有りき。爾に御歌曰みしたまひしく、
尾張に 直に向へる 尾津の崎なる 一つ松 あせを 一つ松 人にありせば 大刀佩けましを 衣著せましを 一つ松 あせを
とうたひたまひき。其地より幸でまして、三重村に到りましし時、亦詔りたまひしく、「吾が足は三重の勾の如くして甚疲れたり。」とのりたまひき。故、其地を號けて三重と謂ふ。
ここは、地名起源説話を寄せ集めたような構成になっている。
美夜受比賣の許へ帰らず、伊勢へ向ったというのは不審であり、どちらかといえば、壮年皇族の物語とすべきであろうか。
地理的な観点からすると、「當藝野」と「尾津の前」は、尾張への帰路と言えなくもなく、この二箇所は、少年皇族のものとしても不都合は生じない。
[13] 伊勢の能煩野で薨去する。
其れより幸行でまして、能煩野に到りましし時、國を思ひて歌曰ひたまひしく、
倭は 國のまほろば たたなづく 青垣 山隠れる 倭しうるはし
とうたひたまひき。又歌曰ひたまひしく、
命の 全けむ人は 疊薦 平群の山の 熊白檮が葉を 髻華に插せ その子
とうたひたまひき。此の歌は、國思ひ歌なり。又歌曰ひたまひしく、
愛しけやし 吾家の方よ 雲居起ち來も
とうたひたまひき。此は片歌なり。此の時御病甚急かになりぬ。爾に御歌曰みたまひしく、
嬢子の 床の邊に 我が置きし つるぎの大刀 その大刀はや
と歌ひ竟ふる即ち崩りましき。爾に驛使を貢上りき。
尾張とは別方向の能煩野という場所と、次の要素との繋がりからすれば、壮年皇族の物語とすべきであろう。
[14] 倭から来た「后等及御子等」が御陵を作ると、命は八尋白智鳥となって飛び去る。
是に倭に坐す后等及御子等、諸下り到りて、御陵を作り、即ち其地の那豆岐田那より下の三字は音を以ゐよ。に匍匐ひ廻りて、哭爲して歌曰ひたまひしく、
なづき田の 稻幹に 稻幹に 匍ひ廻ろふ 野老蔓
とうたひたまひき。是に八尋白智鳥に化りて、天に翔りて濱に向きて飛び行でましき。智の字は音を以ゐよ。爾に其の后及御子等、其の小竹の苅杙に、足■り破れども、其の痛きを忘れて哭きて追ひたまひき。此の時に歌曰ひたまひしく、
淺小竹原 腰なづむ 空は行かず 足よ行くな
とうたひたまひき。又其の海鹽に入りて、那豆美此の三字は音を以ゐよ。行きましし時に、歌曰ひたまひしく、
海處行かば 腰なづむ 大河原の 植ゑ草 海處はいさよふ
とうたひたまひき。又飛びて其の礒に居たまひし時に歌曰ひたまひしく、
濱つ千鳥 濱よは行かず 磯傳ふ
とうたひたまひき。是の四歌は、皆其の御葬に歌ひき。故、今に至るまで其の歌は、天皇の大御葬に歌ふなり。故、其の國より飛び翔り行きて、河内國の志幾に留まりましき。故、其地に御陵を作りて鎭まり坐さしめき。即ち其の御陵を號けて、白鳥の御陵と謂ふ。
然るに亦其地より更に天に翔りて飛び行でましき。凡そ此の倭建命、國を平けに廻り行でましし時、久米直の祖、名は七拳脛、恒に膳夫と爲て、從ひ仕へ奉りき。(■=足+非)
すでに触れたように、明らかに壮年皇族の物語である。
ここで、少年皇族の物語に含まれていたと考えられる要素をまとめると、以下の8点になる。
[01] 天皇から東征を命ぜられる。
[02] 伊勢神宮で姨の倭比賣命に心情を吐露し、草那藝劒と御囊を授けられる。
[03] 尾張の美夜受比賣の家に立ち寄り、さらに東国へ向う。
[04] 焼津で騙され火攻めに遭うが、倭比賣命から授けられた品を使って危機を脱する。
[08] 甲斐から科野へ抜け、科野の坂の神を言向けて尾張へ戻る。
[09] 美夜受比賣と結婚する。
[10] 草那藝劒を美夜受比賣の許に置いて伊服岐山へ行く。
[11] 山中で判断を誤り、山の神に打ち惑わされる。
一方で、壮年皇族のものと思われる要素は、次の6点である。
[05] 走水の海が荒れ、后の弟橘比賣命が入水する。
[06] 東(あづま)の荒ぶる蝦夷と山河の荒ぶる神等を言向け、帰路、足柄坂で「阿豆麻波夜」と歎く。
[07] 東(あづま)から甲斐へ入り、酒折宮で歌を詠む。
[12] 美濃から伊勢へ向う。
[13] 伊勢の能煩野で薨去する。
[14] 倭から来た「后等及御子等」が御陵を作ると、命は八尋白智鳥となって飛び去る。
こうして見ると、東征物語の過半は、少年皇族の物語であり、その途中に弟橘比賣を同伴した壮年皇族の物語が挿入され、最後に、倭に妻子を残した壮年皇族の物語が付加された形になっている。
そもそも、西征物語も、すべて少年皇族の物語であったことからすれば、倭建命の物語の大半が少年皇族の物語として整理されることになる。
物語が記紀に見える形に集約される以前の段階では、
〔イ〕少年皇族の西征・東伐物語
〔ロ〕弟橘比賣を同伴した壮年皇族の物語
〔ハ〕倭に妻子を残した壮年皇族の物語
という三つの物語が、それぞれ独立して存在していたように思われる。
分量的には、〔イ〕の少年皇族の物語が圧倒的に多く、〔ロ〕と〔ハ〕の壮年皇族の物語は、断片的なものに過ぎなかったであろう。
なお、上記のような三つの物語が記紀に採録されるまでには、おおよそ、次のような経過を辿ったように想像される。
イ.少年物語─┐ ┌─古事記の物語
ロ.壮年物語─┼「少年・壮年混合物語」┤
ハ.壮年物語─┘ └─日本書紀の物語
ただし、イ、ロ、ハの物語は、一度に合成されたというよりは、順次、時間を置いて合成された可能性の方が大きいように思われる。
その順番としては、
(イ+ロ)+ハ
(イ+ハ)+ロ
(ロ+ハ)+イ
という三つのパターンが考えられるが、いずれとも決め難いというのが正直なところである。
やや、分かりづらいかも知れないが、図の灰色の部分は、この点を表現してみたものである。
第3節
上記分類によると、少年皇族の物語は、[11]の伊吹山の神に打ち惑わされたところで途切れているが、その後の展開は、どのようになっていたであろうか。
続く壮年皇族の物語では、薨去したことになっていることからすれば、少年皇族の場合も、おそらく薨去したことになっていたものと思われる。
その詳細は、不明とせざるを得ないが、ここで気になるのが家伝下(武智麻呂伝)の次のような一文である。
至坂田郡、寓目山川曰、吾欲上伊福山頂瞻望、土人曰、入此山、疾風雷雨、雲霧晦冥、群蜂飛螫、昔倭武皇子調伏東國麁惡鬼神、歸到此界、仍即登也、登欲半、爲神所害、變爲白鳥、飛空而去也、
ここでは、倭武皇子が伊福山の山中で神に害され、白鳥になって飛び去ったことが語られている。
山の神に惑わされる類例として、誰もが思い浮かべるのが、神武天皇の熊野山中での物語である。
古事記(神武東征段)によると、
故、神倭伊波禮毘古命、其地より廻り幸でまして、熊野村に到りましし時、大熊髮かに出で入りて即ち失せき。
爾に神倭伊波禮毘古命、倐忽かに遠延爲し、及御軍も皆遠延て伏しき。遠延の二字は音を以ゐよ。此の時熊野の高倉下此は人の名。一ふりの横刀を賷ちて、天つ神の御子の伏したまへる地に到りて獻りし時、天つ神の御子、即ち寤め起きて、「長く寢つるかも。」と詔りたまひき。
故、其の横刀を受け取りたまひし時、其の熊野の山の荒ぶる神、自ら皆切り仆さえき。爾に其の惑え伏せる御軍、悉に寤め起きき。
と語られている。
この「横刀」については、同段後文の細注で、
此の刀の名は、佐士布都神と云ひ、亦の名は甕布都神と云ひ、亦の名は布都御魂と云ふ。此の刀は、石上神宮に坐す。
と述べられているが、とにかく「横刀」の力によって、危機を脱している。
この物語と比較して推量すると、倭建命の場合は、草那藝劒を美夜受比賣の許に置いて「徒手」で立ち向かったために、剣の力を得ることができず、惑い伏したまま、その場で薨去したものと考えられる。
同様のことを述べているのが古語拾遺の次のような一節である。
日本武命、既に東虜を平げて還る。尾張国に至りて、宮簀媛を納れたまひて、淹く留まりて月を踰えたり。剣を解きて宅に置き徒行て胆吹山に登りて、毒に中りて薨ぬ。其の草薙剣は、今尾張国の熱田の社に在り。
この文章も、胆吹山の山中で薨じたように見える。
ただし、家伝下、古語拾遺、ともに、簡略な文章であるため、薨去の場所を省略している可能性は否定できない。
例えば、先代旧事本紀(天皇本紀、景行天皇段)では、
日本武尊平東夷。還參未參。薨於尾張國矣。
とも語られている。
そもそも、物語の流れからすれば、美夜受比賣の許へ帰ろうとするのが自然である。
尾張で薨去する筋書きが古くからあった可能性も否定できない。(とはいえ、草那藝劒を、再度、手にすることができれば、倭建命は復活できたであろうから、美夜受比賣の家の手前で薨去したことになろう。)
どちらが原形かは、不明とせざるを得ないが、少年皇族の物語には、伊吹山か尾張での薨去が語られていたと考えておきたい。
┌─── 家伝下・古語拾遺の物語
┌─「薨去場所の伝承」┴─── 先代旧事本紀の物語
│
イ.少年物語┴┐ ┌─ 古事記の物語
ロ.壮年物語─┼「少年・壮年混合物語」┤
ハ.壮年物語─┘ └─ 日本書紀の物語
ところで、古事記の西征の段において、熊曾建から、
汝命は誰ぞ。
と聞かれた少年皇族は、
吾は纒向の日代宮に坐しまして、大八嶋國知らしめす、大帶日子淤斯呂和氣天皇の御子、名は倭男具那王ぞ。
と答えている。
これは日本書紀(景行天皇二十七年十二月条)においても同様で、川上梟帥から、
「汝尊は誰人ぞ」
と聞かれて、
「吾は是、大足彦天皇の子なり。名は曰本童男といふ」
と答えている。
この「倭男具那」=「曰本童男」という名前は、「童男」の文字どおり、少年皇族そのものを指し示している。
記紀以前の独立した少年皇族の物語は、おそらく「倭男具那」の物語であり、西征の際に、「倭建御子」という名前を献呈されたことになっていたのであろう。
人物設定としては、未婚の男子であったが、結婚適齢期に差しかかっていた。
そのため、東征の際、美夜受比賣と結婚する筋書きとなっていたと思われる。
ただし、結婚後、間もなく薨去したため、子をなすことはなかった。
少年皇族の「倭建御子」は、このような人物として描かれていたと考えておきたい。
第4節
上記のような少年皇族の物語に対して、壮年皇族の物語は、大きく分けて、
〔ロ〕弟橘比賣を同伴した壮年皇族の物語
〔ハ〕倭に妻子を残した壮年皇族の物語
という二つの物語に分かれていたようである。
この両者は、同一人の物語というよりも、別々の物語として生成されたと考えた方が自然であろう。
このうち、〔ロ〕の弟橘比賣を同伴した壮年皇族は、どのような人物として語られていたのか。
その点に関連して、注意を引くのは、景行紀四十年是歳条(馳水の場面)の、
時に王に從ひまつる妾有り。弟橘媛と曰ふ。穂積氏忍山宿禰の女なり。
という弟橘媛の記事である。
これと、よく似た系譜記事が古事記(成務天皇段)にも見える。
若帶日子天皇、近淡海の志賀の高穴穗宮に坐しまして、天の下治らしめしき。此の天皇、穗積臣等の祖、建忍山垂根の女、名は弟財郎女を娶して、生みませる御子、和訶奴氣王。一柱
日本武尊の「妾」とされる「穂積氏忍山宿禰の女」=「弟橘媛」というのは、成務天皇の妃、「穗積臣等の祖、建忍山垂根の女」=「弟財郎女」というのと照応していると言うべきであろう。
しかも、景行記(倭建命の子孫段)の、
又其の海に入りたまひし弟橘比賣命を娶して、生みませる御子、若建王。一柱
という記事の中に見える「若建王」という御子と、成務記の「和訶奴氣王」という御子の名前も、かなり近い。
※
以上のような近似点については、すでに、本居宣長『古事記伝』(二十九之巻)が「和訶奴氣王」の注釈の中で、「さて、書紀には、此天皇には、御子坐まさ
ず、其に就て考るに、此は御外祖父の名、及御母の名も似たるに因て、倭建命の御子の、若建王と紛れて、此記と書紀と、傳の異はありしにやあらむ、」と指摘
している。
ここから、単純に推測すると、弟橘比賣を同伴した壮年皇族は、本来、即位前の成務天皇だったのではないかと思えてくる。
そう考えた時に都合が良いのは、常陸風土記の中で、倭建命が「倭武天皇」と表記されていることである。
ここで、“天皇”とされるのも、倭建命と成務天皇が混同されていたとすれば、ある意味、当然のこととなる。
名辞の「倭建」と「若帶日子」が似ているとは言えないが、東国では、両者を“亦名”で結び付ける伝承が存在していたのかも知れない。
なお、常陸風土記(総記)には、
或るひといへらく、倭武の天皇、東の夷の國を巡狩はして、新治の縣を幸過ししに、國造毘那良珠命を遣はして、新に井を掘らしむるに、流泉淨く澄み、尤好愛しかりき。
という文章がある。
一方で、同風土記(新治郡)には、
古老のいへらく、昔、美麻貴の天皇の馭宇しめししみ世、東の夷の荒ぶる賊俗、阿良夫流爾斯母乃といふを討たむとして、新治の國造が祖、名は比奈良珠命といふものを遣はしき。
という一文もある。
両者に見える、「毘那良珠命」と「比奈良珠命」は、おそらく同一人と思われる。
※ 古典文学大系本『風土記』の頭注によると、毘那良珠命は、旧事紀(国造本紀)に見える新治国造比奈羅布命とも同一人とされている。
そうして、前者によれば、「倭武天皇」は、毘那良珠命と同じ時代の人物となるが、後者で、比奈良珠命は、崇神朝の人物とされている。
この二つの命題を敢えて両立させると、「倭武天皇」は崇神朝の人物であるという結論が導出される。
もちろん、古老の伝承であるからには、この程度の齟齬は、当たり前であるし、そもそも毘那良珠命を建内宿禰のごとき長寿の人とすれば、問題も起らなくなる。
ただ、ここで、気になるのは、崇神朝という時代である。
崇神朝といえば、いわゆる四道将軍の記事が頭をよぎる。
記紀ともに同じような内容が書かれているが、古事記(崇神天皇、建波邇安王の反逆段)の場合で言えば、
又此の御世に、
大毘古命をば高志道に遣はし、其の子建沼河別命をば、東の方十二道に遣はして、其の麻都漏波奴麻より下の五字は音を以ゐよ。人等を和平さしめたまひき。
といった具合である。
すなわち、建沼河別命が東方十二道に派遣されたことになっている。
倭武天皇が毘那良珠命と同じ時代の人物とされた背景には、この建沼河別命に係る伝承があったのではないだろうか。
あまり強く主張できるものではないが、東国における成務天皇や建沼河別命の物語が混ざり合って、弟橘比賣を同伴した壮年皇族の物語へと変化していったものと考えておきたい。
ついでながら、常陸風土記(行方郡)に見える「倭武天皇」には、「大橘比賣命」という「后」がいたことになっている。
※ 同風土記(多珂郡)には、「橘皇后」という呼称も見える。
成務記に見える「弟財郎女」という名前と常陸国風土記の「大橘比賣」という名前から、それぞれ「弟」と「橘比賣」を抜き出して繋ぎ合わせると、「弟橘比賣」が出来上がる。
記紀の「弟橘比賣」は、存外に、「弟財郎女」と「大橘比賣」を重ね合わせることによって成立した名前であったのかも知れない。
それはともかく、〔ロ〕の弟橘比賣を同伴した壮年皇族の物語の原形をたずねると、かつて成務天皇や建沼河別命の物語が存在していたようにも思われるのである。
┌─── 家伝下・古語拾遺の伝承
┌─「薨去場所の伝承」┴─── 先代旧事本紀の伝承
│
イ.少年物語┴┐ ┌─ 古事記の物語
ハ.壮年物語─┼「少年・壮年混合物語」┤
成務天皇の物語?─┬ロ.壮年物語┬┘ └─ 日本書紀の物語
建沼河別命の物語?┘ │
└─「あづまの伝承」───── 常陸風土記の伝承
※ この図では、系線を引く都合で、〔ロ〕と〔ハ〕の位置を交替している。
さて、次に〔ハ〕の倭に妻子を残した壮年皇族の物語であるが、こちらは、いよいよもって、断片的な伝承となっている。
ここで歌われている四つの歌は、「今に至るまで其の歌は、天皇の大御葬に歌ふなり。」とされるものであり、この歌謡を除いて残るのは、倭から来た「后等及御子等」が御陵を作ったということと、倭建命の魂が「八尋白智鳥」となって飛び去ったという筋書きだけである。
ただ、その白鳥については、興味深い記事が日本書紀(仲哀天皇元年十一月条)に記されている。
群臣に詔して曰はく、「朕、未だ弱冠に逮ばずして、父の
王、既に崩りましぬ。乃ち神霊、白鳥と化りて天に上ります。仰望びたてまつる情、一日も息むこと勿し。是を以て、冀はくは白鳥を獲て、陵域の池に養はむ。
因りて、其の鳥を覩つつ、顧情を慰めむと欲ふ」とのたまふ。則ち諸国に令して、白鳥を貢らしむ。
こうしてみると、仲哀天皇は、白鳥となって飛び去った壮年皇族の子であったことが分かる。
先に「倭男具那」や「倭建御子」という名前が少年皇族に係る名前であったことを想定してみたのであるが、この白鳥となった壮年皇族(すなわち仲哀天皇の父)の名前は、何と呼ばれていたのか。
積極的に、これという名前は思い浮かばないのであるが、消去法でいくと、「小碓命」の名前が残されている。
ここでは、〔ハ〕の壮年皇族の名前を「小碓命」と考えておきたい。
伊勢に到るまでの経緯は不明であるが、とにかく〔ハ〕の壮年皇族は、能煩野で薨去して白鳥となったのではないだろうか。
先ほどの〔イ〕少年皇族の場合は、伊吹山で白鳥になったという伝承が発生していたように思われたわけであるが、この“白鳥”という共通点によって、伊勢で薨去した壮年皇族と伊吹山で薨去した少年皇族が同一視されるようになったとも想定できるのである。
第5節
倭建命の物語は、少年皇族の物語と壮年皇族の物語が混ぜ合わされていたように解されたのであるが、このような合成は、倭建命の系譜においても、行われているように見える。
景行記(倭建命の子孫段)の系譜を倭建命の系譜、息長田別王の系譜、若建王の系譜の3つに分けてみると次のとおりである。
[系譜1]倭建命の系譜
此の倭建命、伊玖米天皇の女、布多遲能伊理毘賣命布より下の八字は音を以ゐよ。を娶して、生みませる御子、帶中津日子命。一柱
又其の海に入りたまひし弟橘比賣命を娶して、生みませる御子、若建王。一柱
又近淡海の安國造の祖、意富多牟和氣の女、布多遲比賣を娶して、生みませる御子、稻依別王。一柱
又吉備臣建日子の妹、大吉備建比賣を娶して、生みませる御子、建貝兒王。一柱
又山代の玖玖麻毛理比賣を娶して、生みませる御子、足鏡別王。一柱
又一妻の子、息長田別王。凡そ是の倭建命の御子等、并せて六柱なり。
倭建命┬帶中津日子命
├若建王
├稻依別王
├建貝兒王
├足鏡別王
└息長田別王
[系譜2]息長田別王の系譜
次に息長田別王の子、杙俣長日子王。此の王の子、飯野眞黑比賣命。次に息長眞若中比賣。次に弟比賣。三柱
息長田別王─杙俣長日子王┬飯野眞黑比賣命
├息長眞若中比賣
└弟比賣
[系譜3]若建王の系譜
故、上に云へる若建王、飯野眞黑比賣を娶して、生める子、須賣伊呂大中日子王。須より呂までは音を以ゐよ。
此の王、淡海の柴野入杵の女、柴野比賣を娶して、生める子、迦具漏比賣命。故、大帶日子天皇、此の迦具漏比賣命を娶して、生みませる子、大江王。一柱此の王、庶妹銀王を娶して、生める子、大名方王。次に大中比賣命。二柱故、此の大中比賣命は、香坂王、忍熊王の御祖なり。
若建王 大帶日子天皇
‖─────須賣伊呂大中日子王 ‖─────大江王
飯野眞黑比賣 ‖────────迦具漏比賣命 ‖─┬大名方王
柴野比賣 銀王 └大中比賣命
この三つの系譜を個別に独立させて見ている分には、特に問題も起らないのであるが、[系譜1]と[系譜3]を繋げてみると、途端に不自然さが際立ってくる。
すなわち、倭建命の曾孫にあたる迦具漏比賣命を景行天皇が娶るというのは、常識的に考えてあり得ない設定である。
また、[系譜1]と[系譜2]によると、飯野眞黑比賣命は、倭建命の曾孫となる。
そして、[系譜3]によると、迦具漏比賣命は、飯野眞黑比賣命の孫となる。
従って、[系譜1]~[系譜3]を通覧すると、迦具漏比賣命は、倭建命の五世の孫ということにもなる。
その迦具漏比賣命を景行天皇が娶るというのは、前にも増して、あり得ない設定となる。
このような不自然さは、三つの系譜を合わせて考えることによって起ってくる。
本来、この三つの系譜は、繋ぎ合わせては、いけない系譜であったものと思われる。
なぜ、結合不可だったのか。
ひとつ考えられるのは、[系譜1]の若建王と[系譜3]の若建王が、元々、別人であったのではないかということである。
これについては、すでに、本居宣長『古事記伝』(二十六之巻)において、
されば、延佳が、迦具漏比賣爲景行之妃、不能無疑、蓋以孝靈之皇子、稚武彦命、誤爲倭建命乎、と云る、よく當れり、但爲倭建命乎と云るは然らず、此は倭建命の、御子の、若建王と彼若建彦命と、混ひつるなり、【名の同きを思へ】
と指摘している。(「稚武彦命」という名前は、孝霊紀に見えるものである。同一人を孝霊記では、「若日子建吉備津日子命」と記している。)
名前のよく似た「若建王」と「稚武彦命」を混同したというのは、あり得ない話ではない。
日本書紀(景行五十一年条)の日本武尊の系譜では、
初め、日本武尊、兩道入姫皇女を娶して妃として、稻依別王を生めり、次に足仲彦天皇、次に布忍入姫命、次に稚武王。・・・次妃穂積氏忍山宿禰の女弟橘媛は、稚武彦王を生めり。
とあって、日本武尊の子に「稚武王」と「稚武彦王」の二人がいたことになっている。(しかも、「弟橘媛」の子は、「稚武彦王」の方とされている。)
もし、混同があったとすると、[系譜3]の若建王の系譜は、実は、孝霊皇子「稚武彦命」の系譜であったという可能性が大きいであろう。
しからば、[系譜2]については、どのように考えるべきか。
こちらの系譜において、注目されるのは、杙俣長日子王である。
この王は、応神記(后妃皇子女段)に、
又咋俣長日子王の女、息長眞若中比賣を娶して、生みませる御子、若沼毛二俣王。一柱
品陀和氣命
‖──────若沼毛二俣王
咋俣長日子王─息長眞若中比賣
とあり、若沼毛二俣王の母方の祖父とされている。
しかし、応神紀(二年三月条)では、
次妃、河派仲彦の女弟媛、稚野毛二派皇子を生めり。派、此を摩多と云ふ。
譽田天皇
‖───稚野毛二派皇子
河派仲彦─弟媛
とあって、名前が微妙に食い違っている。
この「咋俣」(くひまた)か「河派」(かはまた)かという点で注目されるのは、上宮記一云の
凡牟都和希王 娶 洷俣那加都比古女子 名弟比賣麻和加 生児 若野毛二俣王
凡牟都和希王
‖─────若野毛二俣王
洷俣那加都比古─弟比賣麻和加
という系譜である。
ここに見える「洷」を何と読むかは、悩ましいところであろう。
諸橋『大漢和辞典』によると、「洷」(6-17418)の音は、
[1] チツ、ヂチ [2] チ
であり、意味としては、
[1] 川の名。 [2] うるほふ。㴛(7-17882)に同じ。
と説明されている。
従って、「くひ」とも「かは」とも読めないのであるが、ここで気になるのが「漢」という漢字である。
『五體字類』などを見ると、この「漢」という字の草書体の中には、「洷」に比較的近い形のものも存在している。(そもそも、「漢」の本字は、「𤁉」(7-18554)という形をしており、旁の下の部分が「土」の形をしている。)
見間違い、あるいは、書き間違いなどがあったとしても、さほど不思議ではない字形に見える。
かなり強引な想定ではあるが、もし「漢」であれば、「かは」と読むことが可能であるように思われる。
例えば、万葉集(巻第八、1518番歌)にも、
天漢 相向立而 吾戀之 君来益奈利 紐解設奈
(天の川 相向き立ちて 吾が恋ひし 君来ますなり 紐解き設けな)
とあり、「天漢」は「あまのがは」と読まれている。
若沼毛二俣王の外祖父は、河派仲彦の方が正解ではないだろうか。
いずれにせよ、河派仲彦と咋俣長日子は、本来、別人であった可能性が考えられる。
その場合、河派仲彦が若沼毛二俣王の外祖父であったのに対して、咋俣長日子の方は、飯野眞黑比賣の父であったのだろう。
この両者を混同・合成して成立したのが[系譜2]であったとすれば、万事、丸く収まる。
先の若建王の例も含めて、よく似た名前の混同が、しばしば、起ったものと考えておきたい。
※ 若沼毛二俣王の母の名前が、古事記では「息長眞若中比賣」、日本書紀では「弟媛」、上宮記一云では「弟比賣麻和加」という具合に三者三様であるのも、系譜に混同・混乱があったことを物語るものであろう。
見た目には、上宮記一云の「弟比賣麻和加」という名前の中に「弟媛」と「眞若」という二つの要素が含まれているので、
弟比賣麻和加┬→弟媛
└→息長眞若中比賣
という派生関係も想定できるように思われるが、定かではない。
ところで、「倭建」という名前は、熊襲建から奉られた通称であったし、「倭男具那」というのも、ずはり、少年(童男)を指し示す名辞であった。
双方ともに、実名というよりは、通称と捉えた方が理解し易い名称である。
記紀においては、「小碓」という名前のみが実名と考えても違和感のない名前となっている。
ただし、この名前は、既述のとおり、元来、壮年皇族の名前であったのではないかと推測されたのであった。
してみると、その壮年皇族の物語と結合する以前の段階では、少年皇族の“実名”が別に伝えられていたようにも考えられてくる。
そこで、景行天皇の皇子の中で、子孫の記述がない、少年皇族に相応しい人物を探してみると、小碓命の同母弟とされる倭根子命が目に留まる。
※ 古事記では、上記のとおりであるが、日本書紀では、景行二年三月条の一書に播磨稻日大郎姫の子として稚倭根子皇子が見え、同四年二月条では、八坂入媛の子として稚倭根子皇子が見える。
これは、単なる憶測に過ぎないのであるが、本来の少年皇族の実名は、「倭根子」として伝えられていたのかも知れない。
後記
景行天皇は、倭建命を西征・東伐へと派遣したわけであるが、それより早く、崇神朝には、いわゆる四道将軍が派遣されて、やはり、まつろわぬ人等を服属させていたのであった。
古事記(崇神天皇段)によれば、
又此の御世に、大毘古命をば高志道に遣はし、其の子建沼河別命をば、東の方十二道に遣はして、其の麻都漏波奴麻より下の五字は音を以ゐよ。人等を和平さしめたまひき。又日子坐王をば、旦波國に遣はして、玖賀耳之御笠此は人の名なり。玖賀の二字は音を以ゐよ。を殺さしめたまひき。・・・
是を以ちて各遣はさえし國の政を和平して覆奏しき。爾に天の下太く平らぎ、人民富み榮えき。是に初めて男の弓端の調、女の手末の調を貢らしめたまひき。故、其の御世を稱へて、初國知らしし御眞木天皇と謂ふ。
ということであるし、日本書紀でも、ほぼ同様のことが記述されており、崇神十年十月条には、
群臣に詔して曰はく、「今反けりし者悉に誅に伏す。畿内には事無し、唯し海外の荒ぶる俗のみ、騒動くこと未だ止まず。其れ四道將軍等、今急に發れ」とのたまふ。
※ 文中の「海外」については、日本古典文学大系本の頭注に、「畿内に対する畿外の意。海の外ではない。」という説明がある。
とあって、「四道將軍」の用語が使用されている。
この四道将軍の物語と倭建命の物語を地方征討譚として見ると、倭建命の物語は、二番煎じとまでは行かなくても、重複の感を免れないのであり、繰り返しの原因が気になるところである。
もっとも、この二つの物語の主要なテーマを再確認してみると、人々は、両者を同じ内容の物語とは考えていなかったのかも知れない。
すなわち、崇神朝の派兵が地方豪族を服属させるためのものであったとすれば、景行朝のそれは、やや性格の異なる軍事行動として認識されていたのではないかとも思われるのである。
例えば、倭建命の物語においては、「東の方十二道の荒夫琉神、及摩都樓波奴人等を言向け和平せ。」といった具合に「荒ぶる神」が、しばしば登場してくるが、このような神は、崇神朝の物語の中では見られないものである。
その「荒ぶる神」が何をしたのかと言えば、“渡”や“坂”などの交通の難所で、通行の妨げをしていたのであった。
そうしてみると、倭建命の派遣の理由は、支配領域の拡大と言うよりも、領域内の交通路の確保にあったのではないかと思えてくる。
交通を阻害する神というのは、現実には、そのような神を奉じた豪族の行為を反映したものであったのかも知れない。
いずれにせよ、安定的な通行の確保は、「男の弓端の調」や「女の手末の調」などの貢納を円滑に行うためにも必要不可欠のものであったはずである。
景行朝の派遣の目的がこのような点にあったとすれば、広い意味では、なお、支配領域の拡大という範疇に含まれているものの、細かく言えば、領域内の連絡路の維持に重点が移った段階での物語として認識されていたことになろう。
倭建命が派遣された東方十二道というのは、文字どおり道であって、支配と貢納のために必要な交通路として意識されていたのではないかとも考えられてくる。
それはともかく、“支配領域の拡大”という観点から見た場合、記紀の物語の大筋は、四道将軍の物語、倭建命の物語、そして、神功皇后の物語があって、一応の完成を見るという形になっている。
一方で、宋書倭国伝には、倭王武の上表文が載せられている。
その中の有名な一節を抜き出すと次のとおりである。
昔より祖禰躬ら甲冑を擐き、山川を跋渉し、寧處に遑あらず。東は毛人を征すること五十五國、西は衆夷を服すること六十六國、渡りて海北を平ぐること九十五國。
この一節と記紀を見比べてみると、記紀の物語の流れを、ごく簡潔にまとめたものが当該上表文であるように思える。
この点は、すでに多くの人によって指摘されており、例えば、坂本太郎『日本歴史全集2 国家の誕生』(132頁)では、
半島に出兵して、強国の高句麗と勝敗を争った兵力や、巨大な古墳を造ることのできた支配力などは、けっして、一朝一夕にしてできたものではあるまい。・・・後に、雄略天皇が宋の皇帝に送った国書に、
「祖先たちはみずから甲冑を着て、山川をかけめぐり、休むひまもありませんでした。東は毛人を征すること五十五国、西は衆夷を服すること六十六国、海を渡っては、朝鮮の国々を平らげること九十五国でした」
とあるのは、数字に誇張はあるとしても、代々の天皇が、国内の東西
の平定に力をつくしたことをよく物語っている。つまり、崇神天皇の四道将軍、景行天皇の東西巡幸、ヤマトタケルノミコトの熊襲や蝦夷の征伐など、物語の形
をもって伝えられるものは、こうした代々の天皇の国内平定が、段階をもっておこなわれた事実を、正直につげているのではなかろうか。
と解釈されている。
記紀と上表文の内容を比較した場合、両者の内容を無関係と言い切ることはできまい。
しからば、その関係は、どのように把握されるべきか。
製作年代という点からすれば、上表文の方が古く、記紀の方が新しいということになる。
とはいえ、上表文をもとにして記紀の物語が形成されたというわけにもいくまい。
おそらく、記紀の物語の原形となるものが先にあって、それが上表文にも影響を与えたと考えた方が自然であろう。
これを簡単な図式で表せば、次のようなことになろうか。
記紀の物語の原形┬───記紀の物語
│
└─倭王武の上表文
この図式の中に、上述の倭建命の物語の系統図を挿入すると、次のようになる。
イ.少年物語─┐ ┌─古事記の物語
ロ.壮年物語─┼「少年・壮年混合物語」┬─┤
ハ.壮年物語─┘ │ └─日本書紀の物語
│
└─倭王武の上表文
もっとも、“倭王武の上表文”への分岐点を図のように設定して良いものかどうかは、微妙なところであ
る。
もっと前の段階に設定するのが正解であるのかも知れない。
いずれにせよ、この分岐点の時代というのは、雄略朝のこととなる。
その時点で、すでに神功皇后の物語の原形も存在していたのだとすれば、倭建命の物語の原形も存在したとして、何ら不都合は生じない。
少なくとも、少年皇族の物語と壮年皇族の物語は、その頃までに成立していたのではないだろうか。
補注1 元服と成人
一般に、元服をするということは、成人になるということである。
従って、15歳前後で元服したのだとすれば、それは、15歳前後で成人したというのと同義であることになろう。
ところが、日本書紀(斉明天皇四年十一月条の或本云)を見ると、
方に今皇子、年始めて十九。未だ成人に及らず。成人に至りて、其の德を得べし
という一文がある。
これは、「或人」が有間皇子を諫めて言った時の言葉であるが、19歳を「未だ成人に及(いた)らず」としている。
この点、日本古典文学大系本の頭注には、
令制では二十一歳で授位任官する。
という簡単な説明がなされている。
明確な言及はないが、21歳が「成人」の年齢ということであろうか。
確かに、先ほどの崇峻紀の細注にも、
年少兒の年、十五六の間は、束髪於額す。十七八の間は、分けて角子にす。
とあって、15歳~18歳を「年少兒の年」の中に含めて説明している。
「年少兒」と「成人」は、あくまでも別の概念であろうから、上記の用例と説明からすると、20歳以下が「年少兒」、21歳以上が「成人」ということになる。
ただし、養老令(選叙令)を見ると、
凡そ位授けむは、皆年廿五以上を限れ、唯し蔭を以て出身せむは、皆年廿一以上を限れ。
という規定があり、授位の年齢としては、21歳というよりも、25歳の方が本来の年齢であったように見える。
また、漢語では、20歳を「弱冠」と言って、元服の年齢としていたわけであるから、このような知識も、当然、伝わっていたと考えられる。
つまるところ、「成人」の年齢を21歳として良いのかどうかは、判然としないのである。
そもそも、「元服」と「成人」の年齢が一致しないということになれば、記紀編纂の頃の人々が「元服」と「成人」を、それぞれ、どのようなものとして捉えていたのかも問題となってくる。
これらの点をどう考えれば良いのか、現状では、よく分からないというのが正直なところである。
補注2
歌謡を主題とする説話
古事記の東征物語の中で、歌謡を主題とする説話を探してみると、上記[07]の酒折宮での唱和の他に、[12]の美濃から伊勢へ向う途中の「尾津の前」における説話も挙げることができる。
この[12]の中には、「尾津の前」の他にも、「居寤の淸泉」、「當藝野」、「杖衝坂」、「三重村」という四箇所の説話もある。
これら四話は、いずれも地名起源説話となっているのに対して、「尾津の前」の部分だけが地名の起源に触れず、歌謡と詠歌の経緯を物語っている。
この部分のみが異質で、歌謡主体の説話となっていることは、誰の目にも明らかであろう。
ところで、日本書紀の東征物語(景行四十年是歳条)においては、歌謡が、ほとんど、見られないのであるが、その数少ない歌謡が、「酒折宮」における
新治 筑波を過ぎて 幾夜か寝つる
日日並べて 夜には九夜 日には十日を
という唱和と、「尾津濱」における
尾張に 直に向へる 一つ松あはれ 一つ松 人にありせば 衣著せましを 太刀佩けましを
という歌謡であった。
これらは、上記、歌謡主体の説話の歌と、図らずも、一致している。
当初から説話に含まれていた歌謡は、記紀ともに採録するところとなったようである。
おそらく、歌謡主体の説話は、記紀共通の物語の原形の段階で、すでに存在していたのであろう。
この点、古事記の東征物語の方にのみ見える歌謡は、本来、独立した歌謡であったことを容易に推測できるものが多い。
例えば、[13]能煩野の場面で歌われた「倭は 國のまほろば・・・」などの三歌は、日本書紀(景行十七年三月条)では、景行天皇が日向で歌った「思邦歌」(くにしのびうた)とされているし、[14]御陵を作る場面で歌われた「なづき田の・・・」などの四歌は、「今に至るまで其の歌は、天皇の大御葬に歌ふなり。」とされている。
印象としては、物語を彩るために、その場面に相応しい歌を選んで、後から挿入したもののように見える。
これらの歌謡は、記紀共通の物語の原形から古事記の物語の原形が分岐した後に挿入されたものであろう。
ついでに言っておくと、歌謡主体の説話は、歌謡と物語が強固に結び付いていたのに対して、主人公との結び付きは、比較的弱かったようである。
その典型例と言えるのが古事記(西征の段)の、
やつめさす 出雲建が 佩ける刀 黑葛多纏き さ身無しにあはれ
という歌謡を主題にした説話である。
この歌は、倭建命が出雲建を沐浴に誘い出して討ち取った時の歌とされているが、日本書紀(崇神天皇六十年七月条)には、
や雲立つ 出雲梟帥が 佩ける太刀 黑葛多卷き さ身無しに あはれ
という同じ歌があり、こちらは、出雲振根が弟の飯入根を沐浴に誘い出して討ち取った時の歌とされている。
主人公の名前は、簡単に入れ替えることができたようである。
参考文献
日本古典文学大系『日本書紀 上・下』(岩波書店、1965~67年)
日本古典文学大系『古事記・祝詞』(岩波書店、1958年)
『本居宣長全集 第十一巻、古事記伝 三』(筑摩書房、昭和44年)
井上光貞『日本の歴史 1 神話から歴史へ』(中公文庫、昭和48年)
新日本古典文学大系『続日本紀 一~五』(岩波書店、1989~98年)
新訂増補國史大系『日本後紀』(吉川弘文館、昭和57年、普及版)
日本古典文学大系『懐風藻・文華秀麗集・本朝文粹』(岩波書店、昭和39年)
『水鏡』(岩波文庫、1930年)
「家傳 下」(竹内理三編『寧楽遺文 下巻』、東京堂出版、昭和56年、訂正六版、所収。)
新撰日本古典文庫『古語拾遺・高橋氏文』(現代思潮社、1976年)
鎌田純一『先代舊事本紀の研究 挍本の部』(吉川弘文館、昭和35年)
日本古典文学大系『風土記』(岩波書店、1958年)
黛弘道「継体天皇の系譜についての再考」(同著『律令国家成立史の研究』、吉川弘文館、昭和57年、所収。)
『五體字類』(西東書房、平成26年、改訂第四版)
佐竹昭広 木下正俊 小島憲之『萬葉集 本文編・訳文編』(塙書房、昭和38~47年)
和田清石原道博編訳『魏志倭人伝・後漢書倭伝・宋書倭国伝・隋書倭国伝』(岩波文庫、1951年)
坂本太郎『日本歴史全集2 国家の誕生』(講談社、昭和43年)
日本思想大系『律令』(岩波書店、1976年)