間接的に天皇号の始用時期とも係わる推論二話
※ 本稿の二つの推論は、いずれも天皇号の始用に焦点を当てたものではない。
ただ、いくつかの用字や用語について推理を展開していく中で、
船王後墓誌や天寿国繍帳銘などの史料にも触れる部分があり、
それが結果的に天皇号の始用時期とも係わっているのである。
※ 本文の中で引用した史料等は、文末の参考文献に一括して掲げておいた。
なお、引用にあたっては、字体を再現できず、別の字体に置き換えるなどしたものがある。
第一話
古い紀年を持つ墓誌銘をめぐって
1.冠位
日本書紀推古天皇十一年十二月(五日)条には、
始めて冠位を行ふ。大德・小德・
大仁・小仁・大禮・小禮・大信・小信・大義・小義・大智・小智、并て十二階。
並に當れる色の絁を以て縫へり。頂は撮り總べて嚢の如くにして、縁を着く。
唯元日には髻花着す。髻花、此をば干孺と云ふ。
という記事が見える。
この冠位十二階は、朝鮮三国(高句麗、百済、新羅)の制度にその源流があると言われている。
例えば、井上光貞「冠位十二階とその史的意義」を見ると、
朝鮮三国にはどの国にも、
わが冠位に類したものがあり、推古の冠位十二階は本質的にそれと同じものである。
と述べている。
この「冠位に類したもの」を朝鮮三国では何と呼んでいたのか。
当の朝鮮半島においては、それを窺わせる史料は残されていないようである。
ただ、中国正史では、これを「官」と表現している。
(高句麗)
○魏志 高句麗伝
其官有相加、對盧、沛者、古雛加、
主簿、優台丞、使者、皁衣先人,尊卑各有等級。
○周書 高麗伝
大官有大對盧,次有太大兄、大兄、
小兄、意俟奢、烏拙、太大使者、大使者、小使者、褥奢、翳屬、仙人并褥薩凡十三等,分掌內外事焉。
○隋書 高麗伝
官有太大兄,次大兄,次小兄,次對
盧,次意侯奢, 次烏拙,次太大使者,次大使者,次小使者,次褥奢,次翳屬,次仙人,凡十二等。
(百済)
○周書 百済伝
官有十六品。左平五人,一品;
達率三十人,二品;恩率三品;德率四品;扞率五品;柰率六品。六品已上,冠飾銀華。
將德七品,紫帶;施德八品,皂帶;固德九品,赤帶;(李)〔季〕德十品,青帶;
對德十一品,文督十二品,皆黃帶;武督十三品,佐軍十四品, 振武十五品,克虞十六品,皆白帶。
自恩率以下,官無常員,各有部司,分掌眾務。
○隋書 百済伝
官有十六品:長曰左平,次大率,
次恩率,次德率,次杅率,次奈率,次將德,服紫帶;次施德,皂帶;次固德,赤帶;
次李德,青帶;次對德以下,皆黃帶;次文督,次武督,次佐軍,次振武,次剋虞,皆用白帶。
其冠制並同,唯奈率以上飾以銀花。
(新羅)
○隋書 新羅伝
其官有十七等:其一曰伊罰干,
貴如相國;次伊尺干,次迎干,次破彌干,次大阿尺干, 次阿尺干,次乙吉干,次沙咄干,
次及伏干,次大奈摩干,次奈摩,次大舍,次小舍,次吉土,
次大烏,次小烏,次造位。
こうして見ると、一瞬、朝鮮三国においても「官」と呼ばれていたのではないかという思いがよぎる。
ところが、倭国伝を見てみると、ここでも、
○隋書 倭国伝
内官有十二等:一曰大德,次小德,
次大仁,次小仁,次大義,次小義,次大禮,次小禮,次大智,次小智,次大信,次小信,員無定數。
とあって、「冠位」が「官」と表現されている。
中国正史の「官」は、日本や朝鮮三国の呼称をそのまま反映したものではなさそうである。
しからば、「冠位に類したもの」の呼称を探る手掛かりは、全く残されていないのかというと、そうでもない。
日本書紀には、次のような二つの記事があって、我々の注意を引くのである。
○天智天皇三年十月是月条
高麗の大臣蓋金、其國に終せぬ。
兒等に遺言して曰はく、「汝等兄弟、和はむこと魚と水との如くして、爵位を爭ふこと勿。
若し是の如くにあらずは、必ず隣に咲はれむ」といふ。
○天智天皇四年二月是月条
百濟國の官位の階級を勘校ふ。仍、
佐平福信の功を以て、鬼室集斯に小錦下を授く。其の本の位は達率なり。
前者には「爵位」、後者には「官位」という用語が見える。
これらの記事が書紀編者の創作であるようには見えないし、何かしらの原史料があったとすれば、
その用字を書き換えたようにも思えない。(もし、書き換えたとすれば、
同じ天智紀の近接する箇所に出現する両者は、同じ言葉で統一されていたのではないだろうか。)
特に、後者の記事に見える鬼室集斯は、
○日本書紀天智天皇十年正月是月条
大錦下を以て、佐平余自信・沙宅紹明
法官大輔ぞ。に授く。小錦下を以て、鬼室集斯學職頭ぞ。
に授く。・・・小山下を以て、餘の達率等、五十餘人に授く。
という記事の中にも見え、小錦下の授与が重出している。
坂本太郎「天智紀の史料批判」を見ると、
この両記事は元来
一つの事実から二つに分かれたものではないかと考える。
集斯だけが他の百済人からはなれて先に叙位せられたのではなく、
百済人への叙位はみな同時に行われたのであり、それは十年正月の記事のごときものであろうと思う。
そして四年の記事は集斯一個に関した別の史料からとられたのであろう。
と想定して、その年紀が二つに分かれた理由を
天智天皇の年紀は、
称制の年から数える仕方と即位の年から数える仕方との二通りがある。
という点に求め、
天智紀の史料には
この両様の年紀のものが混在し、編者が無雑作にこれを別々の年にかけたことが想像される。
と述べている。
これに従うと、天智紀の編者は、編纂にあたり、原史料にあまり手を加えることなく採録していたことになろう。
あくまでも推測に過ぎないのだが、「冠位に類したもの」を高句麗では「爵位」、
百済では「官位」と呼んでいた可能性は否定できないように思われるのである。
もちろん、このことは、他の用語が使用されていたことを否定するものではなく、
複数の用語が混用されていた場合など、さまざまな可能性が考えられる。
2.官位
さて、「冠位に類したもの」が百済では「官位」と呼ばれることがあったとすると、
それが日本の「冠位」の呼び名にも影響を与えていたのではないだろうか。
それというのも、船王後墓誌に、その「官位」という用語が見えるからである。
ここで、墓誌の全文を掲げてみると、次のとおりである。
惟船氏 王後首者是船氏中祖
王智仁首児 那沛故首之子也生於乎娑陁宮治天下 天皇之世奉仕於等由羅宮 治天下
天皇之朝至於阿須迦宮治天下 天皇之朝 天皇照見知其才異仕有功勲
勅賜官位大仁品為第三殞亡於阿須迦 天皇之末歳次辛丑十二月三日庚寅故戊辰年十二月殯葬於松岳山上共婦
安理故能刀自同墓其大兄刀羅古首之墓並作墓也即為安保万代之霊基牢固永劫之寳地也
この銘文からすると、墓誌の製作年代は、戊辰年(天智七年)のように見える。
(例えば、山尾幸久「古代天皇制の成立」は、この墓誌を天智七年のものと認めて、
「これが天皇号の初見史料だと考える。」と述べている。)
ところが、『日本古代の墓誌』の「各個解説」(東野治之)では、
文中に推古朝の十二階冠位の
一つである大仁をさして「官位」といっているのも墓誌の年代を考える上に注目される。
この場合の「官位」は位階と同義で、「官職の等級」という意味に他ならない。
ところで周知の通り天武十一年(六八二)以前の位階は冠を具体的な標識としており、
この伝統は位冠着用の廃止後も大宝令までは位階名称に残存した。従って大宝令前には、
位階をさして「冠位」とか「爵」「位」などというのが普通である。
これに対し「官位」という用語は、官職と位階とは対応すべきものという概念を反映した用語で、
官位相当制が制度として確立をみた八世紀以降にその用例が多くみられる。
もちろん『日本書紀』などに「官位」という語は数箇所みえるがほとんどの場合
「官と位」(官職と位階)の意に用いられており確実に冠位をさして
「官位」とよんでいる例は少ない。しかも「官の位」(官職の等級)という意味での「官位」は、
官制や官位相当制の整備過程を考えると、浄御原令以前の段階で一般的に行われていたとは考えにくいから、
『日本書紀』などの用例もあとからの追記である可能性が強いであろう。
と述べて、
この墓誌は少なくとも
天武朝末年以降に船氏の墓域を明示する意図もあって追葬されたと考える方がよいであろう。
と結論付けている。
墓誌の製作年代を考える上で、「官位」という用語が重要な指標として用いられているのである。
しかも、同解説では、
『日本書紀』などの用例も
あとからの追記である可能性が強いであろう。
と論定している。
確かに、日本の冠位の呼称に限定して考えれば、そのようなことも言い得るのかも知れない。
しかし、朝鮮三国の「冠位に類したもの」まで含めた場合は、どうであろうか。
先にも触れたように、天智紀の「百濟國の官位の階級を勘校ふ。」という一文は、
原史料の段階から、そうあったと考えた方が自然であるように感じられる。
墓誌銘の「官位」も、百済の影響を受けて記されたものではないだろうか。
およそ、白村江の戦役後、相当数の百済人が来朝したことは間違いのないところであり、
天智朝以降の文字使用に、そういった人々の影響があったとしても、何ら不思議はないのである。
なお、墓誌銘の問題の部分は、「勅賜官位大仁、品為第三」という表現になっている。
「官位」の「品」についても言及があって、この表記は、周書百済伝の
「恩率三品」などといった表記を思わせるものがある。
(船王後墓誌が周書の影響を受けているかどうかは、今のところ何とも言えない。
墓誌を戊辰年の製作とすれば、西暦668年、周書の完成は636年である。)
可能性を追求すれば、百済にあった“官位表”のようなものが、一方では、唐に伝わり、
一方では、日本に渡って影響を与えたという想定もできそうである。
3.尊称
ところで、船王後墓誌には、「王後首」、「王智仁首」、「那沛故首」とあって
「首」という称号が一貫して採用されている。
この点について、上記「各個解説」(東野治之)は、
なお船氏の姓は史であったから、
墓誌に「王後首」とあるのは尊称であろう。
と推測している。
朝廷から与えられた姓「史」を使用せず、私に「首」という尊称を採用したということであろうか。
このことは、正式?な名称である「冠位」を使用せず、
私に「官位」という用語を使用したこととも通底するものがあるように感じられる。
それから、もうひとつ、正式の姓以外の尊称を使用しているという点では、小野毛人墓誌も注目されるところである。
こちらの銘文には、「朝臣」という用語が使用されている。
飛鳥浄御原宮治天下天皇
御朝任太政官兼刑部大卿位大錦上小野毛人朝臣之墓 營造歳次丁丑年十二月上旬即葬
さきほどの「各個解説」(東野治之)の小野毛人墓誌の項を見ると、
ただこの墓誌が丁丑年(六七七)
に作られたかどうかについては、これを疑う説が有力である。即ち銘の文面には、
天武天皇をさすのに「飛鳥浄御原宮治天下天皇」という過去の天皇をさすような表現が用いられており、
「大錦上」や「朝臣」の姓も、『続日本紀』に「小錦中毛人」とあることや天武十三年(六八四)
に小野氏の姓が臣から朝臣に改められていることを考えあわせると、
贈位・改姓の結果に基くものとみられる。もしこの墓誌が葬送時のものとすれば、墓誌が土葬墓に伴った確実な例となるが、
上述の点から墓誌は少なくとも持統朝以降の追納とみるべきであろう。
と解説している。
一方、土橋寛「“飛鳥”という文字」では、この点について、
早く三宅米吉氏が論じたところで、
墓誌の「朝臣」は天武十三年賜姓の朝臣以前の尊称で(「たまきはる内の朝臣」=記、
七一の用例あり)、賜姓の宿祢以前に宿祢(足尼)の尊称があったのと同じであり、
「大錦上」は誤りでなく、『続紀』の小錦中の方が誤りであるとした(『考古界』三の三)。
『寧楽遺文』も威奈大村の墓誌の例をひいて、この説を支持している。
と述べて、「朝臣」は、“八色の姓”以前の尊称であると想定している。
船王後墓誌の「首」と比較してみると、この場合の「朝臣」も尊称である可能性は大きいとすべきであろう。
※ ついでながら、「各個解説」(東野治之)が「飛鳥浄御原宮治天下天皇」を
「過去の天皇をさすような表現」と述べている点についても一言触れておきたい。
確かに、この形式の通称は、過去の天皇に対して用いられている場合が大半であろう。
ただ、稲荷山古墳出土鉄剣銘を見てみると、「獲加多支鹵大王寺在斯鬼宮時」という表現があって、
多くの研究者が「シキの宮に在る時」と現在形に訓んでいる。すなわち、当代の「大王」に対して
「在斯鬼宮時」という表現がなされたという想定が許容されているのである。
そうすると、それと同系列の表現である「飛鳥浄御原宮治天下天皇」も、また、
“現在形”で使用される場合があったとして、何ら不都合は生じないのである。
なお、引用文中にあった威奈大村骨蔵器には、
小納言正五位下威奈卿墓誌銘并
序
卿諱大村檜前五百野宮御宇 天皇之四世後岡本聖朝紫冠威奈鏡公之第三子也・・・
とあって、「卿」という尊称が使われている。(文中「威奈鏡公之第三子也」とあるように、
父親には「公」という姓が使用されているが、大村本人には、一貫して、「卿」が使用されている。)
こうして見ると、正式の姓以外に私的な尊称を使用することが広く行われていたのではないだろうか。
(先代旧事本紀に見える「物部尾輿連公」などの「公」の場合も、
同様の尊称と言うことができるように思われる。)
さらに言えば、公式の歴史書である日本書紀にも、
・「蘇我稻目宿禰」(宣化元年二月、大化元年八月八日)
・「蘇我大臣稻目宿禰」(宣化元年五月、欽明二年三月、十二年十月、十四年七月、
十六年七月、十七年七月、十月、三十一年三月、用明元年正月)
・「蘇我稻目宿禰大臣」(欽明即位前紀、二十三年八月)
・「稻目宿禰」(推古三十四年五月、大化元年八月八日)
・「蘇我馬子宿禰」(敏達元年四月、十三年是歳、用明即位前紀、元年五月、崇峻即位前紀、
元年是歳、五年十一月、大化元年八月八日)
・「馬子宿禰大臣」(敏達四年二月、十四年八月)
・「馬子宿禰」(敏達十三年是歳、十四年六月、用明元年五月、崇峻五年十一月、大化元年八月八日)
・「蘇我大臣馬子宿禰」(敏達十四年二月)
・「蘇我馬子宿禰大臣」(用明二年四月、崇峻即位前紀)
・「大臣馬子宿禰」(推古即位前紀)
などとあって、蘇我氏の大臣に対して「宿禰」という尊称が用いられている。
(古い時代の「宿禰」については、尊称なのか、個人名の一部なのか、判別できないものが少なくない。
その中でも、特に、「小泊瀬造祖宿禰臣」(仁徳紀十二年八月)の場合は、
「宿禰」がそのまま個人名になっているように見える。)
これらの尊称は、私的という枠を越えて、公的に通用していたのかも知れない。
余談
蘇我氏の紫冠について
話のついでに蘇我氏に触れておくと、稲目と馬子の二代は、
大臣に任命されるとともに「宿禰」という尊称をもって呼ばれていたのであった。
ところが、日本書紀の中では、それに続く蝦夷と入鹿の二代については、この尊称が見られなくなる。
(ただし、紀氏家牒には、「蝦夷宿祢」と見える。)
そして、その代わりと言うわけでもあるまいが、蝦夷と入鹿には、紫冠を著用していたという記事が見られるのである。
○日本書紀皇極天皇二年十月(六日)条
蘇我大臣蝦夷、病に縁りて朝らず。
私に紫冠を子入鹿に授けて、大臣の位に擬ふ。復其の弟を呼びて、物部大臣と曰ふ。
大臣の祖母は、物部弓削大連の妹なり。故母が財に因りて、威を世に取れり。
おそらく、それまで蝦夷が被っていた紫冠を息子の入鹿に譲渡したのであろう。
この紫冠をどのようなものと解すべきか。
例えば、黛弘道「冠位十二階考」を見ると、
紫冠を冠位十二階の徳冠に当てるそれまでの通説を否定して、
紫冠が
大臣の位を表示するものであり、
且つそれは十二階冠位の制定以前から存在したものであろう・・・
と論じて、
かような冠も各家で
代々勝手に著用したのではなく、
一応天皇の認証を必要とする慣習があったのではあるまいか。蝦夷が私に紫冠を授けたということは、
とりもなおさず前代にはその著用に天皇の認可を必要としたことを物語り、従ってかような前例、
故実を無視したことが蘇我氏専横の一事例として国史に特記されたのであろう。
と推測している。
これに従うと、紫冠は、大臣位の表象であり、天皇の認証を必要とする公的なものであったことになる。
一方で、加藤謙吉『蘇我氏と大和王権』(160頁)は、
蝦夷の入鹿に対する紫冠授与
(入鹿への族長権継承の保障とその意思表明)
と述べて、括弧書きで簡潔にまとめている。
遠山美都男『大化改新と蘇我氏』(160頁)も、
また、紫冠を蘇我氏の族長位の象徴と見て、
蘇我氏の族長を誰にするかは
蘇我氏の族長である蝦夷の一存に任されているのであるから、これは決して非難には値しない。
と述べている。
これらに従うと、紫冠は族長位の表象であり、蘇我氏内部の私的なものであったことになろう。
※ なお、武光誠「冠位十二階の再検討」のように
「蘇我氏の横暴を示して蘇我氏を倒した鎌足を正当化するための造作」とする見方もある。
とはいえ、紫冠授与の部分に他の記事と矛盾するような不都合が存在するわけではない。
およそ、安易な記事の否定は、際限のない虚構論に陥る危険性がある。
別の合理的な解釈が可能である限りは、造作説を採るべきではあるまい。
つまるところ、現状では、紫冠を大臣位の表象と見るのか、あるいは、族長位の表象と捉えるのか、
二様の考え方が有力であるように思われる。
果たして、どちらを是とすべきか。
そこで、日本書紀に記述された、その後の蝦夷と入鹿を追ってみると、例えば、皇極紀三年十一月条に、
蘇我大臣蝦夷・兒入鹿臣、
家を甘檮岡に雙べ起つ。
とあるように、蝦夷は、依然として大臣のままであったように記されている。
これは、蝦夷の死に至るまで変わるところがない。
この書き振りからすると、譲渡されたのは、紫冠だけであったことになる。
先ほどの記事の中に「大臣の位に擬ふ。」とあることからすれば、本来は、
大臣位も譲りたかったのであろうが、それは出来なかったようである。
してみると、大臣位は、蝦夷の思いどおりにはならない公的なもの、紫冠は、
蝦夷の一存で譲渡可能な私的なものと言うことができるかも知れない。
もし、そうだとすれば、紫冠を族長位の表象とした方が、より自然な解釈となるであろう。
従って、それを譲渡した蝦夷の行為も、さほど非難を浴びるような行為ではなかったことになる。
ただ、宣化朝の稲目以来、蘇我氏の族長が大臣を兼ねるという慣行が成立していたとすれば、
結果的に、それを無視して、族長位と大臣位を分離させたことにはなろう。
※ また、一歩引いて考えてみれば、当時の族長位は、終身のものという慣行があったのかも知れない。
すなわち、それまで終身の地位であった族長位を蝦夷が始めて生前譲渡したという解釈も可能であろう。
前例のない行為であったがゆえに「私に・・・」といった表現がなされたようにも考えられる。
ところで、皇極紀二年十月(六日)条の後半部分、「復其の弟を呼びて、
物部大臣と曰ふ。・・・」という一文は、難解な文章である。
入鹿の弟については、他に、一切、所見がない。
そもそも、「物部大臣」が個人の通称となっているのは、「大臣」という称号が使用されているからであろう。
「大臣」が朝廷における具体的な地位・身分を表す称号であったがゆえに個人を特定できたのであり、
もし、不特定多数に付与される尊称・敬称の類であったならば、個人の特定までには至らなかったはずである。
その頃の朝廷において、「大臣」に任命されるのは、蘇我氏の族長に限られていたものと想定される。
上述のように、入鹿も、「大臣の位に擬ふ。」とはあるものの、実際に大臣に任じられたわけではなさそうである。
その当時の「大臣」といえば、蝦夷と解するほかあるまい。
そうすると、この記事には、やはり、何らかの錯誤があって、原文が正確に伝わっていないのではないかと推測されてくる。
おそらく、元々の文章には、「物部大臣」とは蝦夷のことであり、
蝦夷の母は物部氏の出身であった・・・といった内容が記されていたのではないだろうか。
第二話
天寿国繍帳銘の日付をめぐって
1.正朔
中国の名分論によると、中国に臣従した国は、中国の年号・暦を使用すべきものと観念されていたようである。
例えば、有坂隆道「古代史を解くカギ─暦の観点から─」を見ると、
中国の皇帝が周辺諸国の王に爵位・
称号を授けることを冊封と申しますのです。・・・冊封というのは、爵位・
称号を授けることだけではないのです。授けられたものは中国の皇帝の支配下にはいったのでありますから、
当然その「正朔を奉ずる」ことが必要であります。「正朔を奉ずる」という言葉は、
皇帝の統治に服する意に用いられます。それはなぜかというと、正は年のはじめ、朔は月のはじめ、
つまり正朔は暦のことで、中国では帝王が新たに国を建てると、新暦を天下に発布し、
国民にこれを遵奉させたからであります。
という説明がなされている。
そのことを明瞭に見て取れるのが、三国史記新羅本紀真徳王二年冬(西暦648年)の
使邯帙許朝唐。太宗勅御史問。
新羅臣事大朝。何以別稱年號。帙許言。曾是天朝未頒正朔。是故先祖法興王以來。私有紀年。
若大朝有命。小國又何敢焉。太宗然之。
という記事である。
この記事を信頼すると、唐の太宗は、新羅が独自の年号を使用していることを咎め、
新羅の使者(邯帙許)は、それに対して、中国が正朔(暦)
を頒布しなかったので独自の年号を使用していたのだという言い訳をしている。
その後、同王四年(西暦650年)条には、
是歳始行中國永徽年號。
という記事があり、唐の年号(永徽)を使用しはじめたことになっている。
その時までに、唐の暦(戊寅暦)が頒布されたということであろうか。
いずれにせよ、新羅は、文字どおり「中国の正朔を奉ずる」こととなったようである。
ただ、三国史記の伝えるとおりとすれば、真徳王の時代に至るまで、暦の頒布が行われなかったということにもなる。
そもそも、隋書新羅伝に、
其王本百濟人,自海逃入新羅,
遂王其國。傳祚至金真平,開皇十四年,遣使貢方物。高祖拜真平為上開府、樂浪郡公、新羅王。
とあり、旧唐書新羅伝にも、
其王金真平,隋文帝時授上開府、
樂浪郡公、新羅王。武德四年,遣使朝貢。高祖親勞問之,遣通直散騎侍郎庾文素往使焉,
賜以璽書及畫屏風、錦綵三百段,自此朝貢不絶。
とあるように、新羅の朝貢・冊封は、すでに隋の頃から始まっていたのである。
してみると、新羅においては、冊封されたものの、頒暦されなかった期間が存在したことになる。
暦に関する名分論は、あくまでも理念であって、現実と一致するとは限らないということであろう。
この点、百済の場合も、隋書百済伝に、
行宋元嘉暦,以建寅月為歳首。
とあって、隋の時代になっても南朝宋の元嘉暦を使用していたことが特記されている。
しかるに、肝腎の隋の暦(開皇暦・大業暦)を奉じたという記述は残されていない。
やはり、冊封と頒暦が、必ずしも、一体のものではなかったことを示唆するものであろう。
ここで、日本の場合に目を向けると、日本書紀に次のような記事が見える。
○欽明天皇十四年六月条
内臣名を
闕せり。を遣して、百濟に使せしむ。・・・別に勅したまはく、
「醫博士・易博士・暦博士等、番に依りて上き下れ。今上件の色の人は、正に相代らむ年月に當れり。
還使に付けて相代らしむべし。又卜書・暦本・種種の藥物、付送れ」とのたまふ。
○欽明天皇十五年二月条
百濟、・・・
仍りて德率東城子莫古を貢りて、
前の番奈率東城子言に代ふ。五經博士王柳貴を、固德馬丁安に代ふ。僧曇慧等九人を僧道深等七人に代ふ。
別に勅を奉りて、易博士施德王道良・暦博士固德王保孫・醫博士奈率王有■陀・採藥師施德潘量豐・
固德丁有陀・樂人施德三斤・季德進奴・對德進陀を貢る。皆請すに依りて代ふるなり。
(■=忄+夌)
○推古天皇十年十月条
百濟の僧觀勒來けり。
仍りて暦の本及び天文地理の書、并て遁甲方術の書を貢る。是の時に、書生三四人を選びて、
觀勒に學び習はしむ。陽胡史の祖玉陳、暦法を習ふ。大友村主高聰、天文遁甲を學ぶ。
山背臣日立、方術を學ぶ。皆學びて業を成しつ。
これらの記事からすると、もっぱら、百済から、暦、および、暦法を輸入していたように見える。
つまるところ、中国の冊封を受けなくとも、暦の輸入は可能だったのである。
当時の日本において、暦は、必要に応じて使用されたものであろう。
その時、「中国の正朔を奉ずる」といった名分論的な意識は、極めて希薄であったと推定される。
このことは、次に触れる年号の使用についても言えそうである。
2.年号
さて、那須国造碑の銘文を見ると、
永昌元年己丑四月、
飛鳥浄御原大宮那須國造追大壹那須直韋提、評督被賜、歳次康子年正月二壬子日辰節殄、・・・
とあって、冒頭に「永昌」という年号が使用されている。
『寧楽遺文』の解説には、
唐の則天武后永昌元年は、
己丑の歳であつて、我が持統天皇三年に當ることより推せば、
寧ろ此地方に移住した歸化人が彼の年號を用ひたものであらう。
という推定が述べられていて、おそらく、その通りなのであろう。
中国の年号を奉じるということは、上述のとおり、中国への臣従を意味し、
日本の朝廷を蔑ろにする行為と受け取られかねないようにも思えるのだが、当時は、
そのような感覚がなかったということになる。
日本において、その年は、持統称制三年にあたり、天武末年に建てられた「朱鳥」
という年号が通用していたか否か、微妙な時期である。(坂本太郎「白鳳朱雀年号考」は、
白雉年号について、「当局は、もとより代変りとともに、旧年号の廃止を認めたであろう。
しかし世人に対して、とくにその意思を表明することはなかった。」と想定しているが、
朱鳥の場合も、おそらく、天武天皇の崩御によって、自然消滅のような状態になっていたのであろう。)
日本の公的な年号が曖昧な状態にあった中で、私的に唐の年号が使用されるに至ったものと考えておきたい。
このように年号の私的な使用が想定されたところで思い起こされるのは、「法興」という年号である。
法隆寺金堂釈迦三尊像の光背銘に、
法興元卅一年歳次辛巳十二月
鬼前太后崩・・・
とあり、伊予国風土記逸文に引用されている“伊予温泉碑”の銘文にも、
法興六年十月 歳在丙辰 我法王大王
與惠慈法師及葛城臣 逍遙夷與村 正觀神井・・・
と記されている。
この「法興元」・「法興」という年号は、隋や朝鮮三国で行われたものでもなく、完全に私的な年号のようである。
※ 上宮聖徳法王帝説では、上記光背銘を引用した後に「釋曰、法興元世一年、此能不知也。
但案帝記云、少治田天皇之世、東宮廐戸豐聰耳命、大臣宗我馬子宿禰共平章而建立三寶始興大寺。故曰法興元世也。
此即銘云法興元世一年也。後見人若可疑年号、此不然也。・・・」という解釈を載せているが、
光背銘と温泉碑を見るかぎり、これは、やはり、年号と解した方が良さそうに見える。(補注1)
また、西琳寺縁起が引用する金堂阿弥陀仏造像記には、
宝元五年己未正月
二種智識敬造弥陀仏並二菩薩・・・
とあって、「宝元」という年号が使用されている。(井上光貞「王仁の後裔氏族と其の仏教」は、
この「宝元五年己未」を斉明天皇五年に当てている。)
※ なお、「宝元」という名称の由来については、田中卓「年号の成立─初期年号の信憑性について─」が
「“宝”の皇女と称された斉明天皇の“元”年に当つて、これを「宝元」と名付けたといふことは、
いかにも自然ではあるまいか。」と述べている。
この年号も、他に所見がなく、やはり、非公式に行われた年号と見られる。
もっとも、公式な年号といっても、大宝以前には、大化・白雉・朱鳥が断続的に行われただけてあり、
その当時の人々からすると、公私を区別する以前に、年号の使用自体に馴染みがなかったというのが実態であろう。
※ 田中卓前掲論文では、斉明即位前紀、および、天智即位前紀に「天萬豐日天皇、
後の五年の十月に崩りましぬ。」という一文があることに注目して、「孝徳天皇朝においては、
もともと、<「後」改元>であったのを、その後、日本紀撰上<(養老四年)>以前の或る時期に、
<「白雉」改元>に追号改筆されたものと推定する。」として、「大化」も含めて、
斉明朝の頃の追建と想定している。
3.暦日
ところで、年号の使用が上記のような状態にあったとすると、暦の使用も、また、
いくつかの暦が私的に使用される状況にあったのではないだろうか。
というのも、金石文等に見える日の干支は、
書紀・続紀の日の干支と一致しないものが少なからず見受けられるからである。
例えば、天寿国繍帳や太安万侶墓誌など、日付が一日ずれていることは周知のとおりである。
○天寿国繍帳銘
「歳在辛巳十二月廿一日癸酉日入孔部間人母王崩」 → 日本書紀の依拠した元嘉暦によると、
同日の干支は、甲戌となる。
○太安万侶墓誌銘
「以癸亥年七月六日卒之」 → 続日本紀によると、養老七年七月庚午(七日)に卒とある。
「養老七年十二月十五日乙巳」 → 続日本紀の依拠した儀鳳暦(定朔法)によると、
同日の干支は、丙午となる。
その原因としては、やはり、依拠した暦法の違いが疑われるのである。
天寿国繍帳の日付について言えば、飯田瑞穗「天寿国繍帳銘をめぐって」に、
現に当時の大陸の現行暦たる
「戊寅暦」によれば、十二月廿一日は癸酉となって、繍帳銘と一致するのである。
という指摘がある。
また、大谷光男『古代の暦日』では、一歩踏み込んで、
かくて、「辛巳十二月廿一日癸酉」は
戊寅暦の推算によったもの、正しくは当時伝来してきた戊寅暦そのものによったことがわかる。
と述べている。
すなわち、暦法を習得して、暦を製作・頒布するという公的な対応とは別に、具注暦のような形の、
製品としての暦が個別に輸入されて、私的に使用された場合も想定されるのである。
日本における暦の使用については、日本書紀持統天皇四年十一月(十一日)条に、
始めて元嘉暦と儀鳳暦とを行ふ。
という記事が見える。
この時、始めて元嘉暦と儀鳳暦が併用されたというのであるが、これは、
あくまでも日本国内で製作可能となった暦について述べたものであろう。
国外で製作された暦の輸入については、別途、考えてみる必要があるように思われる。
(大陸との間では、遣隋使・遣唐使以外にも、さまざまな形の往来があったと考えて間違いあるまい。)
当時の人々は、年号の場合と同様に、特に憚ることもなく、製品として将来した隋・
唐の暦を使用することがあったのではないだろうか。
※ ただし、輸入暦を毎年、安定的に入手できたか否かは不明である。
例えば、金沢英之「天寿国繍帳銘の成立年代─儀鳳暦による計算結果から─」は、
「他に戊寅暦が日本で使用された徴証は全く存在しない。」と指摘して、戊寅暦の使用に否定的だが、
この点については、暦の舶来が不安定で散発的な使用にとどまったため、
他に痕跡が残らなかったのだという説明も可能となるように思われる。さらに言えば、
確実な到着が見込めないため、国内での暦製作が志向されたとも考えられる。
なお、金沢論文では、繍帳銘の「癸酉」について、戊寅暦による推算以外に、
儀鳳暦(定朔法)で計算した場合にも癸酉となることを指摘して、
繍帳銘の成立年代を儀鳳暦の使用され始めた持統四年以降と想定している。
しかし、これに対しては、北康宏「天寿国繍帳銘文再読─橘大郎女と殯宮の帷帳─」に、
「明解な事実提示ゆえにその波紋は大きかったが、
実際のところは儀鳳暦で計算してみれば干支の一日のずれが発生しないという事実を示したにすぎず、
銘文そのものが儀鳳暦によったという積極的な根拠が示されているわけではない。・・・
一歩譲って儀鳳暦による換算を認めたとしても、日本書紀編纂以上に厳密な換算を行なうということは考えがたく、
金沢氏の依拠した複雑な定朔法を避けて、書紀と同様の平朔法が用いられたにちがいない。」という評言がある。
ちなみに、儀鳳暦(平朔法)で計算した場合の問題の干支は、元嘉暦と同じ甲戌となる。
(内田正男『日本書紀暦日原典』など参照。また、同書の「はじめに」では、定朔法の計算が複雑で、
平朔法と比べて数倍の手間がかかるといった点についても解説がなされている。)
※ ここで、太安万侶墓誌の方についても一言触れておくと、例えば、
黛弘道「太安万侶の墓誌と『続日本紀』」は、「つまり墓誌と『続日本紀』との一日のずれというのは、
類例が『類聚三代格』と『続日本紀』にいっぱいある。ですから決して珍しいことではない。」
として、「暦の違いだという解釈も可能であろうと思います。」と述べている。
ただし、使用暦を特定するまでには至っていない。
なお、蛇足ながら、日付のズレを根拠として天寿国繍帳銘を“偽作”とするならば、
太安万侶墓誌も同様に“偽作”としなければならないであろう。
このことは、また、太安万侶墓誌が“真作”であるとすれば、
日付のズレは“偽作”の根拠とならないことを意味しているようにも考えられる。
現状では、太安万侶墓誌を“偽作”とする議論は、あまり見かけないように思うのだが、
いかがであろうか。
補注 1
法興という年号について
法隆寺金堂釈迦三尊像光背銘に「法興元卅一年歳次辛巳十二月」とあり、また、
伊予温泉碑に「法興六年十月 歳在丙辰」と見えることから逆算すると、「法興」元年は、
崇峻天皇四年(辛亥)であったことになる。
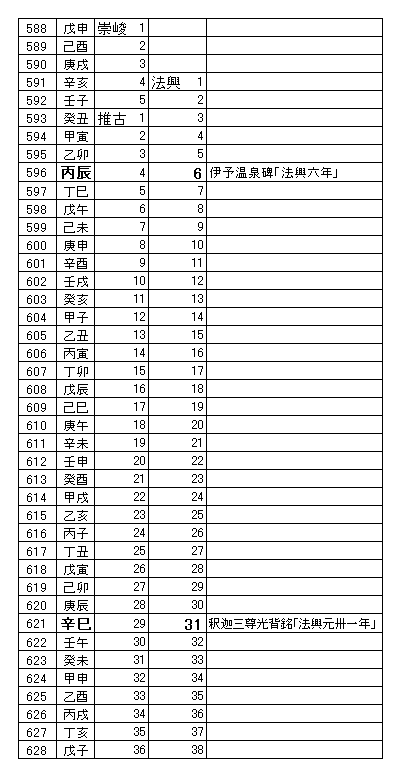
二つの史料の紀年が整合しているということは、
「法興」年号が一定の範囲の人々の間で実際に通用していたであろうことを示唆している。
(東野治之「法興年号と仏法興隆」も、釈迦三尊光背銘が造像当時のものであることを論じた後に、
伊予温泉碑についても触れ、「内容や用字にも不審がないとすれば、原型を損ねているとはいえ、
伊予道後温泉碑を疑う根拠は薄弱になる。まったく系列を異にする釈迦三尊光背銘と、
法興年号の年立てが合致することとも合わせ、推古朝の作と断定してよいと考える。」と述べている。)
それにしても、なぜ崇峻四年が「法興」元年とされたのか。
田中卓「年号の成立─初期年号の信憑性について─」は、
伴信友以来、これを「法興寺」の建立
と関係づけて説明する論が有力であるが、・・・私見では、「法興元」は、やはり通説に従つて、
法興寺の建て初められたその年を“元”として、それより算へて何年、といふ意味の表記であらうと思ふ。
と想定している。
ただ、日本書紀に見える法興寺関連の記事は、
○崇峻天皇元年是歳条
飛鳥衣縫造が祖樹葉の家を壊ちて、
始めて法興寺を作る。此の地を飛鳥の眞神原と名く。亦は飛鳥の苫田と名く。
○崇峻天皇三年十月条
山に入りて寺の材を取る。
○崇峻天皇五年十月是月条
大法興寺の佛堂と歩廊とを起つ。
○推古天皇元年正月(十五日)条
佛の舎利を以て、
法興寺の刹の柱の礎の中に置く。
○推古天皇元年正月(十六日)条
刹の柱を建つ。
○推古天皇四年十一月条
法興寺造り竟りぬ。
則ち大臣の男善德を以て寺司に拜す。是の日に、慧慈・慧聰、二の僧、始めて法興寺に住り。
という六件ほどであり、肝腎の崇峻四年に、法興寺について書かれた記事を見ることができない。
この点について、田中論文は、
日本紀は崇峻天皇の御代を“五年”
としてゐるが、これは踰年改元で、実際の即位は、用明天皇紀二年(丁未、五八七)八月甲辰の条に
「即天皇之位」と見えるから、“治天下”は足かけ“六年”となる筈である。ところが、
古事記にも法王帝説にも崇峻天皇の“治天下”は“四年”と記されてゐる。従つてここに、
紀年上の誤差が、一、二年認められるから、日本紀の〔崇峻天皇五年十月〕の条の記事は、
或いは「壬子」年ではなく、その一年前の「辛亥」年のことであるかも知れない。
と述べて、日本書紀の紀年に誤差のある可能性を指摘して、崇峻五年の
「大法興寺の佛堂と歩廊とを起つ。」という記事を崇峻四年のことかも知れないと推定している。
確かに、それも一案ではあるが、元興寺伽藍縁起に、
時聰耳皇子馬古大臣二柱
共起法師寺処以戊申年仮垣仮僧房作、六口法師等令住。
とあることを生かして、崇峻元年(戊申)に仮僧房が作られたと認定し、
・崇峻四年(辛亥)に至って、正式の僧房が完成したと推定。
・その時、「法興寺」という寺号が定められ、「法興」年号の使用も始まったと想定。
という推論も成り立ちそうである。
ただし、二重・三重の仮定のうえに組み立てた推論であり、強く主張できるようなものではない。
参考文献
日本古典文学大系『日本書紀 上・下』(岩波書店、1965~67年)
井上光貞「冠位十二階とその史的意義」(同著『日本古代国家の研究』、岩波書店、昭和40年、所収。)
『魏志』(“漢籍電子文献資料庫”、台湾中央研究院公開電子テキスト)
『周書』(“漢籍電子文献資料庫”、台湾中央研究院公開電子テキスト)
『隋書』(“漢籍電子文献資料庫”、台湾中央研究院公開電子テキスト)
坂本太郎「天智紀の史料批判」(同著『日本古代史の基礎的研究 上』、東京大学出版会、1964年、所収。)
「船王後墓誌」(『日本古代の墓誌』、同朋舎、昭和54年、所収。)
山尾幸久「古代天皇制の成立」(後藤靖編『天皇制と民衆』、東京大学出版会、1976年、所収。)
「小野毛人墓誌」(『日本古代の墓誌』、同朋舎、昭和54年、所収。)
土橋寛「“飛鳥”という文字」(同著『萬葉集の文学と歴史』、塙書房、1988年、所収。)
埼玉県教育委員会編『稲荷山古墳出土鉄剣金象嵌銘概報』(県政情報資料室、昭和54年)
「威奈大村骨蔵器」(『日本古代の墓誌』、同朋舎、昭和54年、所収。)
鎌田純一『先代舊事本紀の研究 挍本の部』(吉川弘文館、昭和35年)
田中卓「『紀氏家牒』について」(同著『日本国家の成立と諸氏族』、国書刊行会、昭和61年、所収。)
黛弘道「冠位十二階考」(同著『律令国家成立史の研究』、吉川弘文館、昭和57年、所収。)
加藤謙吉『蘇我氏と大和王権』(吉川弘文館、昭和58年)
遠山美都男『大化改新と蘇我氏』(吉川弘文館、2013年)
武光誠「冠位十二階の再検討」(吉川弘文館、昭和59年)
有坂隆道「古代史を解くカギ─暦の観点から─」(横田健一網干善教編『講座飛鳥の歴史と文学2』、駸々堂、昭和56年、所収。)
朝鮮史學會編輯『三國史記』(近澤書店、昭和16年、三版)
『旧唐書』(“漢籍電子文献資料庫”、台湾中央研究院公開電子テキスト)
「那須國造碑」(竹内理三編『寧楽遺文 下巻』、東京堂出版、昭和56年、訂正六版、所収。)
坂本太郎「白鳳朱雀年号考」(同著『日本古代史の基礎的研究 下』、東京大学出版会、1964年、所収。)
「法隆寺金堂釈迦三尊像の光背銘」(『飛鳥・白鳳の在銘金銅仏』、同朋舎、昭和54年、所収。)
日本古典文学大系『風土記』(岩波書店、1958年)
家永三郎『上宮聖徳法王帝説の研究 増訂版』(三省堂、昭和48年)
(荻野三七彦)「河内國西琳寺縁起(公刊)」(『美術研究』79号、昭和13年)
井上光貞「王仁の後裔氏族と其の仏教」(原島礼二編『論集日本歴史1大和王権』、有精堂、昭和48年、所収。)
田中卓「年号の成立─初期年号の信憑性について─」(同著『律令制の諸問題』、国書刊行会、昭和61年、所収。)
飯田瑞穗「天寿国繍帳銘の復元について」(同著『聖徳太子伝の研究』、吉川弘文館、2000年、所収。)
「太安万侶墓誌」(『日本古代の墓誌』、同朋舎、昭和54年、所収。)
飯田瑞穗「天寿国繍帳銘をめぐって」(同著『聖徳太子伝の研究』、吉川弘文館、2000年、所収。)
大谷光男『古代の暦日』(雄山閣、昭和51年)
金沢英之「天寿国繍帳銘の成立年代─儀鳳暦による計算結果から─」(『国語と国文学』78-11、2001年)
北康宏「天寿国繍帳銘文再読─橘大郎女と殯宮の帷帳─」(『文化史学』62号、2006年)
内田正男編著『日本書紀暦日原典』(雄山閣、昭和53年)
黛弘道「太安万侶の墓誌と『続日本紀』」(同著『物部・蘇我氏と古代王権』、吉川弘文館、平成7年、所収。)
東野治之「法興年号と仏法興隆」(上田正昭千田稔共編著『聖徳太子の歴史を読む』、文英堂、2008年、所収。)
田中卓「元興寺伽藍縁起并流記資材帳の校訂と和訓」(同著『古典籍と史料』、国書刊行会、平成5年、所収。)