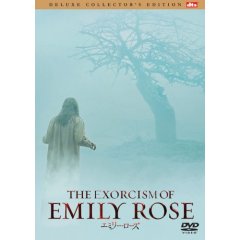
by Kurenai King
不定期刊行、ノンジャンルの評論集です。
新しい物から並んでいます。
#9
『エミリー・ローズ』デラックス・コレクターズ・エディション
監督/スコット・デリクソン
DVD]ムービー>洋画>サスペンス・ホラー>ソニー・ピクチャーズエンタテインメント
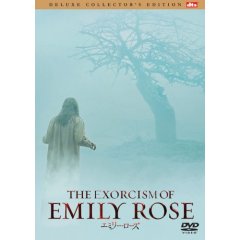
最近読んで面白かった加賀乙彦の『悪魔のささやき』に紹介されていて興味を持って観た。今まで、こんな映画が今年作られていたという事も知らなかったが、面白かった。
悪魔祓いを扱った映画だし、コマーシャルでは、悪魔憑き状態のエミリーを演じたジェニファー・カーペンターのイナバウアー反りしながらのもの凄い形相が強調されていたから、ホラー映画と思って観た人も多かったろうし、サスペンス・ホラーに分類されているけれども、そういう映画ではないと思った。
物語の冒頭で、悪魔憑きの被害者エミリーは既に死亡していて、悪魔祓いを行ったムーア神父が、彼女を過失致死の容疑で逮捕、起訴される。物語は、神父が医療行為を中断させた事でエミリーを死に至らしめたのか、それとも悪魔は実在し、悪魔祓いの行為は正しい事だったのかをめぐって繰り広げられる法廷劇となる。従って、マスコミに露出したジェニファーの悪魔憑きの演技の部分は全て回想シーンである。
『エクソシスト』みたいな映画を期待して観に行った人は肩すかしを食らい、この映画の本当のターゲットだった観客層は見に行かなかったのではあるまいか?
私は『エクソシスト』シリーズをホラー映画として、オカルト映画として、また思弁的な映画としても(特にフリードキン監督の一作目と、原作者ブラッティーがメガホンをとった三作目を)高く評価しているけれども、それらとは全く違ったベクトルを持った映画だ。
ただ、私は予め、知的な法廷劇というつもりで観た訳だけども、回想に現れるエミリーの悪魔憑きに関わるシーンは、かなりショッキングでドキッとするに充分だ。普段、『ヘルレイザー』などを観てもビクともしない私だが、ホラーじゃないと思って観たせいか、逆にゾゾッとしたのかも知れない。
これは、旧西ドイツであった本当の悪魔祓いとその後の裁判という事実、実話を元にした原作をもつ映画である。ダビンチ・コード等と同じく、キリスト教文化に疎い人には、この話の真髄は分かりづらいかも知れないが、そういう事が大好きな私には極上の面白さ、知的興奮を覚える映画であった。
裁判の行方はとてもスリリングであり、その結末にはある種の感動すら覚えた。ネタバレになるので、その結末は書かないが、神も悪魔も、やはり人の心の中にいるものだという事だろうか?
お奨め。
2006/10/23
#8
コマーシャル・ゾーン/COMMERCiAL ZONE
パブリック・イメージ・リミテッド/PUBLiC iMAGE LiMiTED(PiL)
音楽CD>ロック>METRO
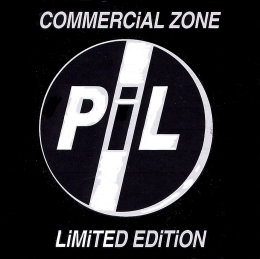
「ロックは死んだ」という名言を吐いたジョニー・ロットンことジョン・ライドンが、セックス・ピストルズ脱退後、ロックの解体という最後通牒に向かってオルタナティブ・シーンを疾駆していたパブリック・イメージ・リミテッド(PiL)の、ロックを完全に葬ってしまった大名作『フラワーズ・オブ・ロマンス』の次回作として予告されていながら、発売直前のバンドの分裂によってお蔵入りしてしまった『コマーシャル・ゾーン』は、喧嘩別れしてしまったキース・レヴィンの手によって、インディー・レーベルからのゲリラ的な発売によって日の目を見た。ヴァージンからの精機発売盤『ディス・イズ・ホワット・ユー・ウォント』の各曲の原型となったマテリアルが、ジョン・ライドンとキース・レヴィンの最後の緊張感を伴って収められている。
おそらく、これがそのままメジャー発売されたとしても、ロック史に燦然たる足跡を残したファースト・アルバム『パブリック・イメージ』、セカンド『メタル・ボックス』、ライヴ盤を挟んだサード『フラワーズ・オブ・ロマンス』のような、音楽史の分岐点としての評価はされなかったろう。ただ、妙にお上手なポップ・バンドという道を歩み始めた『ディス・イズ・ホワット・ユー・ウォント』以降のPiLと、あがきながらも模索していたPiLの分水嶺はここにあったのだと再認識する。
これまで、CD化はされていないのかとさんざん探し回っていたのだが、Yahoo!オークションで偶然みつけた。メイド・イン・イタリーとなっているのだが、ディスクは何もプリントされていないCDロムで、明らかに既発売のアナログ盤からの盤起こし……それでも、これが見つかった事を幸運と考えたい。
CD盤は、東京でのライヴ音源がボーナストラックとして入っているが、正規盤の『ライブ・イン・TOKYO』とは明らかに別の音源だと思われる。案外、元はビデオかもしれないが……まあ、おまけはどうでも良い。
2005/08/18
#7
ハバナ・モード
村上龍・著
書籍>ハードカバー>人文>エッセイ>KKベストセラーズ
書名としてきちんと明記されている訳ではないのだけれど、これは『すべての男は消耗品である』という「ザ・ベストマガジン」に連載されているエッセイの単行本化、その第八弾である。そろそろ出ても良い頃だと思って新刊書を眺めていたら、ようやっとという形で平積みになっているのを発見した。
村上龍は小説を読むよりもエッセイを読む方が好きだ。何というか、元気が出るのである。元気が出るという事を具体的に説明するのは難しいが、閉塞して停滞してしまった頭が、方向を変えて再始動出来る、そんな実感を持つ事が出来る。なんと云うかポジティブになれるのである。だから、頭を切り換えたい時に村上龍を読む事が多い。岸田秀や吉本隆明もそういう時に読んでいる。ただ、村上龍のエッセイは効きは早いが効果も長続きしないし、繰り返し読んでも同じ効果は出ない。だから新刊を心待ちにするようになってしまっている。
この連載ももう二十年以上らしい。最初の頃とは、随分扱う中身が変わってきた。男性性、男性原理から出発したエッセイが、専ら経済中心の話になっている。これは村上龍の最近の全体的な傾向なので、彼は恋愛のエッセイでも経済という切り口から始める。私は経済という分野は好きではないが、村上龍の経済の話には共感するし説得力がある。
例によってだが、少しだけ頭の切り替えが出来た。
最近のこのシリーズの傾向ではあったけれども、凝った装丁がされている。画像では分からないと思う。書店で手にとって見て欲しい。
それから、それぞれのエッセイが、執筆順ではなくて逆順で収められている。本を始めから読むと、新しい物から読んで行く事になるのだ。それはこのホームページでの私のショートコラムでも同じだけれども、新しい物から読むというのは何やら変な感じだった。特に、村上龍は「この話はまた次回に」とか、「前回○○の話をしたが」という書き方が比較的多いので、それが読みにくい原因の一つかも知れない。
この並べ方、筆者の意向か、編集者のアイデアか不明だけれども、筆者に断り無くやったとも思えないので、まあ御本人も納得ずくなんだろう。良かったのか悪かったのか、私としては何とも云えない。
本当は、この本の書評、下記のCD評の前に「スター・ウォーズ エピソード3 シスの復讐」の映画評をするつもりだったのだけれども、それはまた後日、もう一度か二度見てからにする。今日は切羽詰まって藁を掴むようにこの本を読んだので、まあ、新鮮なうちにね……
2005/07/15
#6
グラス・チューブ+シングル/Glass Tube + single
アフター・ディナー/After Dinner
音楽CD>Japanインディーズ>disc union
アフター・ディナーの1984年発表の1stアルバム『グラス・チューブ』と、1982年のデビューシングル『アフター・ディナー』を、ディスク・ユニオンが紙ジャケ仕様で2005年4月に復刻CD化した物。アルバムCDとシングルCDの変則二枚組、そしてまたまた紙ジャケ仕様。どうやらアナログ盤発売当時の形に限りなく近づけるという紙ジャケ仕様は、リスナー以上に、アーティストと版元に拘りがあるらしい。
『グラス・チューブ』は、発売当時、音楽誌フールズ・メイトのインディー・チャートで数ヶ月に渡ってトップを維持していた。30センチで45回転、収録時間は三十分に満たない物だったが、PiLの事実上の分裂解散などで停滞していたポスト・パンク、ニュー・ウエイヴというシーンの中で、ある種の異彩を放っていた。やっと自分の求めていた新しい音に巡り会えたという鮮烈な記憶が今も残る。アヴァン・ポップとも、ポスト・ニュー・ウエイヴとも、またプログレともつかぬ、独自のジャンルの音楽だが、後に急接近したフレッド・フリスらの現代実験音楽が最も近い感性を持っているとは云え、リーダーであり、ヴォーカリスト、HACOのある種童謡的でもあり懐メロ調でもある歌声が、アフター・ディナーの個性を際立たせていたとは云える。
フリスの率いるアート・ベアーズのダグマー・クラウゼ、戸川純、レビュー前出の多加美、そしてこのアフター・ディナーのHACOの四人が、ロック冬の時代であり、尚かつ個人的にも冬の時代であった84年当時の僕を支えてくれた四人の歌姫である。『グラス・チューブ』は、八十年代全般を通じて、最も繰り返し聴いていたアルバムであった。
アフター・ディナーは、前述のフレッド・フリスらとのコラボレートを通じ、国内はもとより英国のアバンギャルドシーンでも注目を集めた。今回の復刻盤とほぼ同じ音源に、ライヴ音源を加えた『After Dinner/Live Editions』は1991年に、アート・ベアーズの発売元である英国のReRメガコープからリリースされている。ただ、こちらに収録の「セビア・チュールI」は、『グラス・チューブ』発表時とは別テイクが収められている。然るに、『グラス・チューブ』収録時の「セピア・チュールI」は初CD化である。十数年ぶりに聴いたワイヤー・レコーダーによるジンタの響は、当時の根源的な創作意欲のような物を呼び覚ましてくれた。
なお、限りなくアナログ盤の発売当時に近づけたこの復刻CDには、ボーナストラックとして、アメリカで発売されたコンピュレーション・アルバムにのみ収録されていた『髪モービルの部屋』が収められている。ライヴ音源でしか聴いた事のない曲だったので、これも嬉しい。
アフター・ディナーは、その後、1989年にセカンド・アルバム『Paradise of Replica』をCDで発売。これも名盤だが、おそらく、現在では入手困難。HACOはアフター・ディナーを離れた形で、現在もソロワークを継続中。こちらの動きもフォローし続けたいと思う。
2005/07/12
#5
天使行(Y.De Noir II) / 夢ノ岸(Yume No Kirigishi)
多加美
音楽CD>Japanインディーズ>BELLE ANTIQUE
今回は二枚のCDを一挙にREVIEW。日本インディーズ史上……と云うよりも、世界のコンテンポラリー・ミュージック史上、最もアンニュイで陰鬱な歌姫、多加美が残した二枚のアルバム、ファーストの『天使行』とセカンドの『夢ノ岸』である。レコードでの初発売時は八十年代前半だが、この二枚のアルバムは95年にCD化されている。
多加美の残した二枚のアルバムは、メロディーよりも歌詞、言葉として世界に対する陰鬱さを投げかける。ファーストの『天使行』では、より言葉に比重が置かれ、『夢ノ岸』は、音楽としての整合性が共同作者のPNEUMAによって高められているが、多加美のアルバムの真価ははおそらくその歌詞の中にこそある。
歌わなければならなかった事であり、語らねばならなかった事……その本質がこの中にある。そして、それは、聞いてしまったら死ななきゃならない程の陰鬱さに満ちているのだ。歌姫多加美の歌は自虐の歌だ。だが、それにシンクロするからこそ、私はこの二十年、繰り返し多加美の歌を聴き続けるのである。
どうやらAmazonでも買えるらしい。陰鬱さに同調する事でアイデンティティーを保とうとする人にはお勧め。死に逆らって生きるのではなく、生に逆らって生きる……それってこういう事かも知れないよ。一緒に仕事をしてみたい歌姫である。どうしたらコンタクト出来るだろう……? 私の舞台に多加美の歌を響かせたい……そんなシンクロを感じる歌姫である。
とにかく聴け! 聴けと云うしかない。この陰鬱さを受け止めよ。そして生に逆らって生き、死にも逆らって生きるのだ。『最后の夢』を見て『夢ノ岸』に立ち、『空の迷宮』に向かって天使の歩みを歩むのだ。
多加美とPNEUMAの造り出す言の葉と音の流れには、類似する何かを提示する、或いは比較する事が出来ない。オリジナリティーという事ではないのだが、この二枚のアルバムには、ここでしか聴けない言の葉と音律の流れがあるのだ。それだけは確かな事である。
二十年を過ぎた音楽だが懐メロではない。多分、今現在の窒息しそうな世界に求められている、そんな音楽。歌と言うよりは謡……そんな物かも知れない。
2005/07/07
#4
『人間の條件』DVD-BOX
監督/小林正樹 原作/五味川純平
DVDムービー>邦画>戦争・歴史>松竹株式会社ビデオ事業室
1959年から1961年にかけて、三年間で毎年二部ずつ公開された全六部の、仲代達矢主演の映画『人間の條件』の全編を収めたDVDボックス。全編の収録時間は九時間半を超える。
この四半世紀、事ある毎に見返してきたのがこの映画であり、また原作を読み返してきた。そのような転機で読み、また見る作品とは、白土三平の『カムイ伝』と五味川純平の『人間の條件』なのである。
この作品は、予告編で告知されるような「戦争否定というテーマを歌い上げた」作品ではない。文字通り、人間の條件を問うのである。反戦とか非戦とか、そういう次元、ステージにこの作品は留まっていない。
物語は戦時下の満州で始まり、日本本土は全く出て来ない。そのような植民地政策の条件を作ったのは人間であってそこで生きていくのもやはり人間だ。主人公、梶は最後の最後まで人間として生きようとするが故に苦悩している。そして、その過酷な運命をお膳立てしたのも、また、人間の営為なのだ。その人間の営為の構造をどう読み解いていくか……我々にはそれが問われているのだ。
五味川純平は、ある意味、ヒューマニズムに拘り続ける。それが『人間の條件』というタイトルの所以にもなっている。そして、ヒューマニズムとは社会主義であるという左翼の希望に対して、ソ連という国家の理不尽をこれでもかと見せつける。私はこの映画を見て、初めて、社会主義はヒューマニズムたり得るかという事に疑問を持った。そして、我々が卓上で議論する反戦論という物が、如何に意味のない事かを思い知らされた。
戦争という状況を作ってはいけないのである。
それまで、私は、圧制された民衆が暴力によって蜂起するとか、侵略戦争に対するゲリラ戦とか、そういう物を肯定しても良いと思っていたのだけれども、人と人が殺し合うという事態に於いて、そのような卓上論が無意味になると云う事が一つ。そして、一旦、殺しあいが始まれば、正統な反逆者も殺人者に変わってしまうというような事が一つ……この映画を見てから、社会主義建設の正義、それも信じられなくなった。多分そうだ……
この作品、『人間の條件』の中で、主人公、梶を取り巻く状況は、物語が進むに連れてどんどん悪くなる。映画ではなく、原作を読めば判る事だが、彼は左翼として検挙された経験もある。そのような中で、彼は皇軍の捕虜として拘束された中国人に対する強制労働の労務管理者として物語は始まる。
梶はヒューマニストだ。だから、捕虜となって強制労働をさせられている中国人達を、戦時下の日本人としても何とかしようとあがく。だが、戦時下という状況が彼の望を打ち砕く。管理者だった彼は軍隊という組織に放り込まれて、組織の中でまたあがく。あがきを続けた彼は、軍の崩壊後、ソ連軍の捕虜となって、更に過酷な運命を強いられる事になる。
とにかく、この話、話が進めば進む程、状況は困難になっていく。その中で梶は生きていこうとする、最後まで、人間として……
この映画は、私の生まれる前に作られた映画だから、もう四十数年前の映画なのだ。
私がこの映画を初めて見た時、まだソ連という国家機構は健在だった。今はソ連もない。この映画に出て来る、梶や丹下の希求した、社会主義国家は、ヒューマニズムの国ではない、単なる国家主義の国々として認識されている。では、何処に我々は人間が人間として認められる世界を求めるのか……? 『人間の條件』はそれを問い続けるのである。
この映画……そして原作小説もそうだが、あのラストシーンを、どうして五味川純平は書き、小林正樹は撮ったのだろう。それは永遠の謎だ。我々読者や視聴者は、それを考え続けるしかない。今の想いはあるけれども、それは書かない。いつかかける時が来たら良いと思う。
この稿は未完とする。また、見直して、思った事は書き足す事にする。
ちなみに、三一書房、文春文庫などで絶版になってしまった原作小説は、今は岩波現代文庫で入手可能。あるうちに読んでおけよ。
2005/06/29
#3
昭和史 1926-1945
半藤一利・著
書籍>ハードカバー>人文>歴史>平凡社
あの井上ひさしをして「疑いもなく一つの偉業」と言わしめた、若い世代向けの昭和史の本。語りおろしというスタイルなので、文章は非常に読みやすい。五百ページを越える大著だが、多分、多くの人が二日三日で一気読みしてしまったであろうと思われる。
やけにナショナリズムに傾いた歴史書が氾濫している昨今にあって、過去の戦争を美化する事もなく、かといって自虐史観と保守系知識人が攻撃するようなタイプの唯物史観に彩られている訳でもない。本書は、軍隊内部の人間関係、それぞれの軍人のスタンスや政治への関わり方を中心に、それに関わる政治家、昭和天皇、マスコミと国民の熱狂といった側面から昭和史を捉え直している点が面白かった。昭和史についての本は、四半世紀以上に渡ってゲップが出る程読み倒してきたと思っていたが、まだまだ新しい観点がある物だ。特に、私のように史的唯物論を元に歴史を学んできた人間からすると、どうしても階級対立や思想対立から近現代史を見てしまうのだが、ミリタリーバランスと戦術戦略、或いは政戦両略でうごめく軍人達を克明に追っているのが興味深い。ある意味で、「昭和史」というよりは「昭和皇軍史」とでも言うべき物だが、それだけ昭和の前半というのは戦争しか無い時代だったのだろう。
筆者の視点は、軍人の愚劣さと、政治家の愚劣さを浮き上がらせると共に、好戦気分を大いにあおり立てたマスコミと国民の責任を見逃していない。天皇に対して同情的な記述は多いが、また、天皇自身の戦争責任を否定する論陣を張っている訳でもない。つまり、筆者はいかなる思想的プロパガンダも行おうとしていない。その事が逆に、過去に学んでいない現代日本を浮かび上がらせる結果になっている。偉業と言われる所以であろう。
元々、劇作のネタ拾いのつもりで読み始めたが、ネタは拾えなかった。軍人の物語として昭和史を捉え、そこに天皇、政治家、マスコミ、国民が絡み、芥川龍之介や永井荷風といった文人達の日記、手記を絡めて描く語り口は広範囲ではあるが、それでも歴史や時代は語りきれないという事なのだろうと思う。近衛文麿と広田弘毅に対する見方がちょっと変わった。目から鱗が落ちると言ったら大げさであろうが、少しぐらいの垢は落ちたような気がする。
結局、ポツダム宣言の受諾と降伏文書の調印というところで本書は終わってしまい、戦争責任、戦後責任というところまでは追究されない。軍部の愚行ばかりがクローズアップされているが、筆者が戦後責任をどう捉えたのか、続編が出るなら読んでみたい本ではある。
面白いけれども昂揚しない……そんなところか。
ただ、学校で近現代史を習う事が出来なかったという人には、格好の昭和史入門書と言えると思う。思想的な偏りがないと云う事が、逆に偏った読み方を可能にするかも知れない。そういう意味では位置づけの難しい歴史の本ではある。
2005/06/27
#2
666〜アフロディーテズ・チャイルドの不思議な世界/666
アフロディーテズ・チャイルド/APHRODITE'S CHILD
音楽CD>ロック>ユニバーサル・ミュージック
これまで何度も廃盤、再発を繰り返してきたに違いないアルバム。最初のリリースは1972年、もう三十年以上前の音源である。私が最初に聞いたのは、おそらく七十年代の後半、そして、音楽環境を完全にCD等のデジタル音源に変えてから、今日までCD化されたこのアルバムを聴いていなかったので、聴くのは間違いなく十数年ぶり。ショップに並んでいた時は何故か食指が動かず、聴きたい時には店頭から消えているといういたちごっこを繰り返してきた。
今回の対象盤は、おそらく2003年末から2004年初頭にかけてリリースされた五千枚限定のリマスター盤。今流行の、発売当時を再現した紙ジャケ仕様である。
アフロディーテズ・チャイルドというギリシアのロック・バンドについて、その名を聞いてピンと来る人は殆ど居ないのではないか? 活動当時、日本では少数の愛好家がデミス・ルサスという歌手(東京音楽祭への来日経験があったらしい)の在籍するバンドとして認識するのみだった。だが、七十年代後半(既に解散後)に再発された時の注目株は、フロントマンのデミス・ルサスではなく、キーボーディストのヴァンゲリス・パパサナシューであった。『ブレード・ランナー』や『南極物語』、『炎のランナー』などのサントラで知られる、あのヴァンゲリスである。この『666』を最後にバンドを解散し、ソロ活動に入ったヴァンゲリスは、キーボーディストというよりは、シンセサイザー・ミュージックの第一人者として大ブレイクする。
ヴァンゲリスが一躍注目を浴びたのは、イエスのリーダーであるジョン・アンダーソンが脱退したキーボーディスト、リック・ウエイクマンの後任としてヴァンゲリス・パパサナシューを指名した事に始まる。プログレという範疇に括られてはいる物の、ヴァンゲリス当人のソロにしろ、アフロディーテズ・チャイルドにしろ、イエスとの共通性は全く感じられない。結局、ヴァンゲリスは音楽性の違いからイエスには加入せず、ウエイクマンの後釜にはスイス人キーボーディスト、パトリック・モラッツが収まるが、この時の縁からか、ジョン・アンダーソンはヴァンゲリスのアルバムに何度か参加している。そして、ヴァンゲリスの所属していたバンドとして、既に解散していたアフロディーテズ・チャイルドは俄に注目を集める事になった。
『666』はアフロディーテズ・チャイルドの最後のアルバムであるが、その実質はヴァンゲリス・パパサナシューのソロに限りなく近い体制で作られている。制作当時、バンドは既に崩壊状態にあり、全ての楽曲の作曲をヴァンゲリスが単独で行っている。国際的な売れっ子であったデミス・ルサスがリード・ヴォーカルををとっているのも、全二十四曲中、僅かに三曲のみ。『666』以前のアフロディーテズ・チャイルドは、プログレというよりもデミスをフィーチュアした良質なポップ・バンドといった曲作りをしていたが、ヴァンゲリスのイニシアティブによって作られた『666』は、ユーロ・プログレの代表的一枚であると同時に、数々の実験に満ちたロックを超越した作品として残っている。
初めて聞いた当初、その後のヴァンゲリスのソロワークとも、この『666』の総体的な印象には殆ど共通点を見いだせなかった。七十年代後半以降のヴァンゲリスのアルバムは、「シンセサイザーの音」という、アナログシンセの多重録音によって作られた豊かなメロディーラインという印象が定着していたからだ。だが、今、『666』を聴き直すと、パーカッションの使い方やアレンジなどに、その後のヴァンゲリスの方向性を示唆する数々の実験が鏤められている事が判る。ヴァンゲリス当人も、このアルバムではシンセサイザーを使用していないが、ブラスや民族楽器による旋律をヴァンゲリス独特のシンセの音に置き換えてみると、後のソロワークとダイレクトに繋がっている楽曲が多数ある事が判る。おそらく、このアルバムの制作当時、ヴァンゲリスの関心はシンセサイザーではなくヒューマン・ボイスにあったのだと思われる。デミス・ルサスの歌う三曲はバンド・アレンジと相俟って、ポップからロックへの硬度を強烈に放っているが、その他の「人の声」の使い方によって、ヴァンゲリスはロックからの跳躍、もしくは逸脱に向かっていったのだと思われる。
このアルバムの制作の為、兵役によってバンドから退いていたギタリスト、シルバー・クルーリスが急遽呼び戻されたという情報がライナーに見える。ギターの音によって、『666』はかろうじてロックの範疇に留まっている。そして、ソロワーク以降、ヴァンゲリスの紡ぎ出す音からは、ロック的なギターの音という物が一切排除されるようになった。これは、ヴァンゲリス・パパサナシューがロックの世界に残した置きみやげのような物なのだと思う。
Disc1、七曲目の『エーゲ海』は今も古さを感じさせない名曲。
ちなみに五千枚限定で作られたこのアルバム、Amazonの在庫も三枚か四枚らしい。欲しいと思っている人は、さあ急げである。
ところで、どうも紙ジャケ仕様というのは私は好きではない。ディスクが扱いにくいし、保管も難しいからだ。誰か、紙ジャケに拘っている人が居るのだろうか?
2005/06/25
#1
フォールン/FALLEN
エヴァネッセンス/EVANESCENCE
音楽CD>ロック>エピック・ソニー
エヴァネッセンスは米国アーカンソー出身の五人組。女性ヴォーカル(エイミー・リー)を前面に押し出し、全体はダークな雰囲気に満ちている。
偶然知った。
『フォールン』は2003年発表のファースト・アルバム。映画『デアデビル』に二曲が使用された事を切っ掛けに大ブレイクし、アルバムも1300万枚を売ったという事だが、私は映画の方は観ていない。アメコミ原作の映画というのはどうも苦手だ。
バンドの編成は、二本のギター、ベースとドラムスというシンプルな編成だが、実際に聞いてみるとピアノやストリングスが多用されていて、聖歌隊のようなコーラスも入っている大仕掛けな曲もあって、グランジ、オルタナティブ系のロック・アレンジと、クラッシックと言うよりはイージー・ストリングス系の曲に二分されている。バンドのメンバーは何もやっていないのじゃないかと思われるバラードも数曲あって、実際は五人編成のバンドと云うよりも、ヴォーカルのエイミーとリード・ギターのベン・ムーディーによる、プロデュース・ユニットと解釈するのが正しいのかも知れない。
二分された曲想でも、トータル・アルバムとしての統一感を保っているのは、ベンのメロディーラインの統一性、後はエイミーの歌唱力によるところが大きい。
七十年代にこういう事(ストリングアレンジの大胆な導入)をやっていたら、「クラシックとロックの融合」等と云われて、第二期ルネッサンスなどと比較されていたかも知れない。だが、現在のロックシーンはどうなっているのか正直良くわからない。音楽誌を読まなくなって久しいが、おそらく、新しいジャンルを造り出す活力という物がロックには既に失われている。だから、既に先人の造りだしたイデオムに乗っかって、その中で気負わない自由度を獲得したアーティストだけが生き残るのではないかと思われてきた。エヴァネッセンスにもやはりその気負いはない。
昔だったらプログレにジャンル分けされていたかも知れない。キーボードとオーケストラアレンジは、今やプログレの特色ではないし、ロックのカテゴライズは既に破壊されてしまった。便宜的にロックバンドとして、またロックのアルバムとして分類されてはいる物の、当人達にとっては、もはやロックであるかどうかと云う事すら問題ではないのだと思う。
日本盤はボーナストラック一曲付。
2005/6/21