上野東照宮
 上野東照宮は、上野公園の中にあります。
上野公園は、元は寛永寺の敷地でした。寛永寺は、寛永2年(1625) 徳川家の菩提寺として天海僧正によって建てられました。
上野東照宮は、上野公園の中にあります。
上野公園は、元は寛永寺の敷地でした。寛永寺は、寛永2年(1625) 徳川家の菩提寺として天海僧正によって建てられました。家康は、晩年病床で藤堂高虎と天海僧正に、末永く魂鎮まるところを造って欲しいと遺言し、これにより 寛永4年(1627)に藤堂家の屋敷地であった上野の山に、藤堂高虎と天海僧正が、家康(東照権現と呼ばれていた)を奉る東照宮を造営しました。
その後、慶安4年(1651)に、三代将軍 家光が総金箔の金色殿に大改築しました。
なお、上野という地名は、高虎の出身地である伊賀上野にその地形がよく似ていることから命名されたといわれています。
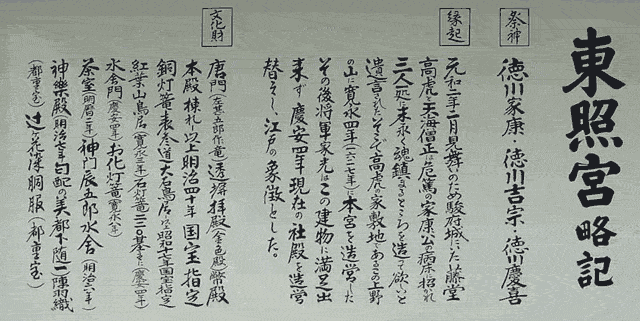

 上野東照宮も小規模ながら日光東照宮を偲ばせる豪華な建造物です。
現在はさすがに総金箔というわけにはいきませんが、それでもあちこちに昔の金箔の名残が見て取れます。
拝殿、唐門、透塀など多くが国宝に指定されています。
唐門の両サイドには左甚五郎作の昇り竜と降り竜の彫り物(右の写真)がありますが、これも国宝です。
この東照宮の入り口にはボタン園があり、近くの不忍池には多くの桜の木があります。ボタンや桜の時期に、
ここに訪れてみるとよいと思います。
上野東照宮も小規模ながら日光東照宮を偲ばせる豪華な建造物です。
現在はさすがに総金箔というわけにはいきませんが、それでもあちこちに昔の金箔の名残が見て取れます。
拝殿、唐門、透塀など多くが国宝に指定されています。
唐門の両サイドには左甚五郎作の昇り竜と降り竜の彫り物(右の写真)がありますが、これも国宝です。
この東照宮の入り口にはボタン園があり、近くの不忍池には多くの桜の木があります。ボタンや桜の時期に、
ここに訪れてみるとよいと思います。








