Paratheraps cf. guttulatus
Guenther,1864
別名 REDTAIL−THERAPS REDSPOT−THERAPS
パラテラプス・グットゥラータスと発音している。

さて成長日記に入る前に、この種について少し考えてみたい。
Aqualogでは『cf.』扱いとなっている。
『cf.』というのはconferの略で、同一種に同定するには疑問であるが、形態的にそうであろうといった感じのものである。
色々と調べてみるのだが、この種に関しての記載は少なく、よく分からないのが現状である。
特徴としては丸みを帯びた頭で口は下のほうにあり、尾の付け根から胸鰭まで幅が広めの縦のラインを持ち、
胸鰭を除く各鰭にはスポットが入り、尾鰭、背鰭、尻鰭の縁は赤く彩られる。
私はずんぐりとした体高のあるヴィエジャであると認識しているのだが、洋書にはとてもスリムな流線型のような画像が
載っていたりして、本当に悩ましい種である。
というわけで、自信を持ってこれがグットラータムであると言える域には私自身も達しておらず、
申し訳ないのだが、自分自身やみなさまの勉強にもなればと思い、公開することにいたします。
 2003年2月13日、買ってしまったのである。
2003年2月13日、買ってしまったのである。
飼育している魚を見てもらえばお分かりいただけるであろう。
私はヴィエージャ馬鹿である。
グットラータムも以前から育ててみたい種であった。
この日、大阪の天王寺のお店へ塾長と共に行ったときに買ってしまった。
こうして今画像を見るとビファシの小さい頃によく似ているような気がする。
ただ目の色は黄色みがかっている。
このサイズでは雌雄の判別は分からない。
口元が赤くなっていて、細身の個体を選んでみた。
大きさは8cmぐらい。60ワイド水槽単独飼育である。
餌はなんでもよく食べる。
 2003年3月 うん?青いか?
2003年3月 うん?青いか?
よく懐いているのだろうか、攻撃しているつもりであろうか、
手を入れて掃除をすると突付きまくる。噛むと言うほどではないが、これがまたちょっとだけ痛い。
で、けんちゃま流教育を施したところ、ビビリンチョである。
色の方は私の好み(どちらかというと青い方が好き)になってきたようで、
将来が楽しみである。
まだ雄か雌かはわからない。
生息地は南メキシコ、Rio Malateng. Almoloya. Chicapa. Tehuantepec. Flores.
Coatcacoalcos.
そしてGrijalva. グアテマラのLake Amatitlan.
 4月、セパ越しの飼育にしたとたん。
4月、セパ越しの飼育にしたとたん。
発情かい?(涙)
なんだかガラリと雰囲気が変わってしまった。
同じ魚なのか?と思ってしまうぐらいである。
隣はビファシアータムである。
こいつに対しては敵意むき出しであるのだが。
60ワイド水槽をスペクタビリスに取られて怒っているのか、
ご機嫌はよろしくない。
『Vieja sp. coatzacoalcos』というのがいるのだが、洋書の画像によると
それに一番近いような気がする。
coatzacoalcosというのは河川の名前である。
 5月、なんだか頭でっかちである。
5月、なんだか頭でっかちである。
もう20cmを超えている。
恐るべし成長の早さである。
餌は朝食はキャット、おやつにベジタブル、夜食はカーニバル。
少しあたまでっかちになりすぎているような気がする。
さて、グットラータムなのか、coatzacoalcosなのか、はたまたハイブリッドなのか?
ワイルドで買ったのだからハイブリッドでないことを願う。
何人かの人達と話しをしたのだが、天然化ではハイブリなどはほとんど発生しないと思うのである。限られた環境や狭い水槽の中では仕方無しにハイブリができてしまうことは事実であるが、自然に生息しているものは種の保存という意識はどんな生物にもあるはずである。わざわざ違う種と交配してしまうとは考えがたいと私は思っている。
 8月、さて、♂なのか♀なのか?!
8月、さて、♂なのか♀なのか?!
非常に悩ましい。
頭の形や鰭などを見ると♂なのかなあとも思えるのだが、
お腹がぽっちゃりしすぎているような気もする。
八月になり成長の度合いは少しストップしているか、大きさはあまり変わらず20cmオーバーである。
これは十分なスペースを与えてやれないせいであろうか。
ということで、60ワイド水槽を新設。
移動させる際に測ったら全長23cm。
現在私が寝ている真横の水槽にいる。
 2003年11月
2003年11月
24cmぐらいであろうか。
20cmを超えたくらいから成長が一気に遅くなる。
肥満との闘いが始まるので、どうも餌の量がはっきりしない。
単独の場合、どうしても運動不足になりがちなので、
食うだけ食わせば太ってしまう。
それに、大きくならない奴はこれくらいで成長が止まるのであろうか。
この種に限ったことではないが。
なんとなく♂であるような気がしてきた。
思い出せば今年の2月に塾長と一緒にどうだろうな?と言いながら買った個体である。
次に塾長が来られるような機会があれば、こんなになったよと報告するのも楽しみではある。
当初は貧弱な印象であったが、なかなかに迫力のある個体に仕上がってきたように思う。
『sp. coatzacoalcos』という種であろうかと思ったりもしていたのだが
いろいろなサイトや洋書を見てみると、どうも『sp. coatzacoalcos』というのは
黄色やオレンジの発色が一部分に見られるものが多い。
なので、私としては『 sp. coatzacoalcos』というのは、グットラータム系のそういう(黄色やオレンジの色が見られる)個体であると、勝手に決めることにした。
とにかくよく分からないのが本音である(笑。
紛らわしい種としては、最近のゾナタム。アクアログのP72の右側上から二段目の『Vieja sp. aff.zonatus』とされているようなもの。
これにも似ているような気がするが、これは先述した『 sp. Coatzacoalcos』ではなかろうかと思う。
ついでに言うとアクアログのP94の『Herichthys cf. geddesi』にも良く似ている。
これってグットゥラータムとちゃうのんかなあ(笑。
うちの個体は、グットゥラータムということで、宜しいでしょうか?(笑。
 2004年1月
2004年1月
25cmぐらいに成長している。
私が横で林檎を食べているとクレクレダンスを踊りまくる。
細かくして与えると、とても美味しそうに食べる。
本当に面白い奴である。
色々な洋書に記載されているグットラータムの特徴をまとめると、
エラブタの上の角から尾鰭の中心にストライプが伸び、それは5〜6本のバンドで補われる。そのバンドは背中にも腹にも届かず、状態によって消えたりもする。
尾鰭、背鰭、腹鰭のエッジの柔らかい部分が赤で彩られ、ボディの基本色は明るいグレーや茶色っぽい黄色の個体とさまざまである。
と、こういうことがよく書かれている。
『Helos.guttulatus』『Cichlasoma.guttulatum』『Vieja.guttulata』『Paratheraps.guttulatus』と呼ばれてきたようであるがGuttulat〜の意味が分からない。
ドイツ語では『gesprenkelter』という名前が使われており、『小さな斑点のついた』という意味のようである。
中国名は『斑麗體魚』。
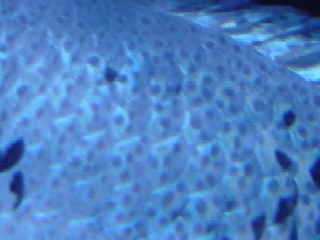 2004年6月
2004年6月
30cmには少し届かずといったぐらいの大きさである。
特徴の変化としては体の上半分に無数のスポットが目立つようになってきた。
こいつも20cmまではあっという間に成長し、それから時間をかけてジワジワと大きくなっているようである。
餌の食べ方が気に入らない。
人工飼料を一度に入れると、食っては吐きだして次のを食うという
暴虐の限りを尽くしている。
しかもエラから出すカスもハンパな量ではない。
なのでこの水槽だけ水の透明度が悪い。
むかつく……。
 2004年10月
2004年10月
90*45*45に移動しての単独飼育である。
大きさは32〜33cmぐらいあるのではないかと思う。
もうなんだかよくわからない迫力である(笑。
← 頭のあたりには赤いスポットがポツポツと出るときがあります。
隣にはガラス越しにアルゲンティアがいるが、そちらにはあまり関心がないようである。
水換え時には本当に要注意で、飛び掛ってくる。
えさの食べ方は相変わらず、食べ散らかしているが
水槽が90と大きくなった所為か、あまり水が濁ることはなくなった。
 2005年2月
2005年2月
横の画像がフラッシュなしの撮影、
そして今回アップしたGoodShot(二段目の左から二番目)がフラッシュによる撮影である。
まったく違う魚のような色合いに写りますね。
こいつも飼育開始から約2年経ちました。
サイズ的にはビファ、ボコに続き第三位にのし上がっているようです。
胸鰭の軟条が両側ともわりとヨレヨレです。
背鰭の棘(前部の尖っているところ)はコブのせいなのか、短いせいなのか、
めり込んでいます。
最近、某氏を通じてアメリカのトップマニアは、グットもゾナもsp.コアルコスも同じ魚であると
言ってるということをお聞きした。
まぁグットとsp.コアルコスは同じでも、ゾナタスは違うのではないかと思う年頃です(笑。
私が思ってるゾナタスにぜひお目にかかりたいもんです。
私が思っているゾナタスはグットよりは身体のドットがはっきりしていて少しメタリックなボディであること。
尾鰭は柄が入る部分が少なく全体的に赤いことですかね。
 2005年6月
2005年6月
もうあんまり変化なしですね。
口の横にほくろができました(笑。
今回の画像でこの魚が持ってるメタリックな部分が少し表現できましたかね。
ブルーの部分が少しメタリックな色をしています
とにかくカメラを構えると、興奮して色のメリハリは良くなるのだが
砂利を運ぶか泳ぎ回るかのどちらかでほんと写しにくいヤツです。
岩組み柄のバックスクリーンを貼ってみましたが、あんまりいけてないですね(笑。
素直に黒か青にすればよかった。
 2005年10月
2005年10月
調子が悪くなりました。
おそらく浮き袋の異常だと思われますが、気を抜くとポテッと下に沈んでしまうようです。
肥満というほどは太ってはいないと思うのですが、原因はそのあたりなのかもしれません。
餌は普通に食べているし、行動も元気なのですが。
塩分濃度を少しずつ濃くしていって様子を見ようと思います。
RED-TAILとかRED-SPOTとか言われる特徴は、うちの個体にも現れているように思う。
目の色は他のヴィエジャやパラテラプスと同じような環境で飼育しているが
こいつだけは金色がやや強い。
 2006年5月
2006年5月
その後のグット君ですが、塩水浴が効いたのかごく普通に元気になりました。
普段は塩を入れてないので、少し調子を落としたときに入れてやると
効き目も良いのでしょうかね。
気がつけばこいつも三年越しましたねぇ。
口のところにできたほくろもかなり大きくなっていますね(笑。
思えば最後にシクラソマを買ったのは2005年の1月のテトラカンサスなので
もう一年以上も魚を買ってないということに気付きました。
環境的にも目いっぱいのところまで来ているし、
これが僕の飼育スタイルなので仕方がないのですが
やはり寂しいです。。。
 2006年10月
2006年10月
なんでも食べるグット君、元気いっぱいです。
一番上に記しているグットの特徴である
「特徴としては丸みを帯びた頭で口は下のほうにあり、尾の付け根から胸鰭まで幅が広めの縦のラインを持ち、胸鰭を除く各鰭にはスポットが入り、尾鰭、背鰭、尻鰭の縁は赤く彩られる。」
これらの特徴はすべて表れています。
「REDTAIL−THERAPS」「REDSPOT−THERAPS」と呼ばれる所以もなんとなく分かる気がします。
この魚に関しては肥満ではないのだが、結構丸っぽい体型をしていますね。
 2007年10月
2007年10月
普通に元気です。
あまり変化は感じませんが、少しまた大きくなったでしょうか。
どの魚についても同じようなコメントですね(汗。
電気を消した後によく暴れて頭に傷を作っていますが、
しばらくすると綺麗に治ります。
約4年半ですね。
改めて一番上のおちびちゃんの頃の写真を見てみると
想像がつかないようなおっさんになってますね(爆。
2008年7月
グットラータス、逝きました。
腹の中で餌が腐ってのガス発生だと思います。
60Wに移してからはベアタンクでの飼育で
毎朝、糞の状態をチェックするのですが、二日ほど糞が出ていませんでした。
その時点で餌を止め、塩を入れて様子をみました。
さらに二日ほど経つと、腹がパンパンに膨れてきて腹を上にした状態になってしまいました。
尋常ではない腹の膨れ方を見ると、おそらく助からないだろうことは想像がつきました。
それから三日ほど経った朝に息絶えておりました。
飼育年数 五年五ヶ月
実寸 37cm
Good Shot! 画像をクリックすると拡大されます。













 2003年2月13日、買ってしまったのである。
2003年2月13日、買ってしまったのである。 2003年3月 うん?青いか?
2003年3月 うん?青いか? 4月、セパ越しの飼育にしたとたん。
4月、セパ越しの飼育にしたとたん。 5月、なんだか頭でっかちである。
5月、なんだか頭でっかちである。 8月、さて、♂なのか♀なのか?!
8月、さて、♂なのか♀なのか?! 2003年11月
2003年11月 2004年1月
2004年1月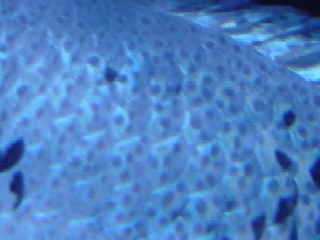 2004年6月
2004年6月 2004年10月
2004年10月 2005年2月
2005年2月 2005年6月
2005年6月 2005年10月
2005年10月 2006年5月
2006年5月 2006年10月
2006年10月 2007年10月
2007年10月









