![]()
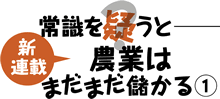
 |
| ストックのハウスと筆者。経営は、水稲5haのほか、ハウス20aで花と野菜を栽培。花は農協と直売所、野菜は2〜3カ所の直売所へほぼ年間出荷(写真は*以外、松村昭宏撮影) |
私は伊勢平野の水田地帯の専業農家です。水田地帯とはいっても、整備済みの圃場がどこまでも広がる田園地帯、というロケーションではありません。地方都市の外縁部に位置し、不整形で小区画の未整備水田の中に、郊外型スーパーマーケットやら小さな住宅団地、川や丘陵などがパッチワークのように存在する、そんな土地で営農しています。
大型農機を使った大規模経営の可能性は地形的に考えると絶望的で、かといって今後急速に市街化・宅地化が進む可能性もありません。この地区400戸の農家のうち、後継者がいる家は私を含めても片手の指に足りず、しかも農業専従者の平均年齢は70歳を超えました。
私の農業経営を取り巻く環境はざっとこのような状況ですが、これは日本中どこでも普通に見られる情景だと思います。「農業は仕事がきついわりに儲からない」という言葉がいつの間にか常識のようになってしまい、「儲からない職業には就けない」ということで後継者がいなくなり、気がつけば地域営農自体が成り立たなくなる寸前。このような農業の現状を打開するのによい方法はあるでしょうか?
 |
| 筆者のハウスとその周辺。整備されていない小区画の水田が広がる田園地帯 |
以前、私の家は、田畑合わせて1ha余りの農地を耕作する兼業農家でした。父も私もサラリーマンで、休日を利用して米だけを作っていましたが、十数年前、私は訳あって突然、そんな厳しい農業の世界に飛び込むことになりました。指導機関とも相談し、借地を増やしての経営規模拡大とともに、田んぼに1000m2のパイプハウスを建てて、何はともあれ切り花ストックの無加温栽培から始めてみました。
当時のことを思い起こして、私が農業を始めたころの経営状態を再現してみましょう。今残っている「JA共選出荷ストック栽培指針」に従って、そのとおりの栽培管理をした場合の経費を計算してみます(次ページ参照)。
| 12年前、栽培スタートの頃 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
出荷数:25000本 経費:121万円 売り上げが145万円だから、 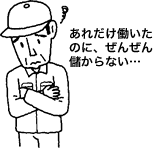 |
||||||||||||||||||
 |
|||||||||||||||||||
| 現在 | |||||||||||||||||||
|
出荷数:32000本 経費:47万7000円 売り上げが166万円だから、  |
||||||||||||||||||
この栽培初年度、10aのハウスからおよそ2万5000本の切り花を出荷しましたが、経費は合計で約121万円かかっていたことになります。1本当たりの生産費にすると、121万円÷2万五5000本=約48円。また、この年のシーズン平均市場価格が58円でしたから、売り上げは145万円程度だったと思われます。つまり、10a当たりの所得は145万円―121万円=24万円。経費率は121万円÷145万円=約83%となります。
8月の播種から始まって、半年以上の苦労の結果が24万円の所得にしかならない。この現実に「農業は仕事がきついわりに儲からない」という言葉を実感し、愕然としたのを覚えています。
その後数年間、ストックの八重率や秀品率の向上による売り上げ増大や、ナバナやブロッコリーなど露地野菜の規模拡大。そして、少しでも安価な資材探しなど、さまざまな改善をして経営を安定させる努力もしました。
その過程で、すでに完成している“常識的な栽培方法”からのコストダウン、たとえば「安い肥料に替えてみる」「大型機械で作業の能率を上げてみる」「栽培規模を増やしてみる」といった発想のもと、試行錯誤しましたが、結局下げられる経費はタカが知れているということを身にしみて学びました。
さらに、5〜6年経過してようやく経営が安定し始めたころ、今度は、いわゆる「連作障害」に苦しむことになります。何年間も休みなく冬場のストックと夏野菜の連作を繰り返した結果、肥料塩類集積による作物の生理障害や苗の立枯れ病、良品比率の低下が見られるようになり、標準的な「栽培指針」どおりに作物が作れなくなってしまったのです。
そしてまた10年が経過した今、私の経営や作物栽培のスタイルは当時とまったく違うものになっています。冒頭で紹介したような営農環境で、無闇な規模拡大や仕事量の増大はもはや無理と悟り、それでも儲かる農業のスタイルは? と考えてたどり着いたのが現在の私の経営です。
 |
| ストック。品種は「チェリーアイアン」の八重 |
当時との比較のため、例として最近のストックの生産費を計算してみます。ちなみに、この年度に出荷した切り花本数は、10a当たり3万2000本でした。経費は合計で47万7000円、1本当たりの生産費になおすと、47万7000円÷3万2000本=約15円になります。
販売単価は52円と、当時よりやや低下していますが、売り上げは約166万円に増加しています。ここ最近の経費率は47万7000円÷166万円=0.29。約30%となり、これを就農当時の24万円と比較すると、約7倍近い儲けになっているのがわかります(前ページ参照)。
このストック栽培はほんの一例にすぎません。「100万円かかっていた経費を90万円に下げる」といった、引き算の“コストダウン”という常識は棄て、経営にしろ作物の栽培にしろ、必要なものだけを積み上げていく“ゼロから足し算するコスト”という発想に立つと、驚くほどムダが省けるのです。「作物が商品になるために必要なもの(こと)」を「必要な時に」「必要なだけ与える(行なう)」という「後補充生産」の考え方が重要です。「ほんとうに苗はこんなに必要なのか?」「肥料は必要なのか?」「土を耕すことは必要なのか?」といった、覆せそうにない基本を覆した時ほど効果は大きく現われるのです。
現在の私の経営を少し紹介すると、労働力は私一人、水稲5haと少量多品目のハウス野菜・花20aを中心に、売り上げベースで約1000万円。そして経費率40〜50%。これが現状での、いわば「小さな経営」の限界です。
野菜や花も元肥ゼロの「への字」栽培。追肥は安い単肥で十分。土はむやみに耕さずに不耕起・半不耕起を作物別に使い分け。農薬もほぼかけない。
 |
| 3連棟1000m2の無加温ハウスで、ストックが終わり野菜がメインになった春の様子。4月中旬で、11品目・21品種の作物と苗類が同居中(*) |
「常識」は徹底的に疑ってみる、ということを栽培の基本にして、今後はさらに、自分ひとりでできる専業経営で、「ラクして儲ける農業」を追求していくつもりです。
最後に、今回、連載記事という企画を頂きましたが、その目的は、特定の作物の作り方を紹介したり、「○○農法」といった新しい生産方式の説明をしたりすることではありません。主眼点はもう少し根本的な部分の「儲かる農業経営」と、そのための「常識の疑い方」にあります。
次回からはごく一般的な作物の作り方・売り方などを例に「私のやり方」と「なぜそうするのか?」を紹介していきたいと思います。連載が終わる頃には「なるほど、そういうことだったのか」と、私の経営についての考え方を理解してもらえるような構成にしたいと思っていますので、しばらくお付き合いのほどをよろしくお願いします。