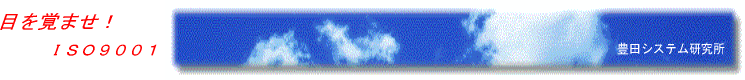
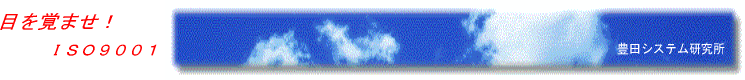
| ISO9001は、評価の基準である ISO9001の序文0.1一般に「この規格は、顧客要求事項、規制要求事項及び組織固有の要求事項を満たす組織の能力を、組織自身が内部で評価するためにも、審査登録機関を含む外部機関が評価するためにも使用することができる。と書いてあります。 つまり、ISO9001は、評価の基準なのです。規格を作った人たちは、品質マネジメントシステムを採用していて「顧客要求事項及び適用される規制要求事項を満たした製品を一貫して提供する能力をもつような組織であれば当然実施しているはず」という事柄を要求事項として書き表したのです。だから、要求事項はむしろ評価事項と読み替え、「すること」は「していること」と読み替えるのが妥当なのです。 しかし、ここで気をつけないといけないことがあります。審査機関によっては、当然実施しているはずのことを一つ一つ検証して、全ての当然実施しているはずのことが実施されていれば、顧客要求事項及び適用される規制要求事項を満たした製品を一貫して提供する能力があると判断してよいと考えているようですが、これは間違いです。規格の要求事項は、必要条件ですが、十分条件ではありません。逆は真ではなのです。森に木があるのは当然ですが、木がたくさんあるから森だとはいえないのと同じです。 また、“組織やその製品の性質によって、この規格の要求事項のいずれかが適用不可能な場合には、その要求事項の除外を考慮してもよい”とあるように7章については組織によって全く該当しない部分がある可能性があります。さらに“組織における品質マネジメントシステムの設計及び実現は、変化するニーズ、固有の目標、提供する製品、用いられているプロセス、組織の規模及び構造によって影響を受ける。品質マネジメントシステムの構造の均一化又は文書の画一化が、この規格の意図ではない。”“手順は文書にすることもあり、しないこともある。”“品質マネジメントシステムの文書化の程度は組織によって異なることがある。”とあるように7章以外の部分においても組織によって品質に影響が少ない部分があるかもしれないのです。だから審査では、ISOの認証を取得したければ要求事項を全て満たさなければならない(「この規格の要求事項に対しどのように満たしていますか」)とアプローチするのは間違いで、プロセスごとにそのプロセスの目的が達成されているかを検証しながら規格の要求事項を満たしていることを確認していくべきなのです。規格ではこれをプロセスアプローチと呼んでいます。 もともと品質マネジメントシステムの目的は、顧客要求事項、規制要求事項を満たした製品を一貫して提供するということです。だからその目的を達成するのに十分な手順があれば、当然規格の要求事項を満たしているはずなのです。不十分な手順を発見した場合のみ規格の要求事項を示して不適合とすればいいのです。 ISO9001は、評価の基準ですが、あくまでも評価するのは“組織の品質マネジメントシステムの能力”であり、評価の結果は、“能力あり”または“能力なし”のどちらかしかありません。 |