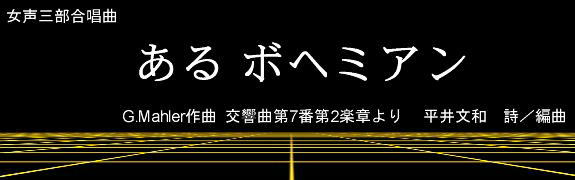
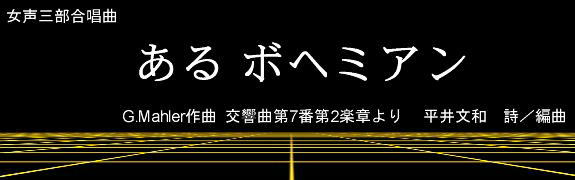
![]() 制作 2000.1.7
制作 2000.1.7 ![]() 演奏時間 約 14分
演奏時間 約 14分 ![]() 初演 2001.3.10
初演 2001.3.10 ![]() 製本済
製本済
 |
 無料 無料 |
 有料 有料 |
 無料 無料 |
| Main Menuへ | ご自由に | 合唱団の方に限定 | 公開中 |
この合唱曲は、マーラーの交響曲第7番「夜の歌」第2楽章に、歌詞をつけ歌えるように編曲したものです。また、原曲を基にピアノ伴奏をつけました。
マーラーの交響曲の特徴として、歌を伴う、もしくは歌の性質を持つ、ということがあげられます。テキスト(詩あるいは歌詞)を持ち、独唱や合唱で歌われるものは … 第2番、第3番、第4番、第8番、及び「大地の歌」です。
これに対し、テキストを持たず器楽的に演奏されるものは … 第1番、第5番、第6番、第7番、第9番です。
しかし、後者のグループに含めた曲も、無言歌のように歌謡的な旋律を多分に含み、その意味でテキストを求めていたといえましょう。ただ、気にいったテキストが見つからなかったのか、あえて言葉をふせたのか、結果的にテキストを伴っていません。
私は、特に第7番において、その感を深くします。このことは、第7番が難解であることと密接に関わっています。マーラーの第7番は未踏の麗峰であるとともに、夜の影の中にその輪郭をおぼろげに見せる、黙示の交響曲でもあるのです。私が第7番を合唱化しようとする理由がここにあります。
さて、第7番の第2楽章については、特に次のような点が疑問視されています。
(1) 「夜の歌」(Nacht-Musik)と指定されながら、行進曲の性格を持っている。(特に曲の第2部分において)
(2) 長調の曲なのか短調の曲なのか判然としない。
(3) 和音(ハーモニー)に透明感が欠けている。
(4) 形式(音楽の構成)や表現の意図が明確でない。
この合唱曲は、これらの疑問にひとつの答えを与えようとする試みです。
私が一番気に掛かったのも、上記の(1)でした。即ち、いったいどのような人物が、いかなる必要性をもって、夜に行進するのかということでした。
この合唱曲は、物語のように展開されます。
そこでは、あるボヘミアンが主人公として登場します。この主人公は、定職も持たず気ままな旅をつづけようとしますが、連れのロバやカラスがどうも素直に従いません。今日、世間一般でいう非常識と常識の対立です。この対立は、幾度かもつれた後、最終的にひとつのものに向かって高められていきます。
要素の対立 → 葛藤 → 昇華 …… これを複合性の変容と呼びます。マーラーの交響曲第7番を理解する上で、複合性の変容という概念は欠かすことができません。その概念を比喩的に分かりやすく示したのが、この合唱曲です。
人の心の奥には、ボヘミアンに対する憧れがあります。チャップリンや寅さんの映画が、あれだけ大勢の人々に愛されているのも、そのためです。人生が流れゆくものであるとすれば、人は誰しも、程度の差こそあれボヘミアンなのでしょう。しかし、そのひとりひとりの人生は、かけがえのない貴重なものなのです。
2000年1月7日
平 井 文 和