 |
 |
�l�֎ԉۑ�P
�l�֎��q
 |
�V�����O�o�X
�ʐ^�@�ʁ`������
 |
�V�����O�o�X
�ʐ^�@�ʁ`������

�o�X

�~�h���o�X

�C�X�Y���q

�q�m���q

���ʎ������q
�����̑O��

�����̑O��
���Ƌ��́A���S�m�F���������A�������A�������l�͌��ĂȂ��悤�ŁA���Ă܂��B
���A�Ⴂ�l�ɗ��s�́A�_���V�i�C�t�@�b�V���������āA�i�@�^�N�V�[�̉^�]�肪�A����ȁA�_���V�i�C�����������Ă邩�E�E�E�@�j
�����ł́i�@���ɑ�^���@�j�u���U�[���l�N�^�C���A �펯�ɐ����Ă���A�����L��܂��B
�����́A�����₷�������ŁA�����̓X���b�N�X�A�����́A�X�j�[�J�[�A�^���C���ǂ��ł��傤�B
��錧�ł́A���ɋC�ɂ��邱�Ƃ́A�����̂ł����A�ӋC���݂������Ă݂ẮA�������ł��傤���H
���Ԏ҂̏��
�҂̎��Ԏ҂́i�@�����A������q�������@�j�㕔���Ȃɏ��܂��i�@�V�[�g�x���g��Y�ꂸ�Ɂ@�j
�R���́A�s����h���ׂ̑[�u�ŁA�O�̎҂̑��s�A��������āA�ǂ��_���Q�l�ɂ��܂��傤�B
���S�m�F�`��ԁ`����
�������q�Ǝ��q���͂̈��S�m�F
���O���Ăꂽ��i�@�ǂ��Ԏ��@�j�Ƌ���n���i�@�ǂ����A�@�j�D��ۂ��������܂��傤
�i�@���Ƌ��҂́A�K���w�����m�F�@�j
���O�ց`�@���q���`�@����ց`�@�i�@����m�F���Č㕔�ɉ��@�j�`
�㕔�`�@�㕔���q���`�i���E�m�F���ĉE���ɉ��j�`
�E��ց`�@���q���`�@�E�O�ց`�@�i�@�O���m�F���Đ��ʂɉ��@�j�O���`�@�O�����q���`�@
�i�@���E�m�F���ĉE���ɉ��@�j�`�@�^�]�ȃh�A�O�Łi���E�j�O������m�F�`�@
�i�@�h�A�J���@�j��ԁ`�@����h�A����m�F�`�@�h�A�߃��b�N
���
�h�A�[�����b�N������A�u���[�L�A�N���b�`��ŁA���Ȃ����킹�܂��B
���̎��A�M���p�^�[�����m�F���A�j���[�g�����ɂ��܂��B
�i�@��^�̏ꍇ�A���[�J�[����q�ɂ���āA�p�^�[�����Ⴂ�܂��@�j
�T�C�h�u���[�L���A�m�F���܂��i�@�I�[�g�}�Ԃ͈Ⴂ�܂��@�j
���[���~���[���A���킹�܂��i�@��ŐG��Ȃ��ƁA���_�ɂȂ�܂��@�j
�V�[�g�x���g�����āA�������l�Ɂi�@�n�߂܂��@�j�Ɛ��������܂��B
�i�@�����́A�n�܂��Ă܂��@�j�ƌ����A�������l�����܂����A�C�ɂ��Ȃ��ʼn������B
����
�N���b�`��ŁA�G���W���n���B
�i�@�^�]�Ƌ��Z���^�[�̎Ԃ́A�N���b�`�܂Ȃ��ƁA�n�����܂���@�j
�i�@�ܓ_�m�F�A�K����U��ڎ��@�@���Z�_�@�j
������ڎ��`�@���~���[�`�@���[���~���[�`�@�E�~���[�`�@�E����ڎ�
�i�@���[���~���[�́A �ۑ�O�A�ۑ�ʉߌ�A���s���ȂǁA���т��ъm�F���܂��傤�@�j
���ʓ��A��^���̏ꍇ�A��q�̈��S���m�F����ׁA�U�_�m�F�ƂȂ�܂��B���q�l�̏�~��z�肵����Ԃ���̔��Ԏ��ɂ́A���q�l�̈��S�m�F���K�v�ŁA�q�Ȃ̖ڎ��m�F�����܂��B
�����w����`�@�M���i�@���ʈꑬ�A��^�@�j�`�@�T�C�h�u���[�L�����`
�i�@�ܓ_�m�F�@�j�`�@����
�i�@���Ԃ̎��́A�ォ�牺�ցA�@�w����@���@�M���@���@�T�C�h�u���[�L�@�j

�������o���A���ʎԃR�[�X�����
�������o���́A�S�ẴR�[�X�ŁA���܂ŏo�܂��B���S�����炩�ŁA����ꍇ�A�ꎞ��~����K�v�́A�L��܂��A���E�̈��S�m�F�A�������݊m�F�A�i�@�R�[�X�ɒ��p�ɂȂ�ꍇ�A�����w����̕t�������@�j�͕K�v�ł��B�R�[�X�ɋ߂��A�����_���甭�Ԃ���ꍇ�A������ʂƓ�������ŁA�R�[�X�ɏo�܂��B�i�@���Ԃ��Ă���́A�����ɂȂ邽�߁A�̓_����܂���B�ׂ����_�́A�C�ɂ��Ȃ��Ă��A�ǂ��̂ł����A�X���[�Y�ȑ��s���o����悤�ɐS�����܂��傤�@�j
�������s
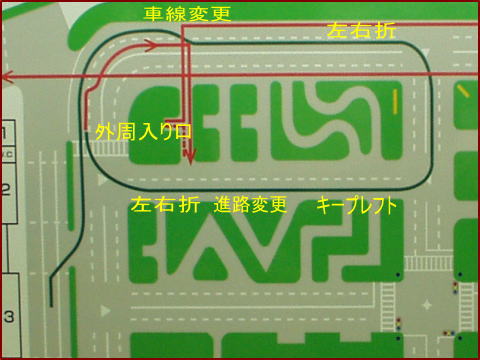
�������s
�������s
�������s�̎n�_�́A�肩�ł́A����܂��A���Ԃ��Ă���A���Ŏ����͈͂ł��B�������s�́A���_�̑Ώۂɐ���܂��A�X���[�Y�ɑ��s���邱�ƂŁA�������l�ɁA�D��ۂ�^���܂��B
�L�[�v���t�g
�����Ƃ��āA�Ԑ��̒������A�����𑖍s���܂��A��^�������q���C�������x�������B�������A���܂��鎞�̊����m�ۂ��āA�L�[�v���t�g�B�����������A�Z���Ă��A�L����x�̑��x���o�������n����t���܂��傤�B
�J�[�u
�J�[�u�̎�O�ŁA�u���[�L���O�A�J�[�u���ł̃u���[�L�́A���_�ł��A�L����x�̑��x��ۂ��A��^�́A��ւɋC��t���āA�J�[�u���܂��B
�i�H�i�@�Ԑ��@�j�ύX�@�i�@�J�[�u���߂�����Ԑ���ύX���܂��@�j
�~���[�i�@���[�������T�C�h�@�j�m�F�`�@������ڎ��m�F�`�@�����w����`�@������ڎ��m�F�`�@�~���[�m�F�`�@�i�H�i�@�Ԑ��@�j�ύX �i�@�Ԑ��ύX��́A�L�[�v���t�g�B�X�O�ɍ��E�܂̏ꍇ�́A�Ԑ��ύX���_�ŁA�Ă����܂��@�j
�Ԑ��ύX����E�܂̎菇�ł��A�����A���Ԃ́A�l�����Ă܂���
�i�H�ύX�A���܂̎菇�ł��A�����A���Ԃ́A�l�����Ă܂���
���E�܁@�i�@�������s�͉E�܂̘A���ł��A�Ԑ��ύX�������_�ŁA�E���ɊĂ����܂��@�j
�~���[�i�@���[�����ܑ��T�C�h�@�j�m�F�`�@�ܑ�����ڎ��m�F�`�@�ܑ������w����`�@�ܑ�����ڎ��m�F�` �u���[�L���O�i�@���x�ɉ����ă|���s���O���M�A�_�E���@�j�`�@�������݊m�F�i�@���E�����̊������݊m�F�̕Ȃ�t���鎖�ŁA�Y��鎖�������Ȃ�܂��@�j�` �ܑ��~���[�m�F�`�@���E��
��x�ڂ̉E�܂́A�����Ԑ��ɊĐi�������܂����A��x�ڂ̉E�܂́A�L�[�v���t�g�Ői�����A�i�H�ύX������ɁA�O���ɏo�܂��B

�O���̓����
�������s���ς܂�����ɁA�O���ɏo�܂��A�s�������_�ɂ́A���H�W��������A���̎��_�ł̌��_�͂���܂��A�W���ނƌ��_�ɐ���܂��̂ŁA�W���܂Ȃ��悤�ɁA�O���ɏo�܂��B���f�������߂����n�_����A�̓_�̍ĊJ�ł����A��^�������q�ł́A���ɁA��ւɒ��ӂ��Ȃ��ƁA���f�������珑���ꂽ�Ԑ��ނ��ƂɂȂ�A���f�������߂����n�_�ŁA�O���̒ᑬ�Ԑ��ɃL�b�`������Ȃ��ƁA���_�ƂȂ�܂��B�i�@�s�������_�̕W���ގ������O���̒ᑬ�Ԑ��Ɏ��q�𑖍s�����܂��@�j

����
�����A�l���i�@�M�A�̎w��́A�L��܂��A�l���ɓ���܂��@�j�S�O�L�����[�g���������ێ����đ��s���܂��B�X�s�[�h�̏o���������A���_�ł��B�|���s���O�u���[�L�ŁA�P�O�L�������ȉ��Ɍ������A�M�A��ɂ��Ƃ��A���s�̓��H�W����ʉ߂��܂��B

��Q��
��Q������菇�@�i�@�Ԑ��ύX�@�j
�@���@���s���A�J�[�u���߂��Ă���A�������܂��A�i�@�g�@�j�̎������_���߂��Ă��炪�x�X�g�B
�@�@�@���[�����ړ����T�C�h�~���[�ŁA���S�m�F
�@�A�@�ړ����̌���ڎ��m�F
�@�B�@�����w����n�m
�@�C�@�i�@���x�ɉ����ă|���s���O�u���[�L�@�j�����w����_���m�F
�@�D�@�Q�x�ڂ̈ړ�������ڎ��m�F
�@�E�@���[�����T�C�h�~���[���m�F���Ȃ���A�n���h������
�@�@�i�@���S�ɎԐ����ړ����A�����w����n�e�e�̊m�F�@�j
�@�F�@�߂鎞�́A�@�`�E���B
�@�@�i�@�n���h������́A���q�̑O�֖��͎��q�̒��S���A��Q�����z���Ă��瑀�삵�܂��B�j
�@���@�Ԑ�����Ԑ��ȏ�L��ꍇ�́A�Ԑ���ύX���āA��Q����������܂��A
 |
| �菇�ł��A�����A���Ԃ́A�l�����Ă܂��� |

�⓹���i
�⓹�̒����ɒ�~����������Ă��܂��̂Łi�@������Ă������Ղ��L��܂��A��O�̔����Œ�~�A���Ȃ��l�Ɍ䒍�Ӊ������@�j�����ŁA�ꎞ��~���A�T�C�h�u���[�L���������܂��B��~������A���q���͂̈��S���m�F���Ă���A���삵�܂��B���ʎԈꑬ�A��^�ԓA���g���A�G���W���̉�]�����グ�A�N���b�`���A�������ƁA�Ȃ��܂��B�G���W���̉��ɒ��ӂ��āA�G���W���̉�]����������n�߂���A���N���b�`�ɂȂ��Ă��܂��̂ŁA�T�C�h�u���[�L���������Ĕ��i���܂��B��̒���t�߂ɁA�x�J�点�̕W�����L��܂��̂ŁA�N���N�V������炵�Ēʉ߂��܂��B�����́A�A�N�Z�����瑫�𗣂��A�u���[�L�y�_���̏�ɁA�y�������悹�A�����w����������āA�~��܂��B

���ݐ�
��~���Œ�~���܂��A���ݐ�ɂ͌��z���t���Ă���A�T�C�h�u���[�L���g�p���܂��B�����J���āA���̊m�F�A���q����̊m�F�A���E�̈��S���m�F���A�G���W���̉�]�����グ�A�N���b�`���Ȃ��܂��A�T�C�h�u���[�L���������A���q�������o������A���E�̊m�F�����Ȃ���ʉ߂��܂��B�i�@���q�S�̂����ݐ��ʉ߂�����ɃM���`�F���W�����܂��A�������q�Ȃǂ̏ꍇ�A���ӂ��K�v�ł��B�j

�r���@������@�����
���ʎ��q�A��^���q���ɉE�ܐi���ł��A���ʈꑬ�A��^�ŁA���N���b�`���g���A���s�Ői���A�E�����Ɋ܂��B���ʎ��q�̏ꍇ�A�^�C�����ǂ̈ʒu�ɗL��̂����A����߂�̂��|�C���g�ŁA���Ƀ^�C�������킹��p�ɁA�n���h���𑀍삵�܂��B��^�Ԃ̏ꍇ�n���h�����A��^���̓n���h���̒��S�����ɉ��킹�đ��삵�A�r���̒����܂ő��s���܂��B

�r���@�E���
����肪�I�������A�n���h�����X�O�ɂ͖߂����ɁA�������q�������̒����ɂȂ�����A�n���h�����A���O�ւ��A�������Ɋ��܂Œ��i���āA���ʎ��q�́A�������Ƀ^�C�������킹�ĉE��肵�܂��B��^���q���A�����悤�Ƀ^�C�������ɉ��킹�܂����A�����̒���������ɁA�n���h���̒��S�����킹�ĉE��肵�܂��B

�r���@�o��
�o���Ǝ��q�����p�ɐ���܂ŁA�E�������܂��A���܂���ꍇ�A���q���C�����A�E���ɊĂ����܂��A���ӂ��Ȃ��ƍ�����ւ�E�ւ��܂��B
���S�����炩�ȏꍇ�A�ꎞ��~����K�v�͗L��܂��A���E�̊m�F�A�������݊m�F�́A�K�v�ł��B

�r���P�A���܂Ői�����܂��B

�r���Q�A�E�����ɑO�ւ����킹�č����

�r���R�A�����̈�Ԑ[���Ƃ���ł�

�r���S�A�E���ɐ�ւ���

�r���T�A�������ɑO�ւ��܂�

�r���U�A���ɉ����đ��s

�r���V�A�o�����܁A�^�������Ɏ��q�������o���A����ւɒ���

�r���W�A�R�R�ŃL�b�`���ƊċȂ���Ȃ��ƁA����Ō��_�ł��B
| �t���[���\�� |