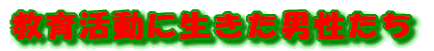
| 新島 襄 天保14年(1843.2.12)1月14日〜明治23年(1890)1月23日 | |
| キリスト教主義教育者、同志社の創立者。 《生い立ち》 上州安中藩の祐筆である父・新島民治(たみはる)と、母・とみの長男として江戸藩邸(神田一ツ橋通リ小川町)で生まれた。幼名は、七五三太(しめた)。上に4人の姉(くわ12歳、まき9歳、みよ5歳、とき3歳)がいた。 弘化2年(1845)新島襄(七五三太)が3歳のとき、長姉くわが松平能登守家臣加賀野加賀右衛門へ嫁いだ。三番目の姉・みよが七五三太を背負っていたとき、過って転倒したため、みよは生涯左脚の自由を失うこととなった。 七五三太が5歳のとき、弟・双六が誕生した。双六は、開成学校に通っていた明治4年(1871)に死去した。新島襄がアメリカ留学中の出来事だった。 嘉永元年(1848)2月14日、6歳になった七五三太の「習字初め」の日であり、以後、毎日ほとんど半日を習字の稽古に費やした。 嘉永3年(1850)8歳のとき、凧揚げや独楽まわしはもとよより外遊びを好む元気な七五三太だったが、ある夕暮れ時に躓いて切石に額を打ち、前額の左端から眉の上のあたりに大負傷をした。そのため2月ほど外出ができなかった。このときの傷は生涯傷痕を残すこととなる。姉たちを困らせることがあると、彼女らは「メッパチ、メッパチ」と七五三太をからかった。 これより粗暴な戸外遊びを好まなくなり、家でもっぱら読書や習字をやり、近隣の画家について山水花鳥の初歩を学び始めた。また両親の意図で礼法の師について礼儀作法の教授を1年以上にわたって受けた。 安政3年(1856)14歳の七五三太は、藩儒添川廉斎の指導のもとで漢籍の勉強に励むこととなった。さらに藩主がはじめて蘭学者を招聘し、門生として藩のなかから優秀な子弟3名を選抜することとなった。その1名に七五三太が選ばれ、最年少者として蘭学の教授を受けた。 安政4年(1857)15歳で藩主の寵により学問所助勤を仰せつかり、句読師となった。 その年の11月15日に元服の式を挙げた。当時の安中藩では、士以上の子弟はその年の1月15日に、士以下はその年の11月15日に元服する習慣だった。新島家は家格が低かったために11月15日に行った。ともあれ、七五三太は、今後は「敬幹」と改め、祐筆補助役を仰せつかった。 元服後の新島は御殿に出仕を命ぜられ、初めて故郷の安中を訪れた。 同僚とともに藩主の出入りの送迎や記録の保管をする職務に対して日々の時間浪費に苦しみ、職務に嫌気をさし始めてきたが、17歳のとき、蘭学をもう一度学び始めた。夜も熱心に勉学に励み、かえって目を患うこととなった。 萬延元年(1860)18歳の新島は、藩の許しを得て、幕府の軍艦教授所に通い数学を学んだ。このころから江戸湾からオランダ軍艦を遠望しては海外文明の進歩に驚き、自ら二本の改革者、日本文明の先導者となろうと、いっそう航海学その他の勉強に励んだ。海軍教授所では世話役(生徒組長)に選ばれた。 このことによりヨーロッパやアメリカへ開眼し、またキリスト教にも関心をもち、心を惹かれるようになった。 21歳のとき、函館から国外に脱出し、アフリカの南端をまわってボストンに上陸した。船主のアルフュース・ハーディ夫妻の好意で高等学校への編入学ができた。次いで、アーモスト大学、アンドーヴァー神学校に学んだ。 アメリカ留学中に父・民治あてに出した書簡(慶応3年3月29日)には、ハーディ夫妻の親切が述べられ、アメリカの学校には自由学校があると、その学校の説明が認められている。 此学校は一文も取不申候故いかなる貧乏人も入門いたし学問修行いたし候故此国には目あき目くら則ち読み書きのできぬものは本一切無御座候 《受洗》 会衆派の教会で洗礼を受けた。 《祖国へ戻る》 キリスト教主義大学設立の夢を抱いて10年ぶりに祖国の土を踏んだ。アメリカでの呼び名”Joseph”(ジョセフ)を”襄”と改めた。 大阪での学校設立計画に失敗したのち、京都府顧問・山本覚馬と会い、京都を候補地と決め、アメリカン・ボード(会衆派系の外国伝道局)の経済的援助のもとに、山本やJ.D.ディヴィスの協力を得ながら明治8年(1875)11月29日、同志社英学校を発足させた。 《結婚》 翌9年1月、山本覚馬の妹・八重子とキリスト教風の結婚式を挙げた。 《教育活動》 結婚をしたその年、同志社英学校に、いわゆる熊本バンドの有志が入学した。彼らは、海老名弾正、金森通倫、小崎弘道、横井時雄らであった。 明治10年(1877)4月、同志社女学校の開校が京都府によって認可された。 総合大学設立の構想を立て、「同志社大学校設立趣意」を作成し広く天下に協力を求めた。新島襄自身、東奔西走し、健康を害して小田原で客死した。 《著書》 『新島襄全集』、『新島襄書簡集』(1960)がある。 《新島襄の葬儀模様》 新島は、1890(明治23)年1月23日午後2時20分、その前年の12月27日から療養していた神奈川県大磯の百足屋でこの世の生命を終えた。彼の生涯は46歳11カ月であった。病名は急性腹膜炎症。新島の遺骸は大磯から京都まで鉄道によって運ばれ、1月24日の夜中に京都ステーションに到着した。駅に出迎えたのは600余名の「同志社教員、職員、及び男女両校生徒並京都教会、四条教会、交話会員中有志者、及び他校生徒数名等」(「葬儀記録」)であった。折からの雪まじりの雨の中、遺骸は普通科生徒、神学科、邦語神学科を7組に分けて交代で担われ、自宅に向かった。 1月27日正午から、自宅で出棺式が営まれた後、柩は同志社に移され、午後1時から葬儀が営まれた。チャペルの前にテントを設営し、会葬者は4000名を越えた。葬儀の説教は、小崎弘道がヨハネによる福音書12章24節からおこなった。「一粒の麦若し地に落ちて死(しな)ずば唯一にて存ん。若し死ば多の実を結ぶべし」という聖句を引いて、「先生の死たる事業の為に其命を棄てたるものにて、或人が唱へたる如く、或る意味に於ては殉教者の死と謂て可なり」と述べた。 葬儀が始まってまもない午後1時半ころから雨になった。葬儀を終えた柩は、同志社各学校の生徒に交代で担われ、若王子の墓地に向かった。「葬送者の総数ハ明知する能ハずと雖も凡ソ三千人余にして、行列の長は十二三町程なりしと見受けたり」。この葬列のなかに、勝海舟の筆になる「自由教育自治教会 両者併行 邦家万歳」という幟もあった。 山頂に達したのは午後5時前。埋葬を終えたのは午後6時頃であった。1月末の雨の若王子山頂は、暗黒の闇に閉ざされていたはずである |
|
| 出 典 | 『新島書簡集続』 『キリスト教歴史』 『キリスト教人名』 『新島襄』 http://kohara.doshisha.ac.jp/virtual_museum/neesima/20.html |