「おじさん」的思考、内田樹、晶文社、2002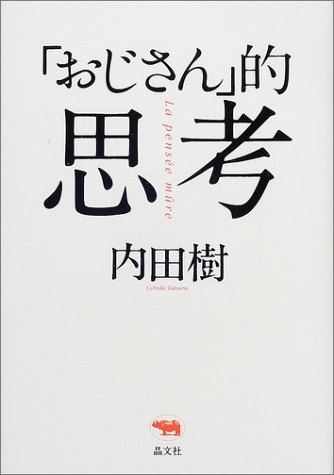
出かけた先で、居間に置いてあった本を読む。内田の名前はネット上で見たことがある。本は読んだことがなかった。 内田は、アイデンティティの多様性について徹底した考えをもっている。一般的には多様性というと、画一、均質の反対と考えられている。そして個性、独創性、差異、差別化といった言葉が多様性を差支える概念として高く評価される。これに対して内田の考えでは、差異を強制することは多様性に反する。つまり、均質であることも多様性の一つのあり方として認められるべきであるし、また社会生活上、有益でも必要でもあると考えている。 具体的な例として、日本語的な名前を通称として使う在日韓国人に、本籍名を強要する場合をあげている。通称を使うかどうかは、社会的環境に基づき本人の意志によって決められるべき問題であって、いわゆるカムアウトして本籍名を名乗ることが、その人のアイデンティティにとって絶対に必要なことではないと内田は述べている(「自称リベラリストたちが陥る論理矛盾」)。 内田の考えによれば、日本名を強要するのも抑圧ならば、本籍名を強要するのも別な形の抑圧。夫婦別姓、専業主婦という職業などについても、まったく同じことが言えるだろう。実際、内田は同じ論理で、夫婦別姓主義者を批判している(「別姓夫婦の『先進性』に意義あり」)。 均質であることを選ぶことも、多様性のあり方の一つであるという考え方に加えて、内田の多様性理解の特徴は、政治的アイデンティティを絶対視しない点にある。つまり、国家に結びつくアイデンティティをその他のアイデンティティに優先させない。「『在日韓国人』と『在神戸福岡県人』のあいだに帰属意識のあり方において、原理的な違いはない」という考え方は、象徴的にそうした特徴をまとめている。 私の考えを付け加えれば、『在日韓国』『在神戸福岡県』という概念に含まれる日本、韓国、神戸、福岡という概念もそれぞれに多様な要素を含でいる。そしてその境界は明確に区切られているのではなく、隣り合う概念(韓国、西宮、大阪、佐賀など)とは重複する部分をもち、グラデーションのように次第に移り変わっている。 福岡県に生まれ、神戸で働き、韓国に旅行したり、韓国の会社と取引したりする人もいる。神戸に住み、西宮で働き、大阪で買い物をする人もいる。その生活のなかで、国籍や民族への思い入れは、労働や余暇、購買と原理的に違いなく、何に重きを置くかは、個人によって決められるべきだし、実際、そうなっているに違いない。 政治的アイデンティティの多様性については、共感するところが少なくないが、本書で違和感をぬぐいきれなかったのも、この多様性についての考え方。具体的には読書の多様性について。政治的アイデンティティでは徹底された多様性が、なぜか読書については徹底されていない。 「苦役に耐えるようにして読まなければならない書物というものがある」「みなさん文学を読みましょう」と、内田は説教する(「ひとは『ドラえもん』だけで大人にはなれない」)。若い人に必要なことは「終わりなき自己解体と自己再生である」から。それに異論はない。ただし、その方法は読書だけには限るまい。 『ドラえもん』だけでは大人になれないとしても、読書だけでも大人にはなれない。スポーツ、音楽、いや、そんな「何か」ではなく日々の生活のなかさまざまな出来事からでも、人は「自己解体と自己再生」を迫られ、そのとき誰でも否応なく言葉を通じて、あるいは身体を動かして、その苦しみを乗り越えようとするのではないか。文学はその一助に過ぎないのであって、唯一絶対ではない。 内田自身、武道にも造詣が深く、読書以外にも「自己解体と自己再生」を若者にもたらす方法を知っているに違いない。にもかかわらず、この文章のなかでは、内田は読書を「自己解体と自己再生」の唯一の方法だと考えているように見えてしまう。端的にいって、内田は読書至上主義に陥っている。 それは、中原中也を「なかや」と読んだ友人をからかったことを懐かしく思い出し、ドストエフスキー、バタイユ、マルクス、ニーチェなど難解な小説や思想書を列挙している点などに感じられる。現代思想の教員としてそれらを推薦するのであれば、それは「おじさん的」ではなく、単なる「教員的」思考というもの。それにしても読書至上主義者はなぜいつもドストエフスキーを挙げるのだろう。 読書をすれば大人になれるかもしれない。しかし、読書をしなくても大人にはなれる。それは内田の多様性に対する考えに従えば、自然に導かれる結論。実際、ドストエフスキーが生まれる前にも大人はいたのだから。 これは内田だけではなく、ウェブサイト上のエッセイからこの一編を選んだ編集者の意図とも関係しているのかもしれない。いずれにしても、「みなさん文学を読みましょう」と本書のような性質の本で述べても、釈迦とは言わないまでも、熱心な檀家に辻説法するようなものではないだろうか。読書をする人がこの一文を読んで感じるのは、「そうだよな、若者は読書が足りないな」というほとんど根拠のない著者への奇妙な共感と若者への軽蔑であって、著者が期待するような「私も読まなければ」という反応ではないだろう。 要するに本書では多様性への理解が、政治的な領域では徹底されているものの、思想的な領域では充分に徹底されていないように感じられる。この不徹底さ、いうなれば多様性理解の綻びの延長上に、書名ともなっている「おじさん」という概念がある。 本書を読んでみて、いくつか共感する考え方もみつけられた。それでも、それらの考え方が「おじさん」という概念とどう結びつくのか、よくわからない。「おじさん」という鍵概念によって、むしろ内田の考えが矛盾させられているようにみえる。内田は、これまでは意識的に逆らってきた「インテリで、リベラルで、勤勉で、公正で、温厚な『日本の正しいおじさん』」を擁護するつもりだという(「あとがき」)。その一方で、内田が批判の対象としているのは、多様性のなかに潜む画一性、反体制のなかに潜む教条主義など。実はこれらこそ、「日本の正しいおじさん」たちが今、陥っている思想的破綻ではないだろうか。 表面的な政治闘争に酔いしれ、「なんとでも言ってくれ。おれは東大出という看板を棄てるわけにはいかないんだよ」と平気な顔で一夜のうちに転向し(「転向について」)、モーレツ社員であることで怠惰な家庭人であることを正当化し、バブルを成功体験と勘違いし、今になっては、国運を分けた闘争すら同窓会気分で懐かしむ。「日本のおじさん」と言われて思い浮かぶのは、こうした世代。 内田が展開するような徹底した多様性の容認、転向などと気取らず、現実に合わせて姿勢と行動を修正するしなやかさなどは、むしろ「おじさん」達より若い世代に見られるような気がする。内田が批判すべきは自分より若い世代ではなく、実は彼が擁護しようと目論む同世代ではないだろうか。そして内田が励まそうが何しようが、彼ら自ら「自己解体と自己再生」をしなければ、彼らが衰退と自滅の一途をたどるのは避けられないだろう。 また内田は、売春する少女、学校で暴れる少年らを理屈ぬきで、というより「おじさん」の理屈で説教しようとしている。ここで問題となるのは「おじさん」の理屈の中身ではなく、「おじさん」が若者を説教するという構図をとることによって、若者と「おじさん」を対立させ、売春する少女がいるような世代、平気で人を刺す少年のいるような世代であると、若い世代を平板に見る結果になっていること。 問題は、「おじさん」という「世代」を意識させる言葉にある。内田が想定する「おじさん」も、そこから私が想像する「おじさん世代」も、ある時代のなかで、ある体験を共有している人々であり、その年齢のほんの一部分に過ぎない。 今や世の中は多様化して世代によって簡単に気質を論じることは難しくなっている。このことは内田自身も積極的に認めている。同じ世代であっても、平気で人を殺す人もいれば、多様な政治的アイデンティティを真摯に模索する人もいる。それは若い世代でも「おじさん」世代でも変わらない。それを若者世代とひとからげにして、「売春するな」「文学読めよ」と説教することは、彼自身の多様性理解と矛盾してしまうのではないか。 つまり今問題にすべきは、「おじさん」的思考の凋落などではない。おじさん、若者といった従来一括りにできた世代ごとに、思考の同質性はなくなっている。そのかわり、同じ世代のなかに倫理観、政治感覚、経済観念、それらを支える知識と資産に、無視できない格差が広がっている。それがいつの世にもある、いわゆるジェネレーション・ギャップと化学反応を起こして、多様性というよりも社会全体を混沌とした状態にしている。それこそが今、考えるべき問題ではないだろうか。 内田は、批判すべき同世代を擁護すべき対象としてしまい、若者世代を対立する世代と設定してしまっている。このように考えると、「おじさん」という概念をもちだすことにより、彼は自分の位置を固定化してしまい、その結果、観察対象をも固定的に見るという、二重の矛盾に陥っていると言える。 ばらばらに書かれたエッセイのなかから編集者が編んだ本書に対して、このような批判をするのは揚げ足取りかもしれない。それでも共感する点も少なくないだけに、違和感はかえって致命的にひびく。言葉だけによって思想を表現することの難しさをあらためて痛感せざるをえない。 |
碧岡烏兎 |