忘れられる過去、荒川洋治、みすず書房、2003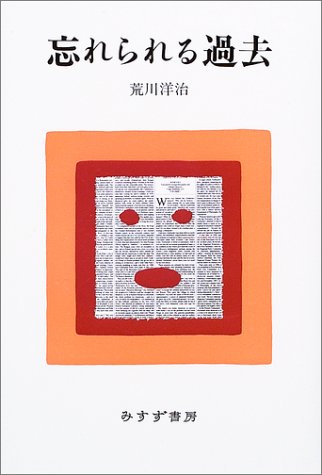
荒川洋治の文章を読み終えると、話しかけたくなる。目の前に著者がいないのがもどかしい。毎週ラジオで、森本毅郎と息の合った対話を聴いているからだろうか。実際、本書に収められた話題の多くは、ラジオでも耳にした。 いわゆるネタが同じでも、おしゃべりと文章はまるで違う。ラジオで聴いた時に印象に残るのは、二人の掛け合いや笑い声、聞いたことがある固有名詞など。ラジオは区切られた放送時間を意識しているのか、起承転結のなかでは、起承まではゆっくり話しているけれども、あとは掛け合いになったり、急ぎ足になりがち。文章では、当然、荒川が選んだ言葉、とりわけ文章を締めくくる一文が強く印象を残す。 だが小説も詩も読まれなくなったいまのような時代には、名前が「読める」か「読めない」かは一大事である。(「読めない作家」) 犀星は永遠や遠い過去だけを歌う人ではなかった。昨日、今日、明日という身近な日のそこにあるものを真剣に見つめた。だから今日からも明日からも、昨日からも詩が生まれたのだ。(「きょう・あした・きのう」) 昔の詩人のたまごたちは、そんなことばっかりしていたのである。おばかさんといえばおばかさんだ。基本だけで生きていたのだ。(「価格」) こういう言葉づかいを詩人ならではと評するのはたやすい。しかし、詩的な言葉を、本来論説的であることを主眼とする批評や書評でつかうことは両刃の剣になる。批評はあいまいととられ、詩は文章の装飾とみなされてしまうから。本来、批評家ではなく、詩人である荒川は、詩が散文の一部分とみなされることに危機感を抱いている。 「詩のことばはフィクションである」という理念を放棄したとき、詩はあたりさわりのない抽象的語彙と、一般的生活心理を並べるだけの世界へとすべりおちる。「詩のことばはすなわち散文のことばである」とみられることへの恐怖心を、とりのぞく。そこから新世紀ははじまるべきだろう。(「詩を恐れる時代」) こう述べながらも、荒川は批評、書評に詩的なことばを使い続ける。恐怖心を打ち払うために、あえて「散文の言葉すなわち詩の言葉」として用いているようにみえる。 おそらく、詩人にとっては、使われる場所が散文であろうと、詩であろうと、あるいは会話であろうと、言葉は記号である以上にフィクション。つまり、言葉じたいが、詩。 保田與重郎について、荒川は「他人にはまぼろしと見えることばをかかえて生きた、市民の一人であった」と書いている(「『詩人』の人」)。他人にはまぼろしと見えるからこそ、過去は忘れられて、人の名前も忘れられても、言葉は忘れられない。言葉は生き続けていく、まぼろしとして。 本書には、そうした、忘れられない、まぼろしのような言葉が、たくさん詰まっている。 さくいん:荒川洋治 |
碧岡烏兎 |