序論
「前ロール」とは、手書きの要約筆記の情報保障時に、事前に用意された話者の原稿内容を
OHP専用のロールシート等に書いておく物をいいます。これを、話者の話に合わせ表示してゆく
ことを、「前ロールを流す」といいます。
また、この前ロールは、全文を伝えたい、事前の原稿をそのまま読む、氏名を正しい漢字表記
で表示したいなど、より正しい情報を伝えたい場合などに使用します。
◆基本的な「前ロール」加工
パソコン要約筆記で使う「前ロール」は事前の原稿等をテキストデータ化し、句読点や、文節で
区切り、話し手の言葉のタイミングに合わせて、排出(表示)していくものです。
例
【本文】
今日は、大変気温も高く、各地で桜が満開となり、見頃となっています。
【前ロール】
今日は
大変気温も高く
各地で、
桜が満開となり、
見頃となっています。
この様に、長い文章を区切ったデータを準備し、話し手の言葉に合わせて排出し、文章を組み
立てて表示します。
◆加工の注意点
しかし、この区切り方にも、工夫が必要に成ります。
理由として次の様なことがあるからです。
1.加工した区切り方と話者の区切り方が違う
例
【話者の音声】
今日は 大変 気温も高く 各地で 桜が 満開となり 見頃となっています。
【加工文字】
今日は 大変気温も高く 各地で 桜が満開となり 見頃となっています。
// まだ言っていない言葉を出してしまったり、言い終わるまで文字を出せない //
2.原稿と違う事を追加や削除してしまう
例
【話者の音声】
今日は、 気温も高く 全国各地で 桜が満開となり 見頃となっています。
【加工文字】
今日は 大変気温も高く 各地で 桜が満開となり 見頃となっています。
// 追加した言葉を省いてしまったたり、言っていない言葉を出してしまう //
| 3.文字がずっと流れていて、読みにくい | ||
| 文字を読んでいるのに、次々に文字が加わり 読むのに疲れる。また、スクリーンに釘付けになり、 話者や資料を見ることができない。 目で文字を追うだけで、必要部分だけを読む、 「流し読み」が行い難くなる。 |
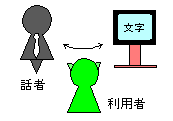 |
|
4.大会場の式典などの挨拶文では、ゆっくり正確に話す。
大会場では、エコーが発生し、聞き取り難くなるため、短い文節に区切って、ゆっくり
話します。
例
本日は ここ 福祉会館に おいて お忙しい中 多数の ご臨席者を 賜り…
5.代読、解説文は感情や抑揚を入れないため、早口になります。
例
平成○年○月○日 埼玉県議会議長 ○○○ 本日はおめでとうございます
この様な場合の事例については、 次の表のデータから 予測できると思います。
◆標準的な加工
以上の事から、加工については、次のような考え方を元に加工をしています。
1.細かく、加工する場合
・大会場の式典などの挨拶文
・本番に違う言葉や、追加をする恐れがある場合
・ゆっくりとした話し方をする場合
・前文を長く残しておきたい場合
2.長目に加工する場合
・参考資料等、棒読みの原稿
・代読文章など、100%忠実に読む原稿
・組織、団体名、スローガンなどの固有(固定)単語
・字幕など、一括標記し、前文が残らない場合。
◆特殊な加工
次のような場合は、特殊な加工をします。
1.表示行数が極端に少ない場合
画像合成などで利用する場合は、2,3行と表示できる行数・文字数が少なくなって
しまいます。このため、「泣き別れ」が生じてしまうと、読む時間もかかり、さらに残像
の文字数(情報量)も少なく成ってしまいます。
事前に表示文字数を加味し、泣き別れがないように、漢字をひらがなに、ひらがなを
例 表示文章 前ロール 通常加工 今日は、大変お忙しい中、お集まりいただき、
まことにありがとうございます。お礼申し上げま
す。今日は、
大変お忙しい中、
お集まりいただき、
まことに
ありがとうございます。
お礼申し上げます。特殊加工 今日は、大変お忙しい中、お集まりいただき、
真にありがとうございます。お礼申上げます。
今日は、
大変お忙しい中、
お集まりいただき、
真に
ありがとうございます。
お礼申上げます。
漢字にするなどして、「泣き別れ」がないように加工します。
◆排出タイミング
前ロールの排出タイミングについては、いろいろと議論されるところですが、大きく3つに
分類されると思います。
1.音声と同時に排出する
皆さん、おはようございます。
▲排出タイミング
話者の第一声と同時に表示されますので、同時性があがり、聴覚障害者にとっては、一括
して、情報を取り入れることができます。しかし、健聴者にとっては、話の内容が先に解って
しまい、つまらないという意見が出てきます。また、話の内容が異なると、加筆、修正が
出来無かったり、間違って、話す前に排出してしまうというミスが生じ易いです。
映画字幕では、シーンに合わせる為、台詞の第一声と同時に表示します。出来るだけ表示
している時間を長くする目的もあります。健聴者としては、台詞と同時でないと、気持ちが
悪くなるという方も多いようです。
2.話しの途中で排出する
皆さん、おはようございます。
▲排出タイミング
ある程度話しが始まり、文章の後半も大丈夫であろうと言う場合は、話しの途中で排出
します。話し言葉より、読む時間の方がはやい為、途中から始まっても、最後まで読む
事が出来ますし、「早合点」して先に出してしまうミスが防げます。
おおよその現場ではこの方法を用いています。
3.話し終わってから排出する
皆さん、おはようございます。
▲排出タイミング
「事前原稿を読んでいる」と思われたくない話者や、リアルタイム入力との排出タイミング
を合わせるため、に有効です。また、内容を確認して排出できるので、突然の内容変更
にも対応出来ます。
反面、文字の排出まで時間がかかるので、同時性が損なわれてしまうという欠点が
あります。さらに、健聴者にとっては「音声は出ているのにまだ文字が出ない」といらだち
を感じる方も出てきます。
排出タイミングは、聴覚障害者と健聴者、つまり、話者の話を聞こえる方と聴こえない方で
とらえ方が大きく違っています。
聴覚障害者にとっては、淡々とした講演会では、タイミングはそれほど気になりません。
しかし、落語、漫才など、観客との笑い等の同時性を求めると、そのタイミングは重要に
成ってきます。様々な現場と対象者の様子をみて、判断しましょう。