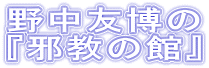
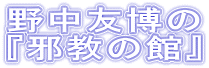
『邪教の館』へようこそ。
2002年10月下旬の現在、国内のニュースは殆ど北朝鮮からの拉致被害者の一時帰国と、それに伴う永住帰国や日朝交渉の問題一色になっている。ほぼ同時期に起こったロシアの劇場を標的にしたテロの問題もあり、演劇人としては看過しがたい深刻な問題ではあるものの、目下、このサイトの掲示板でも議論されている状態でもあるので、その件はまた別の機会に譲りたい。
この原稿を書いている時点で、日本政府は一時帰国している拉致被害者五名を北朝鮮には帰さず、配偶者や子供達を来日させるという形で、日本に永住帰国をさせるという方針を固めた。拉致被害者の家族達からの、強い要望に応えるという形であるが、滞在日数の延長といった議論から、帰さないという決定に至るまでの日数はほんの僅かだ。殆どの拉致帰国者は、永住帰国の問題に対してはノーコメントとしているが、狂喜乱舞する家族達に比べて、複雑な心中にある事は一目瞭然だ。
子女や兄妹を拉致という犯罪行為によって連れ去られ、その奪還と再会にに向けて二十余年を費やした家族達の、「せっかく再会した家族を、得体の知れない国家主義の国に、再び戻したくはない。いったん北朝鮮に戻れば、二度と帰国できないかも知れないではないか」という心情は理解できない事ではない。だが、拉致被害者当人、一時帰国という形で、家族を北朝鮮に残した形で来日……帰国と言うよりは来日と言って良いであろう……した当人達の意志が、決定に全く反映されていないという事は、傍目から見ても明らかな事であると思われる。
この状況は、我々に実に多くの事を連想させる。帰国者を帰さないと躍起になる被害者家族達の一部は、かつてオウム真理教のサティアンに、「子供を返せ!」と言って殺到した、実は子供の事を全く判っていない親権者達の姿を想起させるし、仮に拉致帰国者の子供達が日本に暮らす事になれば、今日まで北朝鮮=朝鮮民主主義人民共和国の公民として生きてきた若者が、自分の両親(或いはその一人)が実は日本人であり、従って自分は日本人であるという事になるが故に、住み慣れた国を離れ、知人もおらず言葉も通じない国で突然生活しなければならなくなるであろという意味で、全く、拉致被害者と同様の体験をするであろうという事……そして、拉致被害者の方々自身が、拉致後、彼ら自身が語るように「帰れるとは思わ」ずに、北朝鮮で過ごした二十余年に渡る新たな人生が、再びリセットされてしまうという、二度目の亡国を経験するという衝撃……
そうした悲喜こもごもの事象の責任を、日本のマスコミや世論は、北朝鮮の拉致という犯罪に求めるだろうし、北朝鮮側からすれば、大日本帝国による朝鮮半島の植民地支配という部分に、その発端を設定するだろう。そうした責任の所在や、起因する出来事を遡及していくという事は、今回の論旨ではない。
私が問題としたいのは、そうした個人の葛藤を生み出すであろう決定を行ったのが、日本政府……つまりは『国家』という疑似人格であるという一点にある。そこには、国家=「公」の決定は、個人=「個」の意志よりも優先される、或いは「公」は「個」の意志を問題としないという無意識の自明生が働いているという事である。
私は、十代の前半に、いわゆるロシア・マルクス主義、東西冷戦時代の東側、左翼陣営に属する世界観を学んだ事があるので、北朝鮮という国の国家社会主義体質という物を、ある程度実感として理解する事が出来る。そのような環境に生きる人々にとって、国家……「公」……という存在は絶大である。絶大、と言うか、拉致、という形で人生のリセットを強いられた人たちにしてみれば、一種の諦観がある。そうした環境に、青春期から生きてきた人々にとって、政府の決定は絶対的な物だ。日本は、国家社会主義の体制に比べれば、遙かに自由に物を云う事が許されている筈だが、二十余年のあいだ国家を絶対とする体制に生きてきた拉致被害者が、身に付いた習慣として、国家や政府の対応に異を唱えるという事は出来にくい筈だ。どうしてその事を誰も言わないのか不思議でならないが、そうした背景をふまえれば、日本政府の決定に拉致被害者自身の多くが口を噤んでいる事は、ある意味当然だと思えてくる。
軍事力や司法警察力という暴力機構の、為政者や支配者の独占という事が国家の起源であると考えられるが、現在の世界史段階上では、多くの国家が必然的に個人を抑圧するシステムとして機能している事が判る。それは、北朝鮮のような国家社会主義の政体や、ロシアのような一国社会主義の根っこを引きずった政体、そして日本のような生き神様への滅私奉公という呪術的な感覚を引きずった政体に顕著である。これらの政体では、国の決定に、否応なく従わねばならず、異を唱える事に対する禁忌が存在している。アメリカやヨーロッパのような近代化の先駆者とも言える国家では、国民が政府=国家に対して反対の意思表示をする事がある程度自由であるように見える。アメリカはロクでもない国だが、国内に限って言えば、個人が政府や国家を批判したり、意思表示をしたりという事に対する自由が、民主主義の大原則として認められている。おそらく、近代化とは、「個」が「公」に対して優位にあるという事を、一種の不文律なり自明の感覚として、国民、或いは個々人の総体としての社会が獲得する事なのではないかと思えてくる。だとしたら、今回の一連の事件は、日本が未だに呪術的な「世間」と「公」の概念に縛られているという点で、本当に近代化を果たしたのかどうかが怪しいという事実を突きつけるのである。
国家や会社、或いは劇団といった「公」とは、社会とも共同体とも異なる、一種の共同幻想であると言って良い。例えば「国が滅ぶ」という表現をした場合、それは国家を支配している王朝や政府が途絶えたり転覆したりという事を意味するが、国民が皆殺しになって殲滅される事は意味しない。この事は、広義の意味で「公」が「個」を含有しているのではなく、また「個」が「公」の部分ですらないという事を如実に示している筈だ。少なくとも、我々日本人は、「大日本帝国」という「公」の消滅を経験している。一種のアイデンティティー・クライシスがあったにせよ、「公」の消滅が「個」の消滅を意味しない事は実体験済みだ。要するに、「国家」のような「公」は、幻想に過ぎず、それは「会社」だろうと「劇団」だろうと同様だ。一種の疑似人格を持った「公」とは、地域とも共同体とも社会とも異なる共同幻想なのだ。
「公」が「個」に優先するという考え方は、近代社会の成熟途上にある過渡的な考え方であろうと思われ、近代社会がある程度の成熟期に至れば、「公」よりも、より「個」にウエイトが置かれる世界観が定着していくと思われるが、実際に近代化が果たされるという過渡期の世界では、「公」と「個」についての認識を異にする世代間の、或いは感覚的な対立が様々な軋みや歪みを引き起こす事になる。現代日本とは、ひょっとするとそのような段階にあるのかも知れない。村上龍は、自著の中で、現代の不可解な事件の底流には、日本(人)が、近代化を果たした事を自覚し切れていない事が横たわっている事をしばしば指摘している。
そうした背景は、当然だが演劇界の組織……具体的には劇団のあり方、或いは老舗の劇団の再編成や、年齢層の広い劇団の分裂危機といった物に反映されている。ここからは、我々により身近な演劇の世界で「個」と「公」の関わり方を考えようと思う。
「公」という幻想に帰属意識を持つ為には、ある種の強固なモチベーションが必要になる。近代化以前の日本には滅私奉公の習慣だの、終身雇用という疑似制度が存在していた為、「個」の「公」に対する帰属は自明の事とされていた。そうした感覚が、演劇の世界で具体的に反映されているのが、多くの劇団に存在するヒエラルキーである。
「ヒエラルキー」は位階制度などと訳され、ピラミッド型の上下関係を意味するが、元はと言えば天使の階級制度を表す言葉であるらしい。前々から『邪教の館』には書いている事だが、軍隊的なヒエラルキーを作っている劇団は意外と多い。曰く、執行部→劇団員→準劇団員→研究生と言うような階級で、私がかつて所属していた『劇団青年座』では、劇団員にもAランクからFランクというような、劇団員の等級まであって、劇団員名簿では、ランクの高い順で並んでいた。ランクというのは、単にワンステージの出演料の高い安いを意味する場合もあれば、文字通り体育会的な年功序列を現す場合もある。そして、カリスマ的な芸術上の指導者(主として演出家)を持たなかったり、方向性や理念が曖昧な劇団程、ヒエラルキーの序列は厳しく、より理不尽な階級制度が敷かれている。
幻想としての「公」である劇団に帰属意識を持たせる為のモチベーション、或いは集団の接着剤とは、単なる仲間意識だけでは不可能だ。演劇を実行する為のエネルギーは膨大だから、仲良しごっこだけでは直ぐに破綻する。だから劇団としての創作姿勢やベクトルが明確でない場合には、強力な年功序列によって調教を施してしまう場合と、劇団の指導者が構成員を甘やかし、構成員が指導者に甘えるという『贈与と支配』の関係を築くかのいずれかになる。どちらの場合も、「個」という自覚が曖昧な、支配者と被支配者という関係によって集団が維持される。この手の劇団では、「個」としての自覚に目覚めた劇団員が、感覚的に支配と被支配の理不尽さに気付いて、劇団を去ってしまうという事がしばしば起こるので、結構、新陳代謝が激しいのが特徴だ。ちょっと注意してみれば、リーダーの年齢と構成員の年齢が離れている事が多いと判る。よほどの馬鹿でなければ、年齢を重ねるに連れて、贈与によって支配されている事や年功序列の理不尽さに気付き、やっていられなくなってしまうからだ。
この辺の状況については、この『邪教の館』シリーズの21回目、『個人の時代の劇集団』にも書いた事なので重複になってしまうかも知れないが、「公」と「個」のどちらを重んじるかという事の世代間ギャップは、演劇集団の中では、より大きく、具体的な形で見えるようになっている。年齢のある程度高い「公」に「個」が帰属する事を自明とする劇団指導者達は、劇団員や研究生達に「黙って言う事を聞け」と言い続けるだけだ。劇団全体の意志決定に個人が従わなければならない理由を自問しようとはしない。だから彼らには若い劇団員達が、何故自分の劇団を辞めていってしまうのかが解らない。例えば、会社組織などの場合は、給与という形で、贈与による支配の形は目に見えるが、多くの劇団では金銭による贈与の支配は明確ではない。精神的な贈与だけなら自立心が芽生えれば劇団を辞めようと考えるだろうし、金銭によって縛られるという事もないからだ。むしろ、劇団という組織では、「劇団維持費」という形で、贈与どころか搾取されている場合さえある。そうした劇団が潰れずに続いていくのは、甘えたいガキどもが後を絶たないからというだけの事に過ぎない。劇団代表がどんどん歳をとって行くのに、その他の劇団員の平均年齢がいつまでも変わらないと言うのも、わりとありがちな話だったりする。
演劇集団という狭い世界を見れば、いったん所属した劇団で一生を過ごすなどという事は、優れた俳優になればなるほど珍しいと言う事が一目瞭然である。仕事の出来る俳優は、劇団を渡り歩くというよりは、むしろフリーになったり、限りなくフリーに近い立場をとるようになって行く。老舗、俳優座を例にとれば、フリーになってしまった平幹二郎、限りなくフリーに近い立場に立つ栗原小巻、自分で別派を構えてしまう形になった仲代達矢という事になるだろう。一つの劇団に骨を埋める……というような事は、ある程度の理念や方向性への共感や賛同というモチベーションが無ければ不可能であろう。そして、俳優というのは、限りなく多様な役や演目をやりたいという欲望を持つ存在であるから、単なる年功序列や贈与による支配だけで特定の劇団に忠誠を尽くしたりはしない。枠に収まってしまうとすれば、それは馬鹿なのかスケールが小さいのかのいずれかだという事になってしまう。私は紅王国の俳優に対しても、野心的であって欲しいと思っている。彼らだって、公演活動で生活が保障されるなら、劇団外の仕事だってどんどんしたくなるだろう。それは私自身にしてからがそうなのだから、早くそのような環境を手に入れたいと思うばかりだ。
知り合いの劇団で、ここ一年ぐらいのあいだに若手が次々に辞めていくという事があった。外から見れば、劇団主宰者と構成員のあいだに、「個」と「公」についての認識に、歩み寄りの不可能なギャップがあるという事が手に取るように判るのだが、多分、主宰者側に、その自覚はまるでないのだろうと思う。小規模なのに軍隊的ヒエラルキーを導入した劇団ではむべなるかなというところだが、おそらく、その主宰者は独りぼっちになってもその根元的原因には気付かないであろうと思う。時代は「個」の時代に移行しており、若い世代は皮膚感覚でその事に気付いているのだ。
ここで再び、日朝問題に戻れば、拉致帰国者を北朝に帰さないという政府の決定、そして北朝で生まれ育った子供達を日本に帰国(!)させろという方針が、ある意味で逆拉致ではないかという点も、私の周辺の人々、20代後半以降の知人達は、素直な感想として捉えている。保守系文化人が「個」と「公」の問題を、「公は個に優先する」という形で声高に叫んだり、イエロー・ジャーナリズムが殊更に北朝鮮を敵視したりする事も、「公の時代」から「個の時代」に移る過程での反動的な痙攣なのだと思う。全てのアメリカ人がブッシュと同じような馬鹿ではないのと同様に、日本人だって政府や『ザ・ワイド』と同様の馬鹿ではないのだ。
それでも、政府は北朝にしろ日本にしろ、個人は政府の決定に従うのが当然という形で動いているのが現状だ。我々は、注意深く、「個の存在の倫理」を侵されぬよう注視しなければならないが、某劇団が「個の存在の倫理」によって崩壊しつつあるように、前時代の遺物は淘汰されて行くと信じよう。迷妄によって孤立する人たちは、些かの同情を感じさせるが、よくよく考えてみれば、そんな事は私の知った事ではない。
最後に、本稿執筆時点で物別れに終わった日朝交渉に関わる朝鮮半島と日本の問題について私見を述べておくと、北朝鮮がどんな国かと言う事を別にすれば、彼らの主張……一時帰国者を平壌に帰すという約束を日本政府が破った事、核問題はアメリカが北朝鮮を先制核攻撃の対象としている問題と絡めなければ解決を図れないという事……の方が理屈は通っているという気がした。そして、日本は拉致帰国者の問題の原点を拉致という犯罪行為に求めるが、朝鮮側から見れば、原点は日本の朝鮮半島に対する占領政策に求めるであろうという事も理解できる。いずれにしろ、朝鮮半島に対する戦後補償の問題は、大韓民国と朝鮮民主主義人民共和国……この二つの政体と政府に分離した朝鮮半島が、何らかの形で統一され、その統一政府と日本政府のあいだで合意に達しなければ、政治的な意味でも終焉を見る事は無いだろうと思う。そして民族的な拘りは、更に更に続いていくだろう。その件は、紅王国で発表する倭王伝シリーズで描く事になるだろう……いつか、きっと……
2002/10/29〜31